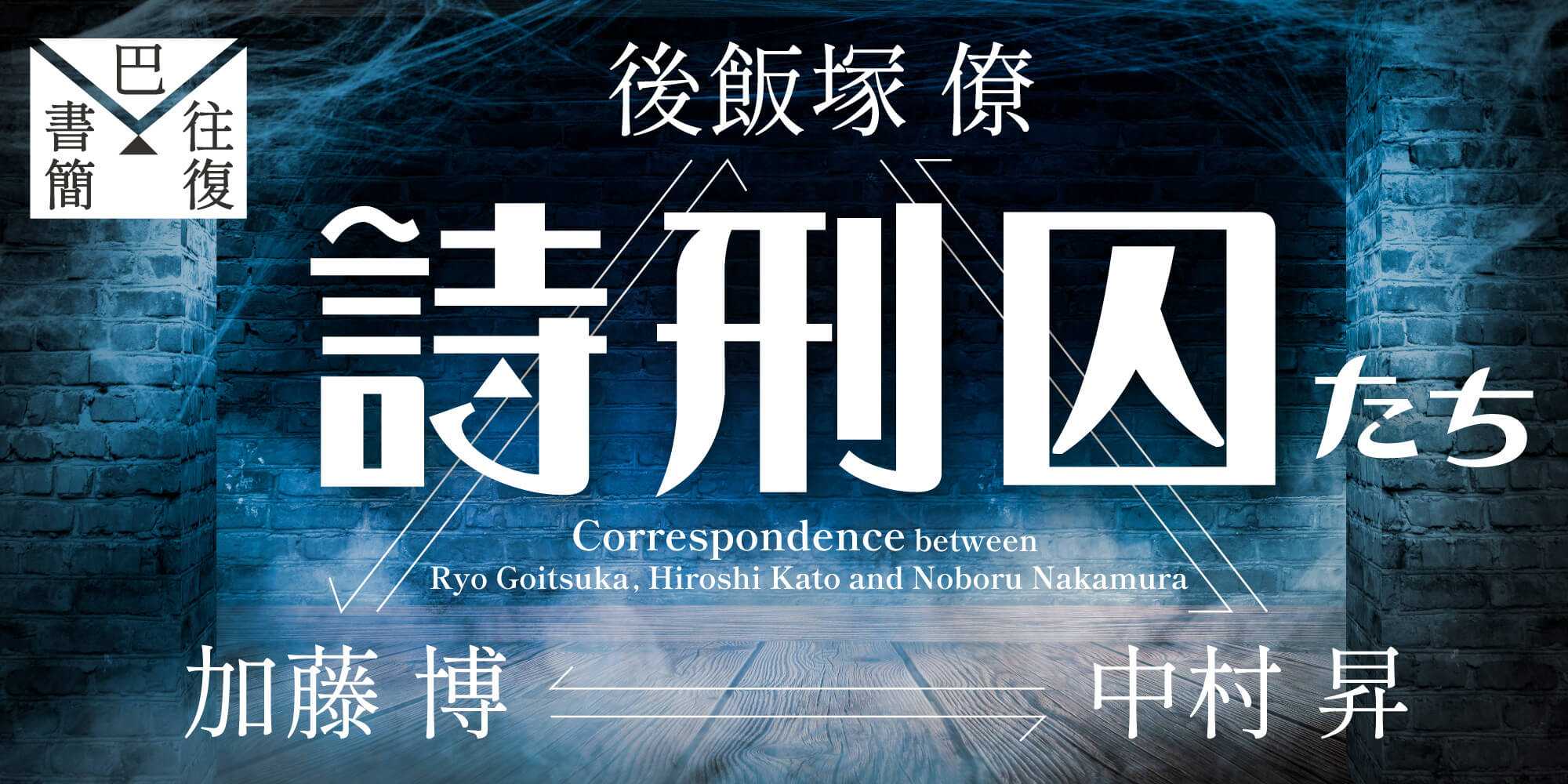指示対象がない「詩の言葉」
後飯塚さんは「序にかえて」で、自作について「言語でのみ到達可能な景色」と書く。中村さんも「トイ人」のインタビューで、詩について「言葉そのものが持つリアリズム」と答えている。そういう「景色」や「リアリティ」を、私はつかみ損ねているようです。二人が「言語でのみ」「言葉そのもの」というのは、後飯塚さんの「意味やイメージに隷属しない」との形容から推測すると、文の指示対象がなくても成立する世界でしょう。私の場合、指示対象を頭の中にイメージできないと、言葉の着地点を見失ってしまう。言い換えると、記憶に沈潜するモノ・コトが文を読むことで浮かび上がり、指示対象として構成されないと分からなくなり、いわゆるシュールな詩は読解不能になってしまいます。そんなわけで、後飯塚さんの「文字列」も、何か胸に迫るものを感じつつも、受け取りかねています。すみません。
このギャップに関して、先日、中井久夫の『アリアドネからの糸』を読み返していて、うまく言い表している(かもしれない)箇所を見つけました。
成人言語世界の成立前後のゆらめく世界こそ、文学にとってもっとも重要な世界であるかもしれない。(同書内「詩を訳すまで」より)
「文学」と書いてありますが、全体の文意から、これは散文ではなく「詩」のことです。中井氏の論を『徴候・記憶・外傷』内の「発達的記憶論」も合わせて若干敷衍しつつ要約します。
幼児は2歳半から3歳の間に急激に語彙を増やす。「言語爆発」(※1)とよばれるこの時期を経て幼児は成人言語世界(象徴界)に入っていく。言語爆発による言語獲得の過程で以前の記憶は消去されるが、消されたはずの古型の記憶がわずかに残存し、深層構造として成人言語を裏から支えている。この言語爆発期の「ゆらめく世界」が、言葉の奥行きと深みをつくっている。しかし「ゆらめく世界」は言語獲得以前の混沌とつながっているため、日常的な言語使用の場面では、成人言語の分節化・文法化圧力により表に出ない。
たぶん詩をつくる人は、成人言語を使いながらも、この「ゆらめく世界」から詩の命を汲み上げることができるのでしょう。
中井久夫は、ご存じのように精神科医にして、ヴァレリーの『若きパルク』『魅惑』の翻訳者です。その経験から、統合失調症患者の言語危機と、詩作者の言語意識には多くの共通点があると指摘します。自身、ヴァレリーを翻訳する中で「その伴示(コノテーション)、類語、類音語、音調、イマージュ、色調、粘膜感覚と筋肉感覚などで一語一語が重すぎるほどであった」と語ります。精神医学の理論と臨床、詩の翻訳の苦闘と喜悦の体験に基づいた論なので、信用してもよいと思います。
この論を「言語でのみ」「言葉そのもの」の話に戻すと、指示対象がなくても詩を“感じる”ことができるのは、言葉が「ゆらめく世界」で裏打ちされて、言葉そのものがリアリティを保持できているからかもしれません。その感知能力が私にはないのか? いや、部分的にはあるような気がします。
中村さんが前回の書簡で書いた「否定の力」。そこで例示した俳句「蝶墜ちて大音響の結氷期」。小さな蝶が墜ちて大音響を発する。そんな音は存在しません。つまり、音の指示対象がない。でも、その音を感じる。感じる以上、どこかにあるかもしれないと思う。
こうした語法は、レトリック的には対義結合(撞着語法)とよばれます。「冷たい炎」「ゆっくり早く」「負けて勝つ」「ピンチはチャンス」……相反する言葉が連結された異常な表現に見えますが、多くの対義結合には指示対象となる事象(または心象)があります。「彼女の瞳に冷たい炎がゆらめいた」というとき、彼女がいだいたであろう尋常ならざる感情が、ある面では「冷たい」と、ある面では「炎」のようだと、矛盾した言葉を表現者に要求した。個々の単語は一方的な捉え方しかできず、しかし現実はそんな言葉の事情などおかまいなしに現実としてある。矛盾した現実が存在するわけではなく、その意味では、こうした対義結合は「否定の力」に当たらないでしょう。
それに対して「蝶墜ちて大音響」は、“ない”はずの音を“ある”と言っているのですから真に矛盾しています。この矛盾を無理なく了解できるのはなぜか。例えば「音なき音」。いかにも矛盾していますが、そんな音があるように感じる。耳に聞こえる音だけが音ではないからです。「香りをきく」「きき酒」「うるさい絵」「静かな心」など、聴覚を超えて他の感覚に、共通感覚として感じる音がある。その音の存在を実際に感じるから、私たちは、ないはずの音を「どんな音だろう」と探す。言葉の受け手は、指示対象を勝手に想像するのです。「否定の力」とは、不在の描写を踏み台にした“在”の探求への跳躍なのかもしれません。
「蝶墜ちて大音響」が凄いのは、直接的な対義結合を使っていない点にもあると思います。「音なき音」のように表面的に言葉が矛盾していると、矛盾した表現に驚き、驚きに惑わされてリアリティを感じてしまいますが、どこか空疎です。一方、「蝶墜ちて大音響」のような内的な矛盾に接すると、より深い謎を感じます。
この「共通感覚+指示対象探し」の仕組みをもつ表現が、広告コピーにもあります。糸井重里による「おいしい生活」です。そして土方巽の『病める舞姫』にもあります。「忘れられたからだ」や「練りに練った光」などです。「おいしい生活」から説明します。
「おいしい生活」がコピーのチャンピオンである理由
広告コピーの金字塔、「おいしい生活」が登場したのは1982年。80年代の消費文化を牽引した西武セゾングループの中核、西武百貨店のキャッチコピーでした。今では想像できないかもしれませんが、西武セゾングループが打ち出すマーケティング施策、パルコ、パルコ出版、ロフト、無印良品、西武美術館、西武劇場、スタジオ200、シネヴィヴァン、WAVEなどはセゾン文化とよばれ、20代だった私たちを虜にしたものです。
「おいしい生活」が衝撃的だったのは、言葉の時代的な背景があります。当時、「生活」という言葉にはうらぶれた印象、それこそ生活臭が漂っていました。コメディアンは「生活かかっちゃってんのよ」と笑いをとり、貧乏くさくて裏路地的な、ネギがはみ出た買い物籠をぶら下げているような暮らしをイメージさせる「生存」のための「生活」でした。「生活」がSIMPLE LIFEとか、ライフスタイルとか、生活者とか、通販生活とか、天然生活とか、オシャレな言葉になったのは「おいしい生活」が出たあとのことです。その貧しく疲れた「生活」を、最先端の西武百貨店が納戸から引っ張り出すように持ち出し、しかもそれは「おいしい」のだという。その驚きから、私たちは「おいしい生活」が何を語ろうとしているのかを探ろうとしました。しかし、それまで「おいしい」には美味(おいしい料理)、都合が良い(おいしい話)、過剰な利益が得られる(おいしい仕事)といった意味しかなく、これらでは「生活」を修飾する「おいしい」の意味が汲み取れない。
そこで私たちは(識閾下で)考えました。「おいしい」とは、基本「食べ物の味がよい」ことだ。しかし「生活」は食べ物ではないし、比喩として食べ物と見なす(擬食法?)のも無理がある。それでもなお「よい味がする生活」があるとしたら何だろう。「味」には、食べ物の味だけでなく、「味のある絵」「味なことを言う」「博打の味をしめる」「味も素っ気もない」「興味」「趣味」「吟味」などの使い方もある。これらの「味」は味覚に限定されず、視覚、聴覚、臭覚、触覚でも経験する感覚全体に通じていて、何か「味わい」とでもいうような共通の感覚に支えられているだろう。こうして私たちは「味」の共通感覚を発見し、それを手がかりに、「おいしい生活=よい味わいのある生活」と捉え直すことで、「おいしい生活」という斬新な概念を受容しました。
ところが、新しい概念は生まれたが、それは何を指しているのか、指示対象がはっきりしない。「おいしい」の共通感覚で「生活」を限定してみたが、具体的にどんなモノ・コトなのか分からない。不安にかられた私たちは、この新概念を着地させるために、「おいしい生活」の指示対象を求めて西武百貨店へ走りました。そういうイマい(!)概念を所有していないことに焦り、ファッション、レコード(CDではない)、インテリア、観劇、美術鑑賞、グルメとお金をつぎ込んだ。広告としては大成功です。指示対象の不在を梃子にした飢餓感マーケティングです。
さて、以後、指示対象は「外延」と言い換えます。言葉の意味は、パロールとしては「指示対象/解釈」に分けられますが、ラングとして説明したいので「外延/内包」の対を使用します。(※2)
言葉の原則として、外延・内包はワンセットです。ところが「おいしい生活」は、このコピーが登場した時点では「よい味わいのある生活」という内包規定があるのみで、外延がない。これでは不安定です。
認知言語学で、言葉の意味は「その語から想起される(可能性がある)知識の総体」とされます。これは百科事典的意味観とよばれ、その知識にはフレーム(日常の経験を一般化することにより身につけた知識の型)や背景知識、さまざまな捉え方、個人的な体験も含みますから、とても広大で茫洋としたものです。個々の発話の場面では、この百科事典的知識の一部が文脈に応じて活性化します。もちろん、発話の送り手・受け手ともに、おのおのが潜在的知識の顕在化をそのつど行っています。糸井重里は『イトイ式コトバ論序説』の中で、この潜在し顕在化するものを「コトバの素」とよびました。なんと美しく的確なネーミングでしょう。以後、私も使用させてもらいます。
内包はモノ・コトの属性なので、曖昧です。あるモノが「黄色い」といっても、隣接するオレンジ色と緑色との境界は不分明です。「愛する」「恋する」「惚れる」「焦がれる」「慕う」「好く」の分かれ目も不明瞭です。このような曖昧さは、コトバの素が集積している記憶の総体の深部ではより深刻になり、モノ・コトの属性はカテゴリーの階層をも飛び越えて溶け合っているでしょう。それに対して外延は、究極的には個物です。個物の記憶が土台となってカテゴリーが多層に形成されています。モノを指す名詞は、こうして個物の記憶に接地していると思われます。一方、コトを指す形容詞・動詞・副詞は、モノと結びついた状態でしか外延になりません。木村敏が『時間と自己』で指摘するように、例えば「落ちる」という現象は「落下」というモノに置き換えて把握するか、あるいは具体的なモノが落ちたことの経験を想起して捉えるか、いずれかでしょう。つまり、外延は結局はモノに還元されるので理解が容易です。だから、例えば禅僧が「山が歩き、山が流れる」と言うのを聞いても混乱には陥りません。内包的な把握には戸惑っても、外延的には山を生き物と見なして怪物のイメージを、流体と見なして波の山が崩れるイメージを投影することができます。言うまでもなく、こうして投影されるのは個別具体的な事物のイメージではなく、類型化され、典型的な物語(野矢茂樹『語りえぬものを語る』より)として捉えられたイメージです。
翻って、コトバの素の活性化の際に、「おいしい生活」のように対応する外延がなく、内包だけが顕在化したらどうでしょう。詩人ではない私たち常人は、内包の流動性に耐えられず、外延を求めて右往左往するでしょう。外延は、語と語の区別をはっきりさせ、内包を固定化してくれます。だから、内包の海で溺れないための、深海に引きずり込まれないための浮き輪、言葉という舟の底板のようなものが外延なのだと思います。以上、私の仮説でした。
のちに糸井重里は、何かのインタビューで「おいしい生活」の自己採点を200点としつつ、「何でも“おいしい”に流し込むのはファシズムだ」というような自己批判めいたことを語っているのを読みました(記憶なので間違っているかもしれません)。これは「共通感覚+外延探し」のシステムについて述べたものと思われます。「おいしい」が「生活」にかかるから広告になりますが、それが「おいしい国」「おいしい民族」だったら、私たちはどんな外延を求めるのでしょうか? ちょっと怖くなります。話がそれました。次は『病める舞姫』の「忘れられたからだ」について説明します。
「忘れていたからだ」を思い出す
「忘れられたからだ」が出てくるのはp.9(白水Uブックス版のページ、以下同様)。この句が含まれている6ページにわたる部分、p.7の最後「饐えた昼飯の臭いなどを嗅ぎながら~」から、p.13「~無意識のうちに一種の疾病として片付けていたかも知れないのだ」の間の叙述が、どうも異質な感じがしてひっかかったのです。
『病める舞姫』は回想の形をとっているので、書いている土方さん本人とは距離があります。ところが、この部分は生々しい。どこか道を踏み外し、しくじりを犯し、悔やんでいる感じがします。それは、p.8からp.10の3ページ間に「~てしまった」「~てしまう」の語尾が8箇所も出現するからかもしれません。また、次のような節や句が散らばっています。
「私は何者かによってすでに踊らされてしまった」「私は~生命を失った物体のようになっていた」「からだが自分の持ちものでない」「私もまたあやまちを重ねた」「ものたちの争いに喰われてしまう」「放って置かれたからだ」「作り話のようなからだ」「たどりつけぬ行方」「私は単純種だった」「誰でも一つ目小僧になれることすら忘れてしまう」「私は水底に降りていけなくなる」「からだの中を蝕む空っぽの拡がりの速さに負けてくる」「このからだは、こうして喰われ続けていく」「不透明なからだはヒステリーを起こしていた」
これらの記述から、この間の状態が、どうも不如意で不本意だったように受け取れます。『病める舞姫』は、主体・客体が交換したり、能動・受動が転倒したり、言葉の意味(価値)が裏返ったりするので、確定的なことは言えないのですが、p.10には「掠め奪られ、またすでに踊らされてしまっているのに、それを奪い返し再生し続けるにはどうやればいいのか見当もつかないでいた」と、この時期の状態を要約したような文もある。「忘れられたからだ」は、その状態を象徴する句に見えました。
「忘れる」には、①記憶を想起できなくなる(名前を忘れる)、②対象についての意識をなくす(我を忘れる)、③意識できなくなる(悩みを忘れる)、④物を置いてくる(財布を忘れる)、⑤すべきことをしないでいる(戸締まりを忘れる)といった意味があります。そこで、「からだを忘れる」がどれに当てはまるかを考えると、明示的には「体(の存在)を忘れてゲームに熱中する」ような、体への対象意識をなくして何かに没入する状態ですが、こんな解釈は成り立ちません。そこで思い浮かぶのが「歌を忘れたカナリヤ」です。⑥できていたことが、できなくなる。それも自然にできていたことが、なぜか突然できなくなる。「自転車の乗り方を忘れる」ような、かなり異常な事態です。でも、最後は「月夜の海に浮かべれば忘れた歌を思い出す」。以上をいったん取りまとめると、①②③は「頭から消える」、④⑤は「頭から消えていたことに気づく」、⑥は「自明な能力がなくなる」。さらに、これらに通底する「忘れる」の共通感覚を探ると、「内的なつながりが切れて見失う(ただし、どこかに残っている)」と推定できます。「解離」と言い換えてもいい。土方少年は、その初期に解離を経験したのではないでしょうか。だとすると、何から解離したのか?
解離状態になる直前、p.7に次の記述があります。
からだは、いつも出てゆくようにして、からだに帰ってきていた。額はいつも開かれていたが、何も目に入らないかのようになっていた。歩きながら躓き転ぶ寸前に、あっさり花になってしまうような、媒介のない手続きの欠けたからだにもなっていた
これは、からだのピュシス(※3)状態でしょう。“出てゆく”と“帰ってくる”が同時。見えているが見ていない。からだが、たちどころに花に変わる。能動が受動であり、作為が無作為であり、姿かたちも瞬時に変幻する。このときまで、土方少年はからだの楽園に住んでいたのだと思います。この楽園から転落した状態を「忘れられたからだ」と言ったのでしょう。
なぜ転落したのかは分かりません。しかしその後、p.13以後、寝たり起きたりの病弱な舞姫と出会うことで再生のきっかけをつかみ、何度か行きつ戻りつしながら、ついにp.22で「何があったのか、からだがゆっくり熟れていく果実のように感じられていた」と完全復活をとげます。「そうして、すっかり何かが終わったように長い昼寝から醒めると、私は待ちぼうけを喰ったように笑っていた」のです。
では、そこから解離してしまった失楽園以前のピュシス、楽園にいた時代として追憶される「忘れていたからだ」の外延は何でしょう。土方さんは、糸井重里と違って飢餓感マーケティングを行う必要はありませんので、『病める舞姫』の中にちゃんとヒントを残してくれています。
p.7の最後、失楽園の記述が始まる最初に、本当は大事だったのに忘れた、という書きっぷりでそれは暗示されています。「饐えた昼飯の臭いなどを嗅ぎながら、粉を吹いている酸っぱい茄子の漬け物の色のまわりで吸いあげていった、茫とした姿こそ大事なものであったのだろう」と。また、p.9に「こういう忘れられたからだの状態でも、漬け物樽の上に白い粉を吹いている石の重さは忘れられない。石を持ち上げ、のびきった茄子を引き上げるときの中腰と、その中腰自体のなかに滲みでている暗がりは、自然にからだにそなわっていたものであろう」と、忘れていても忘れられないもの、つまりピュシスとのつながりを微かに保持するものについて語っています。二つの文に共通しているのは「茄子の漬け物」。なぜ「茄子の漬け物」がピュシスの象徴なのか、まったく分かりません。それは土方さんの個人的な体験に根ざしていて、私たちにはうかがい知ることができません。同じように私たちの言葉も、他人とは共有できない記憶によって支えられているでしょう。
「忘れていたことば」を思い出す
冒頭で紹介した中井久夫が、『アリアドネからの糸』で「二歳半から三歳の間に『言語爆発』とでもいうべきものが起こって、急速に成人文法性とでもいうべきものが成立する」と書くのは、言語心理学の成果を引いてのことです。(言語心理学では「語彙爆発」とよぶ。脚注※1参照)
語彙爆発期の研究で多くの著書がある言語心理学者・今井むつみは、『ことばの学習のパラドックス』で、この時期の直前に、幼児が言葉を「過剰適用」する現象がみられるとします。「子どもはひとつのことばをさまざまな事物に自発的に拡張するようになるが、その拡張範囲が大人の慣習的な意味範囲よりずっと広くなる」と説明し、以下のような例をあげます。
ある女児は、生後9カ月のころ、「ニャンニャン」という言葉を“白い毛製のスピッツのおもちゃ”と“桃太郎の絵本にでてくる白犬”に限定して使っていた。それが生後10カ月になると、「ニャンニャン」はイヌ、ネコ、トラなどの四つ足の動物に、また、実物のスピッツ、白毛のパフ、白毛のついた自分の靴、白い毛糸の束、白い毛布、羽織の紐の房、白い壁などへ拡張され、1歳くらいまでこの「過剰適用」が続いた。
また、同氏は『言語の本質』でも「『開ける』は多くの子どもが過剰一般化することで有名な動詞だ。英語のOpenについてもたくさんの過剰一般化の報告がある。たとえば電気をつけたり、テレビをつけたりするのにOpenと言う子どもがたくさんいる」と書いています。
語彙爆発が起きる直前のこうした「過剰適用」は、「共通感覚」の起源なのかもしれません。そして、成人言語の世界に生きる私たちは、「共通感覚」をたよりに幼児言語の「過剰適用」を追体験し、「忘れていたからだ」ならぬ「忘れていたことば」を思い出す。「外延なし・内包のみ」の詩の理想にはたどり着けなくても、中井久夫のいう「ゆらめく世界」を感じることはできるかもしれません。そのために、とりあえず外延・内包の固定的な結合を解除し、外延を付けたり外したり、柔軟にできるようにしておく。『病める舞姫』は、そのレッスンの最良の教科書だと思うのです。
最後に、糸井重里の『イトイ式コトバ論序説』から私の好きな文を引用します。
子供たちは、コトバの構造が非常に不安定です、大人と違って。だからナンセンスに満ちています。よくウサギさんが洋服着て『ボク、ドコカニイクノ、オベントウヲモッテ』とか言いますね。現実のウサギ、洋服着ていないんですよ。でも、洋服というコトバ(の素)の集まりとウサギというのと一緒につなげてしまう。もともとコトバ(の素)の集まりの方が不安定でブルブルブルブル震えているから、すぐつなげられちゃう(「の素」は筆者補記)
<脚注>
※1 言語心理学では「語彙爆発」とよび、それは生後16カ月くらいから始まるとしているため中井久夫の記述とは1年ほどずれている。中井氏は成人言語への移行期のことを主題に語っており、このずれは問題ないと思われる。
※2 パロール:特定の時、特定の場で個人が具体的に行う言語の使用。ラング:言語活動の中に共通している慣習としての言語体系。外延:概念が適用される事物の集合。内包:概念が適用されるすべての事物に共通する性質の総体。
※3 ソクラテスより前の初期ギリシアの哲学者が思索した自然。生命の源と考えられ、万物はそこから生まれ、そこへ没するとされた。
<参考図書>
土方巽『病める舞姫』(白水Uブックス)
中井久夫『アリアドネからの糸』『徴候・記憶・外傷』(みすず書房)
佐藤信夫『レトリック認識』(講談社学術文庫)
糸井重里『イトイ式コトバ論序説』(マドラ出版)
木村敏『時間と自己』(中公新書)
野矢茂樹『語りえぬものを語る』(講談社学術文庫)
今井むつみ『ことばの学習のパラドックス』(ちくま学芸文庫) 『言語の本質』(中公新書)
『認知言語学大事典』(朝倉書店)
『日本国語大辞典』(小学館)