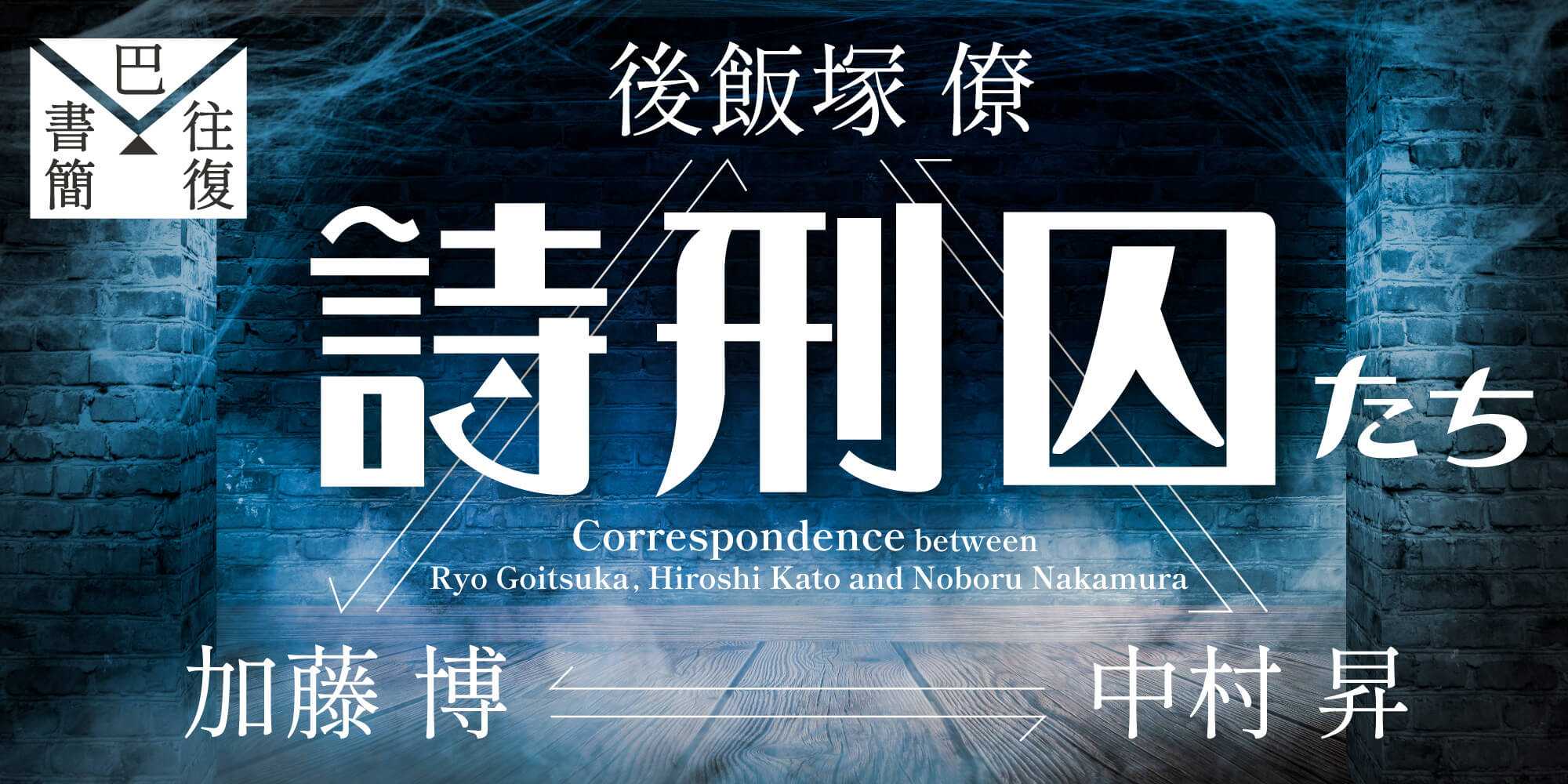僚くんが「意味やイメージに隷属しない、「言語固有」の臨界点(消滅点)」と言い、加藤さんが、「記憶に沈潜するモノ・コトが文を読むことで浮かび上がり、指示対象として構成されないと分からなくなるシュールな詩」と言うときの「臨界点」や「シュールな詩」とは、いったい何か?このことを今回は、わたしなりに考えてみたい。
まず、そもそも言語とは何か?ということからいってみよう。
言語とは何か?
わたしが割とよく知っている三人の哲学者(一人は言語学者)の言語についての考えをまずは、ざっと見てみよう。それも、今回の話と関係するところだけに焦点を合わせて。その三人とは、ソシュールとウィトゲンシュタインとオースティンだ。
まずは、ソシュールから。ソシュールの言語観は、言語は事実とは対応していない、というものだ。一つ一つの単語が、現実に存在している一つ一つの事物と対応しているわけではない。「犬」という語は、実際にそこら辺にいる犬と対応しているわけではない。「犬」という語は、日本語という言語体系のなかのほかの単語(「猫」「狼」「熊」「人間」などなど、体系内のすべての単語)との関係(差異)によって、その意味は決まる。だから、基本的に「犬」という語は、外側の現実世界と直接接触しているわけではないし、ましてや指示しているのでもない。
「中村昇」という固有名詞だってそうだ。日本語のなかで、「中村昇」という語が、さまざまな語(他の固有名詞群、「中」「村」「昇」といった個々の語のほかの語との差異など)との関係で、その意味が決まっている。それを、たまたま私(中村昇)がいるところで、いろんな人が長い年月使っているから、私と関係してくる。指示しているような気になるだけだ。そういう場ができるだけなのである。あくまでも「中村昇」という語は、日本語という母語のなかで意味は決まる。
無数の事物が、切り分けられることなく連続している現実(この世界)に、日本語という言語体系全体が対応してはいる。一対一対応はしていないけれども、全体同士(言語体系と混沌とした名づけられない世界)が対応しているというわけだ。したがって、言語のさまざまな単語やその関係性の網の目によって、連続的世界を「分節化」することができる。ただ、それはもちろん、言語側から、「恣意的に」分節化しているだけであって、言語が現実と接触しているとか、その言語による分節には、事物側にそれなりの必然性があるというのではない。あくまでも、言語側の都合である。ある意味で、言語による現実世界(連続した渾沌)をめぐる錯誤・妄想といってもいいだろう。
だから、日本語と英語とタガログ語とロシア語等々とでは、世界認識(錯誤構造)が異なるのだ。言語という唯一の世界認識の網の目がちがうからだ。異なった分節化をしているから、異なった世界を認識しているというわけだ。これが、言語相対主義と言われるものである。
さらにウィトゲンシュタインは、どうだろうか。もっとラディカルかもしれない。ウィトゲンシュタインは、ソシュールのように言語体系(ラング)などは前提しない。ソシュールの用語を使えば、「パロール一元論」である。われわれは、いつも言語ゲームをしている。さまざまな場面で、さまざまな言語ゲームをおこなっているだけ。言語ゲームにおいて、ことばのやりとりがうまくいっていれば、それでいいという考えだ。「万年筆」という語が、同じ<それ>を指していなくても、「その万年筆とって」と誰かに言って、言われた人がそのへんにある万年筆をもってきてくれれば、それでいい。言語を使ったわれわれの生活が、表面上うまくいっていれば、何の文句もない、というのである。
ソシュールのように、それぞれの母語の体系内の単語の差異が意味を生むなんてことも言わない。それは、ただの仮説だから。ウィトゲンシュタインは、仮説は立てない、目の前の現象(言語ゲーム)を記述するだけだ。もし「意味」というものが存在しているとすれば、ある人がおかしな言葉使いをしたら、その人は、その語の意味がわかっていないな、と他の人が思うときだけなのだ。「その万年筆とって」と言われた人が、鉛筆をもってきたら、その人は、「万年筆」の意味をわかっていない(もしかしたら「鉛筆」の意味も)ということがわかるだけ。実際に存在する万年筆や鉛筆に対応する語(意味が媒介して成立する一対一対応)が、きちんと存在しているわけではない。言語ゲームのなかで、誰かが変なことを言ったら、ちょっとだけ「意味」なるものが顔をだすだけだ。
だから、ウィトゲンシュタインの言語観も、言語と現実は対応していないというものだ。言語は言語だけの自律した世界をもっている。その言語世界のなかで、われわれは何の共通の実体的な根拠もない(現実に対応していない)ゲームをしているだけなのだ。もちろん、現実のなかで言語ゲームをしているわけだから、その言語ゲームには、われわれのもろもろの感情や行為が当然絡まってきてはいる。だから、言語ゲームは、言語だけのゲームではない。そういう厚みのあるゲームが、われわれの生活の仕方(「生活形式」)なのである。
もう一人あげよう。オースティンという哲学者だ。この哲学者は、言語が現実を表しているわけではなく、ことばをわれわれが発するのは、それ自体「行為そのもの」だと考えた。オースティン以前の、言語が現実を表すという考えを「記述主義的誤謬」と言ってばっさり否定した。言語は、現実や出来事を「記述している」のではないというのだ。言語を発するというのは、そのまま「言語行為」なのであって、事実を確認したり、出来事を記述したりしているわけではない。
例えば、「私はあいつが嫌いだ」という発言は、「その発言者本人が、「あいつ」のことを嫌っている」という事実を、その発言を聞いている人に対して記述しているわけではない。そうではなく、<嫌いだということ>を周りの人にはっきり宣言する行為をしたということだ。その発言によって、それなりの影響が、周りの人におよぶだろう。「私はあいつが嫌いだ」と言うのは、ひとつの行為なのだから、その行為によって、「あいつ」が同じように嫌いな人は喜んだり、他の人も「あいつ」が嫌いになったり、「あいつ」が好きな人は、その発言者と距離をとったり、いろいろな影響をおよぼすだろう。発言は、このように「力」をもっているのであり、その「力」は、周りに何がしかの波紋を広げるのである。たんに、外側の事実を客観的に記述しているわけではない。
このように考えれば、オースティンの言語論も、事実をそのまま表すために言語があるわけではない、つまり、言語は事実を指示しているわけではないということになるだろう。
こうして三人の哲学者、言語学者をざっと見ただけでも、言語は現実をそのまま指示しているわけではないことがわかる。言語の本質的特徴は、現実からの乖離なのだ。わかりやすい言いかたをすれば、ことばというものは、根本的に「嘘」なのである。そもそも現実の<ほんとうのところ>(そういうものがあればの話だが)とは対応していない。対応することはできない。事実や現実から乖離して、遠くべつの次元に存在しているものなのである。
たしかに、ことばは、われわれの現実に入りこんではいる。言語ゲームや言語行為というかたちで。ただ、それは現実のわけのわからない渾沌に、異物が入りこんできて、渾沌のなかで少しだけ、われわれが生きやすいようにしてくれるだけなのだ。現実から乖離しているからこそ、現実という渾沌の一部分に薄い光を当ててくれるとでも言えるだろうか。
だとすれば、僚くんの言う「「言語固有」の臨界点」や「言語でのみ到達可能な景色」というものこそ、詩だけではなく、言語そのものの特徴でもあるということになるだろう。ことばはことばだけの世界で、独りで生きている。意味やイメージや現実などからは、そもそも根源的に乖離しているのだ。言語の本質は、「嘘」、ようするに、現実との「根源的乖離性」なのである。
詩とは何か?
だから、詩というのは、この根源的な乖離に忠実にしたがった営為だということになるだろう。あるいは、われわれの勘違いやこれまでの記憶によって手垢のついたことばたちを、すっきりブラッシュアップして、もとの透明体に戻す作業だとも言えるかもしれない。
今回、詩論の類を何冊か読んでみたけれど、一冊だけ、こうした観点から詩を論じていたものがあった。入沢康夫さんの『詩の構造についての覚え書』(ちくま学芸文庫)である。この本をちょっとのぞいてみよう。入沢の詩論の最終的な考えは、「詩は表現ではない」というものだ。詩は、何かを表現してはいない。心情も景色も出来事も何も表現しているわけではない。それが詩だ、というものだ。
入沢はつぎのように言う。
詩人がいて、その詩人が何かその人独自の伝えたいことを持ち、それが表現されて作品が産まれ、読者はその作品を読んで、作者の伝えようとするものを正確にキャッチし、そしてそれに十全に共感する、という図式を、詩に関してはぼくは信ずることができない。(14頁)
その通りだと思う。詩は、<何か>を表現しているのではない。詩人の伝えたいことを詩は表現してはいない。当たり前のことだけれども、詩は言語なので、伝えたいことに直接対応することは、原理的に不可能だ(「根源的乖離」)。だから、詩は<詩そのもの>の現出なのである。
入沢は、つぎのような言いかたもしている。
では、一歩を進めて、「詩作品は手段ではない」と言えるだろうか。さらにそれを裏返して、「手段ではなく、それ自体が目的なのだ」と言えないか。あるいはこう言いかえることも考えられる。「手段ではなくて、言葉で作られてそれ自体で完結した一つの世界、ひとつの事物、つまりオブジェである」と。(15頁)
まさに、ここで言われているのは、言語そのものの特徴を、その極限まで推し進めるとこうなる、ということだろう。だからやはり、詩は、言語の極北の芸術だということになる。それまで着ていたものをすべて剥ぎとって、言語の真の姿をゴロッと投げだす作業なのだ。裸のオブジェにして放りだす。これが詩だ。
入沢も言及しているモーリス・ブランショの『文学空間』のなかには、つぎのような文章がある。
だから、詩の言葉は、もはやただ、日常言語に対立するのみならず、思考の言語にもはっきり対立している。詩の言葉においては、われわれは、もはやこの世に送り返されはしない。避難所としてのこの世にも、目的としてのこの世にも送り返されはしない。この言葉においては、この世は退き去り、目的は、その働きを止めている。この言葉においては、この世は口をつぐんでいる。諸存在(ひとびと)は、さまざまな心使いや計画や活動を行ってはいるが、もはや結局のところ、語るものではない。詩の言葉においては、諸存在が口をつぐんでいるという事実が、表現されるのだ。だが、このようなことが、どのようにして起るのか?諸存在は、口をつぐむ、だがその時、存在が、再び言葉になろうとし、言葉は、存在しようと欲する。詩の言葉は、もはや、或る個人の言葉ではない。つまり、詩の言葉においては、何者も語らず、語っているものは、何者でもないのだ、ただ言葉だけが、自らを語っているように思われるのだ。その時、言葉は、その一切の重要性を得る。言語は、本質的なものとなる。言語は、本質的なものとして語るのだ。だから、詩人に委ねられた言葉は、本質的な言葉と言われ得るのだ。このことは、先ず第一に、語は、自発性を持っているのだから、何物かを示したり、何者かに語らせたりするのに使われるべきではなく、それ自体のうちにその目的を持っていることを、意味する。(粟津則雄・出口裕弘訳、現代思潮社、40-41頁)
日常言語や思考の言語とは、詩のことばは、異なっている。というよりも、詩のことばこそが、言語の本来の姿であり、日常言語や思考の言語は、言語独自の性質が、濁り弱まっているということだろう。
言語は、それだけで自律した体系をかたちづくっているのであり、本来は、日常のやりとりや思考や哲学思想を語るためのものではない。この自律した純粋言語においては、「この世は退き去り、目的は、その働きを止めている」。言語は、何かを表現するものではなく、それだけで、いわば、<純粋な分節化>をおこなっている。
語は、それぞれが、音と象形(「すがたかたち」と読んでほしい)をもつ。そして、この音と象形(すがたかたち)によって、語は、「言語場」とでも言うべき場を開く。そのつど、語が現れると、その語によって、あるいは、他の語とのつながり(文、文章)によって、言語場が開かれる。むろん、語の、その音と象形(すがたかたち)は、たしかに発話者や文章作成者の記憶によって汚染されてはいるだろう。語にまつわる私的な記憶で覆われているだろう。その語という「自己指示の塊」(物質としての言語そのもの)に私的な記憶が付着しているだろうから。
しかし、これは、あくまでも個人的な記憶の被膜であり、それが、実際のパロールの現場(言語ゲーム、言語行為)において、他人の記憶と共通の場を形成するかどうか(意志疎通という幻想)は、まったく別の話だ。語は、それぞれが自己指示の塊である。つまり、他の何かを指示したり表現したりしているのではなく、それだけで完結した音と象形(すがたかたち)なのだ。それを使用する個人、さらに、それを見たり聞いたりする個々人の記憶により、その語の音と象形は、ほかの語の音と象形と関係を結ぶ。
その関係の結び方は、音の類似・対立、象形の類似・対立、意味の類似・対立があるだろう。「おいしい」と「おかしい」・「dog」と「god」、「妻」と「毒」・「上」と「下」、「おいしい」と「うまい」・「おいしい」と「まずい」などなど、その関係は無数にあり、その関係性は、家族的類似を形成している。
いずれも、言語以外の外界や対象との関係(指示や表現)は、そこには入っていない。このような言語やそれを形成する語の本質こそ、詩が生成する場なのだ。詩が言語の極北であるというのは、このような意味である。だから、加藤さんの言う「記憶に沈潜するモノ・コトが文を読むことで浮かび上がり、指示対象として構成され」るというのは、詩の本質を裏側から照射していると言えるし、僚くんの「意味やイメージに隷属しない、「言語固有」の臨界点(消滅点)」というのは、まさに詩の本質であり、つまりは言語の本当の姿であるとも言えるだろう。
三つの詩
こうした観点から、いくつかの詩を見てみよう。
星
その黒い憂愁
の骨
の薔薇
五月
の夜
は雨すら
黒い
壁
は壁のため
の影
にうつり
死
の
泡だつ円錐
の襞
その
湿った孤独
の
黒い翼
あるひは
黒い
爪
のある髭の偶像
(「死と蝙蝠傘の詩」北園克衛)
「星」と「憂愁」と「骨」と「薔薇」は、それぞれ孤立しており、決してイメージを結ぶことはない。そして、その象形も音も何の脈絡もない。詩そのものが、自己表示の塊(詩を構成している語)として投げだされている。詩全体が自律し、自己のみをひたすら表す語群の羅列になっている。見事な「詩」、つまりは見事なことばの透明な姿だと言えるだろう。
あるいは、つぎの詩はどうだろうか。
地上にとどくまえに
予感の
折り返し点があって
そこから
ふらんした死んだ時間たちが
はじまる
風がそこにあまがわを張ると
太陽はこの擬卵をあたためる
空のなかへ逃げてゆく水と
その水からこぼれおちる魚たち
はぼくの神経痛だ
通行どめの柵をやぶった魚たちは
収拾のつかない白骨となって
世界に散らばる
そのときひとは
漁
泊
滑
泪にちかい字を無数におもいだす
けつして泪にはならない
(「みぞれ」安藤次男)
この詩は、ばらばらの自己表示の塊(語)が、投げだされているかに見せて、「ふらん」と「水」と「魚たち」が、不気味なイメージのつながりを潜在させている。そして最後に「さんずい」の雪崩がおこり、自己表示が自己表示のまま「さんずい」に吸収されていく。詩の純粋分節を利用して、「さんずい」という「象形」(すがたかたち)による類似を際立たせた詩だ。意味やイメージが結ばれてしまいそうになるのを「さんずい」という形式(部首)のみで峻拒した詩だとも言えるだろう。
この詩はどうか。
、まだ塊りきっていない、二重人格の、言語を、分裂した鸚鵡が復唱すると、呂律が回らなくなる、人間を、数十年も経過して、死んだ魚が鏡の肉に溶けて、消えない火事に群がる眼玉の距離で、直角の空が崩れる、時刻に、老人がひとり、消えるたび、不安定な中空の、匂いを混ぜて、義眼の水晶体に、指を突っ込んで、流れ出る、汁を舐めている、それが気の毒に思えるようなら、剥がれてずれた電信柱から、遠のいて、足になる、割れた脛に浮き上がる、血管の青さや、ヒールに差し込まれる、爪先を、密かに覗く習慣が、丸ごと飲まれて、口から垂れる、白っぽい泡も、いつのまにか、ひとを、丸呑みにした、くらいには、大きくなって、いる。
(「狂っていくテレパシー(2)~脱落体~」後飯塚僚)
自己指示の塊(語)が、他の自己指示の塊(語)と関係をもつことを毛嫌いしながら、その毛嫌いを、読点という障害物をわざと敷き詰めることによって暗示し、ゴツゴツと自己指示の塊(語)の岩のような硬さ(無意味さ)を強調していく。具体的なイメージはいつまでたっても生産されず、もちろん、何ものも表現されず、自己表示のそのつどの自爆によって時だけが非連続に無慈悲に進行していく。
詩が言語の極北であることを、うまく「表現した」詩であると言えるだろう。