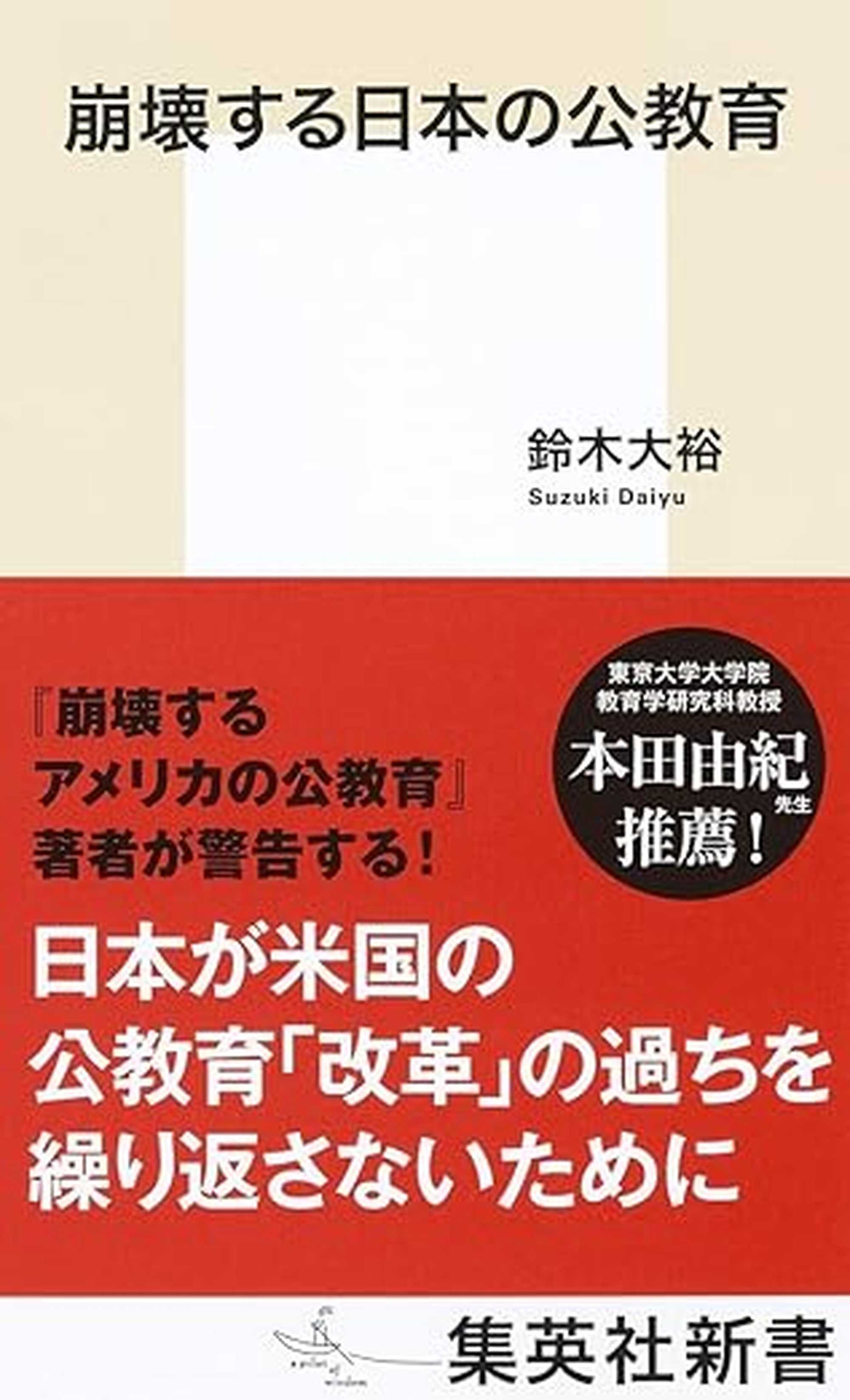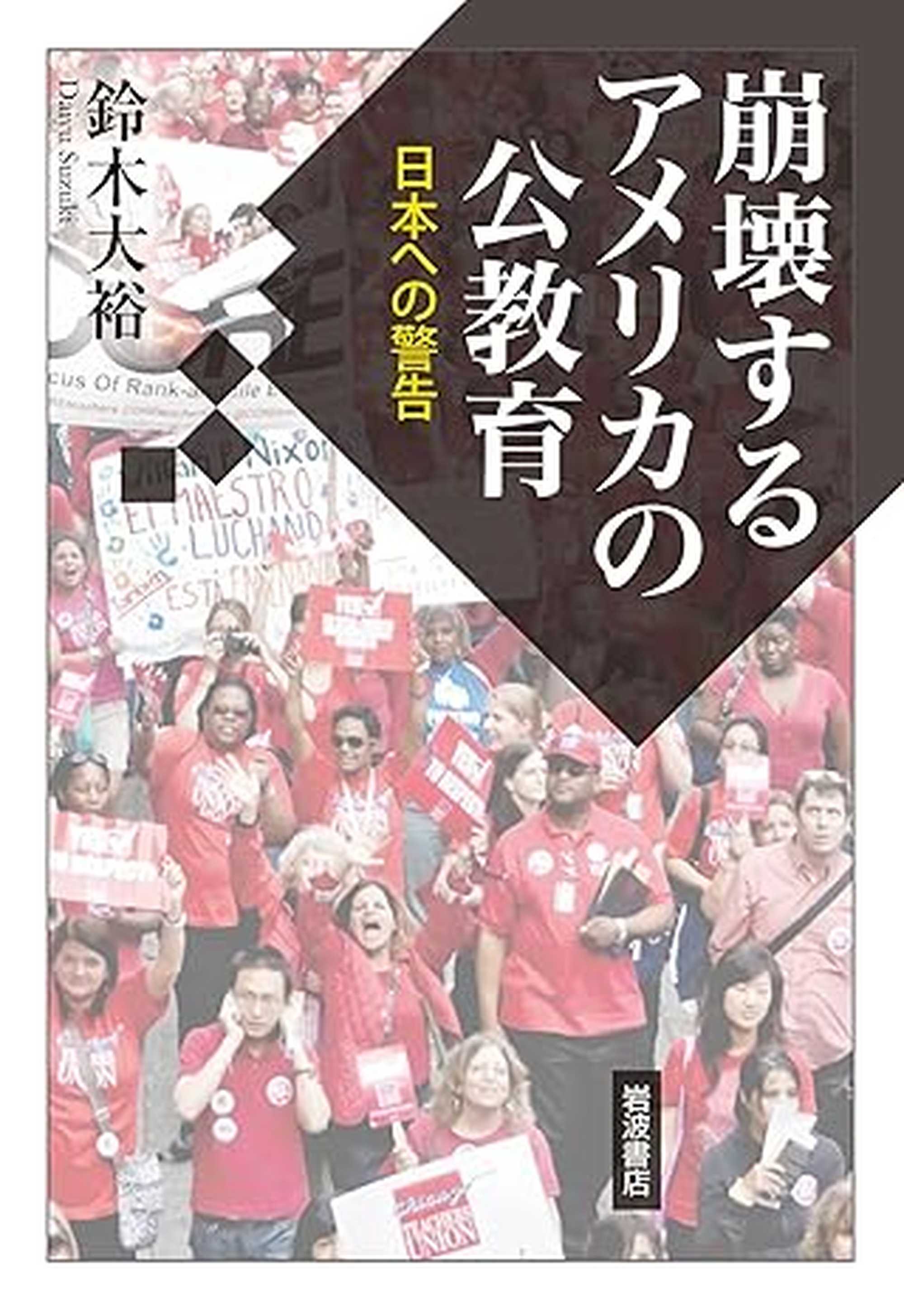学ぶことは生きること
――鈴木さんはいま高知県の土佐町で町会議員をしながら教育の研究をされているわけですが、こうした環境だから気づくことというのは何かありますか。
そうですね、やっぱり地方が本当に再生しないことには、日本社会にしても公教育にしても持続することは難しいと思います。いまの東京の一極集中というのはやはりいびつですよ。あんな狭いところに人がうじゃうじゃいて、こういう自然が豊かで土地があり余っているところにほとんどいないというのはどう考えても不自然です。

環境思想学、経済学、自然科学なども引用しつつ、『崩壊する日本の公教育』の終章でも私は書いていますが、こうした事態の根底には、人間と自然は別物なんだという考えがあると思います。人間を生きものとして見ていないと言ってもいい。その考えがいつ生まれたかというと、やはり資本主義の成り立ちからですよね。近代以降、われわれは農業と工業の境、言い換えるなら生きたものと死んだものの違いを無視し、あらゆる物事を工業的な考えで進めてきました。教育もそのひとつです。この社会が生きものを生きものとして扱わないからこそ、子どもをまるで商品の値札でも見るように、テストの点数で評価することに疑問を抱かないんです。
――大人からそう扱われると、子どもたちもそれが当たり前だと思うようなりますよね。そのなかで認めてもらうには、テストでいい点をとるしかない。
前に紹介した大田堯(たかし)がこんなことを言っています。生きものというのはこの世に一つとして同じものが存在しない。それはDNAによって証明されている。そして生きているすべての者には学びがある、と。
母親のおっぱいをどう吸うか、誰が仲間で誰が自分の敵なのか、食べ物や水をどう確保するか……、こういったことを知らなければ、生きものは生きていくことができない。だから、生きるということは学ぶことそのものなんだと。いまの教育は、ひたすら子どもたちに知識を詰めこもうとしているけど、そうじゃない。そもそも学んでいる命なんだから、教育はその生きようとしている命の支援をするだけでいいんだって。私も本当にその通りだと思います。
私が学校や先生に期待することはすごくシンプルで、学ぶ喜びを子どもたちと分かち合ってほしい、そして学び方を教えてほしいということです。学ぶ喜びと学び方を知った子は、自分でどんどん学んでいきますよ。
――子どもにとっていい先生というのは自分自身が学び続けている先生だという言葉をどこかで読んだ記憶がありますが、学ぶ姿勢を伝えるということこそが教育の本質なのかもしれませんね。そう考えると、先生と生徒の関係をサービス提供者とお客様にしてしまう「教育の市場化」がいかに常軌を逸しているかがわかります。
「数値化」がもたらしたもの
さっき論文を紹介した教育社会学者のアップルは、教育の目的が変われば求められる先生像も変化すると指摘しています。2003年のPISAショック(第2回参照)以降、日本はそれまでのゆとり教育を否定し、詰込み型の教育に回帰しました。そして、教育の目的が、教育基本法の定めている「人格の完成」から、いつしか「グローバル人材の育成」へと転換したことで求められる先生像も変わってきた。いまの学校では、受け持っているクラスのテストの点が良かったり、ICTを駆使して業務をこなす先生が重宝される一方、生徒の心を掴むのはこの人がピカイチという先生はほとんど評価されません。
――単純にわかりやすいですからね、テストの点や単位時間あたりにこなした業務量の方が。でも、私は最近この「わかりやすさ」こそが物事の本質をゆがめ、間違った方向へと導く元凶なんじゃないかと感じています。
そのことは、前にもお話したアーサー・コスタの言葉がまさに示していると思います。「教育的に大事で測るのが困難だったものは、教育的に大事ではないが測定しやすいものと置き換えられてしまった。だから今、我々は、学ぶ価値のないものをどれだけ上手に教えたかを測定しているのだ」と。
いま言われた「わかりやすさ」というのは、突き詰めると数値化だと思います。「人格の完成」という本来であれば可視化することも一義的に定義することもできないものを、テストの点数にすり替えることで比較計量できるようにしてしまった。なぜそうしたかというと、新自由主義にとって都合がいいからです。経済学者のデヴィッド・ハーヴェイは、新自由主義はあらゆるものを数値化しデータ化すると言っています。それによって労働のパフォーマンスを計測し、現場の責任を問うことが可能になり、市場が動き出す、と。
最近よく「説明責任」という言葉を耳にしますよね。これは「アカウンタビリティ」を日本語にしたものですが、この言葉にはもともと「責任」という意味はありません。会社などの財務諸表から来ていて、会社の財務状況に不正がないことを証明できる能力のことを指しています。つまり、「説明責任=アカウンタビリティ」の根底にあるのは不信なんです。
――疑いをかけられたときに、いやいや、ちゃんとやってますよと。
それが新自由主義の要求する「責任」なんですけど、責任は英語だと「responsibility (レスポンシビリティ)」ですよね。で、調べてみるとこの言葉の語源はラテン語にあって、re(返す)―spondere(約束する)―ability(能力)という3つの部分で構成されているということがわかります。
――返す・約束する・能力。
たとえば誰かから物を借りたり恩を受けたりしたときに、それを返す約束をするわけですよね。自分はこうやって返しますよと。それは相手への義務であると同時に自分自身に対するけじめであり、その約束を背負ってまっとうするということ。それこそが「責任=レスポンシビリティ」なんです。見逃してはならないのは、ここでの両者の関係が不確実なものだということです。両者の間には返済の期限や形態を定めた契約書もなく、約束を破ったからと言って法に触れるわけでもない。信頼関係から生じる責任感であるということが大事なのです。
――エビデンスベースドな説明を求められるアカウンタビリティとは真逆の価値観ですね。しかし新自由主義の下で、そのアカウンタビリティこそが責任だとみなす世の中になってしまったと。
もうひとつ大事なのは、アカウンタビリティに基づく「結果責任」の支配が、国家が全国の教室を監視するという権力体制を構築しているということです。ミシェル・フーコーは「パノプティコン」という概念を用いて、権力が人びとを外的な暴力によって従わせるだけでなく、いかに民衆の意識に浸透して内面から行動を規定するかを明らかにしました。「パノプティコン」というのは中心に位置する監視塔からすべての独房を見渡すことができる円形の監獄の設計案のことで、ここに入れられた囚人は監視の目に常にさらされているという意識から、自発的に、模範的な行動をとるようになるというわけです。
教育現場でもこれと同じことが起きていて、それを可能にしているのが全国学力調査です。昔は、様々な「教育改革」が国から降りて来ても、教室のドアさえ閉めれば、先生たちはわりと自由にできていました。しかし学力テストの点数によって学校や教員が評価されるということになると、教員は常にどうすれば点数を上げられるかを考えざるを得ない。学力テストによって、学校の壁も教室の壁もぜんぶ透明にされてしまったんです。
「あそび」の効能
――その話にも通じると思うんですけど、いまの世の中は目的論的な価値観がやたらと幅を利かせているように感じます。テストのために勉強をする・授業をするというのもそうですが、得られる成果を事前に明確にし、そこから逆算して最も効率の良い方法を採用する。それが有効な場面もあることは否定しませんが、すべてを「コスパ」で片付ける風潮には違和感を通り越して危機感を覚えます。
そうですね。いまは本を読む人もどんどん減っていて、ネットの「コタツ記事」で理解した気になってしまう。
――X(ツイッター)やChatGPTなんかもそうですが、いわば要約の文化というか、要点だけわかれば十分と思っている節がありますよね。その方が利用や拡散がしやすいというのも大きいと思います。
いまは楽曲でもイントロがなくなってきています。若者はTikTokなどで音楽を聴くので、短い秒数で「掴む」ためにイントロが消えているそうです。ひとことで言うなら「あそび」のない世の中ですよね、いまって。
昔サモアの島々に住んでいた原住民の酋長ツイアビは、目的と時計に縛られて行動するヨーロッパの白人を見てこんなことを言ったそうです。「ぶらぶら歩き、さまよう楽しみを、私たちを迎えてくれる、しかも思いがけない目標に出会う喜びを、彼らはすっかり忘れてしまった」と。これはまさに、いまの私たちのことですよ。
全国の先生たちはいま、高校の国語から文学がなくなるんじゃないかと危惧しています。2017年の学習指導要領の改訂によって国語科目が再編され、「現代文A/B」が「論理国語」と「文学国語」に分割されました。で、文科省が出してきた長文読解のサンプルを見ると――学習指導要領の改定時には文科省から指導や評価のサンプルとなる資料が出されます――、これまでは小説の抜粋だったり短歌だったりしていたものが、駐車場の契約書とか行政のガイドラインになっていたんです。
――うわあ、最悪……。
要は何の役に立つかっていうことなんですよね。この競争的な格差社会を生き延びようと思ったら、小説より契約書を読める方が現実的には役に立つと。でも、文学は時に、もしも人間がこうなったらどうなるかとか、こういう角度から物事を見たらどう見えるかとか、「あそび」の中で私たちに「現実」から一歩離れてそれを俯瞰することを可能にしてくれる。もし世界がこうであったら……、と。それは子どもたちがこれからの人生や、新しい社会の可能性を想像する上で不可欠なものではないでしょうか。
――おっしゃる通りだと思います。
教育の難しさって、いろんな緊張関係があることだと思うんですよ。子どもの生きようとする力、やりたいこと、保護者が求めるもの、そして国や政治が求めるものという、いろんな引っ張り合いがある。様々な意志による綱引きなんですよね。哲学者のハンナ・アーレントは、「教育の危機」というエッセイの中で、「古き者と新しき者とのテンション」について言及しています。
「古き者」、つまり大人にしてみれば、この社会は自分たちが祖先から引き継いできた歴史や伝統というもので成り立っているわけじゃないですか。それを「新しき者」である子どもたちにメチャクチャにされては困るわけですよ。でも、一方の子どもたちにも自分たちの意志がある。その折り合いをどうつけるのかは簡単ではないし、これだっていう正解もないんだけど、アーレントは、人間というのは常に新しい者として古い世界に生まれてくる。そしてそこには、新しい者しか持っていない“natality”という要素があるんだと言います。私はそれを「生み出す力」と解釈しています。
大人になったわれわれがやるべきことは、この世界の良いところや美しいところばかりではなく、いびつなところや醜い部分を子どもたちに教えることだと思うんですよね。大事なのは、自分たちが引き継ごうとしているこの世界は不完全なんだということを、子ども達にちゃんと伝える。そこにこそ希望があると思うんです。
この話をすると、私の教員時代の恩師、小関康先生は、大人が子どもを持ち上げる「高い高い」がその象徴なんだとおっしゃっていました。普段は見ることのできない大人の高い目線から、「ほら、見てごらん。これが君の生まれてきた世界だよ。君はここからどうする?」って。
突き詰めると、教育の役割はこれに尽きるのではないかと思います。
(取材日:2025年5月30、31日)