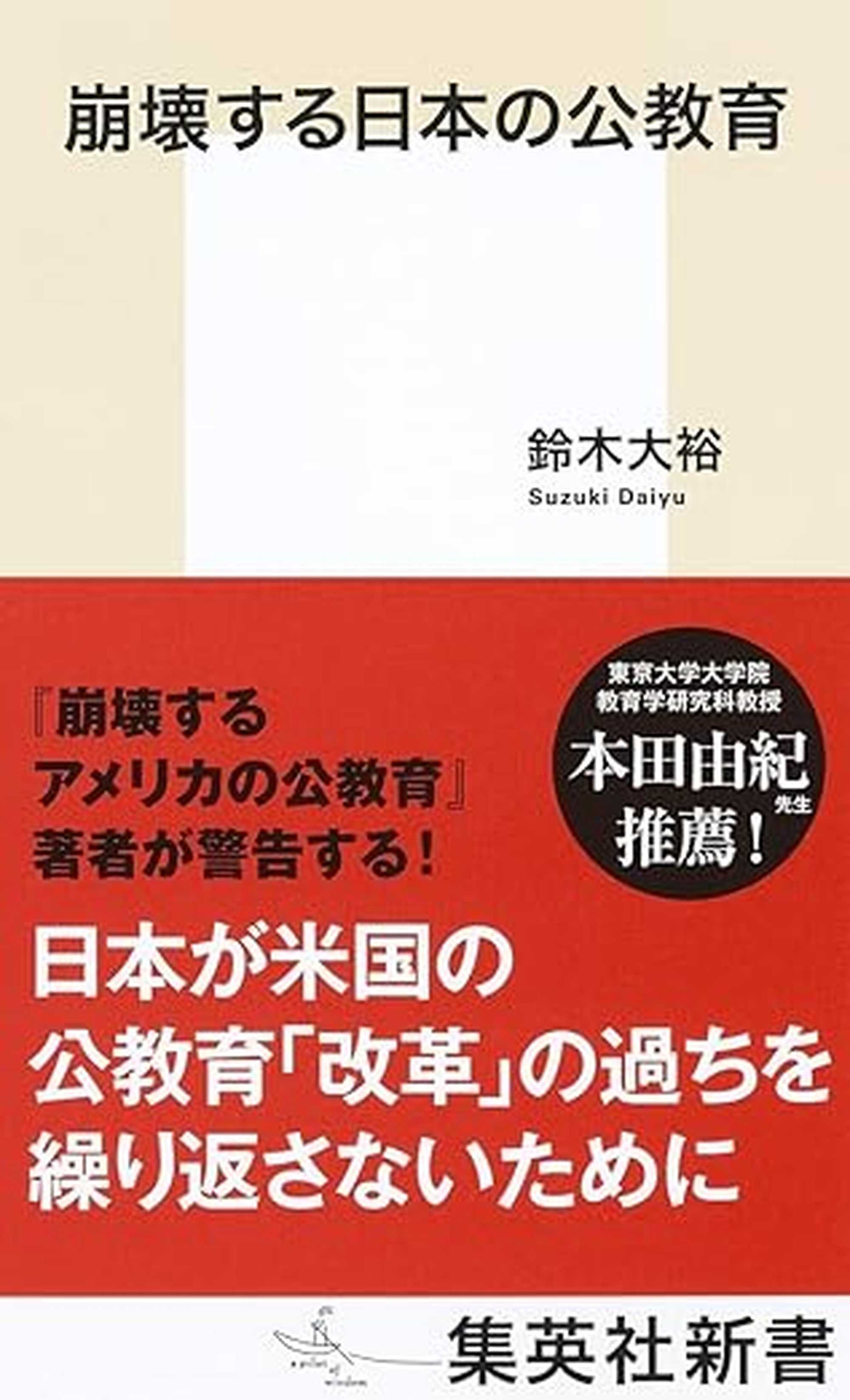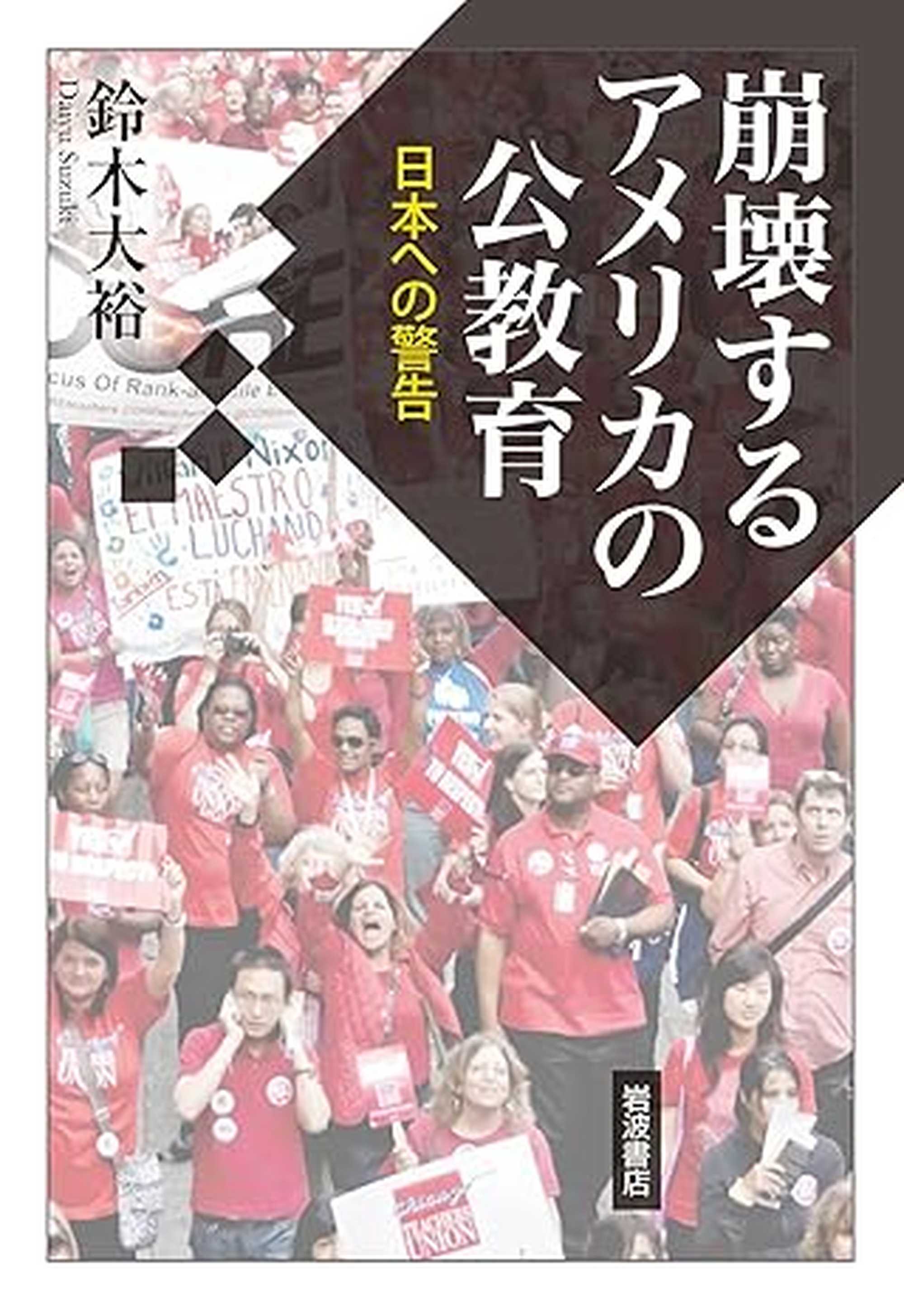「構想」と「実行」の分離
私は教職員組合から依頼されて教員を対象に講演をすることが多いのですが、そのときに必ずと言っていいほど紹介するのが次の文章です。
経済の危機が学校のせいにされ、コンピューター教育など、経済界のニーズに応えることがいつしか教育の目的となり、教員がそれまで培ってきたスキルは価値を失い、「良い先生」像も変化してゆく。多忙化に追われる教員たちは一日の苛烈なスケジュールを乗り切るために、企業によってパッケージ化されたカリキュラムに依存するようになり、自らの仕事に対するコントロールを失った彼らは、強い疎外感にさいなまれ、教員としてのプライドを失っていく…。
これを読み上げた後、「この状況がよくわかるという先生は挙手してください」というとほぼ全員が手を挙げます。そして、「実はこれ、日本でも、ましてや今日の話でもないんですよ。1990年にアメリカで発表された論文の内容なんです」って伝えるとびっくりされるんですね。これを書いたのはマイケル・アップルというアメリカを代表する教育社会学者です。実に30年以上前のアメリカの教育現場で起きていたことが、まさにいま、日本の教室で起きているんです。
私がこの論文を読んだのは大学院生時代ですが、読み返すきっかけになったのは斎藤幸平さんの『人新世の「資本論」』で労働プロセスにおける「構想」と「実行」の分離というマルクス主義の概念に出会ったからなんです。マルクスの文献からは、資本家によって職人から仕事の「構想」が奪われ、業務の効率化によって単純労働の「実行」ばかりを強いられるようになり、大量生産の実現と引き換えに労働者の多忙化が進んだ経緯をうかがうことができます。
――もともとは一人の職人のなかで完結していた「構想」と「実行」が分離してしまったと。自動車の生産でいうなら、どんな車をつくるかというのが「構想」で、それを基にした工場での組み立て作業が「実行」という感じですか?
そうですね。一連の作業が細分化、分業化され、単純作業の組み合わせになったことで職人が消えていったという話なのですが、同じことが教育現場でも起きていると私は思っていて、それを推し進めているのが「GIGAスクール構想」です。これは2019年に始まった文部科学省による取り組みで、小・中学校の生徒一人一人にタブレットなどの端末を配り、インターネットなどを活用した教育環境や学びを実現するというものです。要は、手順に従ってアプリを操作すれば誰でも簡単に授業を展開できるオンラインツールが、いまものすごい勢いで教室のなかに入ってきているんです。
こんなことを講演で話したらある先生から、ずっと抱いていた違和感の理由がわかったと言われました。その方は退職間近のベテランの先生だったのですが、同僚の若い研究主任が、学習支援アプリや健康観察のアプリの活用を推進していて、ずっとモヤモヤしていたそうです。こうしたアプリを使えば、一人一人の活動を教員の画面で集約できるので、机間指導――先生が授業中に生徒の机の間を巡るあれですね――なんてもうする必要がない。健康観察にしてもタブレットで、健康だったら〇、調子が悪かったら×、まあまだったら△を入力するだけなので、「カトウくん」「はい元気です」、「サイトウさん」「はい元気です」なんてやらなくていいと言うわけです。でもそうじゃないでしょって。
机間指導というのは単に生徒がどこでつまづいているかを知るだけじゃなくて、この子ちょっと匂うけどお風呂入ってないんじゃないかなとか、朝ご飯食べてないかもしれないとか、普段は仲のいい二人がよそよそしいから、何かあったのかなとか、子どもの近くに行くことで些細な変化に気づくきっかけを与えてくれる。あるいは、同じ「はい元気です」にしても、その言い方のちょっとした違いに気づかないといけない。そうした異変に気づいたら、どのタイミングで話しかけようか、とその子が一日のターゲットになる。生徒の変化を五感で感じ取って行動するのが教師という仕事なんだ、と言っていました。
でも、ペーパーテストの点数をどれだけ上げるか、という貧弱な「学力」観の中で推進されるGIGAスクール構想のもとで、教師が先輩から後輩へと引き継いできた技術が一つまた一つと失われていってしまいます。現にアメリカでは、「教員の脱技能化」というテーマで数多くの研究がなされてきました。一見便利な教育イノベーションが、教員からスキルを奪い、使い捨て労働者へと変えていく。その結果、学校はますますテストの点だけを追い求める場となり、「人を育てる」という本来の機能が少しずつ、でも確実に失われていくのです。
「働き方改革」の盲点
さっきお話した論文のなかで、アップルたちは、教育現場における構想と実行の分離にはふたつの効果があると言っています。ひとつは「多忙化による教員のバーンアウト」、もうひとつは「労働からの疎外」です。政府がいま進めている「働き方改革」は前者への対応ばかりで、後者についてはまったくと言っていいほど考慮されていません。
最初にアメリカの公教育の崩壊は日本の30年先を行っていると言いましたが、単に崩壊していったのではなく、実はいろいろな反対運動が起きています。そのひとつが教員による抵抗で、ベテランの先生たちが一斉に早期退職するようになりました。それも、ただ単に辞めるのではなく、自分がなぜ辞めるのかをブログに書いたり、子どもたちに向けたビデオメッセージをYouTubeにアップするようになったんです。2013年にはニューヨーク州のある先生が、教育長と教育委員会に宛てた辞表を公開書簡としてネットに載せ、大きな話題となりました。
その手紙のなかで彼は、自分がどれだけ教師という職業を愛していたかを切々と訴えています。素晴らしい生徒たちと出会い、同僚や保護者に支えられて、このしごとが本当に大好きだった。でも、いまのこの状況がはたして教育と言えるのか。自分はもうこれ以上こんなものに加担することはできない。そして、最後にこう書いたのです。「この手紙を書いていて、ひとつ気づいたことがある。それは、私が教職を去るのではなく、「教師」というしごとがわたしを去っていったのだ」、と。
この手紙は全米の教育関係者や保護者の琴線に触れ、拡散に拡散を重ねて、ワシントンポストにも掲載されました。「教師というしごとが私を去っていった」。これこそがまさに労働からの疎外ですよ。一つ言えるのは、働き方改革によって教員の勤務時間を削減したり残業代を支給したりしても、労働からの疎外は解消されない、ということです。
――現行の働き方改革では、先生たちの仕事に対する情熱や矜持が無視されているんですね。
「学校」とはどういう場所なのか、「教師」というのはどういう仕事なのか、というところから議論しなければ、「学校における働き方改革」なんてそもそも進めることすらできないはずです。それをせずに、どうすれば長時間労働を是正できるかということばかり考えているから、授業や生徒指導はマニュアル化され、学校行事は縮小され、部活動は教育という枠組みから切り離されて民営化・商品化される。こういった分野というのは生徒の人としての成長に関わることができる、言い換えるなら、教師にとっての「構想」がいまだにかすかに残っている部分なんです。それをなくしてしまったらもう、マニュアルに沿った「実行」しかない。行き着く先は学校の「塾」化です。
介入を強める行政
――お話をお聞きしていると、教育の市場化というのは社会の変化を受けて自動的に進行したというより行政が先導してきた側面が大きいように感じましたが、教育に対する政治の介入についてはどのようなことが言えますか。
重要なポイントのひとつが2006年に行われた教育基本法の改定です。教育基本法は教育に関する憲法ともいえる法律で、戦前戦中に政治が介入した結果、教育が戦争に加担してしまった苦い経験を基に、「臣民の教育」を国家支配の下に置いた教育勅語からの断絶を掲げて1947年に制定されました。しかしこの2006年の改定によって第10条にあった「国民全体に対し直接に責任を負つて」という重要な部分が削除されたんです。教育学者の大田堯(たかし)は、これによって「教育への(国家による)不当な支配を排除すべきだとする、旧教育基本法の締めくくり条項が封殺された」と指摘し、教育基本法改定は「憲法改定への大きな布石」だと警告しました。
また、これも繰り返しになりますが、「学力向上」というのは文句のつけようがないスローガンなんです。だから全国学力調査なんかも、正面から反対するのは難しい。でも、大事なのは「何をもって学力と呼ぶのか」という本質的な議論がすっ飛ばされてしまっているのです。国語と算数の2教科のペーパーテストの点だけが本当に「学力」なのか、たった2教科の点数だけで全国の学校や教員や生徒を評価するのが妥当なのかは問われていない。
私のよき友人でもある教育学者のピーター・タウプマンは、アメリカで行われてきた新自由主義教育改革にはそれを支える3本の楔(くさび)があったと言います。1本目の楔は「学力」を学力テストの点数に再定義すること、2本目は教員の「指導力」を生徒の点数をどれだけ伸ばせるかというテクニックに再定義すること、そして3本目は「何を教えるか」というカリキュラムの基準を「何ができるようになるか」というパフォーマンスの基準へと置き換えること。ここまでお話してきた通り、日本でも既にこの3本の楔は打ち込まれてしまっているのです。
――状況は思っていた以上に深刻なんですね。この流れを変えていくためには何が必要でしょうか。
端的に言うなら、民主主義の再生だと思います。公教育がなぜこれだけ民営化され、市場化され、商品化されてきたかというと、様々な民主的な討議の場の撤廃による権力の集中があったからです。だからこそ、市民運動を通した民主主義の再生が求められているのです。日本の公教育の崩壊の30年先を行くアメリカでは、あり得ないコラボによる運動が起こってきました。その一つは、「サービス提供者」である教員と「お客様」である生徒や保護者のコラボで、それが現実のものとなったのが、2010年代のアメリカで起きた学力テストのボイコット運動です。
発端となったのは、テスト至上主義に苦しめられていた子ども達の保護者でした。スローガンは、「私たちの子ども達は点数じゃない!」「テスト怪獣にエサをやるな!」でした。つまり、もし子ども達のテストの点数が「通貨」となり、それに基づき学校が序列化され、統廃合が進み、先生たちが評価され、市場システムが維持されならば、テストをボイコットしてシステムを止めようと。
――テストをボイコットしたらその学校の点数が下がるだけじゃないんですか?
ところがそうじゃないんです。たとえば3割の生徒がテストを受けなかったら、サンプルが少なすぎてデータそのものが無効になる。だからボイコットは、システムを機能不全に追いやるいい方法なんです。これに共感する保護者がどんどん増えてきて、私が参加した時にはニューヨーク州だけで24万人が運動に加わりました。
こうした保護者の動きに先生たちも鼓舞されて、テストの監督をボイコットしたり、さらにはストライキですね。私たちはもうこのシステムに加担できないと言って教員ストを行い、それを、いちばん被害を受けるはずの保護者が支えた。さっき紹介した先生の手紙もそうですが、こうした一連の動きがきっかけとなり、教育のあり方が本当にこれでいいのかということを、もう一度、多くの人が考えるようになったんです。