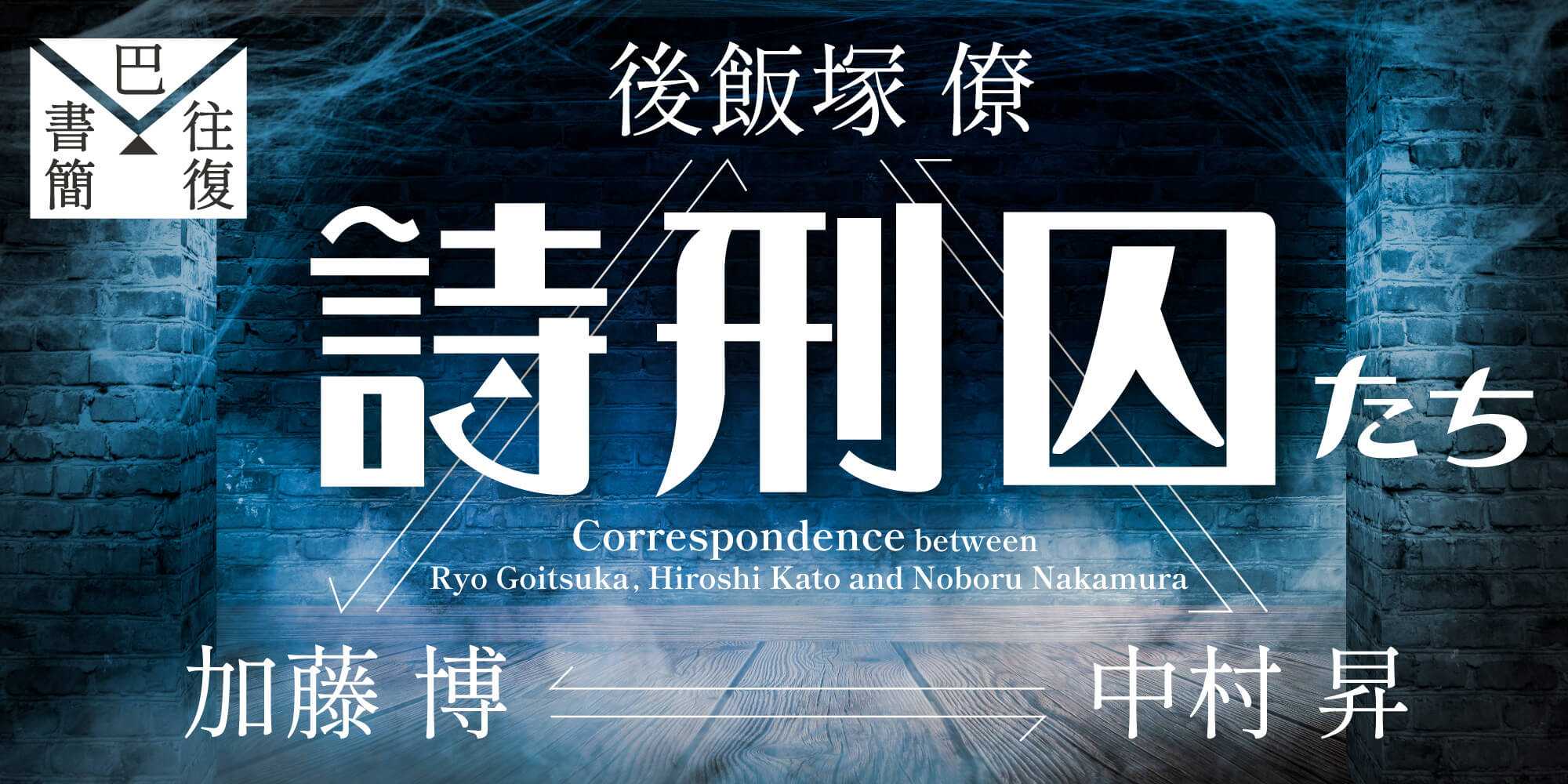序にかえて
“トイビト”には似つかわしくもない、とんでもないタイトルの私の詩作品から突然始まった本巴往復書簡も、加藤さん、ノボルさんの「言葉」と「詩」についての専門的な考察もあって、ひとまず、軟着陸したような気がして、ホッとしている。今回、三巡目に当たることから、問題提起することになった詩作品(吃音体、脱落体)の当初の執筆意図と今回の作品(幼形成熟体)の関連について少々説明させていただくことにする。
まだ単行本として発表される以前、「新劇」(1977年8月号、特集「舞踏 魂の棺」、白水社)連載中の『病める舞姫』(連載5)を読んで、これが現代詩の最先端である、と異常興奮して以来、目黒アスベスト館での生身の土方巽体験を経て、言語表現の面から、それを継承・発展させ、現代詩として甦らせるべく、今ここで、キーパンチしている。つまり、この「狂っていくテレパシー」というタイトルの元に発表される連作は、私にとって初めての公的な詩的言語実験であり、その根源には私の骨身に染み付いた土方巽の言語世界があると考えて頂きたい。
まず、本連載を開始するにあたって、そんじょそこらにはない過激さで、高速度で突っ走る、土方巽を知らない人でも「読める」詩作品を用意することにした。実際、加藤さんの回で指摘があるように、『病める舞姫』は豊穣な詩的言語により構成された作品であるが、それを最後まで読むことは(理解する以前に)至難の作品である。そこで、同レベルの難解な文体を用いて、それを「読める」ものにするために、括弧で括られた会話(正確には脳内のテレパシー)と読点の多用を用いることにした。
ノボルさんが括弧と読点の存在のことを「優しさ」と表現してくれたが、難解な詩が読まれるためには、文字列自体が一定のスピード(速度)で読まれる、つまり、「時間が流れる」必要がある。将棋倒しをイメージしてもらうといい。駒の一つが揺れて傾いて、隣の駒に触れると、それが傾いて、次の駒が傾き、それが連続して、最後の駒が倒れ、勝手に時間が経過して、最終地点に連れて行かれる。
括弧で閉じられた会話は言葉のやりとりなので、静止することができず、揺れて(吃音)、そのうち、つんのめって、倒れてしまい、読点でみじん切りにされた文字列は、意味やイメージを形成するかと思うと前に倒れて、次のイメージへ雪崩込んで、自己破壊を繰り返し、最後に至る(脱落)。七五調は遅すぎるし、韻をふむのはダサすぎる。
以上が、しょぼい手の内の種明かしだが、それが成功したかどうかは読者の判断に任せるしかない。そして、今回紹介する「幼形成熟体」は、20歳の頃(1980年)に書いた文章をもとに、加筆、再構成を加えた「詩」になる。ここには土方巽から学んだ私なりの詩的言語の原型があり、それは現在に至るまで何ら変わることがない。
幼形成熟体
感情に先回りされて、泣くことも笑うこともできなくなって、地蔵になった子供の顔がよく見受けられ、その透明な明るさの内へ、一匹の紋白蝶が迷い込んでくることもあった<チンパンジーに、バナナやると、分裂病になるらしいですよ>しかし、それよりも、暗さとしての黒揚羽の飛来を待ち望んでいる節もあった、何かしら紙一枚で止血されているような空間が偏在していて、そこから、紅いものや黒いものがチラチラしている、呼び込めば言葉になりそうなものが、そのまま、延々と背骨を晒している、そういう後ろ姿には今日や明日が一本背負いを喰らわされているのか、不遜な述語がぶら下がっていたりする<チーターも、病気になるらしいですよ、だから、シマウマを一緒に、いれておくんですって>心持ち身体を湿らせながら、物事の脈絡を、指を折って、数えてみると、欠落していくのは、形だけで、次から次に抜けていく本質は稚拙な頭の中には、なかなか、帰ってこない、なぜなら、物事とは裸足で帰ってくるものだからである。
平然とした顔で、不吉な茶柱を立てている、昨日の残像が化身して、「ただいま」、「おかえりなさい」、そんな言葉のやりとりをしている、それには、二枚下着を履いているような、いかがわしさがあって<ネコ科のなかでも、弱いんですって>疲労の形式はいつも、黒い犬の形となって現れる、その黒い犬を連れて、全てが「ごめんなさい」で済んでしまう世界から、川の堤防を歩いてきた<で、シマウマは、蹴るでしょ>子供というのは、よく片足で立ちたがる生き物だが、ビラッと風の中で、捲れ上がるスカートには、ピッチカートが打たれていたりする。
そういえば、音楽教室があって、神経が失調して、赤子をボロボロと産む先生がいた<だから、追いかけっこするんですって>血は水の中で拡散しないだろう、出会いは、眠りの中で、完了しているので、子供も成長すると、どこからか、何かを拾ってくることを覚える、そういうふうにして、拾われてきたものが、子供に代わって、成長している<それで、チーターも病気にならない>優しいものには、疑いが抜き差し難く付着して、秤量されて成長してきた、それこそが、過ちの始まりだったのかもしれない、ふたつのものが、ひとつになったり、また、ひとつもなくなったりして、存在する、というような許され方が、もう、ありえないのか、全てを「ごめんなさい」で、片付けてしまいたい、などという物忘れも、ありえたのだ。
偶然、他人が骨を折る音を聞いたが、それが病みつきになって、身体中の骨を残らず叩き折って、酸素をストローで吸っているような発育を、何度か繰り返してきたわけだが、その度に、手を抜かれて、いや、手を抜いて、発育したためか、後ろ指や寝首などという、忌まわしい器官に代用されている<玉虫、捕まえましてねえ>そういう手続きを必要としない身体は全て皮膚にして、一緒に育ってきた骨格の人体模型に着せてしまって、借用したものだけで済ませている。
細い糸のような夢の先端はバラバラに砕かれていて、やはり、ここにも、海藻のようなものが巻き付いている<死んだやつですか?>病的なものだけが、けたたましく残っている唖の少女の唇に、煙のように吸いついて、そのまま、気の遠くなるほど、息を吸い続けて、彼女の桃色の鰓を干からびさせてしまったのだった、知恵の輪という、拷問具を与えられて、病みつきになった、意識の濡れた形態に歯型をつけて、白衣を着て、タッタッタッと走っていると、向こうから、虫取り網を持った桃色の襦袢を肌けさせた看護婦や医者が駆けてきて、泥の中で陽気に跳ね回っている、そんな精神の光合成も取り込まれていたのである<いや、飛んでるやつ>老婆が白目を剥いて入れ歯を咥える瞬間や、その柔らかい歯茎で、うどんをプチッと噛み切る時間のまわりから、この存在は濫造されてきたのだろうが、その頃から、頭蓋骨は異様な歪みを持ち始めたのだった。
まだ子供が犬や柱と真っ黒焦げになって、癒着して暮らしていた頃、もしかしたら、それは世間話が形而上化されてしまったのかもしれない、あることとないことの区別がない世界では<ぶ~~ん、ぶ~ん、って、飛んでるでしょ>体温だけがいつも犬の身体と一定に保たれていたので、余計なものは余計なものとして、また、余計なものとなって、暗い天蓋の直下をいろいろな品物が商品化されていった、つまり、全ては店頭に晒されているということで、商品とは店頭で黄昏ているものたちのことだった、だから、どんな商品も体温以下では取引されない<それで、カバンに入れておいたんですけどね、逃げられちゃいました>濁った唾を吐いて、白目を黒くさせている、他所行きの身体が電気的に中性であるように、ひとりがふたりほど存在して、自己同一性を失調しているのだった、帯電している犬や猫を認識したいという欲望はどこか、夢を垂れ流しているような存在臭がする、泣きも笑いもせず、そこで糞と夢を一緒に垂れ流しているような子供でもあった。
新しい歌覚えたか、これがひとつの呪文になって、頭脳線のない女が海亀を仰向けにして記憶を刈り上げている夕刻では、一匹のカタツムリが蒸留されて、不思議な第一印象が深呼吸をしている気配を翻訳して、頭蓋を擦り潰すような歯軋りをする<けっこう、いるみたいですよ、去年は二匹、捕まえましてね>それだけで意思が通じるのか、といえば、蠅叩きを握って振り回すほかはなく、筋道から外れていく産声を言語というのなら、流行歌を中断させながら、溜息を結晶させることが、真面目な悲鳴なのであって、同時に視線を直進させない物質の恥じらいの只中に蜘蛛の巣を張って、月の出を待ち伏せしている不条理な熱病に感染して、神様の声を吹き替えているのか、この病院の中で、陰険な影踏みの習慣を流行させている、その異常に肥満した影が水栽培されているような少年の心配が、膨れ上がっている。
トイレの中で息が切れる、そんな疲労の仕組みだけが無意識のうちに染み付いて、自分勝手な老化を続けている、人格の半分は女湯に引きづり込まれて、育てられてきたせいか、声の出ない真っ赤な喉笛を欲しがったり、盲目の少女に言い寄ったりして、再発という不吉な観念の裏側で、日光を腐らせては、その黄ばんだ光の中で、朝飯をおかわりする、悲劇的な食卓のように、ご馳走様のない世界で、残忍な田植えを繰り返している<それで、宝くじ、買うことにしたんですよ>そこでは、「時々息をする神様」が病院の中をたらい回しにされて、ひとり過剰に聖化しているから、目を瞑ったまま、犬を口説いたりすると、それが果たして暇潰しなのか、それとも一大事なのか、戯れに知恵の輪を与えられた幼心のように衰弱して、その、よく腓返りの起こる魂が終末に足し合わされて、そのまま奇跡の人として硬直している。
精神はというと、真夏の砂浜で西瓜割りにされて散乱しているので、額に蝉を止まらせて、気が狂うまで、ぢいぢい鳴かせている<最初から、買う番号決めてたんですけどね、三枚だけ>それは、身体の中に、ひとり時間差を使って、古びた盆踊りを回復している、潜水の得意な魂に似て、肉体と精神が不幸な結婚式を挙げた格好で、予報されてしまった颱風が迷子になっている、その颱風に視線が介在すれば、表情の奥の風景の時差が順々に裏返しに仕立て直されて、一方的な思い入れのうちに、健康な頭部を妊娠させてしまう、だから、鰯の小骨を箸で選り分けるような神経質な食事や下着を重ね着するようなランダムな発作が瞬く間に、塵紙と交換されていくような日常でもあった。
食ってはいけない道草をなぜ食うというのか、わからずに、また、それを疑問に思うほど頭がよくなかったのか、風船ガムを口いっぱいに頬張って、当たり外れに狂喜しながら、神様を追いかけていたのだったが、いつしか、その青白い坊主頭にも変色し始めた時間の螺旋が捩じ込まれているのだった、「死んでから手術すれば痛くなくていいわよ」、そんな呪文めいた声がどこかで囁かれ始める頃になると、限りなく肥大してしまった影法師の前に立ち竦んで、なぜかひとり謎めいてくる<でも、アキヤマさんが、十枚買おう、って云うもんですから、零から九まで、十枚買ったんですよ>それは現像されたばかりの差出人不明の現実がどっと出前されてくる夕暮れ、つまり、「おまえは馬鹿なのだから」と言われて、それ以来、馬鹿になって暮らしてきたような気配が馬鹿であることにうんざりして、ひとり不条理に悪化しているのだった。
不思議な右手がサッと走って、縁側に静脈が浮かび上がるような小春日和、肉体を電車の中に忘れてきたような魂が風呂に入ると、骸骨になって帰ってくる、箸のグラグラッとする滑りが、沈黙に蝕まれた顔の淵に、白い米粒のようにこびりついている<それが、当たったんですよ>ほの白く肺が縮んでゆき、額にはまった目玉で、足の裏に顔を写したり、その言葉が計量されて、足し算されてしまったら、もう終わりだ、というような感情<いくらですか?>迂闊に声を出すと、その声が選び取られてしまう、泣きたいような手触り、それが、泣きたくさせる感情、そんなものが蚊取り線香の中に溺れていった。
誰にも看取られずにひとりこときれるような夕暮れ、気狂いじみて、割り箸を裂きむしると、手のひらのなかに顔を作って、味のしなくなった笑いを口から出して伸ばしたり丸めたりしているのだった<一万円、で、当たったのは、最初考えてた、三枚だったんですよ、でも、十枚買ってですからねえ>胡座を裏から組み直して、足の先で顔をチラチラさせて、買い物されてしまう、日向ぼっこしていた神経の群れはいつの間にか消えてしまった<一枚いくらですか?>コップを見ていると見ているうちに、そのコップが取り巻かれている空間に溶けてしまう、形容詞などいらない貧困の形式は白い犬である。
目とは暗い穴で、その奥から誰かが覗いている顔の庭を獣が歩いている<三百円>猫が床下に潜り込んで毛を生え替わらせているのか、黒い髪の毛のような雨の降る午後は、時々物忘れの速度が速くなって、風を脱いでいく、新しい下着が皮膚を噛んで、狂気が整列している畦道を、完全に消毒された自分の陰にのめり込むようにして歩いている<じゃあ、もっと、玉虫捕まえなきゃ>次第に無機物に変わりつつあるのを意識して、花の中の雑音を忘却し、衰弱した緑色に混入する鏡面には無数の神様が付着している、そして、ついに無限に切断しうる花弁の中で溺死しないヒヤシンスがガンと咲いている花壇を蛋白質な人が歩いているのだった。
内股にびっしり静脈が浮き上がると、食い残しの骨と蛙の水かきが散乱した畳の上に、すっかり、ばかになって放尿している、そんな嘘のように買い物されていく雰囲気が、搾りたての牛乳のまわりで処刑されて、次々に神経を仏にかえている<で、話は変わりますが、忙しいですか?>それが他人の笑いを全部噛み殺してしまうので、漬物にした人間の脂身のところだけ、まよねえずをかけて食べたいと、親を扇風機の前に置いておくと、二、三日で血縁が切れる、だから、まっぷたつに裂いたわりばしの前でオドオドするような出鱈目は頭ごなしされて、近眼の少女を便所に追い込むのだろう、鯉のぼりの柱に縛りつけたマグロを、そろばんでしばきまくる母親もいた、そういう歯茎がぐらぐらするような美人が洗面器を抱えて、本能だけで生きている精神の腹痛がある。
遊んでいる双子は夏の汗に絡まって、ひとりになってしまう癖がある、それを背中からバリバリ剥がして砂場に戻してやる、そうすれば、下校時間になると、少し知恵の遅れた男が小学校の校門の前に佇んで、びっくり玉や手品を披露してはそれを売るでもなく、そこで時間を過去に変えているだけの人攫いに、いつの間にか入れ替わったりもしたが、卍にもつれた風に吹かれてしまったのか、橋の欄干から干涸びて水のない川底に飛び降りることが子供たちの間では優先された<そいでね、私はやらない、かわりに、やってくれませんか>その頃は人殺しを二、三人殺して、自分も自殺して、翌朝生き返るのは誰か、炎天下に並べられた棺桶の蓋を片っ端から開けて、死顔を覗き込めば、笑う顔のひとつやふたつはあって、身体の消えてしまった棺桶には西瓜を載せて叩き割る、そんなかくれんぼも子供の儀式ではあった<それが、うどん屋のようなチラシでね>今、聴こえている声も、耳鳴りだろう、鼓膜の擦れる音、口の中で、ぬちゃぬちゃになった、粘液の音、虹色の影に暗算される過去は、喉仏のあたりでうたた寝している、二枚舌を切ってやると、尺取り虫のように、地面を這いまわる<お品書きってことですか?>ので、それに、虫眼鏡で光を集めて煙を立てている、少年の背中には、真っ黒い影が貼りついて、それが、大人のかけた催眠術のように地面に広がっている、墨汁を振り撒かれたようでもあり、なにかの暗号のようでもある<いや、うどんみたいなんですよ、字が>そんな子供が、真昼の砂場に集まれば気化してもおかしくはない、無数の黒蟻が蠢いているだけの、その暗号を、不条理な数字に置き換えて、指で数えれば、日が暮れる頃には街角に女が立つだろう、赤の標示のまま、青になることは決してない、いつもの信号の下である<それで、うどんでも作ろうかと、思ってるんですがね>昨日の約束は、そうやって忘れ去られていく、歩き過ぎて、通り過ぎてしまう背中のようである、その背中が人混みの中に見えなくなるまで手を振り続けている、その姿もやはりまた背中だけで振り返れば何もない。