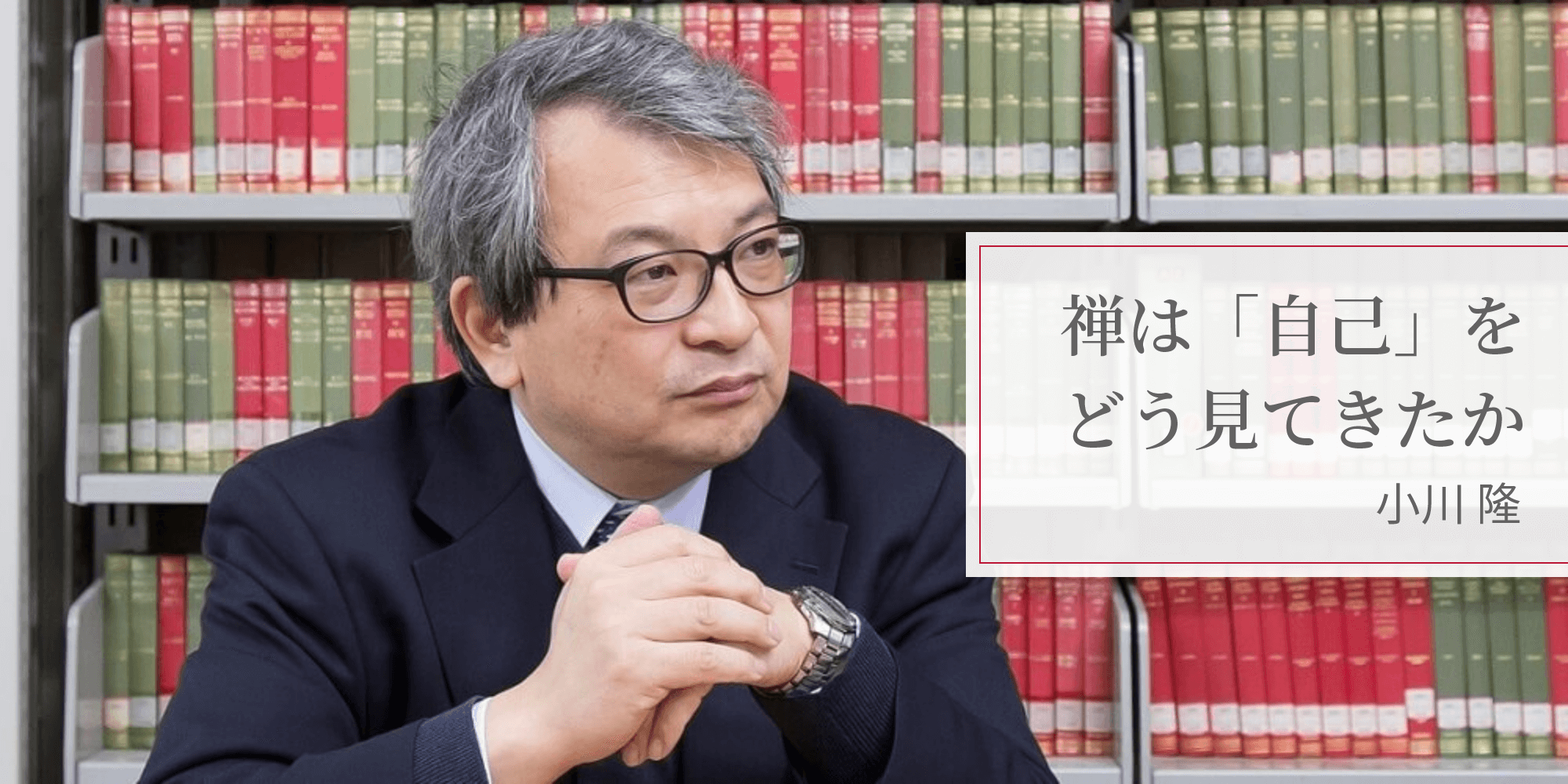――禅では本来の自己と現実の自己の関係づけが、「梅干しおにぎり」「五目おにぎり」「天むす」と変遷していったわけですね。
変遷といっても、後のものが前のものを淘汰していったわけではなくて、新しい考えが加わっていったと言うべきですが、ともかく、禅の歴史はこれで終わらない。次は唐の次の宋の時代の禅。宋代にもいろんな禅があるんですけど、最終的に主流を確立したのが、大慧(だいえ)の看話(かんな)禅。これはさっきの三類型でいうと「梅干しおにぎり」に立ち返る。
――仏性の梅干しと煩悩のご飯の二分法ですね。
いろんな思想はあるけど、結局、生身の人間は迷っている。煩悩と共に生きている。理念としてすべての人が本来仏なのは間違いないけど、現実の人間が迷っていることもまた間違いない。であるなら、やはり生身の自己を克服して悟りを開き、本来の自己に立ち返ることが必要だと。そうやって本来の自己に立ち返ってみたら、そこではじめて、本来ありのままで仏だったと言える、そんな考えです。
――禅が先祖返りしたって、ことでしょうか?
いや、構造としては最初にかえったんだけど、ご飯を克服して梅干しに至る手段として公案という新しい方法が生み出された、そこが宋代禅の特徴でした。宋代でももちろん坐禅をしないわけじゃないけど、坐禅だけで悟れるとは考えなかったようです。
――坐禅から問答になって、最終的に公案へ。でも、それによって悟りが均質的なものになってしまったとも書かれていますね。
それは僕の考えではなく、大拙博士(編注:鈴木大拙)が何度も書いておられることですけど、公案の功罪っていうのかな……。
唐代の禅っていうのは、偶発的な、自然発生的な問答によって悟る。悟れるかどうかは、本人の資質と偶然のきっかけに依っている。たとえるなら、職人になりたい人が親方の下で徒弟奉公するみたいな感じ。技は習うもんじゃなくて盗むもんだ、とか言われて、叩かれたりしてるうちに、身に付く人は身に付くけど、駄目な人は駄目。
それが宋代になると公案という教材を使って、一種のカリキュラムに沿ってやるようになる。技術者養成の専門学校みたいな感じですね。手順通りにやっていけばある程度の確率で悟れるようになり、修了した人はみんなある水準までは行ける。その代わり天才が出なくなってしまったと。
――カリキュラム化されたことで、80点の僧侶がたくさん出るようになったってことですね。
大拙博士は、公案ができたせいで悟りは人工的で小さなものになってしまった。しかし、もしも公案がなかったら禅はとっくに滅びていただろうと、愛憎相半ばみたいな感じで書いておられますね。
――なるほど、禅にも時代的な変化や分岐があったことがよく解りました。でも、そういう変化や分岐を捨象して、すごく簡単に言ってしまうと、悟りというのは、要するに、自己が仏であるということに気づくということでしょうか?

そう考えられていたと思います。悟りによって何かが加わったり、何かが変わったりはしない。本来仏であるという活きた事実に目覚め、そこに立ち返る、ただ、それだけでしょう。
たとえば、唐の時代に石頭という禅僧がいました。小僧の時、かの六祖の最晩年の弟子でした。六祖の没後――そこにも、いろいろ物語があるんですけど――ともかく、六祖の遺言にしたがって、六祖の高弟の青原(せいげん)という人を尋ねていった。青原がドコから来たんだと聞くと、六祖の処から来たという。そこで青原は、六祖の下で何を得てきたかと問う。すると石頭は、六祖の下に行く前から、何も失ってはおりませんと答えた。つまり、六祖の処で新たに得たものは何もない。何も得ていないどころか、六祖の処に行く前から何も欠けたものなどありませんでしたって。じゃあ、なんで、わざわざ六祖の処になんか行ったんだって青原がきいたら、石頭いわく、六祖の下に行っていなかったら、何も失っていないってことが分らなかったでしょう、と。
禅の悟りってそういうものだったんじゃないでしょうか。悟ることによって何かが加わるとか、足されるとかじゃなく、元から何も加える必要がない、十全であるという「事実」に気づく。だから、気づいちゃったら、気づく前と同じ。
――その気づくための手法が、時代によって変わってきたと。
そう。
――手法はともかく、最後はありのままで仏だということに気づくんですね?
いや、いや、言葉尻をとらえるようだけど、そこで「ありのまま」ってつけちゃうと、ちょっとまずい。「五目おにぎり」の馬祖禅では確かにそうです。でも、それだけじゃない。「ありのまま」で仏だったら何もしなくていいや、という人がたくさん出てくる。それに憤った人たちが、「ありのまま」じゃダメだということを強く打ち出すようになる。
でも、馬祖の弟子の中から馬祖禅に対する批判が出てきたように、石頭の門下からもやっぱり石頭禅に対する批判が出てきます。二にして一、一にして二なんていうややこしい考えに内向しているうちに、活き活きと現実にはたらき出る生命力を失っているんじゃないかと。洞山にも師事したことのある巌頭(がんとう)という禅僧は、洞山の真価を認めながらも、こう言っています――洞山はりっぱな仏だけど、ただ、光が無い。禅の思想史は「ありのままに生きる」という考え方と「ありのままを超える」という考え、その二本の対立軸の間を往復しつづけた歴史だったと思います。
――宋代になっても、そうなんですか?
ええ、そうだと思います。ただ、宋代には、円環の論理によって両者を包摂する、整合的な説明が与えられるようにはなりましたが。
――「円環の論理」と言いますと?
「悟りおわらば、いまだ悟らざるに同じ」という禅語があります。悟ってしまったら、悟る前と同じだったと。少し前に「人生が360度変わるな」っていう新聞のコマーシャルがありましたけど、禅ってあれなんですよ。0度の「ありのまま」を突破して一切は空だと悟る。「ありのまま」を超えて、世界観を180度反転する。しかし、それをさらに打破し、さらに180度反転する。すると、結局「ありのまま」にもどる。つまり、世界観を360度転換するんです。
――0度の「ありのまま」でなく、360度の「ありのまま」ということですね?
ええ、有名な『十牛図』は、この宋代禅の円環の論理を視覚化したものにほかなりません。むろん、そういう考え自体は、さきほどの石頭の話のように、唐代から潜在的にはあった。宋代にそれが、整合的なひとつの図式として可視化されたってことかな。
ただ、これはあくまでも説明というか、図式化であって、実際の人間の問題がこの説明でめでたく決着したかといえば、疑問です。実際にはそれぞれの禅者が「梅干しおにぎり」「五目おにぎり」「天むす」、そうした種々の思想や行法の間を行き来し、あるいは相手や場面によってそれらを使い分け、使いこなす。そんなふうになっていったんじゃないかと思います。
圜悟(えんご)という宋代の有名な禅僧は、タライのなかを珠が転がるように180度と360度の間を自由に行き来できなければダメだという意味のことを言っています。日本の白隠禅師の禅は、おそらく、禅の歴史上に現れたそういう各種の思想と方法をみんなとりこんで、壮大で精緻な一つの体系に組み上げたものだったんじゃないかと想像しています。
――歴史上にいろいろな「悟り」の形があったということは解りましたが、じゃあ、けっきょくのところ、どれが禅の究極の「悟り」だったんでしょう?
またまた言葉尻にこだわるようで申し訳ないけど、「究極」っていうのも、違うような気がします。禅の悟りにはゴールがない。ゴールだと思ってそこに居つくのではなく、次のものによってそれを乗り越え続けないといけない。悟りというのは到達点じゃなくて、永遠の運動なんじゃないかと思います。自己を根拠に真理をのりこえ、真理を根拠に自己をのりこえてゆく……。あくまでも、禅の古典を読んでの感想にすぎませんけど。
悟った後にどうするか
悟りとは何かってことが気になるのは、当然だと思います。でも、禅者にとって重要だったのは、必ずしもそこではありませんでした。昔の語録を読んでゆくと、いかにして悟ったかということと、同等か、あるいはそれ以上の重みで、悟っちゃった後、いかに悟りを忘れ去って普通に生きてゆくかって問題が、大まじめに追及されているんです。
――えっ、 そうなんですか?
ええ、悟ったことはおろか、修行もしたことのないぼくなんかには、とても共感も実感もしようがない問題意識ですけど……。でも、昨年、鎌倉円覚寺の横田南嶺老師の講演をうかがう機会があったんです。「如来禅と祖師禅」というテーマでした。たいへん精緻なお話でしたが、その趣旨を自分勝手に乱暴に単純化してしまうと、悟っているのが「如来禅」、悟りを脱ぎ捨て、踏み越えてゆくのが「祖師禅」だということだと思いました。
そのときの老師のお話とお姿から、ぼくも感じたんです。ほんとうに身をもって道を修めている人にとっては、悟りを忘れ去るとか「悟り」を踏み越えてゆくいうことが、ほんとうに切実な現実問題なんだなって。
――うーん、それは、どんな感じなんでしょうね? 悟りすら忘れ去るということは、頭や心の中に何も無くなるということなんでしょうか?
いや、悟ったことがないので何とも言えませんが、禅の語録で見る限り、その逆じゃないかと思います。
――逆といいますと?
たとえば、さきほどお話しした洞山。川を歩いていて、二にして一、一にして二、という自己を悟った。そこで顔色がさっと変わって、からからと大笑いしだした。いっしょにいた兄弟子がビックリして、どうしたんだってきく。すると洞山は、亡くなった老師の教えが、今やっと分かりました、と言う。そこで兄弟子が迫るんです、悟ったのなら、ここで一句言え、と。洞山はそこで偈(げ)を詠んだというのです。
――洞山が本当に悟ったかどうか、兄弟子がテストしたってことですか。
というより、自己完結しないようにってことじゃないかな。言葉にするということは、どうしたって、現実の世界の問題になる。さっきの運動の話にもつながるけど、悟りの世界に居つくことを許さないという意味があるんだと思います。
――行ったままじゃなくて、ちゃんと戻ってこいと。
戻ってくると、現実のもろもろの事物の制約を受ける。だけど、そこをこそ生きていかないと駄目なんだってことじゃないかと思う。
――それはちょっとわかる気がします。
その洞山の師匠が雲巌(うんがん)っていう人なんだけど、洞山が老師になった後に、弟子がきくんです、「雲巌老師は悟っていたんでしょうか」って。伝記には雲巌は悟ってなかったという話があるから、それをふまえての質問でしょう。すると洞山は、「悟っていなければあのように言えたはずがない」と言うんです。
――悟っていなければ、わしに真実を示せたはずがない、というわけですね?
そう。でも、それだけで終わらない。それから、また、こう言うんです。「悟ってしまっていたら、あのように言ってくれたはずがない」と。つまり、悟りの世界を知らなければ真実は言えない。でも、悟りの世界に行ったきりだったら、真実を言葉にしてはくれなかったはずだって。一句言えっていうのも、そういうことを要求してるんじゃないかと思います。