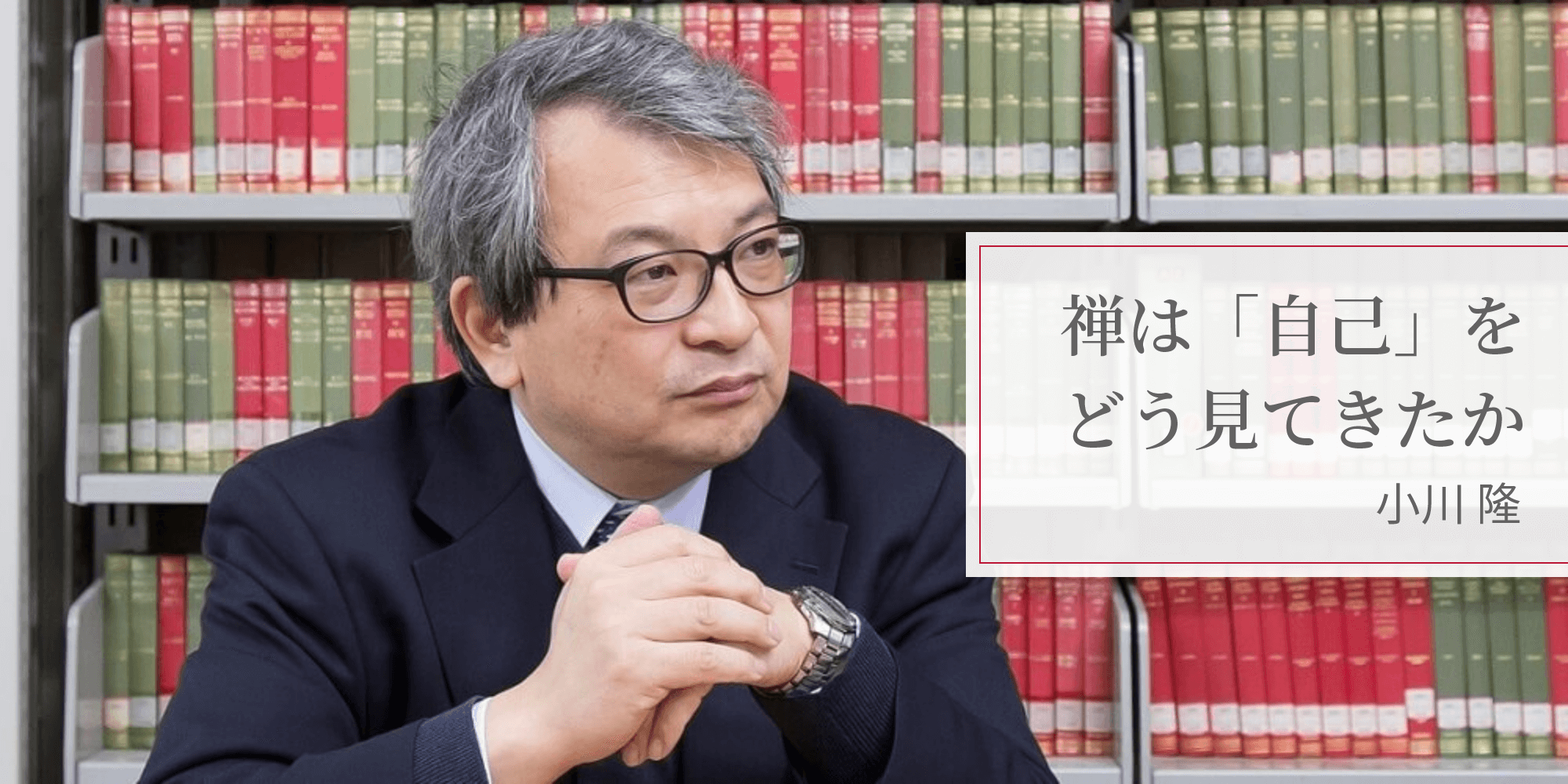――ここでちょっと20世紀の禅についてもお聞きしたいのですが。西田幾多郎や鈴木大拙は明治以降の文明社会への対抗原理として、西洋列強諸国に対する日本人のアイデンティティのひとつとして禅を捉えていたのではないかとのことですが、その西田や大拙の考えとはどのようなものだったのでしょうか。
日本の思想の欠陥は「根底がない」ということで、漱石はこれを「空虚の感」といっています。でも、西田や大拙はそれを逆手に取って、根底がないからこそ、あらゆるものを自在に受け入れて活用できるというふうに逆転したんじゃないかと思います。それは現代にも通じるような気がします。
ちょっと前までは、確固とした根底を築くこと、どれだけ世の中が変化しても変わらぬ立場を持つことがいいと思われていた。でも、いまは、それがもう限界というか、「何があっても変わらぬ立場」は別の立場との対立を生んだり、ちょっとした条件で崩れてしまうと感じる人が多くなっていると思います。
最近、禅やマインドフルネスがちょっとしたブームになっているのは、もちろん実践的な側面もあるけど、根底を持たない生き方にプラスの可能性を感じる人が増えてきているからじゃないでしょうか。
――根底を持たない、言い方を変えると無を根底とする。西田幾多郎は、自己の根底にあるのは絶対無だ、みたいなことを言っているようですね。
「無」といっても、ないわけじゃないんですよね。でも、「これ」と固定されないものといことでしょうか。

ちょっと話が飛ぶけど、英語の5文型って全部に必ずSがありますよね。英語に限らずヨーロッパ語の世界観って、主語がまずあり、主語が世界を認識して、再構成して、言葉の世界が成り立つという構造になっています。でも日本語や中国語は、主語がまずあるんじゃなく、事物自体がそれ自身としてあって世界が成り立っている。主語はその後からついて出てくるもの、というふうに考えているんじゃないかな。
――固有の立場を持たないということともどこか通じますね。
絵もそうかな。ヨーロッパの絵って遠近法で描かれてるでしょ。遠近法っていうのは、視点があらかじめ一つに固定されているということじゃないですか? 固定された一つの視点からの距離と角度で、全体像が再構成されている。でも、中国の山水画はそうじゃない。遠近感がない。だから、外から絵を見ているというより、絵の中の人物になって、そこにある道を歩いていくように思えてくる。
――なるほど。
あそこに描かれているのは空間の構造ではなく、時間的過程じゃないかと思うんです。こっちの、現実の世界から絵の中に入っていき、山道をてくてく歩いて、庵に住んでいる隠者に出会うまでのプロセスが描かれているんじゃないかって。
――それはおもしろいですね。
本当にそうかどうかわかりません。自分で勝手にそう思ってるだけですけど……。西田幾多郎博士が、たしか、自己というのは無限大の直径をもつ円の中心だというようなことを言っておられたと思います。無いわけじゃないけど、どこにも定位しない中心。逆に至るところが中心だとも言える。そういう、固定された視点や立場をもたないありかた、そんなものがひそかに求められているのかもしれません。
ひじ、外に曲がらず
――鈴木大拙は「ひじ、外に曲がらず」という一句を見て「不自由が自由なんだ」という直感を得たとのことですが、これはどういうことなんでしょう。
現実世界っていうのは、いろんな条件に制約されて成り立っていますよね。一方、悟るとまったく無限定で、無分節で、すべてが平等な世界に超出するんだと思うのですが、さっきも言ったとおり、そこへ行ったきりでは駄目。悟りの世界から戻ってこなくちゃいけない。でも、戻ってきたら、そこは相変わらず諸条件に制約された不自由な世界なわけです。悟ったからといって腕が外向きに曲がるようになったり、歩かなくても移動できるようになったりするわけじゃない。その諸条件に従って現実を生きること、実はそれがそのまま「自由」なんだと。
――さきほどお話に出た、0度じゃなくて360度の「そのまま」を生きるというわけですね。「腕は外に曲がらないんだから、できないことは考えなくていい」ってことかと思ってました。
ただ、そこには難しい問題があります。360度の「ありのまま」といったって、ただの現実随順とどう違うのか。禅は基本的に現実肯定なんですけど、それが間違った現実の随順にならないような歯止めがないんです。
――どんな現実でも「ありのまま」に肯定してしまうと。
1990年代にアメリカの研究者が「禅とナショナリズム」というテーマでさかんに大拙を批判したんですけど、問題の本質はそれだと思います。
朱子学の祖の朱子は、若いときには禅をしていました。後にその経験を踏まえて禅批判に転じるんだけど、その論点の一つが「ありのまま」でいいのかということ。禅では歩くのも、水をくむのも、薪を運ぶのも仏性の表れだっていうけど、じゃあ刀でむちゃくちゃに人を殺しても、仏性の表れだといって肯定されるのかと。現実における善悪の規範はやはり必要だと主張した。
禅にとってそれは大きな課題で、規範という枠組みを外すことで自由になるというのが禅の身上なんだけど、自由になったときの善悪の歯止めはどうするのか? 善悪の歯止めを設けたら禅の生命は失われてしまう。でも設けなかったら、軍国主義のときには戦争に邁進してしまうのが禅だってことになっちゃう。それでいいのか? 現に、日本の歴史ではそうなってしまったわけですが……。
――その問題について大拙はどう考えていたんでしょう。
ちゃんと説明はしているんです。禅とは無を根底にした、何にも縛られないものである。でも、だからこそ、禅をやる人は、西洋近代の知識や技術をしっかり学ばなくてはいけない。そして、無を根底とするから、その知識や技術を善用できるんだと。はっきり断言してるし、理屈としては成り立っているんだけど、現実に戦争になだれ込んだら、そううまくはいかなかった。
それで大拙は、禅の悟りとともに、「大慈大悲」の痛切な祈りの心のようなものを、しきりに説いたのではなかったかと思うのです。
(取材日:2018年3月22日)