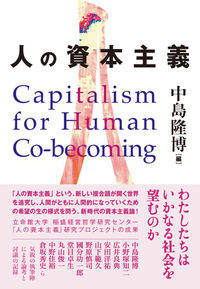――『思想としての言語』によると、井筒俊彦は神秘が成立する条件として、道(=究極の実在)に向かう「向上道」と、到達した道から戻ってくる「向下道」の二つが必要だと言っているそうですね。以前、小川隆先生からお聞きしたお話では、禅の語録にも悟って終わりではなく、悟りの世界から戻ってきて修行を続けなければいけないといったことが書かれているそうなので、同じものを感じました。
こういう考えは至るところにあると思います。禅だけでなく浄土でも往相と還相で「往還」っていいますよね。つまり、行ったり来たりが大事なんだということですね。プラトンの有名な「洞窟の比喩」でも、洞窟を出て太陽――これがイデアの比喩ですね――を見た後、もう一度洞窟の中に戻って、それをみんなに伝えるわけです。こういった例は人間の根源的な共同性、あるいは共生といってもいいかもしれませんが、その方位を示しているように思います。
それこそブッダだって、菩提樹の下で悟った後、そのまま一人で悟ったままでもいいわけじゃないですか。でもそうしなかった。それがみんなに伝わらなければ、シェアされなければ、悟りが悟りにならないと考えたのだと思います。ですから井筒俊彦の中でも、つかんだものをみんなとシェアしなければ本当には完成しないんだという感覚が働いていたんじゃないかという気がします。
――そのときに、それを伝える言語の問題もありますよね。仏教の詩句である頌(じゅ)や偈(げ)には普通に読んでも意味がわからないものが少なくありませんが、その「普通にはわからない」ということ自体に何か意味があるようにも思えます。
言葉に対してある種の負荷を与える必要があると思うんですよ。そうしないと、せっかくわかりかけている真理が逃げていってしまう。たとえば井筒はスーフィズムから「存在が花する」という表現を引用しています。
――花する、ですか?
ええ。日本語としてはおかしいじゃないですか。でも「存在が花する」って言われると、われわれのイマジネーションは一挙に広がりますよね。そういうふうな言葉の使い方を、向下道ということで、井筒は考えていたんじゃないかと思います。
――実は「道」という概念がいまだによくわからないのですが、どういうものだと考えればいいのでしょうか。
道は本当に難しいんですよね。ヨーロッパの中国研究者が道を翻訳しようと試行錯誤したんですけど、「ロゴス」と訳しても、「理性」と訳してもうまくいかない。それで結局「tao」という音訳になった。つまり、わからないんですよ、道とは何かって。

一般的には、非常に根源的なものであり、そこからいろいろなものが派生してくる究極の実在といったイメージなんですけど、その派生したものもまた道を持っているんですよ。だから、大きな道から小さな道がたくさん枝分かれしているといった感じです。
――うーん、わかったような、わからないような……。
「礼」のところでも名前が出たマイケル・ピュエットが面白いことを言っていて、道というのは名詞ではなく動詞的なもの、あるいは動名詞的なものではないかと。だからingをつけて「tao-ing」にした方がいい。つまり、何かを産出していくプロセスのことを中国では道と言っているんだ、というわけです。それを聞いてなるほどと思いました。たしかに、万物の根源のようなものを想像するより、この世界の物事を下支えしている働きだと考えた方がいいかもしれません。
human becoming
――「道」だけでなく「存在」という概念もうまくイメージできないというか、腑に落ちていないところがありまして……。西洋哲学的にいうと実在の根拠となるもの、それこそイデアや、ユダヤ・キリスト教の神のことだというのは、理屈としてはわかるんですけど、どうしても自分のものになったという感じがしないんですよね。
私はできるだけそうした西洋哲学の存在から遠ざかろうとしています。たとえば人間は英語でhuman beingですけど、それよりもhuman becomingといったほうがずっといいと思うからです。存在を意味するbeではなく、「なる」という意味のbecomeを使う。存在というのはbecomingのアスペクト、つまり、プロセスのある瞬間における様相にすぎないのではないかと考えてみたいのです。
――なるほど。先ほどの道の議論とも通じますね。
ヨーロッパの哲学をやると、どうしても存在論というものに入り込まざるを得ないのですが、おっしゃるように、何となく腹落ちしないですよね。実はかなり独特のことを言っている気がしてならないわけです。その独自性に興味がないわけではないんですけど、それがより一般的であるとか、さらには普遍的であるというふうにはどうも思えない。なので、存在を普遍的なものとするのではなく、becomingの一つのアスペクトとして考えてみる。そうするとことで、何か違うものが見えてくるのではないかという気がします。
――今のお話をお聞きして、仏教の「無常」が頭に浮かびました。無常はとてもよくわかるんですよね。この世に常なるものはない、すべてのものは移り変わるというのは、心の底からそうだよなって思います。ですから存在も、それこそイデアのような永久不変のものではなく、先生のおっしゃるように、becomingという運動のひとつの見え方だと考えれば受け入れられるような気がしてきました。
西洋哲学の中での存在、その中でも存在としての存在は神のことなんです。われわれは神ならぬ人間ですから、そこに到達するのは何重にも難しいと思います。誰もが不完全な人間であるという条件の下で、共に生きていくために、乏しい思索をどれだけ巡らすことができるか。結局はそれに尽きるのではないでしょうか。
――その一つが礼という弱い規範であり、その下で「かのように」の実践を積み重ねていくことだと。
それが、われわれ不完全な人間のできることのような気がします。それを超えて、より強力な規範を頭ごなしに適用するというのは、今の時代では難しいかなと。
――宗教がもつ規範や倫理観、それを基礎づけている世界観には個人的に惹きつけられるものがあり、資本の論理に対抗するには、そういったある種の「物語」が必要だと思っていました。でもお話をお聞きすると、これさえ信じていれば、これさえ守っていれば大丈夫といえるような「物語」がどこかにある、といったことではなさそうですね。
私の恩師である宮本久雄先生がこんなことをおっしゃっています。聖書にはいろんなたとえ話がある。あれは非常によくできた物語なんだけど半分でしかない。あとの半分は、それを読んだ人がつくるんだと。本当にその通りだと思うんです。
物語というものには心惹かれるんですよね。でも、心惹かれて終わりではなく、その残りを、今度は自分が、自らの実践によってつくらなきゃいけない。その努力がどうしても必要だということではないでしょうか。