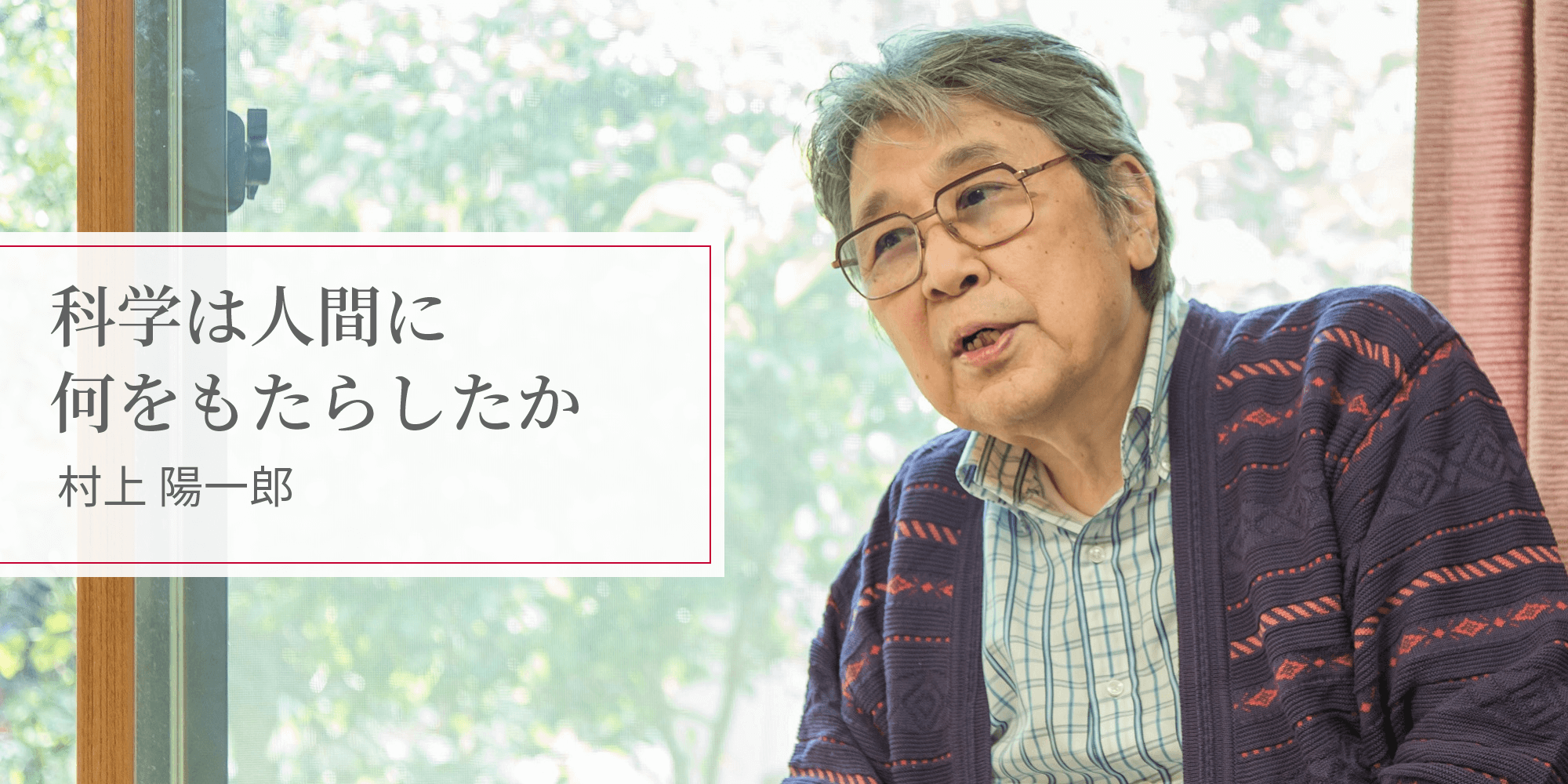――ご著書(『日本近代科学史』筑摩書房)の中で、日本は鉄砲の伝来以来、科学技術の技術ばかりを採り入れたため、科学的な姿勢の方はなかなか根付かなかったといったことを書かれていますが、明治期の日本に入ってきた科学というのはどのようなものだったのでしょうか。
現在のわれわれは常識的に、科学の代表は物理学だと思っています。ところが明治の初め頃、当時は科学ではなく理学と言ったのですが、日本において科学への「信仰」ができていくプロセスで一番働いたのは、実はダーウィンの進化論なのです。
――ということは生物学になるわけですね。
そうですね、東京大学の総長も務めた加藤弘之(1836~1916)は、「われわれの迷妄を晴らしてくれる理学の最たるものは、進化学説である」という信念を持っていたようです。
19世紀の半ば過ぎ、明治維新が1868年ですからちょうど同じ頃です、ヨーロッパではキリスト教の種の創造説に対して、科学的な起源説としてのダーウィニズムが勃興しました。『種の起源』が出るのが1859年ですから、明治維新の直前です。
そんなヨーロッパの学問的状況に接した日本の知識人たちは、どうやら進化論というものがキリスト教に対抗する「科学的」な真理を説いているらしい、宗教的な真理とは別のもう一つの真理を堂々と主張しているという受け止め方をしたんだろうと思います。
恐らくはそのせいで、明治一〇~三〇年代の日本の科学的状況が、進化論を主役として形成されていくという、ちょっと不思議な事態が生じたわけです。
――日本の知識人たちは、西洋の思想的支柱でもあるキリスト教の真理に対抗しているという理由で、進化論を称揚した。
結局そういうことでしょう。自覚的だったかどうかは別にして、あとから考えるとまさにそういうことだろうと思います。
――自分たちで『種の起源』を読んで、これこそが真理だと思ったわけじゃないんですね。
そもそもキリスト教的な種の創造説というのは、日本には浸透していませんから。どっちが本当の真理かなんて議論は起こらないわけです。だから、エドワード・モース(1838~1925)は、日本ではいくら進化論を宣伝しても誰もノーと言わない、なんていいところだって思ったのでしょう。
外科医療の発展
――いまの進化論のお話なんてまさにそうだなと思ったんですけど、日本人って欧米コンプレックスがあるというか。欧米でいいとされているものは無条件で取り入れる傾向がありますよね。
それはだから、幕末から明治にかけて醸成されたのだろうと思います。いわゆる「欧化主義」、「文明開化」ですね。たとえば医療でも、明治政府は日本の伝統的な医療は、医療から切り捨てて、ヨーロッパの医学を医学とすると、明治の初期に言い切っています。
ただ、これにはそれなりの理由があって、当時の日本の医療は漢方が中心ですけど、漢方は外科が駄目だったんです。戊辰の役や西南戦争といった国内戦争で、銃創、銃の傷を負った負傷者に対して、日本の医者はまったく手がつけられなかった。それに対処できたのは西洋人と、西洋の外科を学んだわずかな人たちだけだったわけです。
――日本では外科が重要視されてこなかったということですか。
だって「外科」という言葉自体がそうでしょう。もともと漢方医を指す「本道」という言葉があり、それに対しての「外道」(本来は仏教の言葉ですが)が外科なわけですから。
――外科の「外」は、体の外ではなく、外道の「外」だったんですね。
本道ではない、本筋の医療をしていない人たちという意味です。でもそれは、実はヨーロッパの伝統でもそうなのです。
外科医はもともと医者ではなく、理容師だった。大学で、外科の教授が内科の教授と同じ給料をもらえるようになったのは一九世紀もかなり経ってからです。それまではヨーロッパでも、外科は本道じゃなかった。床屋のねじねじの看板があるでしょう、あれが外科の象徴なのです。
――とおっしゃいますと?
床屋さんはもともと外科医でもあったわけです。あのねじねじは色で体液を象徴している。つまり、床屋さんのギルドにいる人が外科治療をやっていた(床屋の看板が三色のねじねじである理由は諸説あるが、静脈と動脈とを示す、という説が有力、白は包帯か、なお、この説への異論として、動脈と静脈の区別が一七世紀に発見された、という説があるが、これは不可解。ローマ時代から、動脈と静脈の区別ははっきりしていた。ただ、両者が繋がっていることを発見したのは、W.ハーヴィで一七世紀のことである)。
――そうだったんですね。
ヨーロッパに大学病院ができたのは13世紀です。もちろんそこでも、例えば病んだ手足を切り落としたり、解剖めいたことを行うのにも必要なので、外科をやる人は雇われますが、大学共同体の仲間としてではなく、職人として雇われた。だから、大学人が教授も学生も黒の長着(ガウン)を着るのに、彼らは膝下までのワンピースに木靴という服装をしなければならなかったほどです。
そんなわけで、ヨーロッパでは床屋さんが外科治療をやっていたんですけど、その床屋さんのギルドはものすごく発達したんです。

――そもそも外科手術というのは、それこそデカルトじゃないですけど、人間の体を物として、機械として見るわけですよね。
ある意味ではそうです。
――それで、この「部品」がダメになっているから修理しようと。
それがひどくなると、現在の「臓器医療」なんていう言い方も出てくる。でも、日本は、歴史的にはあまりそちらへは行かなかったということは確かだと思います。
長篠の戦い以降は日本でも鉄砲が使われたけれど、江戸時代はほとんど平和だったでしょう。内戦はほとんどないし、幕末までは海外との戦争もない。だから、戦陣医学は、江戸時代には表だって活動する場所がなかったわけです。しかし、ヨーロッパは違っていた。
――ヨーロッパの外科医療がすごく発達したのは、第1次大戦がひとつのきっかけだったと何かで読んだ覚えがあります。
勿論それもありますが、もともと、ヨーロッパ近代には国同士の戦争が絶えなかったからでしょうか。戦陣医学を主とする外科がそれなりに非常に発達したと考えられます。
――必要に駆られて、ということですね。
日本赤十字社というのは、佐野常民(1823~1902)という人が、幕末から維新期の内戦での負傷者を救うために建てた病院が元になっています。
夥(おびただ)しい人びとが道端に横たわって苦しんでいるのに、日本の医者はほとんど何もできない。これを何とかしなければと始めた仕事が、ヨーロッパの赤十字と同じだということになった。そういう意味では、おっしゃったように、江戸末期の内戦が日本の外科を育てたといってもいいかもしれません。
そうやって外科が大事だということになると、これまでの伝統医療には頼っていられないというのが、明治政府の基本認識になった。それじゃあ、外科もなかなか立派にやっているヨーロッパ医学でやっていくより仕方がない。
医療に関する各種の規定を定めた「医制」ができたのは明治七年ですが、そこには医療に加持祈祷を用いてはならないということが明記してあります。それまでは、たとえば精神病なんかは山伏といった人たちが加持祈祷で治そうとしていたのですが、それが一切禁じられたわけです。
――医療の世界も西洋化・科学化していったわけですね。
それがちょうど、ヨーロッパの近代医学が勃興してくる時期と一致していたわけです。パスツール(1822~1895)やコッホ(1843~1910)によって細菌が病気の原因として問題にされたのが、まさにその時期でした。
それともう一人、ウィルヒョウ(1821~1902)というドイツの医師は、病気は政治だと言いました。つまり、結核などの感染症は生活条件と労働条件の悪さから発生すると。「健康都市」という概念が生まれるのもその頃ですが、たとえば日照の確保のために、建物と建物の間は必ず何メートル離すといったことも含めた社会制度を整備することで、病気は克服できると言い立てた。これも一九世紀の半ばです。
そういう考え方が、明確に、日本にどれだけ入ってきたかというのはなかなか難しい。ただ、病気というものを多角的に捉えようという動きが一九世紀半ばのヨーロッパで起こり、それが維新政府によって新しい社会をつくろうとしていた時期とぶつかったのは、日本にとってある意味では幸運だったのではないでしょうか。