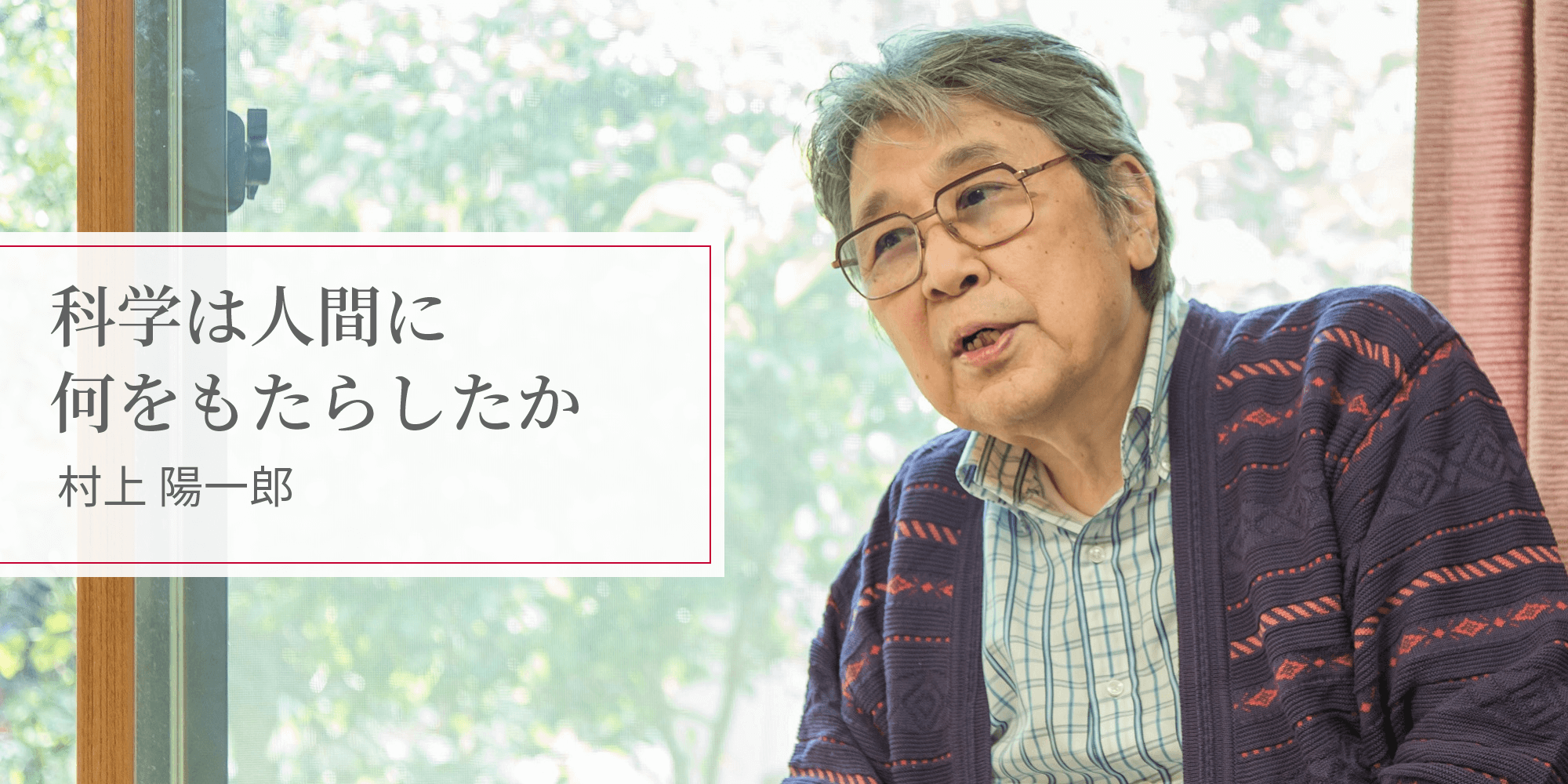――最初に、科学的であるというのはデカルト流に考えるということであり、それは物と心という二つのカテゴリーを設けて、物の方だけを取り扱うことだというお話がありました。それによって、先ほどの医療についてもそうですけど、科学技術は飛躍的に発展した。
結果的にはそうですね。
――その一方で、WHOでも議論されるほど、スピリチュアル的なものが見直されつつある。というのは、科学が一度切り捨てた心というものに、改めて、人びとの目が向けられているということでしょうか。
そういうことだと思います。これはイギリスのある疫学者が言っていることなのですが、社会が文明化されるにつれて問題となる病気は変化していく。
最初に克服されるのは消化器系の感染症、次は呼吸器系の感染症、その次は今風に言うと生活習慣病。その生活習慣病もある程度克服された社会の中で、人びとは何に苦しみ、どんな悩みを持つのかというと、その社会への非適応なのだそうです。
――社会自体は衛生的で、フィジカルには健康的なんだけど、その社会に適応することができない。
ご存知のとおり、日本では年間の自殺者が二万人を超えています。交通事故が昔は一万人超えたこともありましたが、いまでは三千人ほどになりましたので、それよりもはるかに多い。
自殺だけではなく、不登校や引きこもりやといったものも問題になっていますよね。物質的、つまりフィジカルにも、メンタルにも、そしてソシアルにもある程度ウェル・ビーイングとなったときに果たして何がイル・ビーイング(好ましくない在り方)なのか。その答えとしていま、スピリチュアルなイル・ビーイングというのが表に出てきている、というふうに読み替えてもいいのかもしれません。
――では、フィジカル、メンタル、ソシアルがウェル・ビーイングであると同時に、スピリチュアルもウェル・ビーイングにしていくにはどうすればいいのでしょうか。
それが非常に難しくて、極端に言えば、フィジカル、メンタル、ソシアルなウェル・ビーイングをすべて捨てなければ、スピリチュアルなウェル・ビーイングは得られないという考え方さえあります。その穏やかな言い方が、ルソー(1712~78)ではありませんが、「自然に還れ」なのでしょうか。アメリカで今根強い共感を得ているソロー主義もその一つかもしれません。
――ソロー主義?
ソロー主義というのは、アメリカのソロー(1817~1862)の主張を基礎としています。彼は文明生活から一切身を引き、ウォールデン湖畔の森の中に小屋を建てて自給自足の生活を送りました。それは結局二年ほどで終わるのですが、その記録をまとめた『ウォールデン 森の生活』という本を出して多くの人に影響を与えました。
現代でも、およそ文明生活から離れ、自然の中で一人生活するほうが魂の安らぎを得られるんだと考える人は少なくありません。
――まさしく近代の否定ですね。
実は、私がデカルトと言い始めた理由の一つは一九七〇年代初め、学生たちがバリケード封鎖をしていたパリ大学の壁に「デカルトを殺せ」という殴り書きを見たからなんです。
近代人にとって、特にフランス人にとって、デカルトはそれだけの重さを持っているのだという気付きと、同時に、デカルトを「殺さなければ救われない」という主張の持つ意味、それが、私の心に突き刺さりました。もっとも、それこそが、ポストモダンという時代だったのです。
アメリカで言えば、西海岸、カリフォルニアのカウンター・カルチャーがそうでした。それはヒッピーイズム、性秩序の否定であり、ドラッグであり、何物にも縛られない自由のなかに平安がある……。かれらはキリスト教を捨てて鈴木大拙を読み、あるいはタオイズム(道教)をはじめ東洋思想に傾倒していった。まさに、西欧的・近代的価値のすべてを否定したわけですけど、その結果、はたして人間的に、あるいはもしかしたら、スピリチュアルに充足したのだろうかという疑問が、また戻ってきたことも確かではないでしょうか。
いまカリフォルニアに行っても、明かに東海岸の文化とは非常に違うと思いますが、あの頃の主張が実現されて、自分たちは幸福だ、と素直に信じている人々がどれくらいいるでしょうか。
日本人の宗教心
――科学で人は幸せになれるのかという疑問がヨーロッパやアメリカで起こったのは、やはり、宗教的なものへの意識があったからじゃないかと思うんです。それがキリスト教世界への単純な懐古主義ではないにしても、自分を超えた何か、科学の言葉では捉えきれない何かを信じる気持ちがあったからじゃないかって。
それに対して、日本はいわゆる「無宗教」なので、科学的な価値観が相対化されず、科学絶対主義になっているのではと思うのですが、いかがでしょうか。
現象面で言うと非常にそういうところがあると思います。ただ、日本人は本当に無宗教なのかどうか。先ほど古事記の話をしましたけれども、本居宣長は大和言葉の「かみ」を「ある面において人間を超えるすべてのもの」と定義しています。
そう言われてみると、たとえば「オオカミ」というのも人間を食い殺すこともあるように、ある面では人間より強いわけです。そうすると、「オオカミ」は確かに「かみ」なのです。海や山も、そこで人が死ぬこともあるわけだから、われわれよりはるかに強大な存在だし、木だって、屋久島の杉にしても鹿児島の楠にしても人間を圧倒するような生命力を持っている。何百年、何千年と枝を張ってるわけですから。

そういうものに対して思わずひざまづくというか、自分たちの力はここまでだ、そこから先の世界は確かにあるのだと言える「余地」のようなものは、日本人の心のどこかにあるのではないかと思うのです。そしてそれは、ある種の宗教心だと言ってもいいと思うのですね。
――日本人は無宗教だとステレオタイプに思っていましたが、そう言われてみれば、なるほど、おっしゃる通りかもしれません。
そういう日本人の心性がいちばん鮮やかに出ているのが、私は臓器移植だと思います。日本はいわゆる先進国で、恐らく、臓器移植の実例が最も少ない国です。
梅原猛さんは生前、臓器移植に非常に強く反対されていたのですが、そのときに「自然ではない」という言葉を使われていました。機械につながれた上でのことでも、まだ体温があって、脈を打って、呼吸もしている他人の身体を切り開いて臓器を取り出し、それを自分や、自分の親族の体に埋め込むという行為に、どこか不自然さを感じる。
そういう「重し」みたいなものが、良い悪いは別にして、日本の社会には生きているような気がします。そこまでして自分が生きようとは、あるいは、自分の子どもを生かしたいとは思わない。そう考える人は決して少なくありません。
――そう考える人の気持ちもわかる気がします。
もちろん日本にも、何億円もかけてアメリカに行き臓器移植をする、あるいは自分の子どもにさせる親もいます。私はそれを決して非難するわけではありません。日本ではすぐに一億円、二億円のファウンディングが集まるわけですから、それはそれで結構なことだと思います。
どちらがいいとは言えません。近代社会であれば、やれるのであればどこへ行ってでもやるというふうになるし、反近代の価値観で言えば、そこまではしないとなるでしょう。そこは一つの分かれ目です。
日本はいかにも完全に近代化されているように見えて、しかもおっしゃったように、制度的な宗教枠組みが存在しない社会ですが、でも、どこかにそういう反近代的な歯止めのようなものが、緩やかな形では存在していると言えるかもしれません。
(取材日:2019年8月7日)