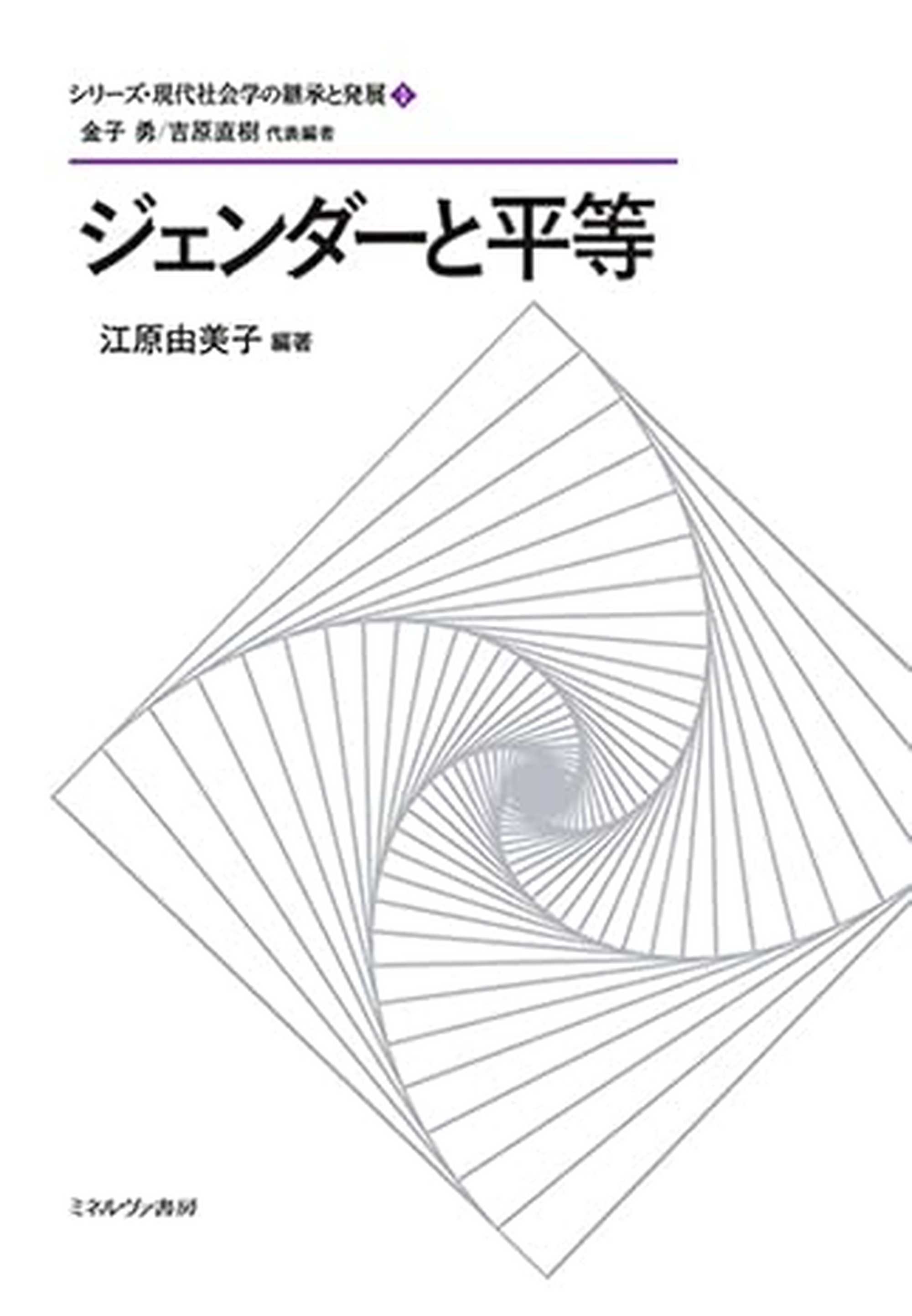5)フェミニズムの「近代社会理論批判」―性差別批判を封じこめる「理論的仕掛け」との関連で
しかし私見によれば、1980年以降「近代化とフェミニズム」の関係を個人の思想的立場の変数として扱うのではなく、それを構造的に読み込むような理論化が、進んでいった。このようなフェミニズムの理論化の方向、つまり啓蒙主義やリベラリズムあるいはマルクス主義などの社会理論が、表向きは女性差別を肯定しはしないものの、それらの理論がそもそも備えていた「女性差別だという批判を封じ込める理論的仕掛け」を解明することで、「近代化とフェミニズム」の関係を読み解こうとする理論化の方向が生まれたのである。このような方向を紹介することで、本稿を終えたいと思う。
前節の最初においた問い、「近代市民革命に於いて人権という思想が力強く宣言されたはずなのに、なぜ近代社会は、まずは女性参政権を1世紀半も認めず、さらに女性参政権成立以降も、女性の人権の根幹であるはずの「身体の自由」を侵害するDV等の暴力を放置し、女性が自由に労働する権利を侵害するような労働環境を放置したのだろうか」という問いに戻ってみよう。
男性も女性からしか生まれない。もし女性が人間でないのなら、その子どもである男性も人間であることが疑わしくなってしまうから、生物学的種としては同じ人間である女性を、人間でないとは言いにくい。しかし彼らには女性を啓蒙主義における人、すなわち生まれながらに「自由で平等な個人」から排除したい様々な理由があった。意図的であったか否かは分からないものの、啓蒙主義者の多くは、実に用意周到に女性を啓蒙主義が言うところの人間=公的領域に参加しうる個人から排除しうる「理論的仕掛け」を、表の思想からは見えにくい裏の細部に、稠密(ちゅうみつ)に作り上げていた。近代社会とフェミニズムの関係を見るためには、まずこれらの「理論的仕掛け」を確認することが必要であると思う。
以下において「理論的仕掛け」とは、女性の視点からしておかしいと思うことに反論しようとした場合、その反論をあらかじめ困難にするような枠組みが理論の中に内在的に仕掛けられている場合に、その枠組みを指すこととする。以下では、公私二元論を、そのような仕組みの一つとして扱う。なぜなら、啓蒙思想を引き継いだ主流社会理論であるリベラリズムは、男女の法的政治的平等を標榜しつつも、社会的・経済的不平等については放置し、家族内におけるドメスティック・バイオレンスをも放置したが、それを正当化したのは、政治などの公的領域とそれ以外の領域を区別する公私二元論であったからである。つまりリベラリズムの公私二元論は、第二波フェミニズムが社会問題化した夫婦間の性別役割分業の不平等性や、性暴力やドメスティック・バイオレンスなどの告発を、ほとんど不可能にしうる性能を備えた「理論的仕掛け」であった(フェミニズムの「公私二元論批判」については、江原 2024「『フェミニズムにおけるリベラリズム批判』の社会学的意義」、江原編『ジェンダーと平等』、シリーズ現代社会学の継承と発展1、ミネルヴァ書房 参照)。
このように近代市民革命を可能にした啓蒙主義は、フェミニズムの立場から見ると、ジェンダー平等の実現を困難にしうる「理論的仕掛け」をあらかじめ備えていた。つまり、近代市民社会の形成した近代的人権思想は、表面的には男女平等思想をも含みつつ、実のところジェンダー平等の実現を困難にする「理論的仕掛け」をも駆動させていたという意味において、まさにヤヌスの相貌を備えていた。
先を急ぐのはこれくらいにして、前節および本節の最初の問いに戻ろう。この問いに対する最初の答えは、かなり前から、英語やフランス語などにおける男性と人間を等置する言語的規則の存在に、求められていた。例えばフランス革命に於ける「人および市民の権利宣言」はフランス語の文字通りでは「男性及び男性市民の権利宣言」を意味し、その意味ではそもそも女性はそこから排除されていたのだ。しかし言語的規則によって、この宣言は「人および市民の権利宣言」とも読めることから、メアリ・ウルストンクラフトらのフェミニストは、そこに女性市民権も宣言されていると読むことができると考えた。にもかかわらず革命政府は、女性は議会などの公的領域の参加に必要な理性を欠いていることと、女性が妊娠・出産する身体機能を持っていることから生物学的に子育ての役割を課されている等の理由で、女性参政権を含む女性市民権を否定した。ここからウルストンクラフトらの近代フェミニズムが誕生したことは、先述したとおりである。
しかし、この革命政府による女性参政権の否定は、たまたまのことではなかった。むしろ革命を支えた啓蒙思想の中に、用意周到に仕組まれていたことが、その後の研究によってかなり子細に明らかになった。女性参政権の否定は、近代市民社会を、公的領域と私的領域から成るものとして構成する、公私二元論によって準備された。公私二元論は、「法の下の自由と平等」等の基本的規範に基づく「正義」が妥当する領域を、公的領域(政治領域)に限定する。そして、その外の家族などの私的領域は、「正義」が及ばない「自然の本能や共感によって支配される」場であるとし、女性の居場所をこの私的領域に限定した。つまり「正義」は、「成人男性が相互の合意に基づく協定に従って他の男性と接する領域」=公的領域にのみ妥当し、家族等の私的領域には及ばないものとされたのだ。
なぜ女性は公的領域に参加できないのか。それは、啓蒙思想(の主流の社会契約論)が、公的領域に参加する個人は、ただの人ではなく「道徳的人格を備えた個人」でなければならないことを前提としたからである(岡野八代、2012、『フェミニズムの政治学』、みすず書房)。「道徳的人格としての個人」は、「自らにとって何が善きことか合理的に計算でき、選択でき」る理性を持っているだけでなく、「他の同等の人格との間に契約を結ぶ潜在能力を持っている」ことが必要だった。したがってそもそも「意志を抱けない存在」や、「自分の意志を抱く以前に他者のニーズに応えなければならない存在」は、そこから排除されることになる。
市民革命当時女性はまずは「合理的に計算でき選択できる」ような理性を欠いているとされ、公的領域から排除された。この女性に対する「理性を持たない」という規定を不当であるとして闘い女性参政権を勝ち取ったのが、第一波フェミニズムである。
しかし女性が公的領域から排除されたのは、それだけが理由ではなかった。公的領域に参加するには、「自らの意志に従い行為することを妨げられない存在」でなければならなかった。子育てをする人(多くは女性)はしばしば、「自分の意志にのみ従い行為する」ことができない場合がある。「自分の意志を抱く以前に他者のニーズに応えなければならない」からである。社会契約論を引き継いだリベラリズムは、「女性は理性を欠く」ことと「家族のニーズにこたえるために自分の意志にのみ従って行為することができない」ということを重ね合わせて、女性を公的領域から排除し、私的領域にのみ属する存在としたのである。そしてそのうえで私的領域を、「社会の秩序=正義」とはかかわりのない「自然の秩序」に属する領域としてしまう。「自然の秩序」とは、身体的能力や本能などによる統制の秩序であり、そこでは支配者は「自然に」成人男性となる。女性は、その生物学的特徴から理性を持たず、よって公的領域には参加できないだけでなく、私的領域における「自然の秩序」=男性による支配に服従することが、前提とされていた(例えば、ジョン・ロックの社会契約論など)。
つまり、公私二元論は、自然と社会を対比的に論じる二項対立論や、「他者のニーズに応える責任を負っていないがゆえに自分の意志のみに従い行為しうる」人だけを「道徳的人格」とする等の、公私の領域に関すること以外の子細な論点も同時に書き込まれた「理論的仕掛け」であった。実際には社会には常に「他者のケアに依存する」人々が多く存在しているにもかかわらず、それらの人々のニーズに応える責任を負わない人々のみを公的領域に参加しうる個人と成しえたのは、そうしたニーズに応える人々(女性)がいることを前提としていたからであった。つまりこうした子細な論点を書き込むことによってはじめて、「自由で平等な個人がそれぞれ自らの利益を最大にするように選択しつつも、同等の他者と契約することで正義を実現できる」近代社会が可能であると論じることができたのだ。
そうであれば、啓蒙主義者の多くは、「人は生まれながらに自由で平等」であるとしながら、その「人」の中に女性を含めようとはほとんど思っていなかったのであり、そのことは「自由で平等である道徳的人格を持つ個人」の意味の中に「契約を結ぶ潜在能力を持つ」ことを含めた時点で、既にそうだったのである。つまり啓蒙主義に基づいて出された「人権宣言」は、文字通り「男性及び男性市民の権利宣言」でしかなかったのだ。
それゆえ、近代市民社会において最初女性に参政権がなかったのは当然であった。女性は、父や夫の保護下に置かれるべき存在であるとされたが、実際には女性は父や夫である男性の財産として扱われていた。つまりそこでは、女性自身が自分の身体を自分の意志の下に置くことを保障する女性の「身体の自由権」は、考慮すらされなかったのだ。だからこそ市民社会においては性的関係にある男女や家族内での男性による女性に対する暴力は、公的権力が介入するべきではないこととして、放置されたのである。第二波フェミニズムが家庭内での男女平等や、性暴力の撤廃等を問題提起した時、当初リベラリズムがそれらの問題を政治の問題ではなく公的権力が介入するべきでない私的領域の問題だとしてその主張を無視したのは、ある意味当然であった。啓蒙主義もリベラリズムも、それまで誰も、そうした問題を「人権の問題」として考えてこなかったからである。
マルクス主義フェミニズムもまた、マルクス主義の「労働」概念の中に、性差別を覆い隠す理論的からくりを見出していた。女性の妊娠や出産及び子育ては、19世紀的労働観によって「自然の営み」とみなされ、「労働」とはみなされなかった。それらの活動は、単に自然の本能的営みとされ、他の「労働」と見なされた活動とは異なり、いかなる経済的価値も生まないものとみなされた。それゆえ人生のほとんどをそうした活動に費やした女性は、夫や子供たちの恩情にすがる以外、いかなる経済的支えも無しに、老境を迎えるしかなかった。
ここから考えれば、啓蒙主義やマルクス主義等の近代思想が女性の公的領域からの排除や女性の「労働」参加の否定によって成し遂げたことは、女性排除や性差別だけではなかった。それは、性や生殖・次世代育成、さらには自立できない人々を支えるケア労働等の問題を、公的領域(=政治)が関与するべき問題から排除することでもあったのだ。落合恵美子は、社会的再生産を外部化する社会の観念の浸透こそがが、性別役割分業とケアの家族化を伴う「近代家族」の社会的構築を生み出したと指摘する(落合恵美子2023『親密圏と公共圏の社会学』、有斐閣)。ケアに関わる問題は全て、女性身体という生物学的自然において起きる事柄であり、理性を持たない動物的存在である女性が本能によって行う自然過程の事柄であり、力が強い父や夫によってそれらが統制されるべきことが当然視されていた。子育てや介護は「家族の責任」、つまりまずは女性が無償で担うべきことであり、その監督責任は支配者たる夫や父親に任されたのである。
つまり、近代市民社会を形成した啓蒙思想は、性と生殖に関わる事柄や、子ども等自立できない人々のケアの問題などを、私的領域である家族の問題とし、つまりは女性の問題として定義することで、公的領域から排除し、そうすることで初めて、「人は生まれながらに自由で平等である」と言いうる理論的備えを、整えることができたのである。なぜならそこにおける「自由と平等」は、女性を排除した経済的に自立した成人男性間の関係にしか適応されないように、理論的に整えられていたからである。
第二波フェミニズムは、1980年代のキャロル・ギリガンによる「ケアの倫理」の提唱に始まり、ジョン・ロールズの「正義の倫理」との論争等数十年をかけて、この近代の最初にあった、「性差別」と「ケア」を「正義」から排除する「理論的仕掛け」を、明らかにしてきた。この洞察は、近代社会が女性を差別することで何を成し遂げてきたのかを明らかにしつつある。現代フェミニズムが目指す未来は、その先にある。