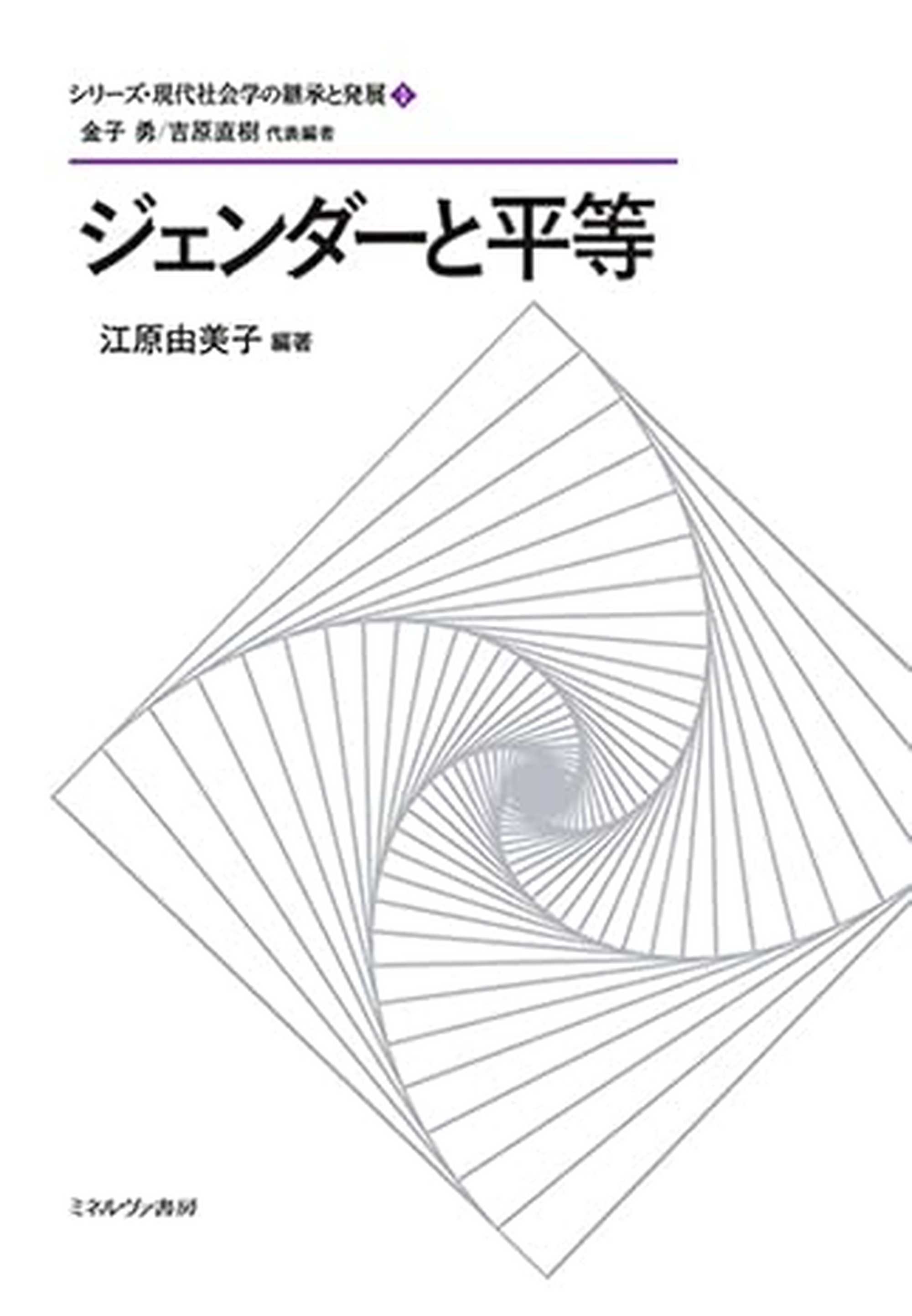1) はじめに
近代化とフェミニズムの関係は、入り組み錯綜している。以下ではこの関係を論じていくが、そこではフェミニズムを、ジェンダー平等の社会の実現を目指す広範囲の思想と運動を意味する概念として、近代化を、「伝統的社会」から脱却し、自由で平等な市民の合理的討議による政治や、科学技術を基盤としたより効率的な産業等、より合理的で効率的な社会に変化していく過程を意味する概念として、ごく一般的に把握しておくこととする。
半世紀以上前の高校時代、女性問題を考え始めた私は、近代化をフェミニズムにとって不可欠な肯定的な社会変動と見ていたように思う。
今私は、近代化こそ現代も続く性差別を生み出した最も重要な社会変動要因ではないかと、批判的に見るようになっている。近代化こそ、ジェンダー不平等を生産し固定化した社会変動であったのではないかと。
なぜそう考えるようになったのか? 逆に問えば、なぜ昔はそうは思わなかったのか? 以下では、過去の(愚かな)自分に対する自戒を込めて、今日までの私の「近代化とフェミニズム」についての思考の流れを、歴史的経緯と共に、振り返ってみたいと思う。
2)「伝統的家父長制的家族」と近代化
高校時代の私も今と同じく性差別のない社会の実現を求めていた。なのになぜ、今よりもずっと近代化を肯定的に見ていたのだろうか。今思えばそれは、戦争を知らない世代とはいえ今よりずっと戦争の影響が強かった戦後期を生きてきた当時の日本人の一人であった私にとって、至極当然のことだったのだろうと思う。
戦争が終わって、財閥解体や農地解放等GHQによる戦後改革が行われ、その一つが「婦人解放」であった。明治憲法・明治民法の下、参政権をはじめとする市民権が与えられないまま、生涯にわたって父・夫・息子に従って家のために生きることを強要されていた女性が、男女平等を規定した戦後の新憲法とそれに基づく改正民法によって、男性と同等の市民権を獲得した。「男女同権」は、青鞜運動(平塚らいてうらが結成した「青鞜社」が中心となり、明治末期から大正初期にかけて展開された日本初の本格的な女性解放運動)以来長年にわたる日本のフェミニズム運動の悲願であった。

そして悲願の「男女同権」の獲得をもたらしたのは、非民主的・伝統主義的・封建的な日本社会こそが日本軍国主義体制を生み出したとするGHQによる、日本社会の民主化・近代化政策であった。
この見方を前提とすれば、日本の女性に従属を強いてきたものは、日本の伝統的社会であり、とりわけ伝統的家父長制的家族制度、すなわち「家制度」であった。その性差別主義的・非民主主義的・封建的体質が、女性を家に縛り付け、女性の自立を困難にし、一人の人間としての自由な生き方を、困難にしてきたのだ。そうであれば、性差別を無くし女性を自由にするためには、「伝統的社会」からの脱却すなわち近代化こそが、求められることになる。私が近代化を肯定的に見ていたのは、まさに戦後社会の支配的イデオロギーであったこのような戦後改革観や近代化観を、当然のものとして観ていたからに違いない。
いや当時の日本人の皆がGHQの近代化施策を頭から信奉してわけではないという批判も、当然あるだろうと思う。日本の伝統社会を維持しようとする現代にもつながる保守主義は、当時もしっかりと存在していた。また戦後の世界は東西冷戦の真っ最中であり、ソ連をはじめとする東欧や中国などの社会主義諸国の情報も、多く伝えられていた。資本主義国であるアメリカが進める近代化政策は、あくまで資本主義のイデオロギーを前提としたそれに過ぎないという批判は、戦後の日本の論壇においても大きな力を持っていた。
しかし経済的に厳しかった戦後直後の社会において、経済成長の意義を否定することは困難であった。また国力に見合わない戦争を引き起こした戦前の精神主義的日本主義に対する反感も強かった。つまり、より効率的で合理的な社会の実現を求めること=近代化を推し進めることは、たとえ様々な異論があったとしても、大方の人々から支持を得ていたのだ。そして古く窮屈な「伝統的家父長制家族」を批判し、核家族や自由恋愛による男女対等の男女の結びつきを肯定することは、それもまた、台所の改善などと同じく、それまでの生活の無理や無駄を省くごくあたりまえの「生活の近代化」の一環であるかのように、認識されていたのだ。
無論、フェミニズムと近代化を等置する見方は、欧米における女性参政権運動を推進した第一波フェミニズム思想自体にも、色濃く流れていた。近代化が合理的で効率的な社会への変化過程であるならば、普遍的人権思想の定着は、近代化の最も重要なメルクマールの一つだと言われていた。個人の自由や権利を保障する人権思想に基づく具体的な政治制度を確立することによって、経済活動や社会活動が活性化し、近代化が推進されていくからだ。
近代フェミニズムは、この近代人権思想の影響によって誕生したと言って良い。メアリ・ウルストンクラフトらは、フランス革命の「人権宣言」における「人は生まれながらに自由かつ平等である」という近代人権思想の中に男女平等の真理を見出し、女性市民権の確立を求める近代フェミニズム思想を生み出した。
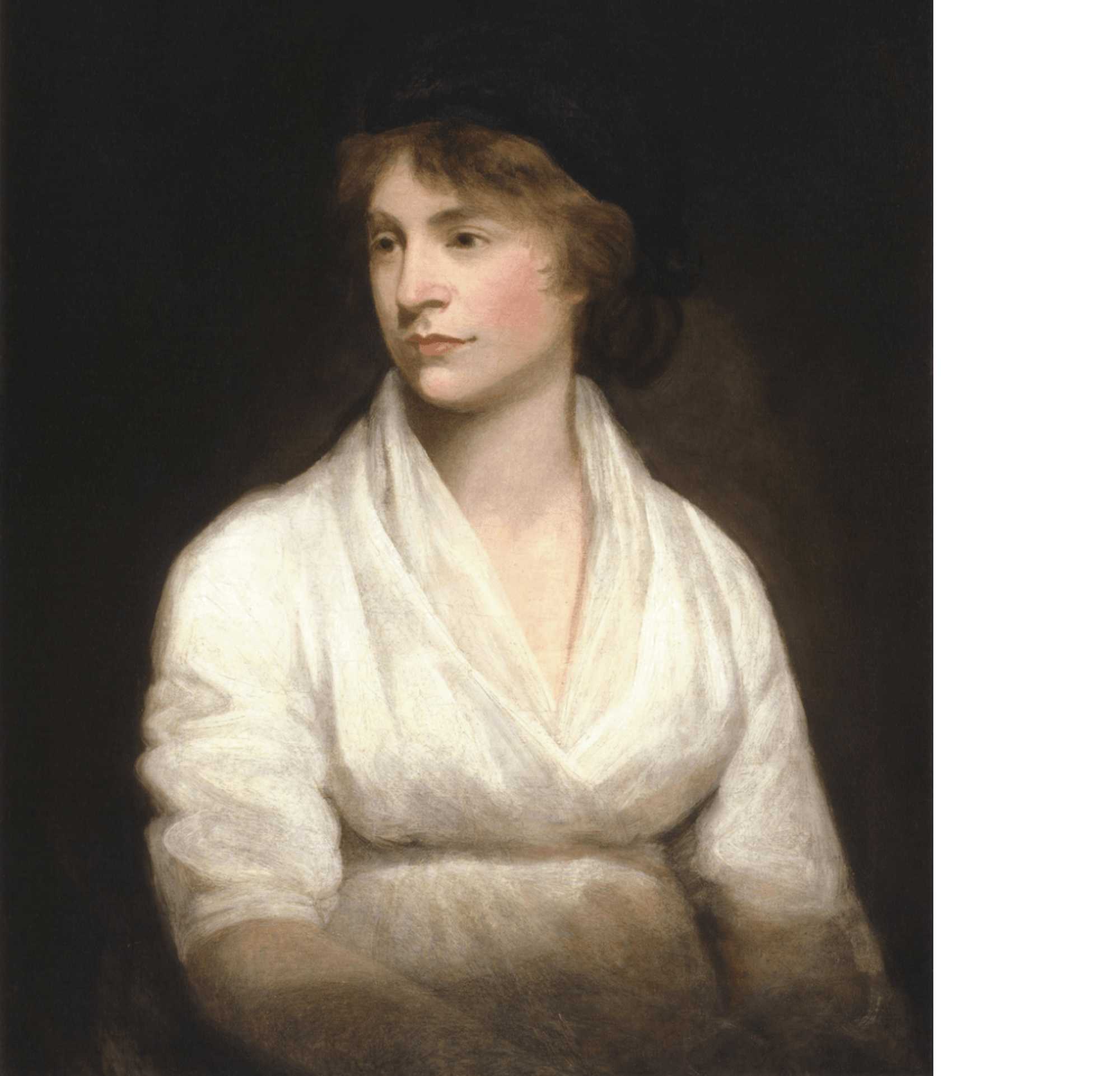
そしてこの近代フェミニズムは、19世紀後半の英米等において女性参政権運動を大規模に展開し、第一次世界大戦後にそれを実現した。この女性参政権運動が、後に第一波フェミニズム運動と呼ばれることになる。
しかし明治憲法下の日本においては、人権思想の政治制度化は不十分だった。明治憲法は、人権を天皇を元首とする明治国家における法の範囲においてのみ保障される「臣民の権利」としてのみ認めていたに、過ぎなかったからである。そのため、戦前の日本社会で女性が男性に従属していたことも同様に、基本的人権という人権思想の政治制度化の不十分性に求められたのだ。確かにイギリスやアメリカにおいても、女性参政権の実現は第一次世界大戦後のことであり、近代市民革命期において実現したわけではなかったことも無論よく知られていた。しかし少なくとも日本より先んじていることは確かだった。つまり、敗戦直後の日本では、日本と欧米との違いを、近代化の度合いの違いとして観る見方が強かったのだ。
3) 第二波フェミニズムと近代社会批判
しかしこのようなフェミニズムを近代化と等置する見方に対しては、私が大学に入った1970年代には、様々な疑問が寄せられるようになっていた。それは、1960年代から70年代にかけて、当時の先進資本主義諸国において、資本主義的階級社会やキリスト教(特にプロテスタントの倫理観)を背景とする禁欲主義的文化に反対する新左翼運動や若者運動が台頭したこと、そしてそうした運動の一つとして第二波フェミニズム運動が展開されたことが、最も大きな理由である。
この第二波フェミニズム運動は、アメリカから始まった。女性参政権の実現以降数十年たっても、アメリカ社会は、男女平等から程遠いところにいた。結婚した女性は職場を去るのが当たり前だったので、生きていくためには未婚女性は、良い結婚相手になる独身男性を捕まえて主婦になるしかなかった。アメリカの女性たちは、女性参政権を得、二つの世界大戦期に戦場に行った男性の代替労働力の役割を立派に果たしたにもかかわらず、職業選択の自由も経済的自立の可能性も得られなかった。この状況に、女性参政権運動(第一波フェミニズム運動)の成果である法律的男女平等だけでは不十分であり、既婚女性も職業を継続できるような「男女平等の職場」「男女平等の働き方」の確立が必要であると考える女性たちが、社会的実質的平等の確立を求めて、声を挙げ始めた。第二波フェミニズム運動の始まりである。
しかしこうした女性たちの主張は、社会からなかなか受け入れられなかった。誰もが自由に働く権利を持つのは、「自由と平等」を基本的価値観とする近代社会では当たり前のことであり、認められるはずと考えていたフェミニスト達は、「女性の居場所は家庭」という社会規範の根強さに直面することになった。「男は仕事、女は家庭」という性別役割分業は、家庭という私的領域が「男女平等」という(近代的な)価値観の浸透がたまたま遅れた領域だったからそうなったわけではなく、むしろ性別役割分業の確立自体がより深く近代化に根差していたのである。ここにおいて、近代化と女性の生き方の関連性が、見直されたのだ。
実際、産業化以前の社会においては、農業などに従事している家族が多く、そこでは既婚女性たちも産業に従事していた。「女性の居場所は家庭」という意味が、「女性は生産労働に従事せず家事育児など消費労働のみ行う」という意味になったのは、主要産業が工業生産になった産業革命以降のことである。つまり近代化は、女性の経済的自立を促すよりもむしろ父や夫等の男性への依存を強めたのだ。産業化に伴う核家族化も、家庭内の家事や育児を一人の女性の肩に担わせる結果をもたらし、女性に自由をもたらしただけでなく、孤独感や家族への従属感を強めることにもなったのだ。
他方当時のアメリカ社会は、公民権運動やベトナム反戦運動等、若者を中心に様々な社会運動が台頭していた。女性もこうした社会運動に参加していたが、その運動の場で女性を雑用係や性的対象物として扱う男性活動加家の言動に直面して、女性自身のための運動の必要性を認識し、運動参加経験のある若い女性たちが中心となって女性運動を立ち上げた。主な主張は、女性に厳しい家父長制的性規範を課す伝統文化と女性を性的対象物として扱う商業主義的男性中心主義性文化を共に否定することや、性暴力の否定・人工妊娠中絶の合法化等であった。この運動は後にラディカル・フェミニズム運動と呼ばれ、先述した第二波フェミニズム運動の重要な一派として位置付けられることになる。
この主張に対しても、当時の新左翼運動等の社会運動やリベラリズム的立場の知識人から、強い批判が寄せられた。例えば、ラディカル・フェミニズム運動が主張するような女性を性的対象物として扱う商業主義的男性中心主義性文化を否定することは、性に関する表現の自由に対する国家の規制を正当化することにつながりかねないという批判が多く寄せられた。セクシュアル・ハラスメントの社会問題化に貢献したことで知られるキャサリン・マッキノンらが議案化したインディアナ州ポルノグラフィー規制条例案問題などが、その例である。
他方ラディカル・フェミニズム運動の中で強く主張されていた人工妊娠中絶規制の撤廃問題に対しては、一部のリベラリズムからの賛同は得られたものの、胎児の生命権を主張する宗教右派をはじめとして非常に強い反対意見が寄せられた。この人工妊娠中絶の是非をめぐる問題は、周知のように、今日に至るまでアメリカの政治的分断の最大の争点の一つとなっている。
このラディカル・フェミニズムによる性暴力や人工妊娠中絶等の問題は、女性の身体をめぐるそれまでの「近代市民社会の法規範」がジェンダー不平等であることを、一気に明るみに出すことになった。なぜなら、リベラリズムの最も中心的な価値観は人間の尊厳にあったはずであり、その核心には個人の身体に対する侵害や拘束を排除する「身体の自由」という概念があるはずだからである。性暴力や人工妊娠中絶禁止は、女性の「身体の自由」を奪うものであり、女性が「身体の不当な干渉からの自由」や「身体の自己決定権」を持つとするならば、当然にも性暴力は撤廃されなければならないし、女性の人生に多大な影響を与える妊娠を継続するかどうかを決定する権利を女性が持つことは当然であるからだ。にもかかわらず、近代市民社会の民法や刑法においても、女性の「身体の自由」は、未確立だった。「女性の権利は人権である」ということが国際的に初めて確認されたのは、1993年のウィーン世界人権会議であった。
つまり、近代をもたらした啓蒙主義(およびそれを引き継ぐリベラリズム)は、女性参政権を否定しただけでなく、女性の労働権の正当化にも役立たなかったし、実際の近代化の過程も、女性に「自由と平等」をもたらしたわけではなかった。また、近代市民革命において確認された「普遍的人権」はあくまで男性の権利であり、性や生殖における女性の権利を認めたわけではなかった。つまり第二波フェミニズムによる問題提起は、近代啓蒙思想に対する信頼を一挙に突き崩し、近代主義と近代化への疑念を一気に強めた。
この第二波フェミニズムの見方は、日本社会にも大きな影響を与えた。戦後の日本社会においてフェミニズムを家制度等の伝統的家父長制的家族制度の変革、つまり近代化と等置する見方が強かったと述べたが、アメリカなどの第二波フェミニズム運動の影響を受けて、恋愛結婚で結ばれ親世代と同居しない戦後の核家族も、男性優位主義=家父長制的性格を免れていないという見方に変わったのだ。
こうして近代社会に対する批判的な見方を強めた第二波フェミニズムは、その後実践的にも理論的にも様々な方向に模索を続けて行く。以下では、その歩みを、やや強引ではあるが、簡単に振り返る。
4)冠付きフェミニズムと「近代主義」・「反近代主義」
近代市民革命に於いて人権という思想が力強く宣言されたはずなのに、なぜ近代社会は、まずは女性参政権を1世紀半も認めず、さらに女性参政権成立以降も、女性の人権の根幹であるはずの「身体の自由」を侵害するDVを放置し、女性が自由に労働する権利を侵害するような労働環境を放置したのだろうか。第二波フェミニズムが問題にしたのは、その問題を直視することすら困惑するような、あまりにも大きな問いであった。なぜなら少なくともアメリカでは、(近代啓蒙思想を引き継いだ)リベラリズム思想は最も正当な政治思想であり、既存の法学や政治学の主流派であったからである。近代思想の大哲学者や彼らを引き継いで展開されている学識に異を唱えることは、大学等の高等教育機関にやっと入学を許可されるようになった女性たちにとって、非常に難しいことだった。
それゆえまず最初に第二波フェミニズムがとった理論化の方向は、主に男性学者たちが展開してきた近代化をめぐる立場のどれかを選択し、その理論に即した形で、自分たちの疑問を提示し、理論化することだった。1970年代から80年代、欧米においては、リベラル・フェミニズム、マルクス主義フェミニズム、ポストモダン・フェミニズム等、男性たちを含めた主流の社会理論の立場を語頭にかぶせたフェミニズム理論が展開された。これを「冠付きフェミニズム」と呼んでおくことにする。
例えばアメリカの第二波フェミニズムの主流派であったNOW(全米女性機構)は、その主張をリベラリズムの範囲内に収まるように抑制する傾向があった。したがってNOWの立場は、リベラル・フェミニズムと呼ばれている。NOWの最も大きな主張は、既婚女性も含めて「女性が自由に労働する権利」を持つこと、つまり女性が働くことに関する様々な制限や差別を取り除くことだった。要するに女性が男性と同等に働き、差別されることなく評価され、昇進したり高給をとれるようにすることである。しかしこのリベラル・フェミニズムの枠内でも、実際には強い抵抗が存在した。それゆえNOWは、リベラリズムから「急進派」として嫌われる可能性がある主張は、なるべく抑えようとした。例えば、その指導者のひとりであったベティ・フリーダンは、ラディカル・フェミニズムの同性愛差別反対の主張に対しては異を唱え、それを運動の主要なスローガンから排除しようとし、他のフェミニストから強く批判された(なお現在のNOWは、LBGTQ差別反対の立場をとっている)。
他方、反資本主義的で社会主義的立場をとっていた左翼のフェミニストも多かった。彼ら・彼女らは、そもそも近代啓蒙思想やリベラリズムの政治思想を、単に資本主義体制を正当化するものとしてしか位置付けていなかったので、それが性差別的限界性をもっていることは、自明だった。また近代社会において女性差別や女性抑圧が続いていることも、資本主義社会の矛盾として、当然だとみなされた。理想的社会は(マルクスが言うように)資本主義社会の変革後にしか生まれないはずだったからである。
また60年代から70年代にかけての先進資本主義諸国において流行した新左翼運動や「新しい社会運動」からは、近代市民革命以降の資本主義社会の政治や文化を否定的に見る見方が強まった。手段的価値を重要視し、あらゆるものを「効率的」かどうか、「合理的」であるかどうか、「金銭的価値を生むかどうか」によって評価し、その評価結果によって、人の行動や活動、あるいは人自身の価値を定めてしまうような近代主義こそが、先進資本主義国の人々が陥っている精神的貧困の原因だと考え、そこから逃れる対抗文化にこそ価値があると考える運動が勃興した。こうした考え方に根拠を与えうる思想として読まれたのが、近代西欧思想を批判的に相対化するフランスのポストモダン思想であった。フェミニズムの中にも、男性と平等に活躍することを目指すリベラル・フェミニズムではなく、「理性」に支配された思考ではない女性性の中に解放を見出すポストモダン・フェミニズムが生まれた。
このようにこの時期においては、近代化とフェミニズムの関係は、これらの「冠付きフェミニズム」のどの立場をとるかによって、異なることになった。逆に近代化や近代主義に対する立場の違いによって、「近代主義的フェミニズム」や「反近代主義フェミニズム」等が対比的に論じられることもあった。つまりこの時期では、「近代化とフェミニズム」は、その人の理論的立場によって選択できる変数であるかのように、扱われていたと、言いうるだろう。