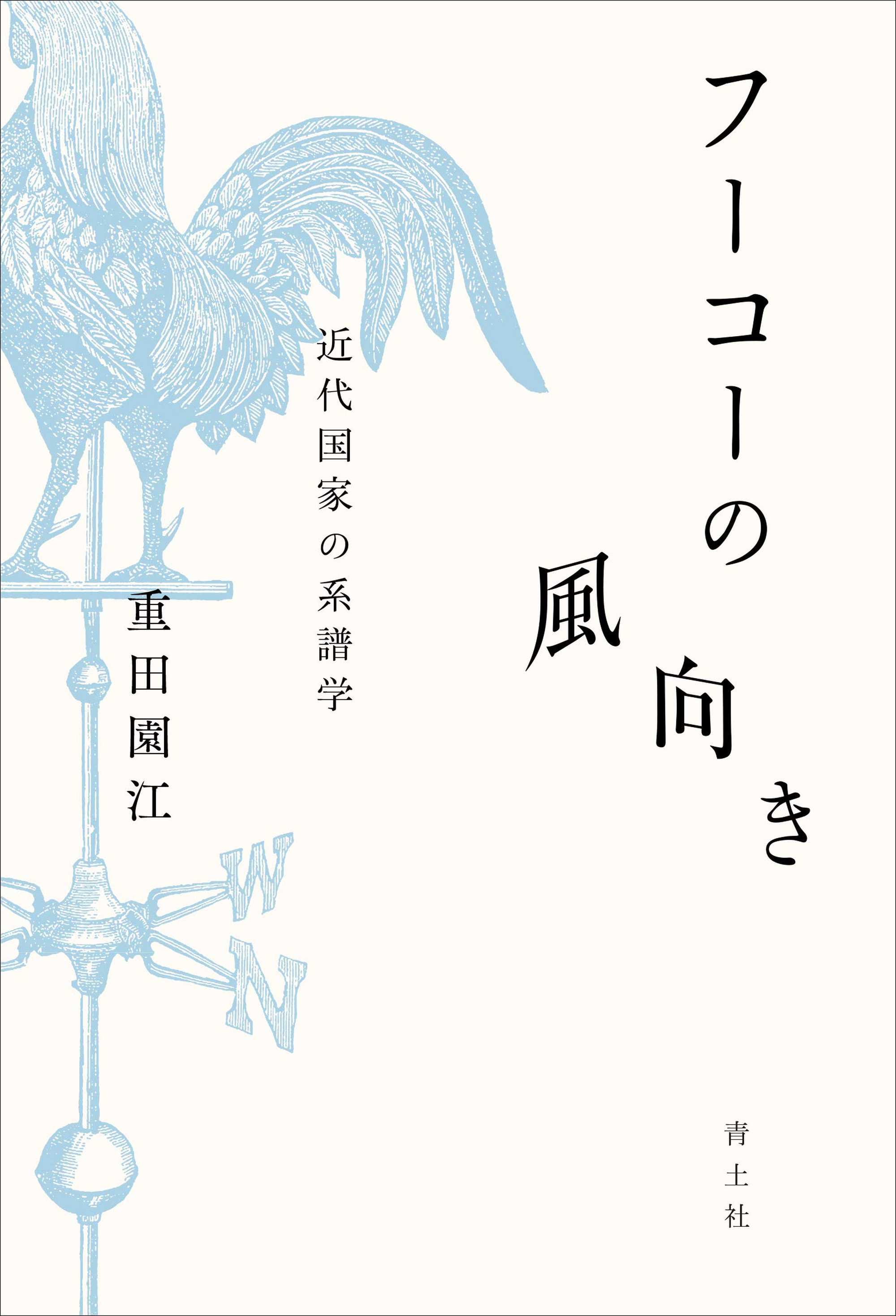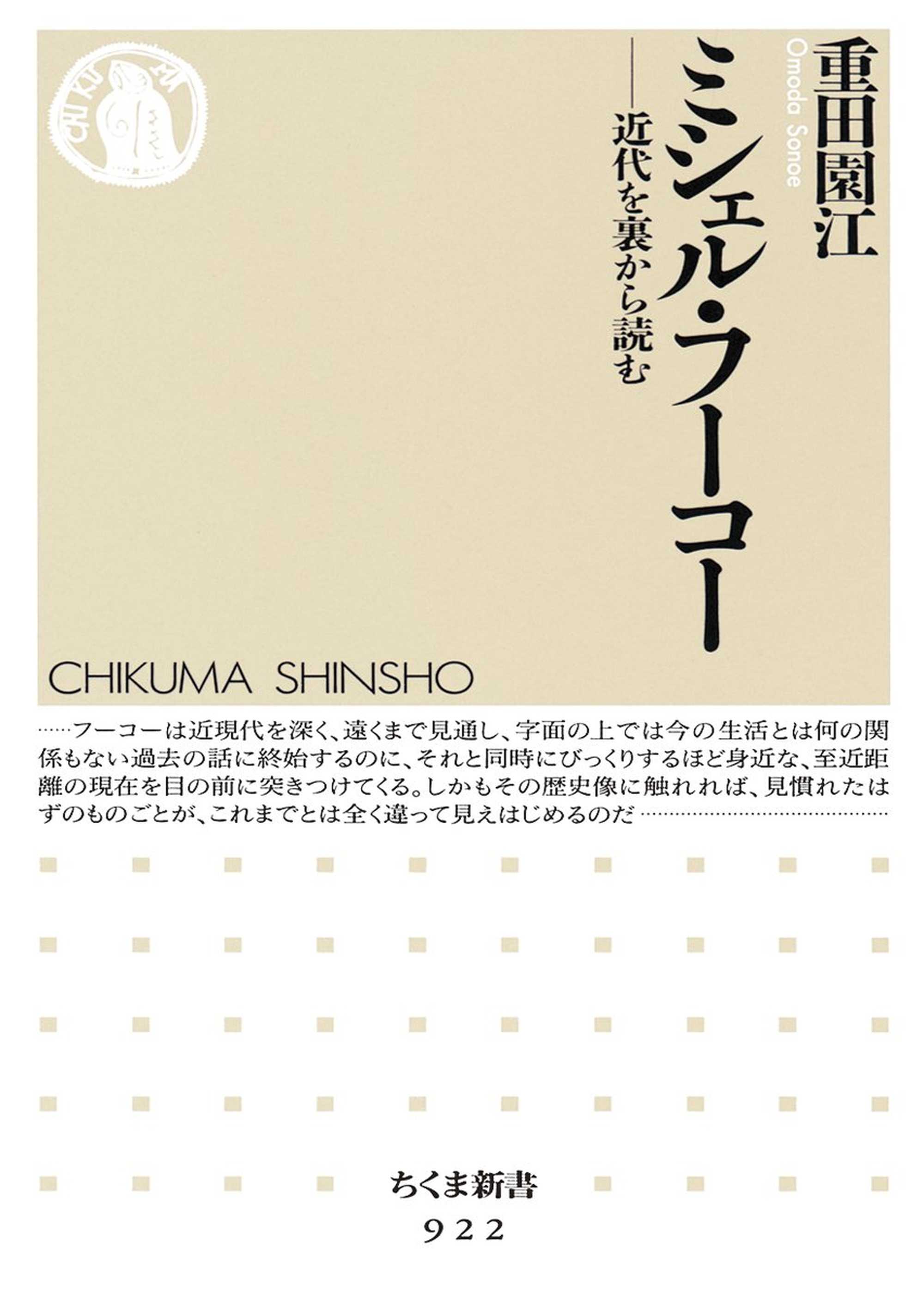――規律による権力を、監獄や学校といった特定の場所ではなく、社会全体において作動させる装置として「ポリス」というものがあったそうですが、具体的にはどういったものなんですか。
ポリスは厚生労働省と財務省と国土交通省と経産省をあわせたような機関です。そこに内務省が加わっている。つまり内政に関わることを全部やる役人です。王権の行政機関として最初にパリで作られ、その後他の地域にも広まりました。
――現代の警察みたいなこともやるんですよね?
ポリスという名称から、そこはよく勘違いされるところです。たしかに警察業務もやることはやります。でも警察って悪いことした人を捕まえるという感じですよね。それよりは秩序の維持というか、悪いことをしそうな人がいたら阻止するというイメージ。なので、スパイ活動なんかもやります。
内務省的というのはそういうことで、単に犯罪者を捕まえるのとは性質がちょっと違う。どちらかといえば予防ですね。予防と管理。その意味で、あまり法的な存在ではありません。法というのは違反者を取り締まるためのものなので、ポリスは法的というよりは行政的な存在。ポリス役人は行政全部を担っているような人たちです。
――公務員は公務員ですか?
そうなんですけど、革命以前のフランスの場合は「官職売買」といって、お金で官職を買うんですよ。出世したければ最初に低い官職を買い、そこでお金を貯めて上の官職を買うということを繰り返す。なので、現代の公務員とはかなり異なります。
たとえば日本の公務員はおかしなことをしたらすぐ懲戒免職になるけど、それに比べて、ポリスの役人ははるかに自立しています。なんせお金を出して買った身分ですから。もちろん、王様が「こいつは駄目だ」といって首にすることもあるけど、国権からもある程度独立した、今見ると宙ぶらりんな存在なんです。

ちなみにフーコーが著書でなぜポリスを取り上げたかというと、一つの機関としてまとまっている分、見やすかったからだと思います。厚労省とか財務省みたいに分かれてなくて、内政に関する権力の特徴が全部ポリスの中に含まれていたから注目したんだと思うんですよね。なぜこんな奇妙な機関があったのだろうと。
――逆に言うと、現代はポリスがしていたことをいくつかの機関が分担しているわけですね。ポリスの役人はどれくらいいたんですか?
数はよくわかりません。ポリスは一番上に警視総監(ポリス総代官)がいるピラミッド型の組織なんですけど、そのピラミッドの下の方の役人は、自分の仕事を補佐する者を自分で勝手に雇うんです。そういった非公認の者まで合わせると、何人いたかっていうのはちょっと数えられない。ただ、フランス革命が近づくにつれてどんどん増えていったようです。
――そういえば「鬼平犯科帳」でも、鬼平が昔捕まえた罪人を手下にして情報を集めたり、取り締まりを手伝わせたりしますよね。
そう、まさに鬼平の世界ですよ。ちょうど同じ時代に、同じようなことが、パリと江戸で起きていた。こういう仕組みがいつからあったのかはよくわかりませんが、少なくとも都市化の中で形成されたものだということはいえると思います。
――そもそもの前提として、都市化ということがあるわけですね。
その点は本当に重要です。この30年いろんなことを学びましたけど、結局、近代は一から十まで都市化がきっかけですよ。都市に人が集まってこなければ、規律なんていらない。農村を規律化することは不可能です。だって、朝9時に畑に集まれといったって、雨が降ったら何もできないんだから。それに農夫って、夏と冬で生活がまったく違うんですよ。夏はほとんど寝ないで働くけど、冬は逆に16時間くらい寝ている。起きていてもやることがない。こういった自然に大きく左右される生活では、規律化は起こりません。
都市が発達してあちこちから人が、それこそ価値観も生活習慣も違うような人がやってくると、すぐにケンカや殺し合いをはじめる。彼らはどこにも根を持たない人びとでした。あるいはスラム地域には娯楽がないから、朝から酒を飲んでいる。そういう状況にいかに対処して治安を維持するか、さらには都市の生産性を高めていくかとなった時に、はじめて規律やポリスが必要になるわけです。
国力をはかる
――すこし視点を変えて、規律というメカニズムの背景にある国家についてお聞きしたいと思います。近代国家は一般的に18世紀末のフランス革命によって誕生したといわれますが、それ以前のヨーロッパの国々はどういう状況だったんですか。
中世のヨーロッパというのは国がまだちゃんとできていないんですよね。王や諸侯と呼ばれる封建領主があちこちにいて自分の領土を治めているんだけど、では全体は何かというと「神聖ローマ帝国」でした。つまり、ヨーロッパというのは一つのキリスト教の普遍帝国であり、その外部には「蛮族」であるイスラム教徒の国があるという世界観だった。
そこから、各地の王朝と王朝がくっついたり離れたりということを繰り返して「領域国家」と呼ばれるものができるのが大体16世紀から18世紀。そして、いま言われたように、18世紀終わりのフランス革命によって国家と国民が重ね合わされるということが起きたわけですが、その前段階でポイントになるのが「ウェストファリア的秩序」というものです。

これは1648年に結ばれた「ウェストファリア条約」にちなんだものですが、要するに、神という唯一の中心によるものではなく、それぞれが中心を持つ複数の国家が並立する世界秩序というものが、この頃からぼんやりと構想されるようになったのです。
そうなると、それぞれの国がどれくらいの力をもっているのかが重要になります。たとえばA国とB国が同盟を結んだら、隣接しているC国が攻め込まれないためには、どこかの国と同盟を結ぶ必要がある。その相手をD国だとすると、AとBの同盟と、CとDの同盟が本当に同じくらいの強さなのかがわからないといけない。その時に、国の力とはそもそも何なのか、どうやったらそれを大きくできるのかといったことが考えられるようになったわけです。他国だけでなく自分の国の力も、誰も知らなかったのですから。
――すぐに思いつくのは民衆の数や領土の広さでしょうか。
そうですね。最初は、人の数は多い方がいいし領土は広い方がいいと考えられていたようですけど、どうもそう単純ではないぞと。たとえばロシアです。ロシアの領土は全体がつかめないくらいに広いけど雪と氷ばっかりだし、農奴はほとんどゴミみたいに扱われている。力はあるにしても、領土の広さや人の数がそのままロシアの国力だとはとても思えない。逆にイギリスはあんなしょうもない場所にあって、天気もずっと悪くて、土地はじゃがいもしかできないようなところなのに、国としてはすごく力がある。それは一体なぜだろうと。
そういった議論から出てきたものの一つに経済学があります。近代経済学の父といわれるアダム・スミスの主著は『国富論』です。つまり、国を富ませるにはどうすればいいかということです。スミスは、労働者の賃金は安いより高い方がいいとか、人びとの自由を認めた方がいい、他国との貿易の差額で儲けるのではなく自国に産業があった方がいいといったことを主張していますが、それらはすべて国力を高めるための方策であり、そこから政治経済学が確立されていったわけです。