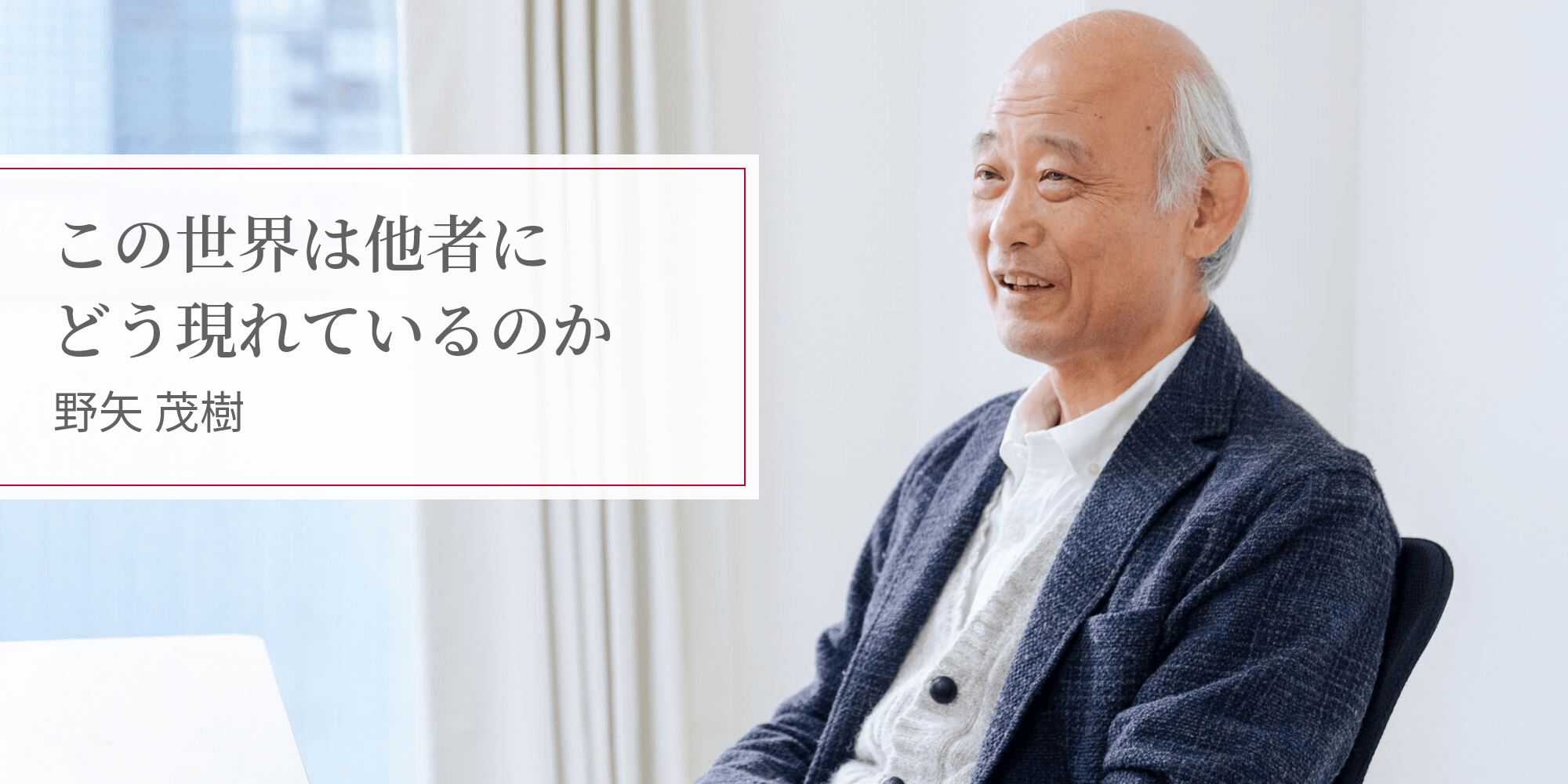じゃあどうするかというと、ここからはなかなか難しい哲学の話になっていくんですけど、いま持っている常識、つまり、ただ一つの客観的世界の中に私たち一人ひとりが生きているという考えを投げ捨てて、ゼロから考え直してみましょう。まず私は刺激の場の中に生まれる。
――刺激の場、といいますと?
たとえば道ばたの石は太陽の光を受けて熱くなっていきますよね。雨や雪が降ると、今度は冷たくなる。そんなふうに物は外界の刺激を受けて変化する。これが植物になると太陽から光を受け、土からは水分や養分を受け取って成長していく。私たちも同じです。外界の刺激を受けて変化していくという点では、人間も石や植物と変わりありません。
でも、太陽の光や風雨にさらされているだけでは、せいぜい植物と同じような生き方しかできない。人間は植物と違って動き回るし、もっと先の話をすれば、人間同士で社会をつくって生きていく。社会的な動物は他にもいますが、人間の社会はやはり独特です。もちろん、こうした言語的コミュニケーションも人間ならではの営みですよね。
このような生き方をしていくためには、自分が置かれている刺激の場を、その生き方にふさわしい形へと秩序立てていく必要がある。いつまでも無秩序な刺激のままでは、食べ物を得たり、雨露をしのいだり、あるいは他人と共同体をつくったりといった行動への指針が得られず、私は死んでしまうでしょう。
――刺激の場を秩序立てる、というのがもうひとつよく分からないのですが……。
たとえば向こうに何かほしいものがあって、それに近づいていくとします。近づくにしたがってその対象の見え方はどんどん大きくなるけど、私たちはそれが違うものになったとは考えない。それはつまり、同じ対象であっても、そこまでの距離や見るアングルによってその対象の見え方は変わるという秩序を見出しているわけです。
さらに、その対象から目をそらしたり、まぶたを閉じると見えなくなるけれども、それは自分がそうしたからであって、対象が消えたわけでも、世界そのものが変化したわけでもないと捉える。
――世界のあり方と自分の行為との関係性を理解していくわけですね。
刺激の場は時々刻々と変化していきますが、私たちはその変化をいくつかの要因によって捉えています。
たとえばそこにリンゴが1個ぽんとあったとして、そのリンゴは小さくなることもあれば、見えなくなることもある。小さくなるのは私がリンゴから――あるいはリンゴが私から――遠ざかったからだろうし、見えなくなるのは私が別の方向を向いていたか、目を閉じていたか、もしくはそのリンゴを誰かが食べてしまったからだと考える。
つまり私たちは、対象との空間的な位置関係、身体の状態、そして対象のあり方という因子の関数として、この世界を秩序立てている。そうすることが私たちの生存に寄与してきたわけです。
――空間的な位置関係と身体の状態と対象のあり方が分かれば、世界のあり方が分かる。
この程度の秩序立てであれば、人間以外の動物も普通にしているでしょう。こう言うと、動物が関数なんて知っているはずないじゃないかと思うかもしれませんが、理屈として理解していなくても、空間、身体、対象という三つの要素で世界を捉えることで、餌を探したり、天敵から逃れたりといったことが可能になっているのだろうと思います。
眺望論
世界を空間と身体と対象の関数として捉えることが他我問題とどう関係してくるのかというと、世界がこういう秩序を持っていることは独我論者であっても認めるわけです。リンゴから離れたら小さく見えるし、目をつぶったら見えなくなる、誰かが食べたらなくなるという秩序を持った世界に自分が生きているということは、かれらも否定できません。
そして、そういう秩序を持った世界であるということは、向こうから見たらこう見えるとか、私が目を閉じたら見えなくなるといったことが、そこにひとつの対象、リンゴならリンゴがあるということの中にすでに織り込まれている。
これはいまこう見えているけど、向こうから見たらもっと小さく見えるという理解がなければ、同じ一個のリンゴがあるとは言えない。だから、もしも向こうに人が立っていたとしたら、その人の目にこのリンゴは、自分が見ているより小さく見えているということを私は知っているわけです。それはその人の主観的世界や脳みそがつくった世界ではなく、この世界のあり方、この世界の秩序なんです。
あそこから見たらこう見えるという形で、われわれは世界を理解している。『心という難問』の中では鎌倉の大仏を例にとりました。私はいま正面から大仏を見ている。横に回れば、正確には分からないけれど、大仏の横顔が見えるだろう。そしていまあの人は大仏の横にいる。だからかれには大仏の横顔が見えているはずだ。つまり、他人と同じものを見たければ、その人と同じ位置に立ち、その人と同じ方向を向いて、その人と同じように目を開けばいいわけです。
――空間的な位置関係と身体状態を同じにすれば、対象が同じように見える。つまり、他人と同じ世界が現れるわけですね。
そういうことです。もう一つ別の例を挙げると、いま加藤さんは頭痛がしていて、私はなんともないとします。じゃあなぜ加藤さんは頭が痛いのに、私は痛くないのかというと、加藤さんと私の身体状態が違うからです。
普通は誰もこんなことを問題にはしませんが、つまり他人と私で見ているものや感じているものが違うのは、結局、どこに立って、どっちの方向を向いているのかという空間的な要因と、身体的な要因の違いで説明できてしまう。そうすれば、その人の主観とか心の中といった言い方をしなくてすむわけです。世界は空間と身体と対象の関数であり、われわれはそれらの要因で決まるアウトプットを受け取っている。こう考えれば他者問題はほどけていくんじゃないかと。
――なるほど。
ただ、これだけで他我問題が解決するかというと、大森荘蔵先生が「野矢君、そうだね」と言って喜んでくれるかというと、そんな甘いものじゃない。こういう他我問題や独我論にはまり込んでしまった人、ヴィトゲンシュタイン的な言い方をすれば「知の病」にかかっちゃった人――正直に言うと、私もその病気にかかったから自己治療したわけですけれども――を治療するには、なんでそういう病気にかかったのかを、もっと立ち入って、ゆっくりゆっくりやっていかなくちゃいけない。そのことが、あれだけ長いものを書かなければいけなかった理由です。
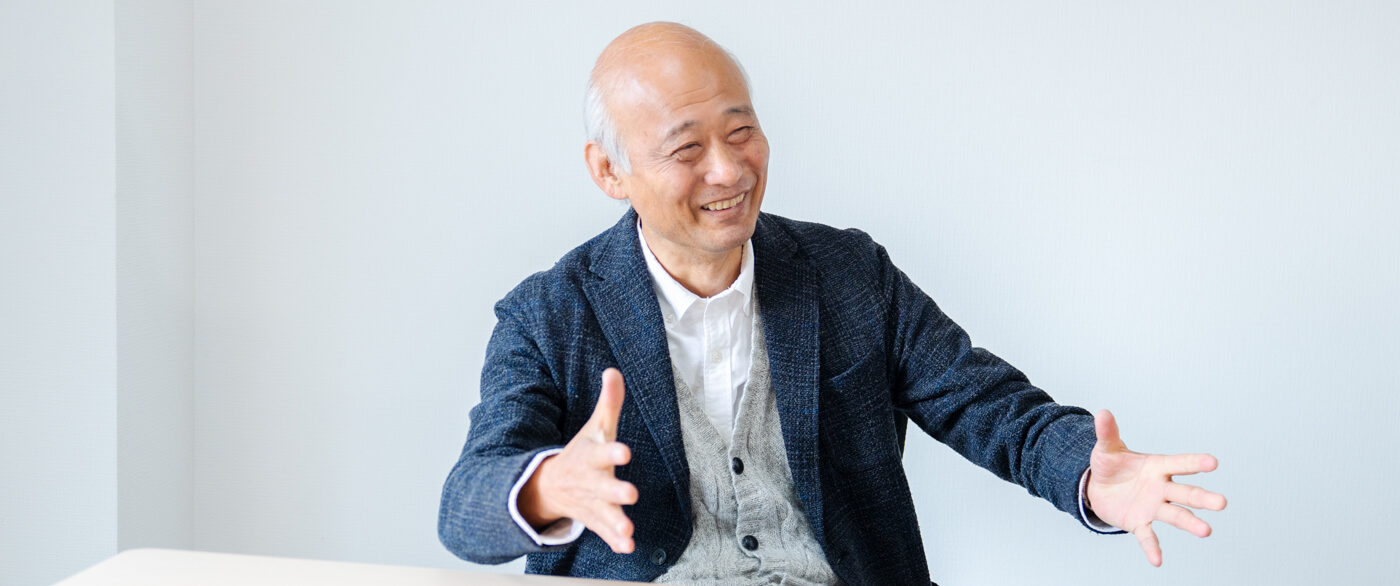
ともかく、いま話したのが議論の前半にあたる部分で、私はこれを「眺望論」と名付けています。そして、視覚や聴覚といった空間的な位置関係によって決まる世界の現れ方を「知覚的眺望」、痛みや熱さ冷たさといった身体状態に起因する世界の現れ方を「感覚的眺望」としました。この眺望論が一応、他人が見ているものや他人の痛みは私には分からないという他我問題を克服する方向を示してくれると思ったわけです。
――同じ場所に立ちさえすれば、誰であれ同じ眺望が現れるということですね。
そういうことです。なんで「誰であれ」と言えるのというと、世界の現れというのは空間的な位置関係と身体の関数として秩序立てられているのであり、そこには私が、あなたが、彼が、彼女がっていう人称的な要素は入り込んでいない。私とあなたがなぜ違うものを見ているのかというと、私とあなたが違う場所にいるからだという、非常にもう、能天気と言っていいような答えを与えるわけです。
でも、こう言うと、他我問題に苦しんでいる人は、いや、そうじゃないと。私は私であり、あなたはあなたであって、私とあなたは違う。仮に同じ場所に立ったとしても、私とあなたは違うんだから違うものを見ているんだ、というふうに、世界の現れを、私やあなたといった主体の関数にしようとする。だから、いかにしてそこに私とかあなたを入れさせず、世界は空間と身体と対象の関数として捉えていいんだと納得させるかが勝負どころになるわけです。