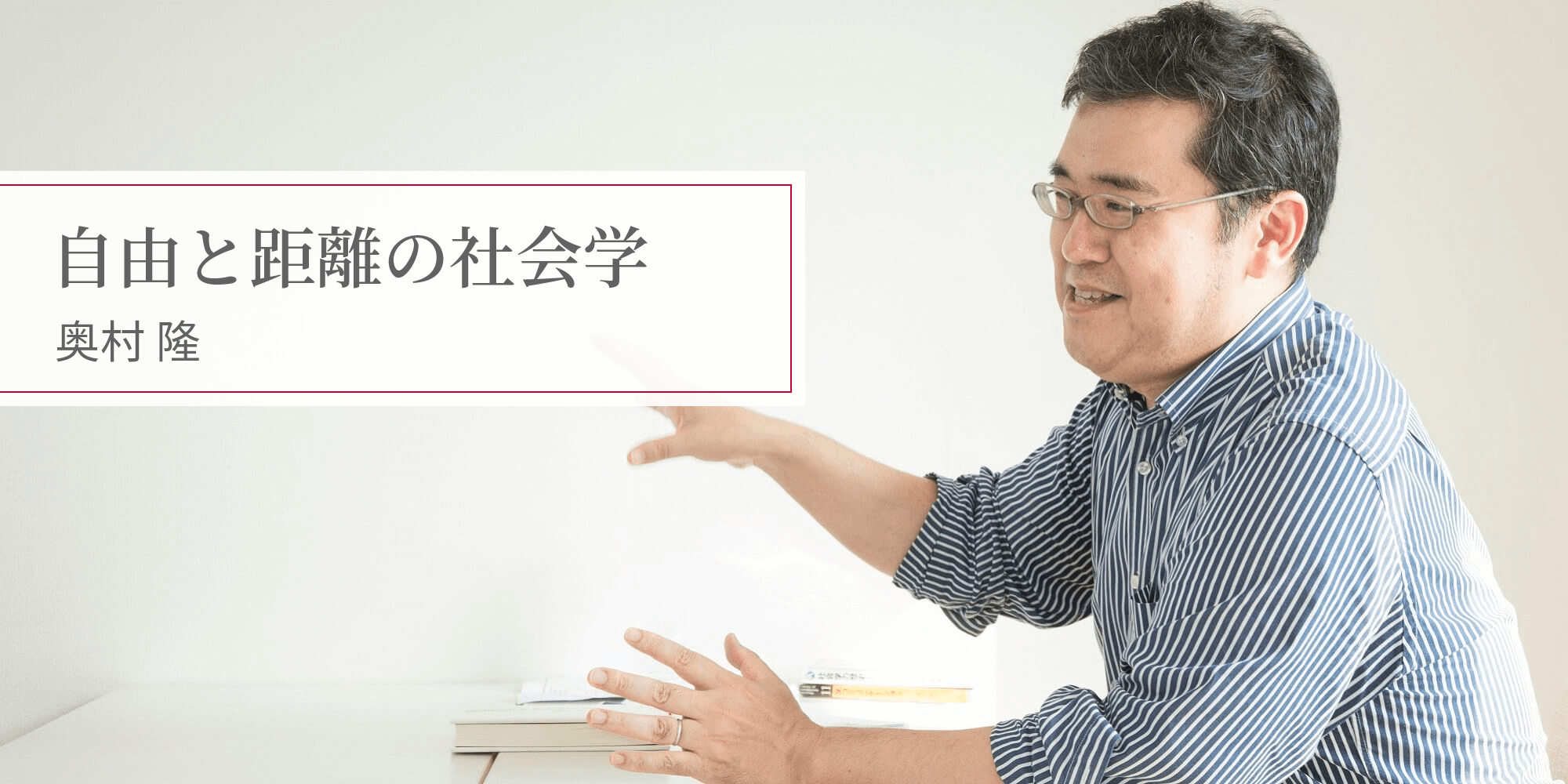「距離」というものを考えたときにいつも対になって出てくるのが、ちょっと雑な言い方ですけど、「自由」だと思うんです。つまり、それぞれの人が勝手なことをできるし、勝手なことを考えられる「自由」。もしもそれがなかったら、他者が何を考えているかを気にする必要もあまりないですよね。大体みんなが同じようなことを考えているか、あるいは、違うことを考えることができないかですから。そういう自由がないところ、それぞれの人が自由に考えて、違う人になり得る可能性がないところっていうのは、いま話したような社会が生まれることはないと思います。
――みんながそれぞれ自由に考えて、自由に行動できる。そのことが得体のしれない、怪物のような他者を生むと同時に、先生のおっしゃる意味での社会を準備するわけですね。
社会学という学問ができたときに、まさにそういう自由が決定的に重要だったんじゃないかと思います。
フランス革命から半世紀ぐらいたった1839年に、オーギュスト・コントっていう人が『実証哲学講義』という本のなかで「社会学」という言葉をはじめて使ったといわれています。彼がなんで社会学というものが必要だと言い出したかっていうと、これはドイツ生まれの社会学者ノルベルト・エリアスの解釈なんですけど、フランス革命後に人々は共通に「社会という経験」をしたからだと。
どういうことかというと、フランス革命前の体制、いわゆるアンシャンレジームは身分社会で、王や貴族が社会のあり方を決めるものすごく大きな力を持っていた。それ以外の人々の自由は非常に制限されていたわけですね。個々に何かを考えるということはあったのかもしれないけど、それを主張することも、表現することもできなかった。

フランス革命というのはすごく簡単に言うと、王や貴族だけで社会を決めるのは間違っているので変えなければいけない、という運動ですよね。それで、王様の首をはねた。社会のことを決めていた一つの間違った意思を取り除いた。こうすれば、自由で、民主的な社会ができるはずだとみんなが思ったわけです。悪い意思を取り除いて、市民たちの良い意思が社会の方向を決めることになれば絶対にうまくいくだろうと。
――すごく自然というか、ふつうはそう思いますよね。
でも、うまくいかなかった。革命後頻繁に体制が代わり、テロリズム、戦争といった大きな混乱が起こった。これはエリアスの言い方ですけど、誰も計画していないような「意図せざる結果」が繰り返し生じた。王様の悪い意思を人民の良い意思に取り換えた結果、王様がいたときとは別の種類の不幸が生まれたわけです。
なんでかっていうと、それは自由になったからです。一人ひとりが自分の意思を持てるようになり、それぞれ、ああしたらいい、こうしたらうまくいくと言うようになった。でもそうなると、王様がいるときとは違って、誰の意思も決定的ではない。
それぞれの人が良いと思ってやってるんだけど、誰の意思も決定的じゃないから、最終的にどこに行くのかが全然分からない。それが民主化であり、自由です。それによって誰も望んでいないことが起こる。まるで自然現象のようです。台風が発生したり、暑くなったり、寒くなったり、疫病が流行ったりするような。それは人間の意思でどうにかなるものではなく、さまざまなファクターが関係し合って起こるわけで、人間がコントロールできない法則がある。それと同じように自由になり民主的になると、それぞれの意思には還元できないような変なことが起こる。
――一人ひとりの意思は良いもののはずなのに、なぜか悪いことが起きてしまうと。
人間の意思を超えて、勝手に動きだすような社会。フランス革命後の人々はそれを経験したんだと思うんです。誰か一人の人の意思が悪いのではない。だから、その社会から距離を取って、観察して、こういう法則があるんだったら、こうしたらいいんじゃないかということを考えなければならない。そこから社会学というものがはじまったんだと思います。
リベレーションとフリーダム
――そのフランス革命のちょっと前にはアメリカの独立戦争があったわけですけど、その二つの違いといいますか。自由や平等という理念を掲げたフランス革命に対して、独立戦争はとにかくイギリスの支配から逃れたいみたいな感じですか。
僕自身は歴史を専門に研究しているわけではないのでそんなに詳しくないんですけど、フランス革命とアメリカの独立戦争について僕が印象的なのは、政治哲学者ハンナ・アーレントの『革命について』という本です。この本の中で彼女は、フランス革命は社会を一つの意思にまとめようとした、と考えるんですね。実際にはさまざまな意思がある。でもそれを、フランス共和国という一つの意思にまとめ上げようとしたと。
フランス革命は王様とともに神様もなくそうとしたわけですけど、じゃあそこが空白になったかっていうと、そんなことはなく、宗教的なものに通じるようないろんな祭典をやってるんです。革命祭典とか、理性の祭典、最高存在の祭典だったかな。
――すごく形而上学的な祭典ですね。
つまり、「理性教」みたいな感じだったと思うんですよ。パリにはカトリックの教会がいっぱいありますけど、それが神様を抜いた「理性の神殿」みたいなものに変えられて、そこでそういうお祭りが開催されてたみたいです。理性という、ある意味で神様に替わるものによって社会をつくろうとした。アーレントはそれを、一つの意思、単数の意思でフランス革命はつくられようとしたと表現しています。
――それが結果的に大きな混乱を生んだと。
もう一つ、アーレントが批判しているのが同情です。フランス革命を動機づけたものの一つは、苦しい生活を送っている民衆を見たより豊かな人たちの同情だったと思うんですけど、同情というものはいくらでも暴力的になり得る、とアーレントは言います。
あんなにかわいそうな人たちがいる、あの人たちを救わなければいけない。その気持ちがエスカレートすると、非常に暴力的な方向へと行ってしまう。アーレントの言い方では、同情は人と人との距離をゼロにしてしまう。最初にお話したこととも通じますけど、いってみればこのテーブルを無くして、僕が「加藤さんはこんなにかわいそうなのか」と感じてしまう。それで加藤さんをいじめてる人に「お前、何やってんだ!」みたいになると。
同情はそういう距離ゼロの状態をつくり、誰か敵をつくり出して、それを暴力的に倒そうとする。フランス革命にはそういうエモーショナルな動きがあったのではないか、とアーレントは言うんですね。
それに対してアメリカの独立戦争の方はどうかっていうと、イギリスの13の植民地が話し合って、独立したいから一緒にやろうぜっていう感じだと思います。考えてることはそれぞれ違うけど、折り合えるところを話し合って決めていこうと。
――独立という共通の目的があったからまとまったわけですね。
これは別の本で読んだんですけど、イギリスとアメリカっていうのは同じエスニシティーなわけですよね。だから、そこに違いをつくるには、理念が必要になる。アメリカという国はイギリスとは違うんだ。それは自由と平等を実現するユートピアなんだ、というふうに差異化した。だから独立戦争も共通の理念があったわけですけど、ただそこで、みんなが違う利害を持ちながら話し合っていこうとした。複数の意思の空間といいますか、違いながら一緒にいる空間があった。

そういう、違いながら話し合う空間のことを、アーレントは「公的領域」と呼び、それこそが「政治」であるというふうに言っています。つまり、フランス革命のように同情して一つになるっていうのは政治の正反対であって、愛もそうだと書いていますけど、愛も同情も公的領域を破壊する。だから、みんなが一つになるんじゃなくて、違った人たちが一つの空間をつくるために、みんなで話し合ってルールを決めよう。憲法を制定するとはそういうことだって、アーレントは考えているようです。
どっちも自由と平等を求めているわけですけど、この二つの考え方は決定的に違うように僕自身も思うんですね。アーレントは、フランス革命は「リベレーション」で、アメリカ独立戦争は「フリーダム」だと言います。前者は抑圧や支配から解放されるという自由。それに対して後者は、みんなで話し合って自由をつくる。そのためにはルールと、話し合いの空間を守るための権力が必要だと言っています。
――リベレーションは既存の支配体制を壊していく運動で、一方のフリーダムは逆に構築していく運動だと。
そうなんだと思います。違う意思を持った人たちが話し合う。こうやってテーブルを間に挟んで話し合うことによってフリーダムは守られるんだ、というふうにアーレントは考えていると思います。