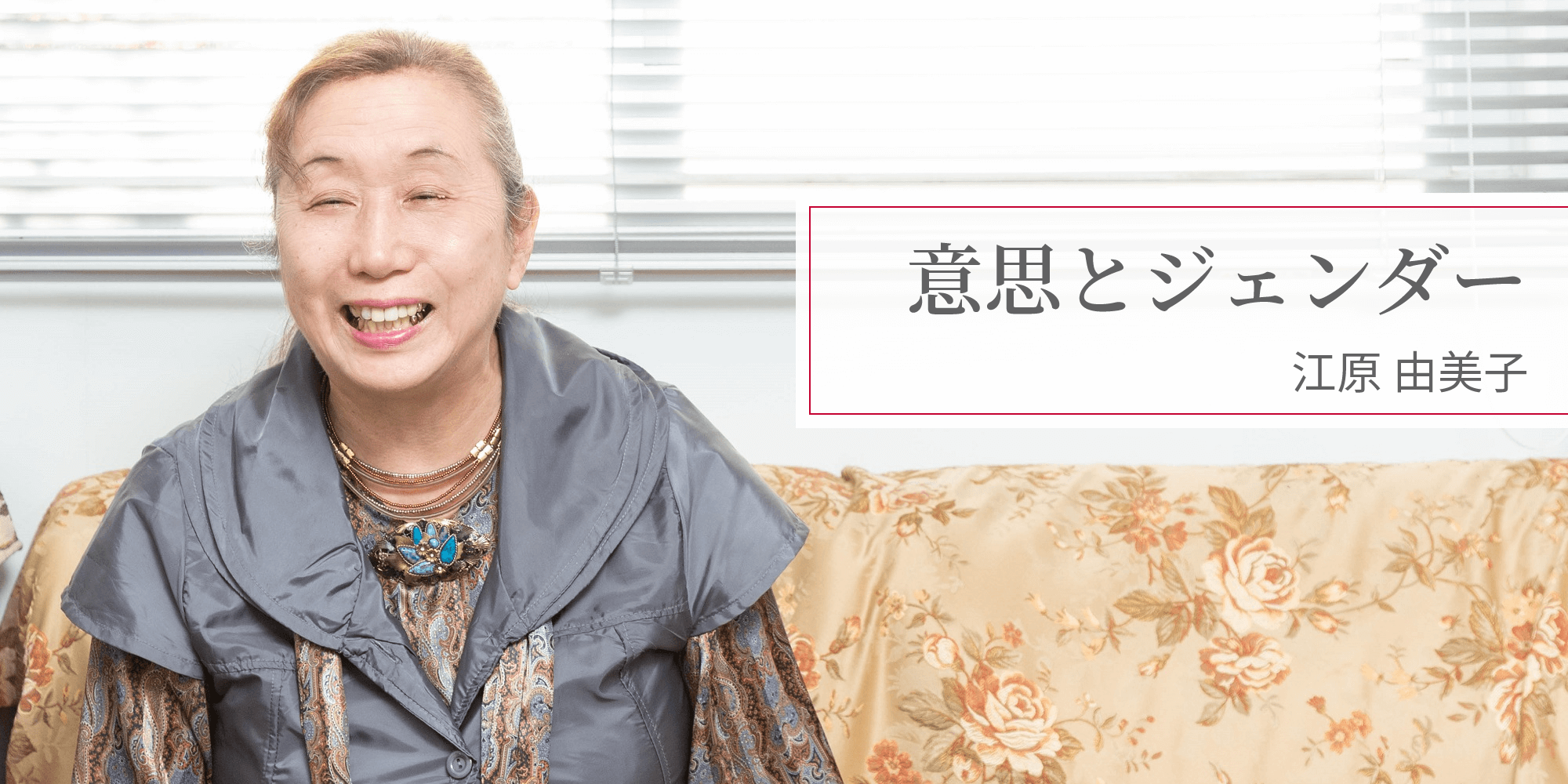――ご著書『自己決定権とジェンダー』(岩波書店)の中で、性別による考え方、感じ方の違いを「ハビトゥス」として捉えるという議論をされていますが、そのハビトゥスというのはそもそもどういう概念なんですか。
ハビトゥスというのは文化人類学や教育社会学・文化社会学などで活躍したフランスの学者ピエール・ブルデュー(1930-2002)の言い出したもので、物事の見え方や感じ方などが、これまでの自分の経験によって規定されるという考え方です。ブルデューは、いい/悪い、おいしい/おいしくない、キレイ/キレイじゃない、心地よい/心地よくないといった感情がいかに階級によって、つまり育ってきた環境によって形作られるかということを重要なテーマとして研究しました。
彼は「趣味」を主題としている『ディスタンクシオン』という本の中で音楽の趣味を取り上げているんですけど、評論家たちは音楽を「洗練された趣味」と「大衆趣味」に分けて、趣味がいい悪いという話をする。
そこでは『美しき青きドナウ』は大衆趣味だとされていて、たとえば労働者階級の人たちはそれを聴くと「いい音楽だ」って感じるんだけど、クラシックのストラヴィンスキーだとか、現代音楽なんかを聴いても、「何これ」って思っちゃう。音楽をよく知っている人がそれを見て、やはり労働者はレベルが低いみたいなことを言うんだけど、そういう感じ方を構成するのは、個々人の資質ではなく、属している階級なんだということを言っています。
仮にそういう階級社会の中で育つと、服でも子どもの頃から着ていて、自分が心地よいと感じるものを大人になっても身に付けるようになるし、自分にとって違和的なものは、たとえ高級であっても求めないようになる。ブルデューはレストランの例も挙げていて、大衆趣味の人たちは、街中華は大好きだけど、高いレストランに行ってもあまりおいしいと思わないといったようなことを書いています。
――何をおいしいと感じるのかは、その人がどの階級に属しているかで決まる、という考えですね。
自分が何を望むか、欲求するかということ自体が、自分の経験によってつくられていく。それがハビトゥスです。そういう風にして身体の中に一度構築されると、「どのレストランに行く? 自由にしていいよ」って言われても、「いつもの定食屋がいちばんうまいんだよなあ」となるわけです。そこから、ある種の自発性を通じて形成される階級再生産みたいなことを論じたんですね。
――労働者階級に生まれた子供はしぜんと大衆趣味のものを欲するようになり、そこから抜け出したいとは思わないわけですね。
フランスという国は文化的な価値観がすごく高く評価されるらしいので、文化的に洗練されてない人びとへの差別感があるみたいです。問題なのはそういうハビトゥスが、大学進学とか、教育上の達成にも大きく影響するということ。学校とか大学というのは基本的に、いわゆる教養を身につけるための場ですから、労働者階級の子どもたちはそういうものに違和感を覚え、早めにドロップアウトしてしまう。すると、次世代も同じような階級が再生産されることになるわけです。
この考え方はジェンダーにも使えると私は思っています。ブルデュー自身、ジェンダーもやろうとしていて『男性支配』という本なんかを書いているんですけど、本格的にやる前に亡くなったんですね。
ブルデューが書いていることので言うと、男は自分を大きく見せようとする。足を開いて、胸を張り、肩をいからせて、できるだけ大きな空間を占めようとする。それに対して女はなるべく細く、小さくなって、空間をふさがないように、人の邪魔にならないようにする。これが男女のハビトゥスだと。
――大人たちがそうするのを見たり、周りからそうするように求められたりして、身体化されていくわけですね。
もともと女は謙虚だとか、つつましいとかって言われると「ん?」ってなるけど、経験によってそういうことを身に付けていくんだっていわれると納得しますよね。

でも、すべての性差はつくられるとか、男性と女性が生物学的に同じだとか、性差なんかないとかいうことを言いたいのではありません。「生物学的」に違うところも、山ほどある。でも同時に、男女の違いが、その社会の持つジェンダーによって構成されているという側面もあるんだってことが言いたい。私たちの身体には、無意識のうちにものすごく多くの社会的なものが入り込んでいて、それが私たち自身の感じ方に影響を及ぼしている。そのことは非常に大事だと思います。
――それで言うと、男女による話し方の違いも大きいですよね。
そうですね、大きいですね。
――こちら(前掲書)にも書かれていましたけど、普段は女子の方が活発なのに、ゼミでの議論や発表の場になると急におとなしくなるっていうのは、確かにそうだなと思いました。
だんだん変わってはきてますけどね。その辺は昔のほうがはっきりしていて、私たちの世代だと、会合等話し合いの場は、本当に男性が牛耳っていました。さらに上の世代になると、女の人が話しているのに遮って、平気で割り込む男性がいっぱいいましたよ。女がしゃべっていても、それはおしゃべりに過ぎないから、無視してよい。俺が話したら重要なんだから、皆聞け、みたいな。
――その男性にとっては、それがハビトゥスになっているわけですね。
今の学生は、その辺はかなり変わってきていますが、まだ多少そういう傾向もあるかな。たとえば論文の相談なんかで私の部屋に来るときに、少なくとも最初のうちは「先生、ちょっといいですか」みたいに、「お邪魔してすみません感」を強く出して言ってくるのは、女子に多く、男子はそうでもない。
逆に、一方的に「何時に行きますから」と都合を聞かずに言ってくる学生もたまにいますが、どちらかといえば男子が多いですね。単に「礼儀を知らない」だけかもしれませんけど、自分がどれだけの存在で、他人からどの程度重要視されて当然なんだと思うかどうかという根本のところに、ジェンダー・ハビトゥスが効いてるかなと思ったりもします。
一人ひとりは単に、自分が「感じのいい人」になろうとしているんですよ。ただ、その「感じの良さ」っていうのが、男版と女版で違うから、男は堂々と、女はそそとしていたほうが評価される。それでだんだんそうなっていくっていうことなんでしょうね。
職業選択の不自由
性別による行動の違いがはっきりすることの一つに、将来子どもを持つことまで考えて仕事を選ぶかどうかがあります。この前ゼミで聞いてみたんですけど、女の子はほとんどが手を上げたのに、男の子はぜんぜん考えてもいない。
――学生のうちはそこまで考えられなくても無理もない気もしますけど……。
でも、女の子のほとんどは考えているんですよ。育児休暇がとれるか、子育てと両立できるかみたいなことを20代の初めでもう考えて、仕事選びをしている。これはつまり、子どもをもつのは誰の問題かっていうことです。女の子は初めからそれに関わるんだって考えてるけど、男の子はいざ結婚して、子どもをもつまで考えない。子どもをもっても考えない人がいるから困っちゃうんですけど。
以前不妊治療の話をしていたら、ある大学院生が「僕に一番遠い話題です」と言っていました。その学生も20代の前半くらいだったかな。だから、数年とか十数年で直面する可能性があるのに、自分にとって最も遠い問題で、関心がないと言う。不思議ですよ、本当。
――子ども産むのは女性で、育てるのも女性だっていう環境の中で生きてきたから、それがハビトゥスになってるんですね。
そうそう。それで「男は考えなくていい」というハビトゥスを作ってるんだけど、実際には当然男も関与してるわけですよ、子ども持つことに。
――じゃないと自分の子になりませんもんね。
確実に関与してるんだけど、子どもができるまで、あるいはつくろうとするまでは、子どもをもつというのがどういうことで、その時にどんなことが生ずるかといったことへの想像力や責任感が欠けている。
それで実際に子どもができて、たとえば出生前診断でその子に障害があるらしいとわかると、妻に「キミが決めればいい」って言う男性がいるらしいんですよ。「キミが育てるんだから、産むも産まないもキミが決めればいい」と。「何それ?!」、ですよね。生殖医療の調査をしてる時にその話を聞いて、もうびっくりして怒りを感じました。
一見、女性の気持ちを大事にしているように見えて、実のところ、「産むこと・子供を育てること」を女性の問題として責任放棄している。二人の子のはずなのに、そういう問題は女性の問題と思い込んでいる。だから、女性が人工妊娠中絶を選択すると、「責任は女性にある」ということで、「子どもを殺した」と女性だけを非難できると思っている男性も出てくるわけです。それはとんでもないことだと思います。
本当は男性も含めてみんなが考えるべきことですよね。障害を持つ子どもさんを産むかどうかっていうのは、障害を持った子どもさんが幸福に生きられる社会を作れているのかということを含めて、私たちみんなが、人間として本当に考えなきゃいけないことで、誰だって避けては通れないはずなんです。
――本当にそうですよね。
自分自身が将来障害を持つかもしれないし、親が持つかもしれない。そういうときの死生観とか家族観にも関わってくる根本的な問題なのに、子どもをもつときに、そこから逃げてしまう男性がいることは、とても残念に思います。