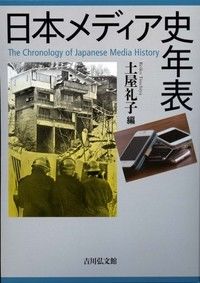――まずはメディアの定義といいますか、どういうものをメディアと呼ぶのかというところから教えていただきたいのですが、先生の編集された『日本メディア史年表』(吉川弘文館)を見ると1837年のモールスの電信機、いわゆるモールス信号の発明からはじまっていますね。
メディアのはじまりをどこにするかというのにはさまざまな議論があり、それこそ古代のアルタミラの洞窟壁画から始めるという考えもあります。しかし私は、メディアは近代科学によって生み出されたものであり、科学技術と人間のコミュニケーション能力が融合したものだと思うんですね。
モールス信号とか無線電信といったものが出てくる前は、たとえば手紙でも、本でも、絵画でもいいんですけど、情報を人が持って歩いていました。人が手紙を持っていって渡すわけですし、本も、人が移動することではじめて移動する。いまだったらAmazonの倉庫みたいに機械が運ぶということもあるかもしれませんが、近代以前はメッセージが人と共に、あるいは人を介して移動していたわけです。
――なるほど。
英語の「コミュニケーション」にはもともと「交通」という意味もありました。つまり、人や物が移動することとメッセージをやりとりすることはイコールだった。ところが電信というのは、人とは別にメッセージだけが飛んでいく。人の移動とメッセージが分離しちゃったわけです。メディアを考える上では、そのことがすごく重要だと思います。
――メディアの画期としては、15世紀の活版印刷もよく取り上げられますよね。
もちろん、活版技術もすごく大きな発明です。それによって本や新聞の大量生産が可能になったという点では非常に重要な出来事なのですが、では人の移動と情報の移動が分離したかというと、分離はしていない。近代の新聞産業が飛躍的に発展したのには、遠く離れた場所のニュースが電信によって、人を介在させることなく集められるようになったことが大きく寄与しています。

――よく分かりました。日本で新聞が発行されるようになるのは明治になってからですか。
新聞の最初がどこかというのにもいろいろあるのですが、大きくは三つに整理できると思います。
一つめは江戸時代末期の1862年(文久二)に幕府が発刊した『官板バタビヤ新聞』で、これは長崎の出島に入ってくるオランダ語の新聞を洋書調所が翻訳したものです。これが日本で一番古い新聞だと言われていますが、実はそれより先に入ってきていたものがありました。当時の船は航海できる距離が短いので、オランダの商人は長崎に着くまでに香港とか上海の港を経由して来ていたんですね。これらの地域は当時イギリスの植民地になっていたので、そこではキリスト教の宣教師が1840年頃から中国語の新聞を発行していたんです。
――布教のために。
そうです。そういった中国語の新聞は、漢字で書かれていたので“華字新聞”と呼ばれたんですけど、それもまた出島を通じて入ってくる。日本の知識人は、中国語は話せなくても漢字漢文は読めるので、ちゃんと理解できる。ただ、その中には当然キリスト教に関わる事柄が入っているので、それらを幕府が削除し、編集し直して出版したのが“官板華字新聞”と呼ばれるもので、『官板六合叢談』『官板中外新報』など何種類か出ました。これが二つめ。
――当時禁制だったキリスト教の宣教師による情報を輸入したっていうのも皮肉ですね。
三つめは、長崎や横浜などが開港されると、いわゆる「外国人居留地」に住む人びとに向けた新聞が、外国人の手で発行されるようになります。かれらは基本的に商売をしに来ますから、時事的な情報が欲しいわけです。最初は長崎で出るんですけど、長崎は江戸から遠いため、幕末には多くの外国人が横浜の居留地に移動してきて、横浜が英字紙発行の中心地になっていきます。英国人ハンサードが出した『ジャパン・ヘラルド』やリッカビーなどが創刊した『ジャパン・タイムズ』がその代表です。
すると、日本の知識人の中にも英語を勉強してそれを読む者が出てくる。福沢諭吉はその一人です。そういった新聞は当然外国人が読むことを前提としているので、日本だけでなく、アジア、ヨーロッパ、アメリカのニュースも載っているわけです。当時は外国人と交流するのもままならなかったので、知識人たちはそういうところから情報を仕入れていたのでしょう。
――幕府の統制下にある当時としてはものすごく貴重な情報ですよね。
新聞の禁止と奨励
――居留地の英字新聞はもちろん、『バタビヤ新聞』にしても“官板華字新聞”にしても、それを手にできたのはごく一部の人だけだったと思うのですが、新聞がもう少し一般に広まるのはいつ頃からですか。
ひとつのきっかけとして、戊辰戦争が挙げられると思います。江戸幕府の下では、そもそも、いまの新聞に載っているような時事ネタや政治経済に関するものの発行が禁じられていました。当時の幕府の政治方針は「民は由(よ)らしむべし、知らしむべからず」、つまり民衆には情報を与えず、指示だけするというものでした。当時の日本の人口の約9割は農民で、教育もなく、情報を与えても騒ぐだけでろくなことがない。武士は支配層として学問が必要でしたが、商人も読み書きを学ぶのは基本的には商売のためで、民衆には余計な知識はいらない、暴動さえ起こさなければよろしいといった感じの、かなり愚民的な見方です。
――命令だけして、理由は説明しない。
そういうところがありました。ところが、倒幕運動がさかんになるとその規制がどんどん緩んできて、時事的なことや幕府批判がかわら版や人びとのうわさによって流通するようになる。やがて戊辰戦争が始まると、倒幕を目指す薩長派は新政府の政治方針を述べるパンフレットのような新聞を出し始めます。その一つに京都で発行された『太政官日誌』というのがあって…
――だじょうかん?
太政官というのは明治維新の年(1868年=慶応四年)の二月に設置された最高行政機関です。おそらく、帝(みかど)を奉じて新しい国をつくるという意図を表すために『太政官日誌』としたのでしょう。日誌はジャーナルなので、要は新聞と同じで、政令や当時の戦況などを載せていました。ただし木版だったので――当時はまだ活版印刷が広まっていませんでした――3日か4日に一度という発行頻度だったようです。対する佐幕派からも、戦況などについて書かれたパンフレットが『中外新聞』『江湖新聞』など20種類ほど出ています。
ただ、当時は『新聞』がどういうものかもよくわかっていないし、記者や編集者という取材体制もないので、正確な報道というより、巷のうわさや落書、要人の誰かが出した手紙などをかき集めて載せていました。
――「報道」という概念自体がまだ理解されていなかったわけですね。
戊辰戦争が薩長派の勝利で終わると、明治政府は佐幕的な新聞や反政府的な新聞をすべて発刊停止にします。残ったのは薩長派の『太政官日誌』と、あとは外国人居留地の新聞だけ。居留地にはある種の特権があったので、明治政府の検閲を免れたんです。その中に、もともと下級武士だった岸田吟香(1833-1905)がヴァン・リード(1835-1873)というオランダ系アメリカ人と一緒につくった『横浜新報もしほ草』という新聞があり、これは英字紙の翻訳記事なども載せて、当時信頼できる日本語新聞として評判になりました。

――新政府にとっては厄介な代物だったでしょうね。
ただ、情報が民衆に届かないのは政府にとっても不都合でした。というのは、政府が進めようとしていることに対して変なうわさが立ち、各地で民衆の抵抗が起こるんです。たとえば、電信のための電線を敷設しようとすると、「あれには処女の生き血が塗ってある」みたいな訳の分からないうわさが広まりました。メディアがないと、それを正すのもすごく大変なわけです。
――『太政官日誌』だけじゃ間に合わない。
ということで明治2年に新聞の新しい条例をつくるんですけど、これは取締ではなく、新聞を奨励するものでした。具体的には、発刊した新聞を政府が買い上げたり、新聞社が日本語の活字を作るのを補助したりして、要は政策を一転させたわけです。これは木戸孝允などが中心になったと言われていますが、結局、新しい文明や新しい社会の在り方を広く知らせる手段として、新聞が必要だと考えたのでしょう。
――政府広報として、みたいな感じでしょうか。
そういうイメージでしょうね。明治政府はとにかく新しい国づくりを進めようとしていましたから、民衆に受け入れてもらわないと困る。そのための情報提供や宣伝みたいなものと考えられていたと思います。
でも、庶民にしてみれば「なんのこっちゃ?」だったと思います。そもそも新聞がどういうものかわからないので、読む人もいない。明治3年に『横浜毎日新聞』――いまの毎日新聞とは関係ありません――という初めての日刊紙が出るんですけど、計算したところ、どうやら最初は500部くらいしか発行されていません。後に『日新真事誌』を発行したジョン・レディ・ブラックという英国人が大きな商店で新聞の購読を勧めたところ、主人に「これ、先日も買いましたよ」と言って断られたというエピソードがあります。つまり、本と同じように一つ買えば十分であると考えて、毎日、毎日、新しいものが出て更新されるという発想がなかったんですね。