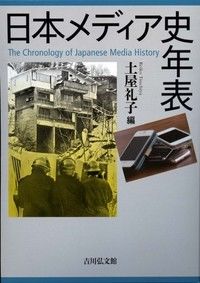――庶民の理解は追いついてなかったにしても、政府の方針が奨励に転じたことで、新聞自体はけっこう出るようになるんですか。
そうですね。明治5年(1872年)に、『東京日日新聞』(現在の毎日新聞)『郵便報知新聞』などの5紙が創刊されます。とはいえ、つくる側にも新聞とはどういうもので、記事にする情報をどう取ってくればいいのかを分かっている人はあまりいないわけです。政府もできたてのほやほやだし、民主主義という思想も理解されていないし、議会制も整っていないので、当初はお上の出すお触れなどをただ載せておけばいいと思っていたようです。
そんな中、先ほど話したイギリス人ブラックが創刊した『日新真事誌』だけは、政府の各省庁と特約を結んで取材をしていました。政府の出した法令や文書をただ載せるのではなく、いろいろな角度から検討したり、問題提起をしたりということを率先してやった。それが刺激になって他紙も取材をするようになり、だんだんと「新聞らしく」なっていったところで、明治7年に二つの大きな出来事が起こります。
一つは「民撰議院設立建白書」。その前年に、いわゆる征韓論でもめて下野した板垣退助らが、選挙による議会、つまり国会の設立を政府に要望する文書を提出した。ふつう政府はこういうものを公開しないんですけど、『日新真事誌』がスクープしたんです。すると、それを読んだ士族たちがそうだそうだと。明治政府ができて以来、彼らはこれまでの特権を失うばかりで不満がくすぶっていました。このスクープがきっかけとなって、「自分たちも政治に参加させろ」という声が巻き起こり、その後の民権運動へとつながっていきます。
――民権運動の火付け役が新聞だったというのは知りませんでした。新聞によってまさに「世論」が形成されたわけですね。もう一つの出来事というのは?
もう一つは「台湾出兵」です。明治5年、宮古島から出た首里行きの船が暴風雨で台湾の南に漂着し、乗組員69名のうち54名がそこの原住民に殺されるという事件が起きました。当時の宮古島は琉球王国の一部だったのですが、政府は日本人が殺されたとみなして、台湾が帰属する清に抗議をした。つまり政府は、琉球を日本のものだと主張したかったんです。

これに対して清は、事件の起きた地域は「熟蕃(じゅくばん)」と呼ばれた自分たちの影響力の及ぶ原住民たちではなく、管轄外の「生蕃(せいばん)」と呼ばれる文明化されていない原住民の土地なので責任はないと言ってきた。実際、その地域には当時「ブータン族」と呼ばれた、首狩り族とみなされていた民族が住んでいて、その人たちに殺されたのです。日本側は、それなら自分たちが懲らしめるというので出兵するわけですけど、そのときに先ほどお話した岸田吟香が、初めての従軍記者としてついて行ったんです。
――横浜で『横浜新報もしほ草』をつくった岸田吟香ですね。
このときは『東京日日新聞』の記者になっていました。彼はすでにクリミア戦争などで従軍記者が活躍したのを知っていました。実は彼の他にも、英字紙の外国人記者エドワード・ハウスが軍隊に同行していて、岸田は正式に認められたわけではありませんでした。軍が嫌がったんですね。新聞記者などというスパイみたいなやつを連れていけるかと最初は拒否されるんですけど、物資を調達した大倉組の手代ということにして、なんとか潜り込んだようです。
――なぜそこまでして行きたかったんでしょう。ジャーナリズム魂?
というよりは多分、彼の中に日本人のナショナリズムを鼓舞しようとした部分があったと思います。
――ナショナリズム
日本政府が出兵を発表したのは軍を乗せた船が出た後ですが、横浜の英字紙はそれ以前からこの問題を取り上げていました。というのは、イギリスやフランスはもっと早くから東アジアに進出して領土の分捕り合いをしてたわけですから、居留地の外国人はそういったニュースを注視していたし、そこで日本がどう動くかにも興味があった。一方で日本の新聞にはそういう情報がないから、日本人は、自分たちの国のことなのに全然知らない。岸田吟香に言わせれば、国民としてそれでいいのかと思ったのでしょう。
――それで、自分が知らせるしかないと。
このときには記事を絵解きした“錦絵新聞(にしきえしんぶん)”も作られているんですけど、それには日の丸が大きく描かれていて、すごくナショナリスティックです。ともあれ、この台湾出兵から戦争時に記者が従軍し、日本国民に向けて報道するというスタイルがとられるようになりました。
記者の仕事
――やっぱり戦争というのが、報道の在り方にしても、読者層の拡大にしても、メディアが変化する大きなきっかけなんですね。
多くの人が関わりますし、家族や親しい人が戦地に行っていれば、安否をできるだけ早く知りたいですからね。それに、後のほうになればなるほど情報戦といったものとも関わってくるので、メディアにとって戦争はすごく大きいです。
――記者が従軍するようになれば、戊辰戦争のときのようにうわさ話ではなく、「事実」に則って記事を書くようになりますよね。
それはありますね。西南戦争の際に『東京日日』の記者として従軍した福地桜痴(1841~1906)は、弾がこんなふうに飛んできたとか、西郷軍の様子はこうだったというように、自分が見たことを記事にして名声を上げました。今では当たり前でしょうけど、当時は画期的なことです。当時の記者は実は自分では取材しないんですよ。
――え、そうなんですか?
文章を書く記者というのは大体が教養のある武士階級の出身ですけど、それとは別に「種取り」という今のレポーターみたいな職種があって、それほど文章の知識のない彼らが市中へ出て取材をしてくるんです。それで、あの事件は誰がどこで何してこういうことらしいですよと報告し、記者はそれを聞いて文章に書く。そういうことが普通に行われていました。だから、伝聞のまちがいも結構多かった。
この記者と種取りの二層制は大正くらいまで続きます。記者が取材もやるようになるのは、基本的には日露戦争後からですね。なので、従軍記者のように、自分で見たものや体験したことを書くというのは、かなり斬新だったと思います。
――軍部は記者のことをどう思っていたんでしょうか。
軍は基本的に秘密主義なので、岸田吟香のときのように、新聞記者なんてものは信じられんというのが本音でしょうね。軍が従軍記者を正式に認めたのは、日清戦争が初めてです。
――それまでは正式じゃなかったと。
いうなれば勝手について行ってたのです。ただし、戦地に入るためには何らかの身分証明が必要なので、適当な役職を名目としてもらっていました。西南戦争の時の福地桜痴は政府軍の書記という役目を得て、その傍らで記事を書き送るのを認められたので、特例というべきでしょう。こうした先例とはちがって、日清戦争の時に「新聞記者従軍規則」が定められて公式に認められ、記者証をつけるとか、検閲を受けるといったことがシステム化されました。
でも、これが変なところですけど、日清戦争のときの従軍記者は武装しているんです。いまだったら大変ですよね。戦地のプレスが銃なんて持っていたら、戦闘者とみなされて撃たれますよ。だから丸腰が絶対なのですけど、日清戦争の記者たちは勝手に日本刀や銃を持って行って、場所によっては戦闘に参加していたようです。もしかすると、自分は軍隊と同じく国家の代表だ、みたいな感じだったのかもしれません。特に「対外硬」と呼ばれた記者たちには、日本は自主外交すべきだとか、朝鮮は征服すべきだという思想がありました。

――それは記者の多くが武士階級の出身だったっていうのと関係してるんですかね。
それもあると思います。ナショナリズムの観点で言うと、日清戦争当時の紙面を見ると、清国の人びとや文化に対して、ちょっと信じられないくらい差別的な表現がされています。
――日清戦争の10年後には日露戦争がはじまりますが、そのときの紙面はどうたったんですか。
国内の日本語の新聞を見る限り、ロシアに対してはそれほど差別的ではないですね。ある程度公平な報道がされています。重要なのはこのとき、日露開戦が正しいかどうか、つまり、戦争をすべきか否かという議論が新聞で起きたことです。東京には当時『東京日日』とか『萬朝報』といったさまざまな個性的な新聞があったのですけど、それぞれが主戦論派と非戦論派に分かれて論争を繰り広げています。これは日本のジャーナリズム史上極めて珍しいことで、戦前はほぼこの時だけです。
――それくらい、日露戦争には国の存亡がかかっていたと。
それはもちろんありますが、当時の日本は世界の一等国の仲間入りをしたかったので、国内だけでなく、国際的な世論も意識せざるを得なかった。なので、進んだ民主主義国家の原則である「言論の自由」を認めないのはまずいという意識が政府に働いたのだろうと思います。それに、このときには海外で国家予算の何倍もの国債を発行しているので、国際世論を無視してそれが売れなかったり、暴落したら困るわけです。そのお金で戦争をするのですから。そんな事情もあって、各紙が自由に議論を戦わせることができたのではないかと思います。