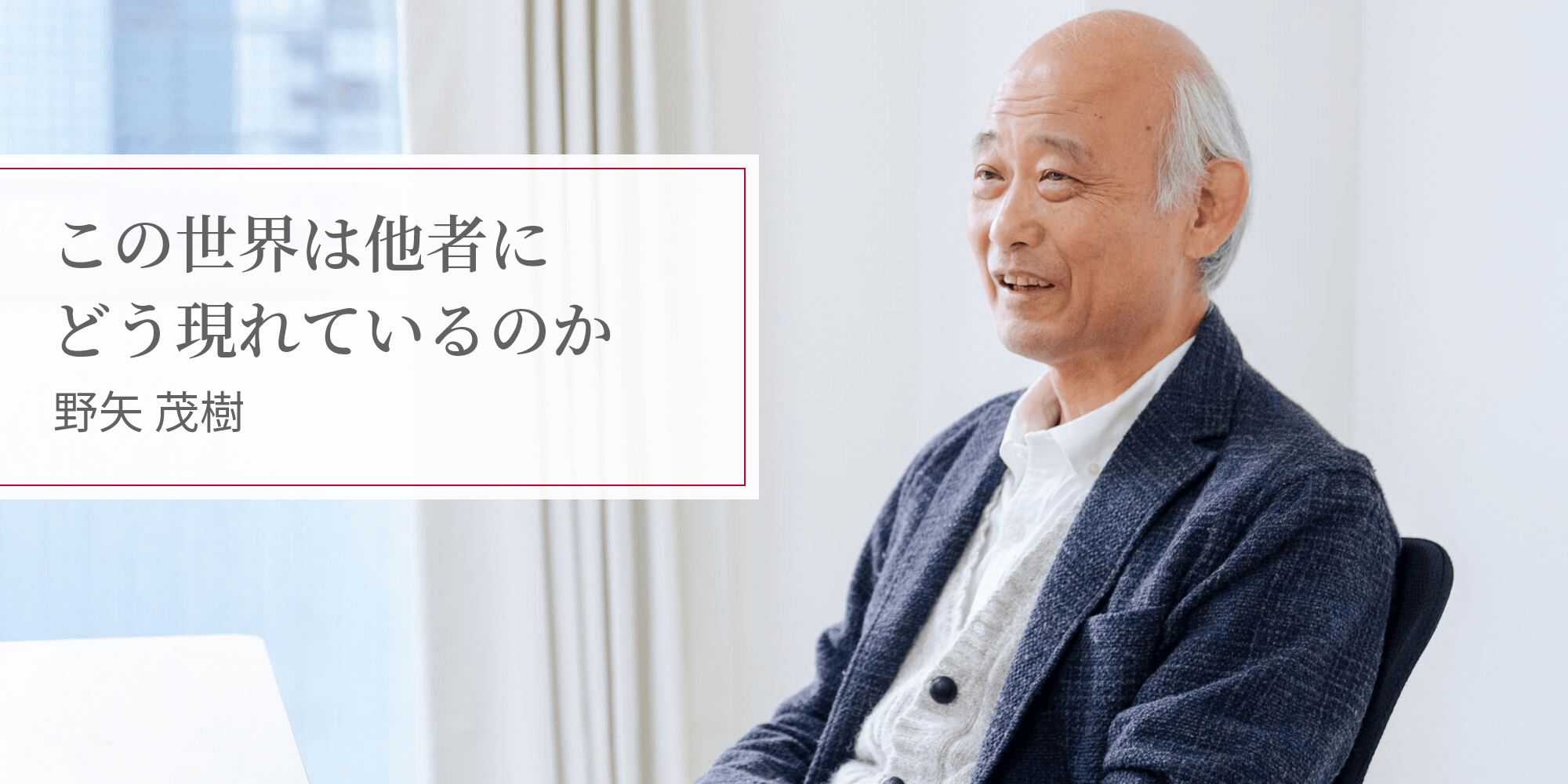――「独我論」というものを初めて知ったときに恐ろしい、というのとはすこし違うんですけど、いま立っている足元が揺らぐような、すごく奇妙な感じがしたんです。この世には自分しかいないかもしれない、他人は存在していないかもしれないなんて、絶対そんなはずがないのに、理屈上それを否定することはできない。それがなんて不条理なんだろうと思っていたのですが、先生の『心という難問』を読んで光明が射したというか、世界や自分をそう考えればいいんだって。ですので、今日はその辺りのお話をお聞きできればと思います。
わかりました。
――まずは先生が長年向き合ってこられた他我問題とはどういうものか、といったところから教えていただけますか。
いちばん素朴なところとして、私たちには他人の気持ちは分からないという漠然とした思いがあります。それはぜんぜん哲学的な発想じゃないし、不健全でもない。当たり前のことですね。ここですこし考えてみたいのは、人間以外の生きものは痛みを感じているのかってことです。これは簡単そうで、実は非常に難しい。
たとえば魚は人間に手で持たれると実は非常に熱いんだとか痛いんだといった話を聞きますし、スイスではロブスターを生きたまま茹でることを禁じる法律があるそうで、理由はロブスターに苦痛を与えないようにということのようですが、ロブスターが痛みを感じているかどうか、どうしてそんなことが分かるんだろうと思うんです。
仮に脳波を調べて変化が見られてもそれが痛みと関係しているかどうかわからないし、人間の痛覚神経に対応するようなものがあったからといって、それが痛みを生み出しているとは限らない。つまり、かれらが痛みを感じているかどうかは原理的に分からないわけです。
そこから考えていくと、じゃあ、人間同士だってなんで分かるんだろうという気持ちになる。日常的な感覚でいうと、他人の気持ちはある程度は分かるけど、完全には分からない。ところがこれを理屈で押していくと、実はまったく分からないんじゃないかという気持ちになってくるんです。
――なるほど。
哲学には伝統的に「逆転スペクトルの懐疑」と呼ばれるものがあります。これはどういうものかというと、たとえば誰かといっしょに歩いていると、交差点で信号が赤になった。それを見てお互いに「赤になったね」と同意はするんだけれども、相手にその「赤」という色がどう見えているのかは分からない。もしかすると、自分なら「青」あるいは「緑」と呼んでいる色をこの人は「赤」と呼んでいるかもしれない。体系的に、つまり他のすべての色についても同様に食い違っていたら、その違いに気づけないわけです。
そう考えていくと、この人が見ているものも、さらには見ているのかどうかさえ分からなくなってくる。見ているような振る舞いをするけども実は見ていない、痛いような素振りをするけど実は何も感じていない。そういう存在を哲学では「ゾンビ」あるいは「哲学的ゾンビ」と言いますが、他人が、いまだったら加藤さん(編注:質問者のこと)がその哲学的ゾンビではないことを証明しろと言われても、できないんです。われわれが手にできるのは他人の外面的なことだけであって、内面的なことはまったく分からない、そんな気持ちになってくる。
これが他我認識の懐疑というやつで、この問題の特徴は、日常的で健全な、他人の内面はある程度は分かるけど完全には分からないよねというところから、原理的にまったく分からないという、非常に不健全な、グロテスクな懐疑に入り込んでしまっているところです。
――たしかにグロテスクですね。
私は大森荘蔵先生のもとで哲学を学びましたが、大森先生はこういった問題をさらに突き詰めて――病が深くなったとも言えるのですが――、もう一段深いところまで行かれました。が、今日はそこまではやめときましょう。私にとってこの他我問題は大森先生にもらった宿題みたいなもので、これに一応自分なりの解答を提出したのが『心という難問』という本なんです。結局30年以上かかりましたけど。
心身二元論
――他我問題に対して、まずは何から手をつけていけばいいのでしょうか。
先ほど、私たちに分かるのは他人の外面だけで、内面についてはぜんぜん分からないという言い方をしましたが、なぜそうなるのかというと、他人を内と外に分けちゃってるからなんです。外面的なもの、つまり言動や振る舞いといったものと、内面的な心とを分けて考えるのを「心身二元論」と言いますが、まずはこれを何とかしなくちゃいけない。内と外を分けてしまったらもう他人の外側しか受け取れず、内側は分からないというところから抜け出せません。
――人間を心と身体に分けて捉えるというのは当然のことに思えますけど、そこにこそ問題があると。
心身二元論の前提になっているのは、われわれは一つの客観的な世界の中で、それぞれの主観が生み出す世界を生きているという考え方です。最近は特に脳科学がこういった考えに拍車をかけています。テレビの特番なんかでよく脳科学者が「すべては脳が生み出している」みたいなことを言いますよね。
たとえばいま私に見えているこの部屋も、机も、加藤さんも、実は脳が見させている。つまりこれは主観がつくり出した世界であり、それとは別に客観的世界というものがあるんだというイメージが、漠然とながら、今のわれわれの常識になっていると思うんです。
この考え方からすると、じゃあ私はどこにいるのかといったら、私に現れているこの主観的な世界、脳が見させている世界の中に閉じ込められていきます。それを極端にまで推し進めると、もしかすると私は脳みそだけなのかもしれない。だって、脳みそに刺激を与えさえすればどんな風景でも見えるし、音も聞こえる、痛みも感じる、お腹もすく……。すると私はどこかの実験室にある培養層の中の脳みそで、マッドサイエンティストがそれをいじくっているだけなのではないか、といった荒唐無稽な話になっていくわけです。
その根本にあるのが、客観的世界の中に脳みそを持った人間がいて、その脳みそがそれぞれの主観的な世界、つまりは心あるいは意識と呼ばれる世界をつくり出してるんだ。こういう世界観というのか、人間観だと思うんです。
――よくわかります。
こういうふうに考えちゃったらもう、他人の主観的な世界、加藤さんの脳みそがどういう世界を生み出しているのか私には分かりようがない。私が見ているのは、私の脳みそが生み出した世界だから。そして、私はその世界の中で生きているわけだから、客観的な世界は手の届かないところに行ってしまう。これを純粋に、潔癖に考えたら、独我論です。

これは私の意識の世界であり、私が死んだらぜんぶ消える。他の人の世界はどこかにあるのかもしれないけど、それは私の知ったことではない。とにかく私は私の意識の世界の中で生まれ、日々起きて、眠る。夢はまさに意識の世界ですけど、夢と区別がつかない、まさにデカルトの夢の懐疑と同じような構造が出てくるわけです。
ここに、つまり客観的世界と主観的世界を分けてしまうところに――これもやはり二元論です――他我問題の根っこがあると思うわけです。
――いまのお話をお聞きして思い出したんですけど、以前、病院で内視鏡検査を受けてるときに奇妙な感覚に陥ったことがあって。お医者さんがカメラを操作しながらモニターを見せてくれるんですけど、自分の体の中をいま自分が見ている。でもこの映像は、先生がさっきおっしゃった通り、脳がこういう知覚イメージを構成しているということだろう。じゃあ、もしも内視鏡がこのまま脳まで行ったら、脳が脳の知覚イメージを生み出すことになるのか。そうなると自分というのは何者で、一体どこにいるんだとか考えてるうちに気分が悪くなっちゃったんです。
普段見られない体の中の映像をリアルタイムで見せられると、リアルとバーチャルの境目がなくなっていく感覚になるのかもしれませんね。
――体内をどれだけ探しても、心は見つからない。すると自分が胃や腸や脳といった部品で構成されている機械のように思えてしまって、いま見ている自分は何者なんだろうと。
それも結局は心身二元論的な発想にとらわれているんです。身体や脳みそを調べたって心が出てくるわけではない。全部が物理現象にすぎない。するとそれ以外に何があるのか。これをもう少し科学者っぽい問い――「ぽい」だけでぜんぜん科学者の問いではないと思いますが――にすると、物理現象の中でどうして意識現象なんてものが生まれ得るのだろうか、みたいなことになる。そこが不健全なんです。