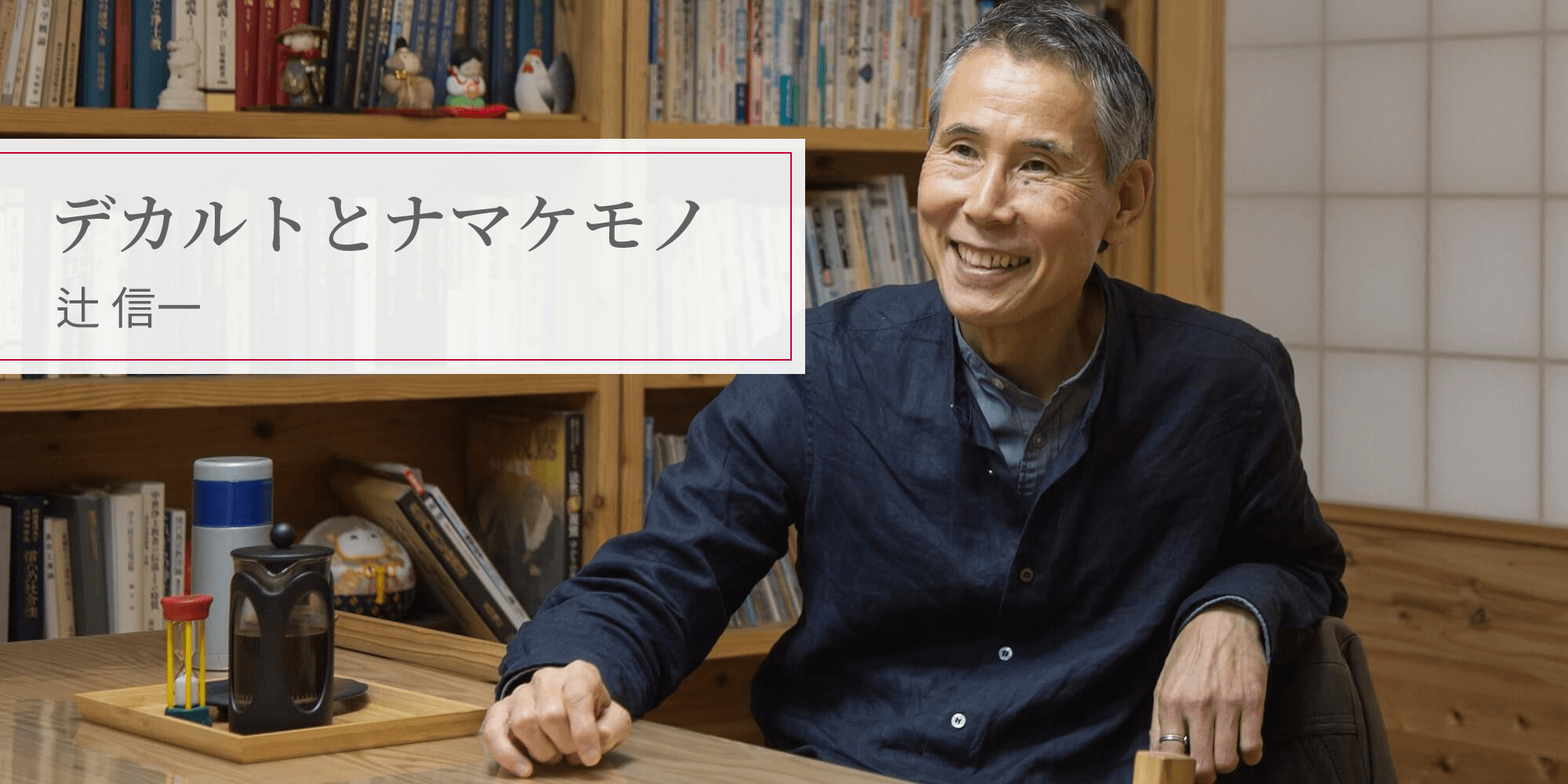――先生はさまざまな活動を通して自然破壊への警鐘を鳴らしてしておられますが、自然破壊とは簡単に言うとどのようなものですか。
自然破壊はいろいろなレベルで語れますけど、一つは空気や水の汚染ですよね。生き物というのは空気や水によって生きてるわけなので、それが汚染されれば、生態系全体に深刻なダメージを与えるという単純なことです。ゴミによる汚染、プラスチックによる海の汚染、排気ガスによる汚染などがありますね。
でもそうした目に見えるものから、今ではもう一つ違う次元の環境破壊が起こっている。CO2をはじめとした温室効果ガス。あれって、二酸化炭素自体が汚染物質なわけじゃなくて、問題なのはその割合なんです。大気中の二酸化炭素の割合は、少なくとも60万年~100万年の間、350PPM、つまり、空気のうちの0.035%でほぼ一定だったという。割合が一定ということ自体が驚くべきことですけど、それによって気温もまた一定に保たれていた。この奇跡のようなメカニズムを温室効果っていうんですけど、温室効果ガスの一つであるCO2の割合が上がってその効果が高くなりすぎると、気温がどんどん上昇していく。
――なるほど。
二酸化炭素が一定に保たれるメカニズムがどういうものなのか、実はまだよく分かってないらしいんですが、それによって地球の平均気温が15度くらいに安定し、数千万といわれる種の多様性が可能になり、地球は文字通り、命の星になったわけです。ところが、それを支えてきたメカニズムが狂ってきたせいで、生態系の微妙なバランスが崩れてきている。0.035%が0.04%になったという、五感では感じられない微妙な変化なんだけど、それが温暖化や気候変動を引き起こしているっていうんだから、分かりづらい。
――システムが壊れてきているということですか。
「壊れる」というのはちょっと文学的な表現かもしれないけど、とにかく変化している。それを気候変動っていうわけです。これが何を意味するのか、本当のところはまだよく分からないらしい。でも科学者の大部分が、これは二酸化炭素の排出を急激に増やしてきた人間活動の結果だと考えている。とにかく長く保たれてきたバランスが、今、大きく乱れてきているってことは確かだとぼくは思っています。
――新聞やニュースなんかではたまに目にしますけど、日本でふつうに生活していると、その変化や重大さに気づくのはなかなか難しいですね。みんな他にもいっぱい問題を抱えていますし。
でも、気温や空気や水っていうのはまさにぼくたちの生存の基盤ですから、ある意味これ以上大変なことはないわけですよ。それなのに、おっしゃる通り、これが最大の問題であるという認識があまりにもない。それこそが最大の問題ですね。

環境問題っていうと、動物が絶滅してかわいそうとか、砂漠化で暮らせなくなってかわいそうとか、他人事として話す人が多いんです。でも、そうじゃない、これはぼくら自身の危機なんだとまず気づかないと。で、この自然破壊というものの原因を考えていくと、行き着くところは、人間が自然から切り離されたことだ、とぼくは考えています。
――どういうことですか?
自然から人間が切り離されることで、人間にとって自然は「自分」の外側にあるものとなる。自分と切り離せないものではなくなってしまう。そして自分が自然の一部であるとか、自分の中に自然が生きているとか、という感覚がなくなる。すると、その外なる自然を単なる手段と見なしたり、資源と見なしたり、またそれを汚染したり、破壊したりすることも平気になる。しかし、自然を破壊すればどうなるかといえば、自分たち自身の生存条件が損なわれ、結局は自分自身も壊れてゆく。それは普通、身体的な意味での危機として語られますけど、実はそれ以上に心の在り方が大きく乱され、危機を迎えているのが現実だと思う。その兆候は今、至るところに見られます。
ぼくは大学で教えていますが、若者たちには身体的な病も、精神的な病もあって、ますます一般的になってきている。ひと昔はなかったような身体の問題があり、それとほとんど切り離し難いものとして心の病がある。元来、身体と心は一体で切り離せないものですけど、かつてぼくたちが「病気」という言葉で想定してきたようなこととはちょっと次元の違う、心身一体の病気が広がっている。ぼくたちは今、そういう時代に生きているんだと感じています。
ぼくは、これは個人の問題ではなく、社会全体の問題だと思っている。つまり、社会が病んでいると考えたほうがいいと。話を戻せば、環境問題や生態系の危機といった問題は、人間の思考方法と営みが引き起こしたものだ、ということ。そしてそれは単に、人間の外側にある自然が危ない、ということじゃなくて、われわれ自身の存在の基盤――単に物理的、身体的な基盤だけじゃなくて、社会的、精神的な基盤――が崩壊していくということだと。
「学びほどく」
――自然のメカニズムや生態系といった生存の基盤にかかわる問題を、私たち自身が最大の問題だと認識していない。その理由としてはどんなことが考えられますか。
ちょっと先回りして言うと、いろんなことが大変だといって、たくさんの人が活動しています。でも多くの場合、これはぼく自身が長い間活動していて気づいたんだけど、いつの間にか、自分だけをどこか例外的な場所に置くようにして、その場所から「これが問題だ」、「あれが問題だ」って言ってる感じなんですよ。でもいつだって自分は問題の一部だし、多くの場合、自分こそが問題なんです。みんなそれを忘れている。逆に言えば、絶望的に見える問題であっても、自分を変えることはできる。これは希望だなって思う。
――自分の外部に問題があるんじゃなくて、その問題の中には自分自身も入っている。スーパーマンのようにやって来てかっこよく解決する、ということじゃないんですね。
そう。で、どうしてそういうことになるのかってことなんだけど、近代のマインドセットというか、心の枠組みに関わってくるんじゃないかと思うんです。心と体、自然と人間、私と世界といった二元論。まさにデカルトが言ったような二項対立の世界です。
何世代にもわたって、ぼくらはそういう二元論的世界観の中で生きてきた。子どものときからそういうものを空気のように吸って、教育を受け、またそういう教育を受けた大人たちに育てられてきたわけですから、それはもうぼくたちの中に染み付いていると思う。だから、まずはそれを何とかしていかないと……。ぼく、よく「unlearn」っていう英語を使うんですよ。
――アンラーン?
ぼくにとってのキーワードでね。
――学ばないっていうことですか。
そう思うでしょ。learnの反対だから、学ばない、忘れる、ってことかなと。でも違うんです。英語ではよく使う言葉なんだけど日本語に訳すのが難しい。ぼくが勝手に師と仰いできた故鶴見俊輔さんの訳では、学びほぐす、だったかな。あるいは学びほどく。ほぐして、ほどいては、また編み直す。そんなふうに学びをほぐしてはまた学び直していく。
――学んだものを固定化しない。
現代の日本の教育っていうのは、子どもを空っぽの容器に見立てて、その中にどれくらい詰め込めるかを競争してるみたいなところがあるでしょ。でも本来、教育はそういうものじゃなくて、もともと自分の中にある可能性を引き出していくもの。一説によると、エデュケーションの語源はラテン語で引き出すという意味の「エドゥカーレ」だそうです。種子のように内側に秘められた可能性を引き出していく。もちろん種子が育つためには、空気、水、太陽の光、土などが必要です。人間にも外からの手助けが必要だし、刺激や情報や知識も必要でしょう。

でも現代の詰め込み教育はどう見ても異常です。プレッシャーと情報過多と知識過剰で、子どもたちはもう自分が何の種だったのか、思い出せないくらいじゃないかな。つまり、自分を見失っているんです。何かを学んだら、それをほぐして、ほどいて、また学び直す、というスローな教育に戻らないと。大人のぼくたちも同じです。自分自身を縛ってきたマインドセットをunlearnしていく。もちろん容易なことじゃない。でも、今の危機的な状況の中で、それを避けて通ることはできない。でも多くの人がそれを避けて、最新のテクノロジーや発明によって、どんな深刻な問題も解決できると思いたがっている。でも、それは幻想だと思います。
――すごくよく分かります。便利な生活を一度知ってしまったら、もう元の生活には戻れないとかってよく言われますけど、私、それにすごく違和感があって。そんなことないだろうって思うんですよ。そんな根拠なんてどこにもないのに言い切られると変な説得力が出て、そうだよね、ってなっちゃう。それがおかしいって。
確かに、それ、よく聞きますよね。
――ぜったい嘘だと思うんですよ、そんなの。
環境運動や社会運動をしている人たちも過激なことを言っていると思われたくないから、そういう問いにちゃんと向き合わないで、いやいや、極端なことを言ってるんじゃないんです。「便利で豊かな」生活をそのままにしてもできることはありますよ、要はバランスです、なんて、そんなふうに言いがちですよね。
でも、ぼくもおっしゃるとおりだと思う。そこには大きな問題が潜んでいる。そこにあるのは一種の怖れなんです。この「便利で豊かな」社会には抗いがたい力があって、それにたてつくわけにはいかないし、それに慣れきった自分を変えることなどできないし、変えたくもない。そもそも人間はそれほど強くもない、みたいな。
――そうですね。
でも、ぼくはこの「便利で豊かな」っていうマインドセットを、やっぱり一度しっかりunlearnしなきゃいけないと思っています。