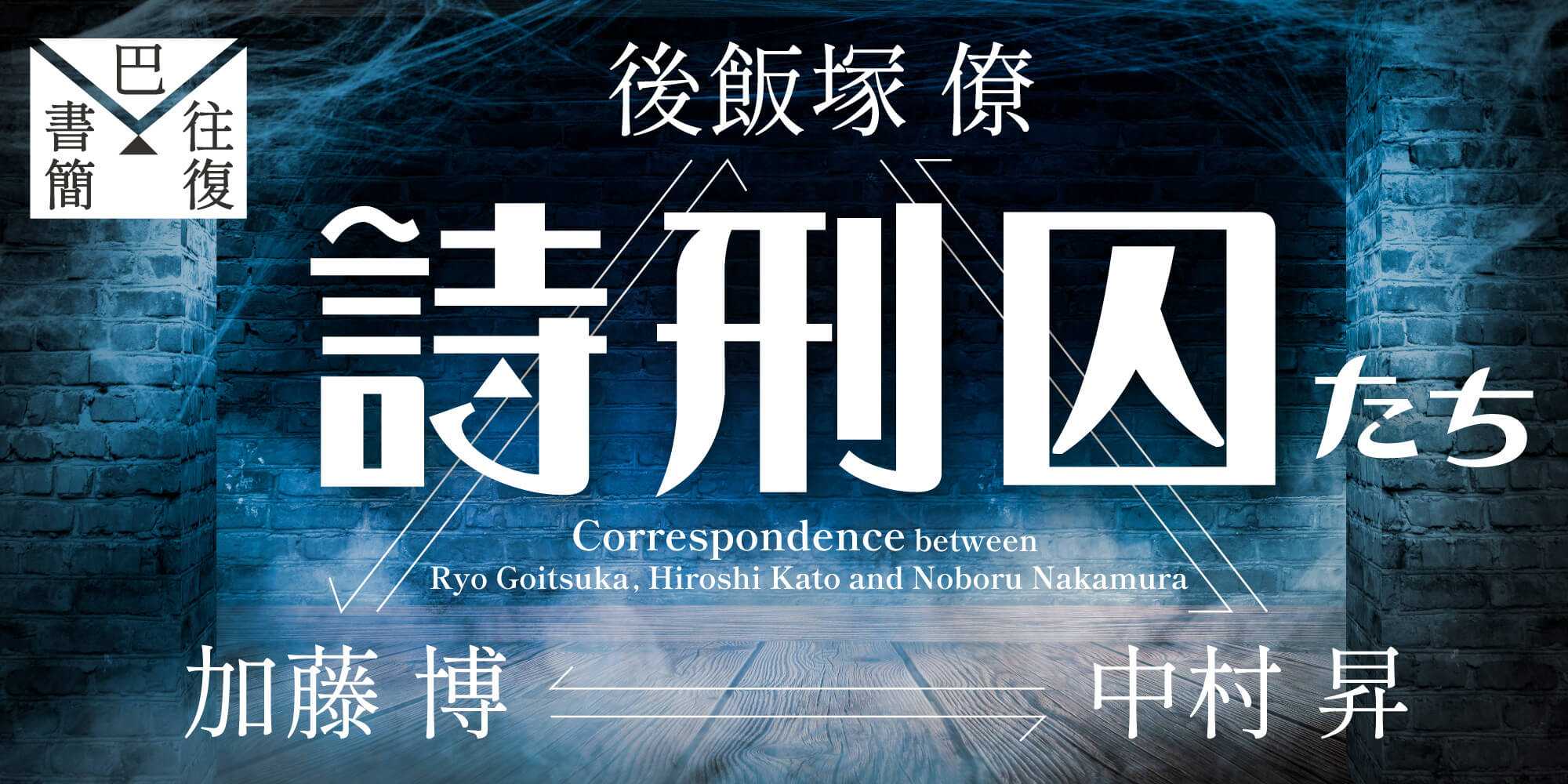誤読のすすめ
後飯塚僚、凄い。何がなんだか分からないけど凄まじく、そこに何かがあることだけは伝わってくる。後飯塚氏本人、「『病める舞姫』はもう体内化しているから、次は現代の『病める舞姫』を生む」と語っていたから納得です。
さて、まず連載タイトルと私のテーマとの関連についてひと言。後飯塚さんや中村さんと異なり、私の場合は「詩に苦しめられた」という意味で「詩刑囚」です。恥ずかしながら告白すると、高校時代に詩人をめざしたことがありました。当時、読んで憧れたのは主に中原中也などの近代詩。詩人をめざしたからには今の詩を、との意気込みで現代詩(60〜70年代のもの)を読んでみたら、さっぱり分からない。詩なのだから通常やらないような言葉の連結をしているのは当然です。それは心得たうえで読むのですが、詩の言葉が指し示す事物(つまり指示対象)を現実の中にも空想の中にも探せない。たとえ具体的な言葉だったとしても、具体的な事物をイメージできない。近代詩は心象世界と繋がっているが、現代詩は断絶して感じられ、言葉の着地点が見えないために躓いたのでしょう。
ちなみに本棚で長く眠っていた飯島耕一の詩集を引っ張り出してみると、「塔は方法のように明るい」とある。「塔」とは何なのか? これなんか「その塔は何かの方法のように明るかった」と書いてくれれば、記憶の中の「塔」に結びついて分かった気になれたのにと恨みがましい気持ちにもなります。まあ、おかげで文学的な感受性が乏しいことに気がつき、早々に諦めて、同じく短めの文をつくるコピーライターになったわけですが。そんな情けない経歴と資質の私でも『病める舞姫』は少しは読める。現代詩が分からない“ふつうの人”である私が、難解で鳴る『病める舞姫』をどう読んでいるのか。その方法を伝え、私と同じように詩の読解に苦労している人の参考になればと思います。
と、ここまで『病める舞姫』を言わずもがなの前提にしてきましたが、知らない読者のために簡単に紹介しておきます。『病める舞姫』は、暗黒舞踏の創始者、土方巽が少年期の記憶を再構成するようにして書いた「心象的自伝」(吉岡実)です。研究者の言葉を引用しましょう。
次々とからだの感覚から湧出するイメージを飛躍させ、主語と述語が混乱し、主客が転倒する文章構造、時間と場所が錯綜する独自の文体によって書かれたもの(稲田奈緒美)
書き手と描かれているものの主客のみならず、描かれているもの同士も境界を持たずに伸びていく。意識の主体がどこにあるのかわからないような、書き手の眼の所在が無限に変化していくような描き方(三上賀代)
意味を凝固させないで言葉を出来事の渦に直結させようとしている」「世界は繊細な差異と運動の群に微分され、生と死も分かたれないような銀河に変わってしまっている(宇野邦一)
なんとも異常な文章に貫かれているわけですが、こういう「おそるべき書物」(中村昇)を「詩刑囚」の私が曲がりなりにもなぜ読めるのかというと、体の感覚で向き合えばいいから共感できる部分があるためです。言葉を体に着地させればいい。
20歳の頃、アスベスト館で土方さんの稽古を三人で受けましたね。まずは歩行。硫酸が満たされた水盤を頭に乗せて、天と地の間を歩く。額にガラスの目玉。そこに差し込む光。抜け出た魂に追いすがる。足の裏にかみそり(または、鈴の音をかみそりで切り、その音の上を渡る)。ルドンの目が上空を横切り見入られる。……次々と言葉を浴びせられ、それらに同時に体を反応させて歩く。どのイメージをとっても体験したことがなく、体はまったく新しい体験を新しく体験する。ひとつの動きに集中することは許されず、意識は分裂。日常生活で習慣化された身振り、有用性に馴らされた動作は解体していき、多重に張られた言葉の糸に操られる人形になったように感じられたものでした。
ある日「長い耳掻きが鼓膜にとどいている」と投げかけられました。「そんな経験ない」と戸惑いながら、でも、ちょっと深めに掻いたときのこと、鼓膜にゴミが触れてカサコソいったことを思い出し、そして長い耳掻きだから大きく揺れて鼓膜が破れるかもしれないと恐れ、仮想の耳掻きから逃げようとしたら思わず首が横にずれた。実はこのフレーズが『病める舞姫』にもあります。「そうか稽古と同じなんだ」と安心し、「俺でも読めるかも」とその気になったわけです。
例えば「姫君の体温を自分の血管の中に抱きしめた」という文。寒い日に暖をとろうと、洗面器にお湯をはって手を浸すと温熱が腕の血管をのぼってくる。体が内側から徐々に温まり、この感覚かと合点がいく。
ただし、これら例にあげた文は平易で、即物的なため身体感覚に直結しやすい。難しい文の場合は、体感に結びつくように、まずは解釈が必要です。
『病める舞姫』の冒頭近くに「からだの中に単調で不安なものが乱入してくるから、からだに霞をかけて、かすかに事物を捏造する機会を狙っていたのかもしれない」という記述があります。これは、このままではピンとこないので、「単調で不安なもの」を「ついた嘘がばれる不安感」と読み替えます。「単調」とは、ひとつのことに意識が囚われて単一化している状態と解し、それで不安になるのはどういうときかと記憶の中に探したら、私の場合は「嘘がばれる」でした。「嘘がばれる」と読み替えると、そういう恐怖に近い不安感があるときの、体が痺れるような、ゾワゾワするような感覚が想起される。そしてそれが、あとに続く「からだに霞をかけて、かすかに事物を捏造する機会を狙っていたのかもしれない」ことの動機として理解できる。「からだに霞をかける」「事物を捏造する」は土方巽の根本思想に関係すると思うので、ここでは立ち入りませんが、要は抽象的な言葉には具体例を見つける作業をします。もちろん、単に「嘘がばれる」に置き換えるのではなく、元の「単調で不安なもの」と同時にイメージする。目的は「単調で不安なもの」という不可解な言葉を感覚的に把握するためなので、類概念と種概念を重ね、類概念を種概念で支えるようにして読むのです。これは一般に、抽象的な概念を理解するために誰もがやっていることだと思います。
しかし、こんな読みはおそらく誤読です。土方が大いなる嘘をつくことはあっても、セコい嘘がもとで不安になるなど想像できませんから。それは承知しているのですが、にもかかわらず勝手な誤読をするのは、そもそも言語表現が伝達するメッセージは、受け手によって実現されると思うからです。目の前の物を指し示して語り合っているのでない限り、いや、言葉は物ではなく、言葉をはさんで送り手と受け手が相対しているだけで、両者が共有している意味など厳密に言えば存在しません。語られた言葉は謎であって、送り手が投げかけた謎を受け手が解く。その努力、解読への参加、協力があって初めて意味は生じる。(すみません、我が心の師匠、佐藤信夫の受け売りです。) それなら、作品の世界と自分の体験や記憶が地続きになるように、翻訳しつつ読むことは読者に許されるでしょう。
レトリックから連想へ
こうした“受け手の協力”は、言語コミュニケーションが成立するための基本です。私どもコピーライターの仕事では、この“協力”を上手に引き出す工夫が重要になります。
マーケティングの世界にAIDMA(アイドマ)の法則というのがあります。消費者は、Attention(注意)→ Interest(関心)→ Desire(欲求)→ Memory(記憶)→ Action(行動)の5つの心理段階を経て商品を購買する。この法則では大雑把だとして、のちに「注目」「興味」「連想」「欲望」「比較検討」「信頼」「行動」「満足」の8段階が提唱されました。ウインドーショッピングの場合だと、ディスプレーされている服に「あっ」と注目し、「素敵ね」と興味がかきたてられ、「今度の旅行にいいな」と連想し、「欲しい」と欲望がわき、「ほかも見てみよう」と比較検討し、「やっぱりこれ」と信頼し、「これください」と行動し、「買ってよかった」と満足する。どこかの段階で躓くと購入(あるいはリピート)に結びつかないので、各段階に対して対策を立てる、そのための枠組みとして使われています。
広告の場合は、8段階の最初の「注目」「興味」「連想」までが守備範囲です。気を引く言葉、意外性のある言葉を投げかけ、ハッとさせ、関心を呼び起こし、あわよくば自分事として使用場面を想像してもらい、商品への欲求をかきたてる。言葉があふれ返っている世の中で、読む義務も聞く義理もない人々にまず「注目」してもらうために、広告コピーは通常とはちょっと違った言葉づかいをします。レトリックによる謎かけです。とはいえ、謎といっても、一瞬にして解ける程度の謎にします。(詩ではないので、解読に負担がかかるとお客さまは逃げてしまうから。) そして、受け手は謎を解いたことに快感を覚え、また謎を解く過程で、ふだんは安定している言葉の構造が一瞬微かに揺れて「興味」をもつわけです。けれども、その「興味」はうつろいやすく、次の「連想」まで引っ張っていけるか、ここが難しい。実例を示します。
かなり以前に見たハローワークの広告に、「明日を探しに」というコピーの電車中吊りポスターがありました。特にめずらしくもない表現ですが、実はかなり複雑なレトリックが使われています。まず「明日」。これは「あしたのジョー」と同じで、未来や将来といった広大な領域をその一部分である「明日」という一日で代表させた換喩です。そして、その未来を「探す」のだから、未来は「欲しいもの」であり、「欲しい未来」がポジティブな面(幸せ、幸運、希望、成長、成功…)をともなって想起される。これは概念メタファーです。そして、そのハッピーな未来の具体例として、ハローワークの広告だから「ハッピーな転職」のことを言っているのだろうと伝わる。これは類概念により種概念を表す(類による)提喩です。こんな平凡な表現でも3つのレトリックが仕込まれているのです。
ちなみに、同じ「明日を探しに」がオープンキャンパスのコピーだったら、受験生には、ハッピーな未来の具体例として入学後のキャンパスライフがイメージされるでしょう。また、演歌に「明日が怖い」という歌詞がありますが、この場合は「怖い未来」がネガティブな面(不幸、不運、失敗、衰弱、死…)をともなって想起され、演歌だから「別れ」が具体的にイメージされるでしょう。「明日が怖い」が予備校(そんな広告を出すバカな予備校はありませんが)のコピーだったら「不合格」「浪人」です。いずれにしても、レトリックの解読は瞬時になされます。
ハローワークの広告に戻ると、ハローワークのことは誰でも知っているので告知としての価値はなく、とはいえ、その存在を「ハッピーな転職」との良い印象で包んだ効果はあったでしょう。しかし、記憶には残らない。転職を考えている人が目にすれば「興味」喚起はされるかもしれませんが、それでどういう仕事や生活がもたらされるのか「連想」させるまでは至りません。まして転職と関係ない人は無視するでしょう。いずれにしても、瞬時に解読されても即座に忘れられてしまいます。広告は、見たその場に商品があるわけではないので記憶に残すことが大事です。その意味でハローワークの中吊りは、広告としての効果は疑問です。
一方、「連想」への誘導ができている広告に、同じ業種で同様のアプローチをした傑作があります。リクルートがコーポレートスローガンとして送り出した「まだ、ここにない、出会い。」です。「ない」は「まだ」も受けるので、「まだない、ここにない」と読めます。そして、「まだない」は「いずれある」と、「ここにない」は「どこかにある」と無意識のうちに反転して解釈され、「いずれ・どこか」で望ましい出会いが運命的に予定されていると感じる。さらに「ない」という言葉の打ち消し作用により、「いま・ここ」における出会いの不在が立ち上がります。未来は今の延長ではないと感じられ、「いま・ここ」を否定することでやってくる未来を想像する。広告を見たそれぞれの人が、それぞれに「いま・ここ」から脱出することで手に入れられる「いずれ・どこか」にある未来を「連想」するように誘導できているのです。
さらに言えば「出会い」は「マッチング」のことで、まさにリクルートが提供する価値の核心。仕事、結婚、住宅、旅行……と、受け手の関心に応じてその不在かつ希望の未来がイメージされます。同社の事業すべてを包括するコーポレートスローガンとして、憎らしいほどの完成度です。ところが、レトリックとしては緩叙法(伝えたいことの対義概念を否定する)を用いているだけで、ある意味平易です。いや、「ない」という否定表現は普通に使われるので、レトリックが存在することさえ感じさせません。ハローワークがレトリック“臭い”のと比べて格段の違いです。
さて、ハローワークとリクルートの広告効果に、なぜこれほどの違いが生じるのか? そして、その違いは、『病める舞姫』の読みにどう関わるのか? この分析には、私が現在勉強中の認知言語学の知見を借ります(前述の概念メタファーも、認知言語学の創始者のひとりジョージ・レイコフが提唱した用語です)が、予定の文字数に達したので次回にします。『病める舞姫』を体の感覚に結びつけるための「連想」をどう起こすか、その手段としてレトリック解読を用いたいと考えています。
もちろん、土方巽がレトリックを弄していたということではまったくありません。『病める舞姫』の雑誌連載時に毎回通読し、校閲を行った詩人の三好豊一郎氏は、「書き始めるとつぎつぎに連想が湧き出すらしく、それが繁った蔓のようにはびこり、幹が消えて枝から枝へと発展」とその執筆の様子を証言しています。たぶん、土方さんは素直に言葉を発し、それが私たちには複雑怪奇なものに映るだけなのでしょう。そうした本来は率直な文をレトリックとして読むことに問題はないのか?
佐藤信夫は、「レトリックは、その《教則》的なたてまえの都合上、効果的な表現がなぜ効果的であるのか、という仕組みを説明しなければならなかった」と述べます。「何となく印象的な文章に出会ったとき、その効果を目に見えるかたちで説明するために」レトリックという技術体系は構築されたそうです。これを極論に振れば、レトリックは、文を書く側にではなく読む側に発生する。レトリックは、書く技術ではなく、読む技術なのだと言っていいでしょう。
<参考図書>
土方巽『土方巽全集Ⅰ』『土方巽全集Ⅱ』(河出書房新社)
稲田奈緒美『土方巽 絶後の身体』(NHK出版)
三上賀代『器としての身體』(春風社)
宇野邦一『土方巽 衰弱体の思想』(みすず書房)
佐藤信夫『レトリック感覚』『レトリック認識』『レトリックの意味論』(講談社学術文庫)