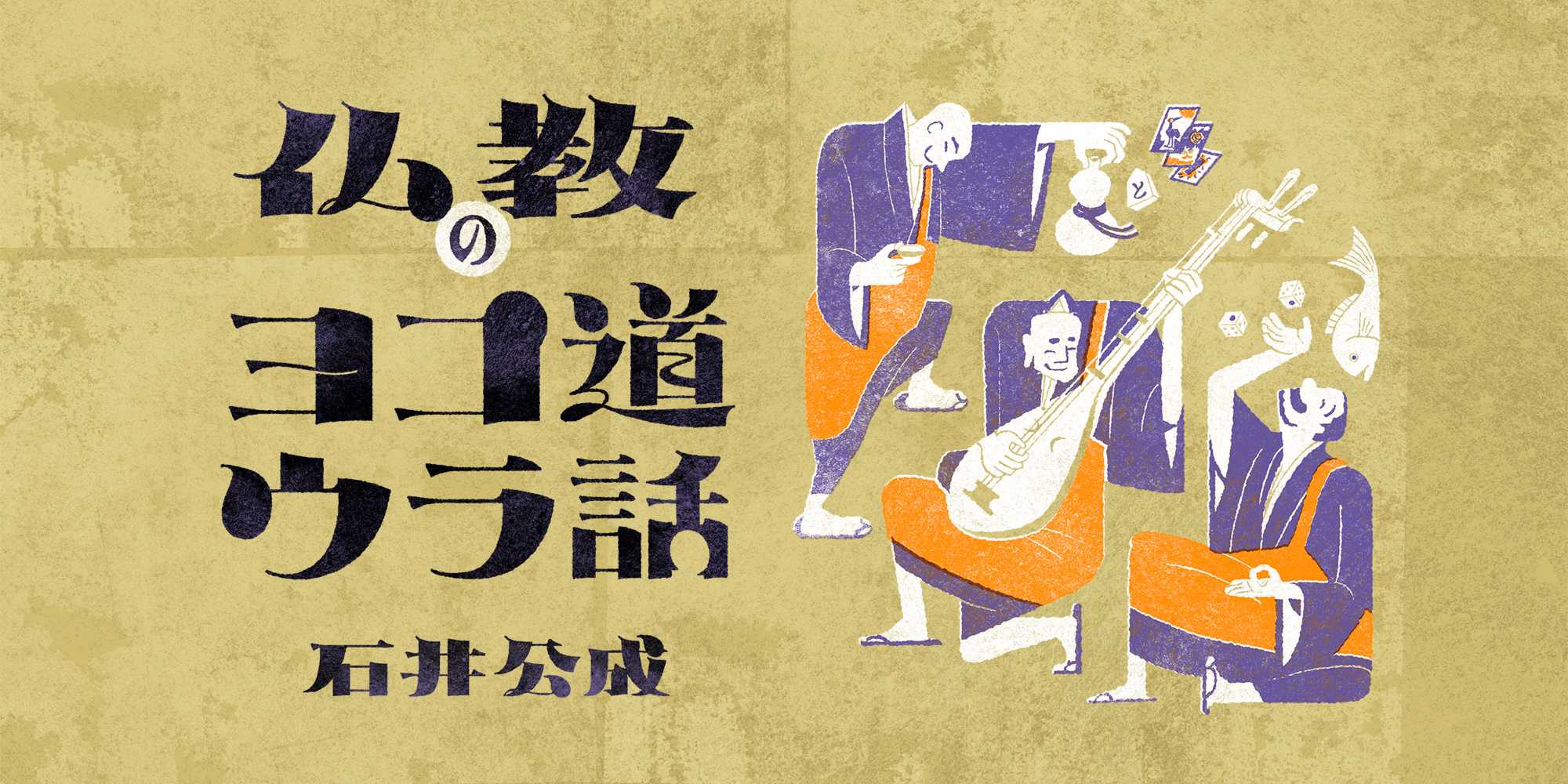閻魔大王が嘘つきの舌を抜く経典も絵もない
前回は地獄で亡者たちを苦しめる牛頭馬頭[ごずめず]に触れました。ただ、牛頭馬頭は下っ端であって、トップは閻魔大王ですので、今回は閻魔をとりあげましょう。
閻魔大王については、怖い像や画をあちこちで見かけますが、小さい頃の私の受けとめ方は、「仏教はインドでできたはずなのに、どうして閻魔は中国の王様みたいな格好をしているんだろう」というものでした。
その当時は、「嘘をつくと、閻魔様に舌を抜かれるよ」という言葉をよく聞いたような気がします。後になって仏教を学び始め、地獄に関しても多少調べるようになったものの、閻魔が舌を抜くという経典は読んだことがなく、そうした地獄絵も見たことがありません。
この疑問を解決してくれたのが、昨年の年末に刊行された東洋哲学研究所編『仏教東漸の道 西域・中国・極東編』(東洋哲学研究所)に収録されていた田辺勝美氏の論文、「嘘をついたらなぜ閻魔様に舌を抜かれるのか?―シルクロードと閻魔大王(イマ、ヤマ)の東漸―」でした。
イラン・インドの閻魔と日本の閻魔
田辺氏によると、閻魔と音写される Yamaは、仏教が誕生するはるか以前の伝承では、「最古の人間で、最初に死んだ者」とされていた由。古代イランのゾロアスター教では Ymaと表記され、正直で善良な国王だったものの、ある時から嘘をつく傲慢な人間になったため、王位を失って弟に殺された結果、死者の国に落ちた最初の人間となったと伝えられているそうです。
ただ、ゾロアスター教では、それはあくまでも死んだ者たちが行く国であって、地獄とは別であるため、Ymaは地獄におらず、死者の裁判もしない由。ただ、西アジアの大半を支配したササン朝(224-651年)のゾロアスター教文献では、嘘をついた男女は舌を引き抜かれたり、切断されると明記してあるそうです。
仏教の場合は、古い経典にも地獄の描写が見られ、嘘をついたら地獄に墜ちるとされ、獄卒が鈎[かぎ]で罪人の舌を引き出して痛めつけるとされていますが、そこにはYamaは登場しません。それよりやや新しい経典では、Yamaが出てくるものの、死者を尋問し、どの地獄へ送るか判決を下すだけです。
日本では、平安以降、地獄絵が流行し、妄語の罪を犯した罪人たちの舌を引き抜いたり、傷つけたり、燃やしたりする場面も盛んに描かれるようになりましたが、それをするのはやはり獄卒たちです。
田辺氏は、江戸時代の地獄絵でも、閻魔大王が自ら罪人の舌を抜く様子は描かれていないと述べ、「閻魔大王の獄卒が、嘘をついた者の舌を抜く」という文句から「獄卒」の部分が抜け落ちた結果、江戸時代あたりから「嘘をついたら閻魔大王に舌を抜かれる」という日本だけの俗説が生まれたのではないか、と推測しています。おもしろいですね。
閻魔様は江戸時代の人気者
実際、江戸時代には、どういうわけか閻魔様は大変な人気となっており、閻魔百ケ所参りなども行われました。つまり、閻魔様の像で有名な寺を回るのです。しかも、百ヶ所のうち三十四ヶ所は郊外にありました。ピクニック気分で出かけたのです。
百ヶ所の中でも有名だったのは、こんにゃく閻魔として知られる小石川の源覚寺の閻魔像です。これは、宝暦(1751-1764)の頃、眼病となった老女が、地中から出現したとされるこの閻魔像に祈願したところ、閻魔が自分の片目を与えると告げる夢を見、覚めてみると両眼の痛みがなくなっていたものの、閻魔像が片目だけ盲目になっていたため、老女が自分の好むこんにゃくを絶って閻魔像に供養したのが流行の始まりと伝えられています。イランやインドの閻魔とはかなり違ってきましたね。
あと、深川の賢法寺の閻魔堂も大変な人気でした。ただ、こんにゃくを供えて祈る点は源覚寺と同じでも、こちらでは、こんにゃくは嘘をついた舌の代わりと説明されており、深川の花街の芸者たちは、競って数多くのこんにゃくを供養したそうです。これは、多ければ多いほど嘘をついて多くの客をとりこにしたことになるためだとか。
閻魔をやりこめる子供
このように、閻魔様の信仰は非常に盛んであって、明治時代になっても縁日は大変な人出となっていました。廃仏毀釈をおこない、仏教を廃して神道を盛んにしようとした明治政府は、一方では西洋の科学教育を推し進めようとしていたため、当時は仏教のこうした迷信をなくそうとしていました。
そのため、開化本と呼ばれる啓蒙書が明治政府に近い立ち場の人たちによって次々に出版されたのです。その中の一つに、地獄などはない、閻魔などはいないことを説いた明治15年(1882)の勝木吉勝編『開化地獄論』があります。この本は、閻魔の縁日に11才か12才ほどの子供がやってきて、閻魔と地獄の有無について討論するという設定になっているのが面白いところです。
子供はひどくませていて、地理に関する知識を披露し、閻魔に地獄はどこにあり、その面積はどのくらいかなどと詰問して閻魔を困らせます。閻魔が逃げ出そうとすると、子供は閻魔の裾をつかみ、地獄にも戸籍があるなどといつわりを言った罪により、警察に突き出し、処罰してもらうなどと言いだします。このため、赤鬼や青鬼が閻魔を助けようとして棒を振り回し、子供と大喧嘩になりかけたところ、向いの店で働く丁稚が仲裁に入った結果、和解するにいたったとして話が終わります。
不妄語の罪
この本では、閻魔が地獄に関して嘘をついていたことになっていますが、仏教の五戒のうちの「不妄語」の罪は、僧侶について言う場合、最も重いのは「自分は悟った」などと言うことです。これは、そうしたことを言うと、世間の人々がその僧だけに食事や品物を布施するようになってしまうためです。
このため、この妄語をなした場合は特別扱いされることになっており、波羅夷[はらい]、すなわち教団追放という最も重い処置がくだされます。殺人などと同様の重罪とされているのです。パーリ語の律によると、この「大妄語戒」が定められたのは、次のような事件によるとされています。
釈尊がヴェーサリーに住していた際、飢饉となった年がありました。ところが、ヴァッジの地で修行してたいたひと握りの僧たちは、互いに「あの修行者は悟りを得ており、神通力を持っている」などと賞賛しあったため、その地の住民たちは、自分たちは食べなくても、功徳を求めてそうした僧たちに食べ物を布施したのです。
その結果、雨期が終わって修行僧たちが各地から釈尊にご挨拶するために集まってきたところ、多くの僧侶たちは食事を布施してもらえず、痩せ衰えていましたが、ヴァッジから来た一団の僧たちだけは、肥っていて顔色も良かったのです。そこで釈尊は事情を察し、「どんな者であれ、悟りを得ていないのに得たと称したならば、波羅夷であって共に住むことはできない」と定められたのです。これは特別な例ですが、教団を分裂させるような言葉も重い罪とみなされていました。
このように嘘が問題とされるのは、釈尊が「真実しか語らない人」として尊崇されていたためでもあります。経典では、釈尊は翌日の食事の招待などを受けた場合、「沈黙によって承諾を示した」と記されている箇所があります。これは、「行く」と答えておいて突発事態のために行けなくなったりすることがないよう、返事をしなかった、ということです。
やや行きすぎのようにも思えますが、伝統教団ではそれくらい「真実以外を語ってはならない」という意識が強かったことが分かりますね。この伝統をひっくり返したのが、大乘仏教の「嘘も方便」説です。相手に有益であれば真実でないことを語っても良い、という主張です。一理あるものの、これもまた行きすぎになりがちであったのは当然のことでしょう。