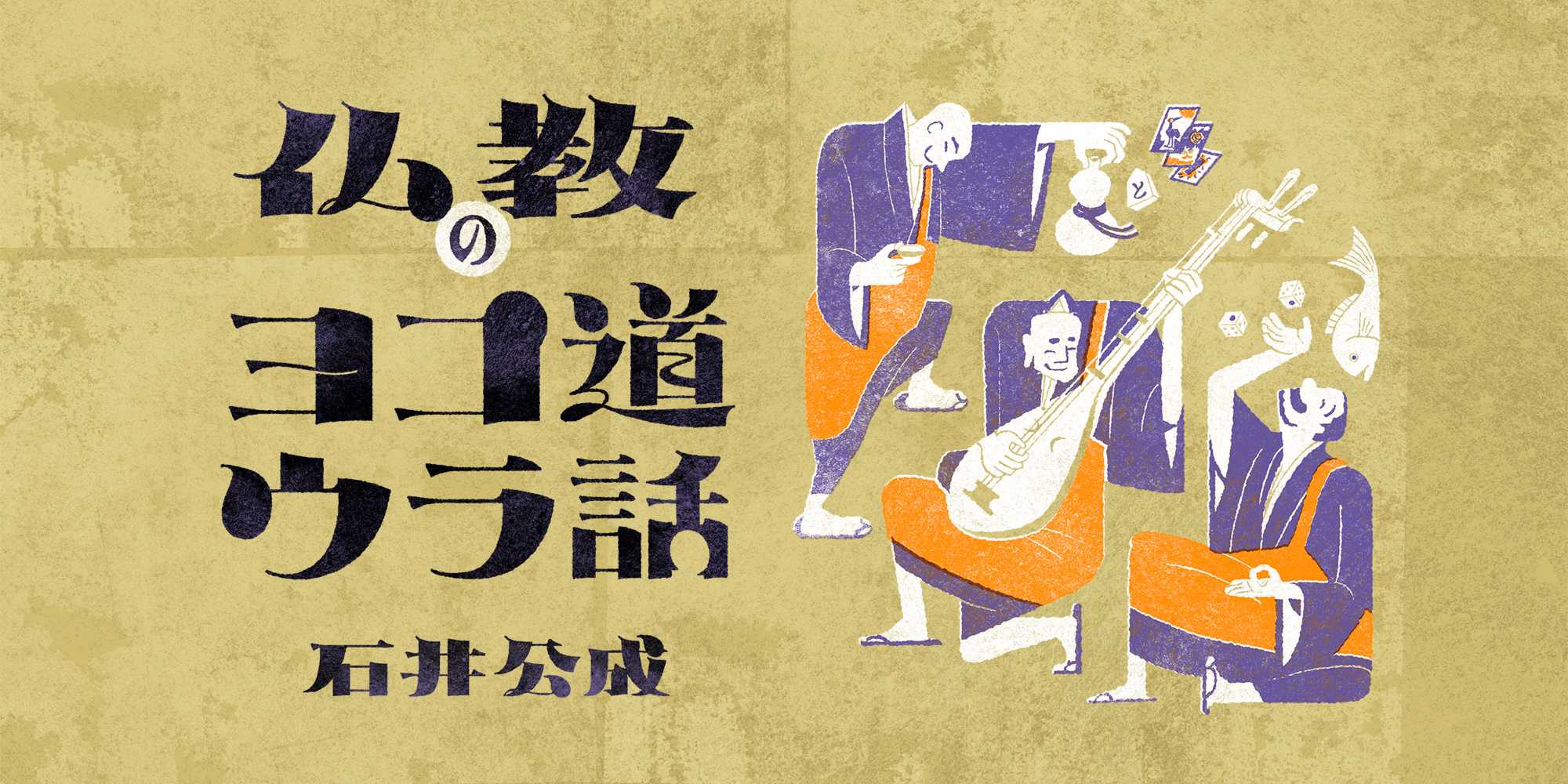インド仏教における肉食
前回は、飢饉になった際、悪い修行者たちがインチキ宣伝をして食べ物をたくさん布施してもらった結果、肥っていて顔色も良かったという話を紹介しました。そこで、今回は食べ物に関する話にしましょう。
仏教と食べ物と言えば、「精進料理」という言葉が頭に浮かびます。法要などの時に出される肉や魚を用いない料理ですね。しかし、インド仏教では、僧侶は肉や魚を食べており、それが伝統として続いていました。乞食[こつじき]をしている際に布施された食べ物は、豪勢なものであろうと粗末なものであろうと、分け隔てせずに受け取るべきであって、それこそが修行だとされていたのです。
後に整備されて詳しくなっていく戒律も、肉食を認めていました。ただ、時代がくだるにつれ、いろいろな条件が加えられていっています。最初期の条件は、三つです。つまり、僧侶に布施するために動物をわざわざ殺すところを見たり、聞いたり、そうしたのではないかと疑われる場合は不可とするのであって、そうでない肉は「三種浄肉」と呼ばれ、食べることが認められていました。
三種浄肉でも、特殊な肉は早い段階から禁止されていたようです。特殊な肉とは、馬肉、龍肉、狗(犬)肉、人肉などです。律によっては、象肉、馬肉、人肉、狗肉、毒虫肉の「五種肉」を禁じていたり、さらに獅子肉、虎肉、豹肉、熊肉、羆[ひぐま]肉の五種も禁じているものがあります。
「三種浄肉」や「五種肉」は律に記されていますので、その条件を満たすような鶏とか豚とか羊や魚は食べてかまわないとされていたことになります。牛を神聖視するヒンドゥー教とは異なり、牛肉も禁止されていませんね。実際、東南アジアの仏教国では、一部の派を除いては、布施されれば動物の肉でも食べるのが伝統です。
人肉の禁止と提供
ここで気になるのは、禁止される肉の中に人肉が入っていることでしょう。実は古代インドでは、人肉は病人には薬になるとされており、売買もされていたようです。このため、律には、病気の僧が人肉を食べて治ったという話も見えていますが、こうした場合、それを聞いた釈尊は人肉については食べてはならないと禁止した、という話になっています。
ただ、釈尊の前世の姿である菩薩の物語を語ったジャータカの中には、菩薩が自らの肉を食べ物として提供しているものもあるのです。それは、兔であった釈尊が食べ物がなくなった仙人のために焚き火に身を投じ、自らの肉を提供した話です。たとえば、『雑宝蔵経[ぞうほうぞうきょう]』の「兔、自ら身を焼き、大仙を供養する縁」の話はこんな具合です。
ある仙人が山の中で修行していた際、ひでりが続いて果物や食べられる草などがなくなってしまった。仙人が町におもむいて乞食しようとしたところ、仲良くしていた兔が、自分が食べ物を用意するので山林での修行を続けるように言い、薪を集めて火をつけ、その中に身を投じた。仙人が悩みながらもその肉を食べると、感動したインドラ神が雨を降らせたため、植物がたちまち実り、仙人は修行を続けて神通力を得ることができた。
以上です。この話が発展したものが、火の中に身を投じた兔は月に生まれたという伝説ですね。
人肉の提供
この話では、釈尊が自分の肉を食糧として提供していますが、あくまでも兔であった時のことです。一方、釈尊が前世でシビ王という王であった時の話では、インドラ神とヴィシュヴァカルマン神が、シビ王は本当に仏になる決意をしているかどうか確かめた際、シビ王は自分の体を切って肉を提供しています。それは、以下のような話です。
ヴィシュヴァカルマンは鳩に姿を変え、インドラ神が化身した鷹に追われてシビ王の脇の下に飛び込みます。鷹がシビ王に鳩を返せと要求すると、シビ王は、自分は生きとし生けるものをすべて受け入れるので返せないと断ります。鷹は、自分も生きものであるのに、なぜその食べ物を奪うのかと責めたため、シビ王は自分の体を切って肉を与えると申し出ます。
鷹が鳩と同じ重さの肉を切り取るよう求めると、シビ王は大きな秤[はかり]を持ってこさせ、片方に鳩を載せ、片方に自分の腿から切り取った肉を載せます。しかし、秤は鳩の方に傾いたため、シビ王は腿の部分をもう少し切り取って足しますが、鳩の方が重いままです。シビ王は体の他の部分を切り取って足していきますが、いくらやっても状況は変わりません。
シビ王が最後に血まみれになった全身を秤に載せようとしたので、鷹が苦しくないのかと尋ねると、シビ王は自分は仏道を求めるのみだと答えます。すると、天地が振動して皆が感動し、シビ王の体は元通りになったとされています。
ヴェニスの商人
自分の体の肉を切り取って提供するという話は類話が多く、『マハーバーラタ』などインドの叙事詩にも見えているばかりか、東西諸国に似た話が存在します。特に思い出されるのは、シェイクスピアの『ヴェニスの商人』ですね。『ヴェニスの商人』では、ヴェネチアの商人、アントニオが友人のためにユダヤ人の高利貸しであるシャイロックから金を借り、返せない場合は自分の肉1ポンドを渡すという約束をします。
しかし、当てにしていた商船が難破し、アントニオが借金を返せなくなると、アントニオを嫌っていたシャイロックは肉を要求し、裁判になります。裁判では、アントニオの友人の恋人であるポーシャが裁判官に扮し、シャイロックの言い分を認めたものの、契約にあるのは肉1ポンドであるため、それ以外の血を流したらシャイロックの財産を没収すると言い渡します。ポーシャは結局はシャイロックを許し、慈悲の意義を説くのですが、これはシビ王の話で慈悲が強調されていることと一致しますね。
『ヴェニスの商人』の種本の一つは、13世紀頃にラテン語で書かれた教訓説話集、『ゲスタ・ロマノールム(ローマ人の行状)』の第195話です。この書は、ヨーロッパ諸国の言葉に訳されて広まりました。第195話は、おそらくインドの伝説がイスラム圏を経てヨーロッパに伝わったものでしょう。
というのは、13世紀後半にイタリアの大司教によって書かれた『黄金伝説』も、インドの話をイスラム圏経由で載せており、その話が大人気になったからです。その話とは、国王の子として生まれたヨサファットが、キリスト教の聖者であるパルラーム修道士に出逢ってキリスト教徒となり、迫害されたものの、やがて父王を改宗させたとする「聖パルラームと聖ヨサファット」の物語です。
この話はヨーロッパ中に広まって大人気となり、ヨサファットはカトリック教会から正式に聖人として認定され、「聖ヨサファットの日」まで定められました。しかし、19世紀になってインド研究が進んだ結果、ヨサファット伝説は実は釈尊の伝記の変形であって、ヨサファットはボーディサットヴァ(菩提薩埵)が訛ったものであったことがわかり、「聖ヨサファットの日」は取り消されるに至っています。
人肉食が事件となった例
そのキリスト教の立ち場も考慮して人肉食の問題に取り組んだのが、浄土宗の僧侶であって作家となった武田泰淳が1954年に発表した戯曲、『ひかりごけ』です。これは、戦時中に軍用船が北海道沖で難破し、4人の乗組員が島に流れついたものの、食糧がないため次々に死んでいくという状況で、船長一人が仲間の死体を食べて生き残った事件を元にしています。
この戯曲では、死んだ者の肉を食べただけなのか、食べるために仲間が弱って死んでいくことを願っていたか、食べられたくなくて逃れようとした者を殺して食べていないか、という点に争点が置かれていました。裁判にかけられた船長は、自分は、裁判官によってではなく、食べられた者たちに裁かれたいと語り、人の肉を食べたものは、首の周りにヒカリゴケのような光の輪が出来るため、自分のその光の輪を見てほしいと語ります。
しかし、ゴルゴダの丘に向かうキリストのように描かれる船長の首は光らず、逆に、裁判長や検事や傍聴人たちの首に次々に光の輪がついていく、という場面でこの戯曲は終わっています。
この作品が日本社会で思い出されたのは、いわゆる「アンデスの聖餐事件」です。40人の乗客と5人の乗組員を載せてウルグアイを飛び立った飛行機が、アンデスの雪山に墜落した1972年の事件ですね。墜落直後は28人が生きていたのですが、寒さと飢えで次々に死んでいくなかで、熱心なクリスチャンである彼らのうち、悩みながら「これは自らを犠牲にしたキリストの体なのだ」と言い聞かせて死体の肉を食べた者たち16人が生き残り、救助されることになります。
この中に仏教信者が混じっていたらどうなっていたか。考え方は、おそらくどの国のどのような系統の仏教かで違ってくるでしょうし、同じ系統でも個人によって差がありそうな気がします。