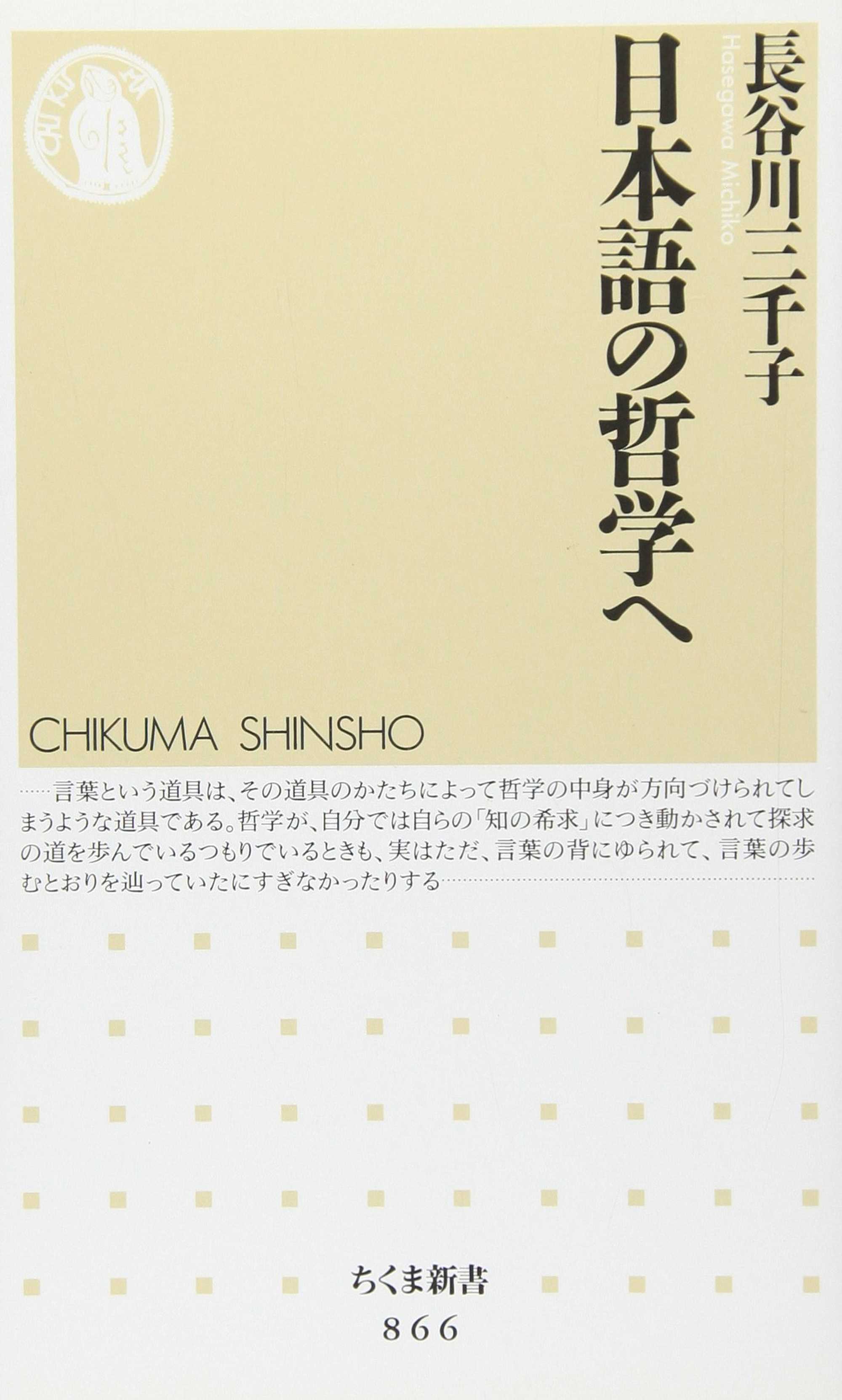語の「無意識的領域」
ウィトゲンシュタインの「文法」という概念があります。これは、われわれが学校で習った「文法」ではなく、この哲学者独自の意味をもつ言葉です。言語の構造や用法、あるいは言語体系というのではなく、語がもっている独自の領域のことです。「語の文法」という言い方をします。
たとえば「出来事」という語は、「出来事」という語独自の領域をもっています。日本語で「出来事」というと、「時間と空間が限定された場所で、起こった特定のこと」といった意味でしょうか。ちなみに手元の辞書だと「社会や身のまわりに起こる事柄。また、ふいに起こった事件・事故」(『大辞泉』小学館、1995年)と書かれています。
そういう意味に伴って、私たちが漠然ともっているイメージとして、「複数の人間が登場し、建物や機械やさまざまな知覚できる物体なども登場すること」というのもあるのではないでしょうか。ただ、この「イメージ」というのは、わたしたちの側の恣意的なイメージではなく、語がこちらに喚起する「イメージ」です。語そのものの「領域」のようなものです。
「出来事」という語で言えば、日本語の「出来事」(できごと)という語のもつ唯一の「領域」のことなのです。「出来事」といっても、いろいろな「出来事」がありますので、共通の性質を挙げることはできませんが、たとえば、入学式や交通事故、コンサートや食事会などいろいろなものが考えられます。それらのうちの典型的な「出来事」のイメージ(「出来事」自体の「領域」)が、この語に付随しているのではないでしょうか。
ウィトゲンシュタインのいった「家族的類似」(ある語が指すさまざまな対象の似ている点が、重なり合って漠然とその語の大体の範囲を決めていること)によって、「出来事」という語のイメージが、この語のまわりに形成されているといえるでしょう。これが、「出来事」という語のもつ「文法」です。表面上の「意味」とはべつに、それぞれの語が、いわば「無意識的領域」を形成しているというわけです。ウィトゲンシュタインは、どんな単語でも、こうした「文法」をもっていると考えています。
「象は鼻が長い」
なぜウィトゲンシュタインが、こんな面倒なことを言いだしたのかというと、われわれが、この「文法」によって、間違いをおかすことが、しばしばあるからです。たとえば、「出来事」という語をつかって、われわれは自然に「心のなかの出来事」などと言ったりします。ある人の心のなかで、ある動きや感情が起こったことを表そうというわけです。たしかに、そう言うことはできますし、意味も通じます。しかし、この語を使ったとたんに、われわれは、ある間違いをおかしている、とウィトゲンシュタインは言います。「出来事」がもっている「文法」による間違いです。
「出来事」という語に付随している「文法」(語の無意識的領域)は、「複数の人間が登場し、それが関係しながら建物や機械やさまざまな知覚できる物体なども登場する事柄」といったことでした。ところが、われわれが「心のなかの出来事」とつい言ってしまうと、このような「文法」で表される事柄が、心のなかにもあると勘違いしてしまうというわけです。「心のなか(他人には決して知覚できない場所)の出来事」なのに、誰もが見たり触ったりすることができる事柄が生じているとつい思ってしまう。つまり、「心」という語と「出来事」という語が結合することによって、「出来事」の文法が、「心」のあり方を誤解させてしまう(「心」の「文法」を汚染してしまう)のです、しかも無意識のうちに。これが、ウィトゲンシュタインのいう「文法による錯誤」です。
なんで、こんな話をしたかというと、われわれが使う日本語の語がもつ「文法」と、他の言語の語の「文法」とでは、かなり異なっている、ということを確認したかったからです。「出来事」という語のもつ「文法」は、英語のeventやaffairやoccurrenceやaccidentなどとは、まったく異なるのです。日本語を母語とするものだけにわかる「文法」が、「出来事」にはあるのです。だから、「もの」と「こと」という語を対象にする際にも、これらが日本語のなかでもっている「文法」を注視しなければならないということになります。
これらのことを前提にして、さらに考えてみましょう。これは、あとで詳しく論じるつもりですが、三上章の著作のタイトルでもある「象は鼻が長い」という文。この文の主語は何か、という疑問から、最終的に日本語には主語はない、という結論が導かれるのですが、そのことは後にして、まずは、この文を例に「文法」について考えてみましょう。
この文は、日本語話者には、すぐにその意味はわかります。何の問題もありません。なぜ、何の問題もないかといえば、われわれは、日本語をマスターしているからです。つまり、「象」「鼻」「長い」といった名詞、形容詞の意味を会得しているだけでなく、「は」「が」という助詞も自在に使えるからです。これらの語の「文法」(この場合は、一般的な意味での「文法」とウィトゲンシュタイン的な意味での「文法」の両方)を、われわれはしっかり身につけているのです。
そのように考えると、「象は鼻が長い」という文は、日本語独自の「文法」領域を形成しているということになるでしょう。とくに日本語の大きな特徴である助詞(「は」「が」)のもつ「文法」領域(語の無意識的領域)は、日本語を母語とするものだけが身につけているものです。その助詞が、縦横に働いているこの文の「文法」は、独特のものになっているはずです。こうして「象は鼻が長い」という文は、日本語ネイティヴだけが、「理解」できる文となっていると言えるでしょう。
つまり、われわれは、それぞれの母語で、唯一無二の「文法」領域を切り開いていることになります。それは、まったく独自のものであり、普遍的な思考や包括的な論理とは、著しく異なるものだと言えるでしょう。この地点から、「日本語と哲学」と考えるとどうなるのか、というのが、この連載が最後に目指すところだと言えます。
「が」と「は」
さてそろそろ、和辻哲郎に戻らなければなりません。「もの」と「こと」の問題へ方向を転換しましょう。いま説明した「文法」ともかかわりのある話から、方向転換したいと思います。和辻の「日本語と哲学の問題」について詳細に検討している長谷川三千子さんの『日本語の哲学へ』(ちくま新書、2010年)では、つぎのように書いてあります。
さらには、「これはペンだ」と「これがペンだ」とでは、ただ一文字、「は」と「が」を入れ替えただけなのに、意味合いがまるで違ってしまう。「これはペンだ」というのは、いま手元にあるさしあたり用途不明の物体の素性を明らかにして、「ペンだ」と言っている言い方である。(中略)これに対して、「これがペンだ」というのは、「ペン」という名だけは知っているけれども、ボールペンでも万年筆でもない、昔ながらのペンを見たことのない子供に「これがペンだ」と言って教えてやる――そんなときの言い方である。(17頁)
「もの」と「こと」の話に移行するつもりだったのですが、この文章を引用してしまった(?)ので、もう少し「文法」の話をしたいと思います。「象は鼻が長い」とも関係の深い「が」と「は」の話です。
ランボーの有名な言葉に「私とは一つの他者である」(Je est un autre)というのがあります。この文について考えてみましょう。この文の一番目につく特徴は、「je」という主語であるにもかかわらず、動詞が「est」になっている点でしょう。本来であれば、「je」につづくのは、「suis」でなければなりません。英語に訳せば、「I am」ではなく、「I is」になっているのですから、一種異様な文ということになります。
このことによって、「je」(私)が、「他者」(autre)であることが、ことのほか際立つことになります。しかし、そのように説明されれば、われわれ日本語を母語とする者は、なるほどと理解はできますが、この文のもつ「異様さ」(衝撃)は、体感できないでしょう。それは、フランス語のなかにある語のそれぞれの「文法」を体得していないからだと思われます。フランス語の母語話者であれば、「je」という語(「私」)には、「suis」が否応なく付随しています。つまり、「je」の「文法」領域にしっかり入っているわけです。
それなのに、「je」のつぎに「est」が来るわけですから、コーヒーだと思って口にしたら、昆布茶だったくらいの(もっとかもしれません)違和感を覚えるでしょう。こう考えますと、「Je est un autre」という文を、たしかに「私とは一つの他者である」と日本語に訳すことはできますが、このフランス語の文が、ネイティヴに対してもっている衝撃は、まったく訳されていないということになるでしょう。
これは、逆のことも言えます。このフランス語の文を、「私は、他者である」と訳すのと、「私が、他者である」と「私」という一人称代名詞の次の助詞を変えて訳してみるとどうでしょう。もともとのランボーの言葉は、同じ一つの文(Je est un autre)なのに、日本語を母語とするものにとっては、これは、歴然と違う文になります。その違いをはっきりさせるためには、さっきの長谷川さんの引用のような説明をせざるをえなくなるでしょう。これは、「が」と「は」という助詞の「文法」の違いだということになります。そして、つかっている言語がこれらの助詞をもっていて、その「文法」の違いが日常的に現れるのは、日本語を母語とする者たちの会話や文章においてだけなのです。
さらに言えば、日本語は一人称の言い方がいろいろありますので、「私は、他者である」を、「俺は、他者だ」「おいらは、他者だよ」「わしは、他者である」「わたくしは、他者でございます」などなど、無数のヴァリエーションも想定可能(それに、すでに列挙した文が、一人称の違いだけではないですが)ですし、そのヴァリエーションに、「は」と「が」の助詞の組み合わせを考えると、とんでもないことになるでしょう。それぞれの語や文が、日本語ネイティヴだけにわかる「文法」領域を形成しているのです。
こういう観点から、「もの」と「こと」という日本語独自の名詞についても、そして、さらに「日本語による哲学」についても、次回以降、考えていきたいと思っているのですが…。大丈夫かな、俺??