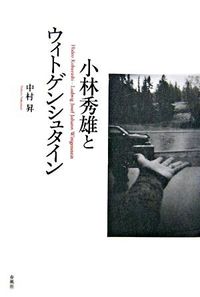――先生は小林秀雄にもたいへん興味をお持ちですよね。
中学のときに好きだったんです、小林秀雄。中学のとき親元を離れて一人暮らしだったもんですからすごく索漠(さくばく)としてて。毎日とにかく本屋に行って、本ばかり読んでたんです。太宰とか、三島とか、大江とか、小説ばっかり読んでたんですよ。
で、たまたま手に取った石原慎太郎の本の中に小林秀雄のことが書いてあったんです。鎌倉の八幡さまの上の一軒家に住んでたんですけど、そこに泥棒が入った。夜中に。で、抜き身の短刀をベタッとほっぺにつけられて「起きろ」、と。「金出せ」みたいなことを言われたんだけど、小林秀雄は悠然と「ちょっと待て、タバコを吸わせろ」。吸ってその泥棒に「おまえ駄目じゃないか」と説教し始めて、それで帰したらしいんです。そしたら後から泥棒が菓子折り持ってお礼に来たって。本当かどうか知りませんよ。でもそう書いてあったんです。それで小林秀雄すげえ、と。
その日から読み始めて大好きになりました。内容はよく分かってなかったんだと思うんですけど、とにかく無我夢中になって、手に入る物はぜんぶ読んだ。中3とか高1になると学校に出すレポートはぜんぶ小林秀雄の文章をまねて、今思うとすごく恥ずかしいんですけど。ばかみたいに上からのね。受け取った先生はムカついてたと思います。
――小林秀雄の言語観っていうのは、ソシュールやウィトゲンシュタインとどう違うんですか。
小林秀雄はもともとフランス文学専攻で、恐らく詩人になりたかったと思うんですよね。ランボーやボードレールが好きで、ポールヴァレリーとかも読んでいたし。ですから、現実をそのものをそのまますくい取るような言葉。本当にいい詩っていうのは、我々があずかり知らないような真実を見せてくれるんです。あ、世界ってこういうことだったんだって。
たとえば絵で言うなら、ゴッホが麦畑をあの色で描いたら、もう麦畑はあの色にしか見えないってあるじゃないですか。表現が現実に影響を与えるというか。それと同じように、詩も「本当の世界」を見せてくれる。そういう「本当の言葉」を目指してたと思うんですよね、小林秀雄は。

――現実を改変してしまうような言葉。
それはウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」と「語りえないもの」が接触する地点であって、ソシュールが言うような、体系の中にある語同士の差異によって生まれる意味とはまた違うもの。それを狙っていたんじゃないかって思います。
――その「本当の言葉」っていうのは、既存の、手垢のついた表現ではないけど、でも既にある語彙を使って語られるものではあるんですよね。
さっき言葉の発生のところでちょっとそういう話になったと思うんですけど、たとえば初めて何かに会ったとき、それを命名しますよね。そのときそれは唯一無二の、言葉の真のあり方だと思うんです、命名した瞬間は。でも、命名した一瞬後はもう駄目。命名しちゃうとただの言葉になるから。日本語なら日本語という言語の体系にバーッと取り込まれる。命名する直前。直前というか直後というか、もう本当にその瞬間。それが本当の言葉のあり方。
――名前がついてしまったら、既にある言語のシステムの中に落ち込んじゃうわけですね。
落ち込んじゃう。結局はただの言語になってしまう。小林秀雄はあるエッセイの中で「童話」という言葉を使うんですけど、それは、既成の、手垢のついた物語にはさせないぞっていうことだと思うんです。『感想』っていうベルクソン論の連載第一回目の有名なエッセイなんですけど。
おっかさんという蛍
母が死んだ数日後の或る日、妙な経験をした。誰にも話したくはなかつたし、話したことはない。尤も、妙な気分が続いてやり切れず、「或る童話的経験」という題を思い附いて、よほど書いてみようと考えた事はある。今は、ただ、簡単に事実を記する。仏に上げる蝋燭を切らしたのに気附き、買いに出かけた。私の家は、扇ヶ谷の奥にあって、家の前の道に添うて小川が流れていた。もう夕暮れであった。門を出ると、行手に蛍が一匹飛んでいるのを見た。この辺りには、毎年蛍をよく見掛けるのだが、その年は初めて見る蛍だった。今まで見たこともない様な大ぶりのもので、見事に光っていた。おっかさんは、今は蛍になっている、と私はふと思った。蛍の飛ぶ後を歩きながら、私は、もうその考えから逃れることが出来なかった。ところで、無論、読者は、私の感傷を一笑に附する事が出来るのだが、そんな事なら、私自身にも出来る事なのである。だが、困ったことがある。実を言えば、私は事実を少しも正確に書いていないのである。私は、その時、これは今年初めて見る蛍だとか、普通とは異って実によく光るとか、そんな事を少しも考えはしなかった。私は、後になって、幾度か反省してみたが、その時の私には、反省的な心の動きは少しもなかった。おっかさんが蛍になったとさえ考えはしなかった。何も彼(か)も当り前であった。従って、当り前だった事を当り前に正直に書けば、門を出ると、おっかさんという蛍が飛んでいた、と書くことになる。つまり、童話を書くことになる。後になって、私が、「或る童話的経験」という題を思い附いた所以である。(『小林秀雄全作品 別巻1』11-12頁)
小林秀雄がこの話を書いたとき、読んだ人たちは「もうあいつはおかしくなった」と思ったそうです。
――わかる気がします。
ええ。おかしいじゃないですか、おっかさんという蛍と出会ったって。でもそれが、自分の体験を表すのに、誰もが使っている手垢のついた言語ではなく、なんとかギリギリ童話という形で頑張ろうという彼の戦略だったんじゃないかって思うんですよね。
――母が亡くなった後、歩いていたらおっかさんとしか言いようのない、でもそれは何かと言われると一般的には蛍なんですよね。
そうです。
――その現象は小林秀雄の中で起こっているんでしょうか? 起こっているっていうのとも違うのかな……。
ちょっと別の角度から言えば、たとえばこれはサインペンとかなんとかって言えますけど、言葉がなければなんだか分からないものじゃないですか。これだって(コップを手にもって)何だろう、みたいな。われわれは通常日本語を使っているから、日本語をいろんなものに当てはめて、それはペンとかコップとか言えますけど、それはあくまでも言葉の話であって、このモノが実際何かっていうのは本当は分からない。

「これちょっと初めて見たから名前つけろよ」と言われて、何かしら名前をつける瞬間はそんな感じですよね。だから蛍が出てきたときわれわれは「蛍だ」って言うけど、小林秀雄はそのとき恐らく命名する、本当に原初的な段階にいたんだと思うんです。それはもう「おっかさんという蛍」って言うしかなかった。
――それは最初に出てきた、初めて痛みの感覚を味わった人が「いてっ」って言うのと……
同じですね。
――「いてっ」なのかどうか分からないけど、そこで出てきた言葉ってことですよね。
小林秀雄は初めて、人類で初めておっかさんという蛍に出会ったんです。だから「おっかさんという蛍」って言っただけなんですよ。でも「おっかさんという蛍」って言っちゃうと、おっかさんと蛍に分かれちゃって、何だそんなものおかしいだろう、おっかさんという蛍なんているわけないじゃないかってことになっちゃう。
――なるほど、面白いですね。
だから、もし、われわれが今持っている言語をすべてバーッとはぎ取られて、この世界をありのままに見たら、恐らく小林秀雄がおっかさんという蛍を見たような状態で何か始めなきゃいけない。でもたぶん発狂しちゃいますから、今持ってる言語でやるのがいいとは思いますけどね。
――なんだかよく分からない物を見た瞬間にも我々は、これは多分机だろうとか、多分ペンだろうって、既に自分が知っているものに
かぶせて安心するんです。たとえばこれもその話とつながるかどうかあれですけど、ガリレオ・ガリレイが自分の作った天体望遠鏡で、初めて木星の衛星を見たときに「衛星があるよ」と言って他の貴族に見せたら「どこにもない」「見えない」って言われたそうです。
つまり、見る側にある程度の図式がないと見えないものがある。小林秀雄にはおっかさんという蛍が見えたけど、他の人だったら何も見えてないかもしれない。そういうふうに、現実っていうのは一元的じゃないんですよね。一元的にしてるのは、われわれの言語活動だという言い方もできる。言語を共有しているから、われわれは同じ現実を見ていると、いわば錯覚して、安心しているのかもしれません。