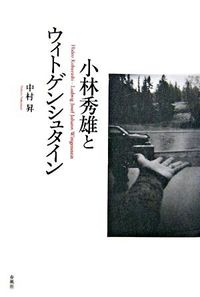「哲学」についての随筆を書いているわけですから、このあたりで、そもそも「哲学とは何か?」ということについて、一言二言私なりに説明した方がいいのかも知れません。ただ、「哲学」という語にこだわる必要は、まったくないと思っています。というのも、当りまえのことですが、言葉は言葉にすぎないからです。いったいどういうことでしょうか。
私は、生まれてこのかた、さまざまな経験をして、これまで生きていきました。無数の経験をして、日々あらゆる行為をしながら、ここまで生きてきたと言えるでしょう。誰でもそうですが、考えたり、話したり、悩んだり、動いたり、食べたり、いろいろな要素からそれらの行為は構成されています。
そういった行為のつながり(「紆余曲折」とでも言えるもの)の結果、いま「哲学」という領域のなかで生活していると言えるのです。それらしい問題につきあたり、それにこだわり、その結果、まぁ具体的に言えば、いま「哲学」を大学で教えてしまっている。なぜだか知らないけど、こういうことになってしまったということです。「為体」(ていたらく)という言葉を使いたくなるくらいです。
ようするに、あくまでも私の行為の連関があり、それが「哲学」にかかわっているだけなのであって、「哲学」という語が最初にあって、その語から元気に出発して「よし、哲学をやるぞ!」と宣言して、「哲学にかかわるようなこと」をやり始めたわけではないのです、当りまえですけど。つまり、私は、何もわからない状態で、この世界に投げこまれ(ハイデガー的ないい方をすれば「被投性」でしょうか)、この世界のルールを否応なくたたきこまれ、どうにかこうにか生存してきただけなのです。そういう言葉で表現できない状態で長く生きてきたのです。
その過程で、ある種の悩みや問題とつきあうようになり、何か特殊な少数民族的な分野(哲学)に入ってしまったということです、いいわるいは別にして。だから、「お前のやっているのは哲学じゃない」「あなたのやっていることこそ哲学だ」などと言われても、大きなお世話だということです。何と言われても、これは私の個人的な事情なので。
そもそも「哲学をやろう」などと思って、始めたわけではないのです。何度も言いますけど。これは、いろんな人が言っていますが、「哲学」は一種の病気なのであって、自然と(?)かかるものなのです。しかも、この病気は、その個々人に唯一無二のごく限定的な病気であり、一般的な病名はつかないのです。「哲学病」という病名は、「地球人」というくらい広範囲な病名であって、本当の病名は、固有名詞と同じくらい個々別々のものなのです。だって、フッサールがかかっている病気とウィトゲンシュタインがかかっている病気とでは、まったく異なるのは誰でもわかるでしょう。
何をそんなに息巻いているのだ、と思われるかも知れませんが、ようするに方向が間違っているということが言いたいのだと思います。「哲学」と私との関係は、「私の行為から「哲学」という名詞へ」という方向が本当のところであって、「「哲学」という名詞から私の行為へ」という方向ではない、ということなのです。それに、その唯一無二の私の行為と「哲学」という名詞が同じかどうかは決してわかりません。もしかしたら、無関係かもしれません。
余計なことかもしれませんが、これは「哲学」という名詞だけに限ったことではありません。たとえば「趣味」といったよく使われる語についても、私は、とてつもない違和感を覚えます。「あなたの趣味は、何ですか?」などと何気なく尋ねてくる人がいますが、何という恐ろしい質問でしょう。私は、いろいろなことをします。音楽を聴いたり、本を読んだり、美術館巡りをしたり、将棋をネットで観たり、格闘技の雑誌を眺めたり、歩いたり、ときどき筋トレをしたり、落語を観たり。しかも、これらの行為は、地続きです。音楽を聴きながら本を読み、美術館に行き、スマホで将棋を指す。
それなのに、「趣味は何ですか?」と訊いてくる。「趣味」という単語があるから、私はいろいろなことをしてるわけではありません。いろいろなことを勝手にしているだけなのです。それなのに、「趣味は何ですか?」と尋ねてくる。「趣味」という語が、ちゃんとした定義があり、きちんとした範囲をもって存在しているかのような錯覚をついもってしまうくらい素朴な質問です。こちらが、「趣味は何ですか?」という質問に対する答を、最初から準備していなければいけないかのような強制力があります。何ということでしょう。
でも、実際われわれは、そのように「準備している」のです。挨拶を無意識に交わすように、いろんな質問に対する答を、おそらく用意しているのです。面倒くさい。それが、言語をもってしまったわれわれの生活なのです。言葉は、こういったかたちで、日々の暮らしのなかで、暗黙のうちに力を発揮していると言えるでしょう。
閑話休題。さて、そういう(面倒な)名詞のひとつである「哲学」という語に、私はどのようにして出合ったのでしょうか。おそらくきっかけは、小林秀雄だったと思います。この批評家との出会いは、偶然でした。中学の頃は、四畳半の下宿で一人暮らしだったので、とにかく本を読むのが「趣味」(笑)でした。一人だけでしたので、誰の目も気にすることなく、いろいろな本を読んでいました。そうしているうちに、後に都知事になる芥川賞作家のエッセイのなかに、とても興味深いことが書かれていました。
鎌倉在住の批評家の自宅に強盗が入って、寝ていた批評家を日本刀で脅した。しかし、その批評家は、目を覚まし煙草を悠然とくゆらしながら、その強盗を説教して追いかえしたというものです。その批評家の名前は、小林秀雄でした。その頃、剣道をやっていて宮本武蔵本人になりたいと思っていたファナティックな中学生だった私は、この話に異常に反応しました。それから小林秀雄が書いた本は、手当たり次第すべて読破しました。太宰や大江や司馬遼太郎などにも手をだしながら、小林を耽読しました。
そうしているうちに、小林がベルクソンやニーチェ、ショーペンハウアーといった哲学者について言及している文章も多く読むことになったのです。どうも私が悩み苦しんでいる問と同じものを、この人たちも考えているのでは、と見当をつけて、そちらの方(哲学方面)に移行していったというわけです。その頃、小林秀雄の文章をちゃんと理解していたとはとても思えないのですが、最初のきっかけが「強盗退治の批評家」でしたので、勢いで読みつづけたということでしょうか。
そういえば、同じ頃、本のタイトルに、はっきり「哲学」という語がついている本も読みました。三木清の『哲学ノート』です。当時、新潮文庫から『人生論ノート』と『哲学ノート』が同じ装幀(タイトルをオレンジ色で囲っていました)ででていました。『文庫目録』マニアだった私は、その二冊を目ざとく見つけて買ったのだと思います。
ところが、「哲学」という語にであい、自分がそれまで考えてきたことが、この語とかかわりがあると思い始めていたのに、これらの本は、十代の私には、まったく面白くありませんでした。不思議なくらいこちらの胸に響いてこないのです。内容なのか、相性なのかわかりませんが、中学生にとって同じくらい難しい小林秀雄の本は夢中で読めるのに、三木清の文章は、こちらに1ミリも入ってきませんでした。後に大学生の頃に同じ三木の『パスカルにおける人間の研究』(岩波文庫)を読んだときには、とても面白かったので(ハイデガーの影響が鼻につきはしましたが)、相性ではないかもしれません。やはり、この二冊の内容が原因だったのではないかと思います。
『哲学ノート』の最初「新しき知性」の冒頭は、こういう書きだしです。
いったい知性に時代というものがあるであろうか。知性には旧いも新しいもなく、むしろつねに同一であるということが知性の本質的な特徴であると考えられるであろう。
なるほど。いま読めば、まぁわからないではないですが、中学生にとって、「知性に時代があるのか」といきなり言われてもねぇという感じですね。こういう問いかけから始められると、さすがに、うんざりするでしょう。まず「知性」につまづきます。しかも、この「知性」という語の背後には、カントの顔が、ぼんやり浮かんでいるのですから、なおさらです。カントを知っている中学生は、おそらくごく少ない(とくにここ極東では、限りなく0に近い)のではないでしょうか。
こういう文につまづいていた中学生が、のちにウィトゲンシュタインを専門にしたのも、とても頷けることです。ウィトゲンシュタインは、こういう思わせぶりな文章は絶対に書きませんから。もっとわれわれがいるこの現場から、普段使っている言葉で話を始めますので。
またまた寄り道しすぎですね。次回は、井上忠の「哲学」観から始まり、ベルクソン、ウィトゲンシュタインの「哲学」について、そして可能であれば、ハイデガーについてもお話したいと思います。(つづく)