「よそ者/新参者」としてのフィールドワーク
9.11同時多発テロから約一年後の2002年秋、私はニューヨーク市ハーレム地区でムスリム・コミュニティのフィールドワークをはじめた。その経緯や探究内容については、『残響のハーレム――ストリートに生きるムスリムたちの声』(共和国、2015)などに発表してきた。また、フィールドワークの舞台裏でのことは、『人間と社会のうごきをとらえるフィールドワーク入門』(新原道信編著、ミネルヴァ書房、2022)に少し書いた。

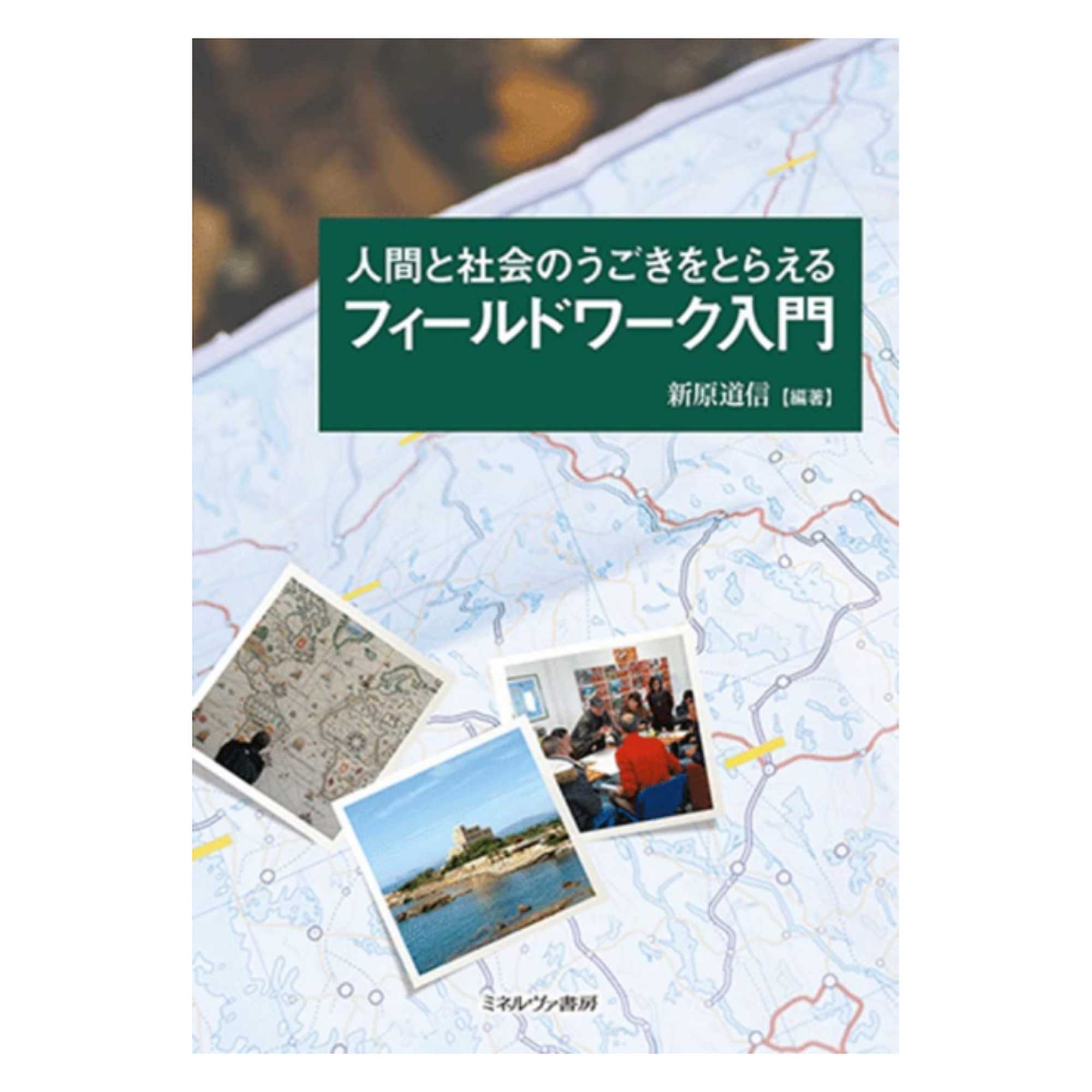
このときのハーレムでのフィールドワークが、私にとって、はじめて単独で挑む本格的なフィールドワークだった。人類学を志していたということもあり、2年間現地に住み込んで参与観察をおこなった。
人類学の博士課程では通常、最低2年間、場合によってはそれ以上、フィールドにて暮らすことが求められる。母語ではない言語圏や見知らぬ世界で、「よそ者stranger/新参者novice」としてフィールドワークをおこなう機会が多い人類学者にとって、膨大な時間をフィールドで過ごすのが重要であることが、今は実感をもってよくわかる。とくに、フィールドワークを通じてなにごとかを学び、考え、「学びほぐすunlearn」(cf. 鶴見俊輔)という営みそのものを、実際に手足をうごかしながら初学者として学ぶ時期は、一見すると無駄に思える時間をたっぷりと過ごすことが大事かもしれない。
その後私は、ハーレムのアフリカ系アメリカ人ムスリムというトピックを離れ、写真家の友人と組んでアメリカの地理的・文化的「周縁」をフィールドワークしたり(成果の一部は、『アメリカの〈周縁〉をあるく――旅する人類学』平凡社、2021参照)、ニューヨーク全体を対象に「底辺層」の生活や労働の変容を調査したりしてきた。その一方で近年は、デザイン人類学と呼ばれる応用人類学的な実践を展開し、自分の会社を立ち上げ、デザイン・ファームや企業と連携し、日本の地域課題や社会課題に取り組みはじめた。

一見するとばらばらのテーマや活動に見えるかもしれないが、これらに通底するのは、ハーレムで出会った暴力と社会的痛苦という大きな問題系である。暴力といっても、殴る・蹴る・撃つなどの物理的暴力だけではない。象徴暴力と呼ばれる見えにくい暴力や、人と人とのあいだの戦引き、自然化され当然のように思われている慣習や制度、人間以外の生き物に対する接し方、などが含まれる。
以下、ハーレムでのフィールドワークを通じて出会ったことがらが、どのようにして現在の自分の活動につながったのか、書いてみたい。
アフリカ系アメリカ人のイスラーム運動というテーマ
1999年に大学院に進学した時点で私が選んだテーマは、アフリカ系アメリカ人によるイスラーム運動だった。ヒップホップやスポーツが好きな人なら、アメリカの著名なラッパーやアスリートたちの幾人かが、ムスリムであることを知っているかもしれない。1950〜60年代の公民権運動のうねりのなか、イライジャ・ムハンマドやマルコムX、ムハンマド・アリといった著名人の活躍もあり、アフリカ系・アメリカ人たちのあいだでイスラームへの関心が高まったことがある。その後、マルコムXの暗殺を経て、イライジャが亡くなると、運動自体も下火になっていくかに見えたが、1990年代に入り、あらためてイスラームへの関心が高まった。
近年、ブラック・ライヴズ・マター(Black Lives Matter)の運動がひろがりをみせ、関連するニューズが日本にも入ってくるようになった。だから、警察による暴力(police brutality)や、刑務所への大量収監(mass incarceration)などの社会問題を、耳にしたことがある人も多いだろう。もちろん、これらはいずれも、最近の新しい現象ではない。
アメリカ合衆国の建国前からつづく人種差別や、それに関連するさまざまな制度的暴力のなかで、なぜ1990年代にアフリカ系アメリカ人たちがイスラームに関心を寄せるのか――大学院修士課程に入ったばかりの頃の問いは、そのようなシンプルなものだった。キリスト教の教会が提供できない価値をイスラームが提供しうるからだろうか。90年代の関心の高まりは、冷戦構造崩壊後のアメリカ外交政策上のイスラーム脅威論の台頭や、世界的なイスラーム復興運動の高まりと関係があるだろうか。70〜80年代の都市部での治安悪化や、社会全体の保守化・右傾化との相関関係はどうだろうか。キリスト教徒からイスラームに「改宗する」という経験はどのようなものだろうか。
修士課程の2年間ではそうした問いに答えが出せず、博士課程に進学し、ハーレムという具体的な生活の場で、ムスリムたちがどのように生きてイスラームを実践しているのかを知りたいと思った。メディア上に飛び交う情報だけでは、きわめて重要ななにかが抜け落ちるように思えた。先行研究はいくつか優れたものが存在していたが、それらからは個々の「ごく普通のムスリムたち」の語りや仕草は見えてこなかった。だからこそ、時間をかけて丹念にフィールドワークするのだ!と意気込んだ。明確な戦略もないままに。
テーマ設定以前、フィールドワーク以前
フィールドワークをするにあたって、テーマや問いの設定は欠かせない。もちろん、テーマや問いが身体化され、ほとんど無意識になっていれば、準備もなく手ぶら状態で「あるく、みる、きく」を実践し、そこからなにかの気づきをえるということはある。だが、通常は、なんらかの枠組みを設定しないと、ただの見学や観光だけで終わる可能性が高い。しかし、テーマや問いに縛られすぎて、それだけを追いかけることになると、それはそれでフィールドワークの醍醐味が大きくそこなわれる。なぜなら、フィールドワークの醍醐味は、入念に用意したはずの問いが崩されていき、問いをつくりなおさざるをえなくなるところにあるのだから。
けれども、そもそもなぜ、どのようにして、上記のようなテーマにたどり着いたのだろうか。横浜で中学生時代を送っているときにふいに遭遇した「差別はなぜ起こるのか」というシンプルな問い、アメリカのイリノイ州シカゴ郊外の高校に通うなかで経験した人種間の隔たり、大学の地域研究ゼミで学んだヨーロッパのムスリム移民たちの直面する問題――それらをかけあわせてリサーチをしていくなかで、修士課程のテーマを決めていった。いわば、偶然経験したことと、自覚的に勉強したこととをかけあわせる形でテーマを設定したことになる。
大学教員をやっていると、「勉強が得意なのですか」「研究がお好きなんですね」といったことを言われることがある。しかし、まったく誇れることではないが、私にかぎってそういうことはない。考えたいことは、物心ついた頃からずっとあったかもしれない。だが、勉強は得意ではなかったし、好きでもなかった。今でも……。
逆に好きだったことはなんだろうか。引っ越しの多かった小学校時代に、新しくできた友だちをひとりひとり家に招き、彼らの話に耳を傾けるのが好きだった。たとえば、クラスでは目立たない子が、最近手に入れた顕微鏡を持ってきて得意げに見せながら、眼を輝かせてその面白さを語るのが好きだった。成績がぱっとしない子が、夢中になってあることを調べたり、絵や設計図を描いて世界観を創作しているのを見るのが好きだった。初期のコンピュータを駆使して、簡単なプログラムを書き、「バタリアン(当時かかっていたホラー映画のタイトル)」と発話させて喜んでいるのを見るのが好きだった。
そして、時折、その子たちの話のなかに、暴力の影が見え隠れした。たいていは親からの暴力だった。そのたびに強い怒りをおぼえたが、どうすることもできなかった。年齢があがると、そうした語りのなかに、親だけでなく、恋人や友人からの暴力も交じるようになった。
そのような原体験が、ハーレムに行くにあたってのテーマ設定や問いに、あるいはその後フィールドワークから戻ってつくりなおすことになる問いに関係しているかどうかは、よくわからない。しかし、ひとりの人間に向き合って話を聞くことは、基本的にはとてもおもしろいし、まったく苦にならない。もちろん、話の内容によっては、深くえぐられ、沈み込むことはあるから、毎回楽しいわけではない。具合が悪くなることもあるし、体調を崩すこともある。聞きたくない話もあるし、語り手の波長にあわせるのが難しいときもある。それでも、気がつくと話に引き込まれていることが多い。
テリー・ウィリアムズとの出会い
フィールドワークだ! と鼻息を荒くしてやってきたハーレムではあるが、うまくいかないことの連続だった。とくに最初の数ヶ月は、ほぼなんの進展もなく苦しい時期がつづいた。しかし、その期間に、いくつか決定的に重要な本を読むことができたのは幸いだった。そのうちの一冊が、Terry Williams and William Kornblum, The Uptown Kids: Struggle and Hope in the Projects, A Grosset/Putnam Book: New York, 1994.である。のちに、編集者の西浩孝氏の尽力で出すことができた、拙訳『アップタウン・キッズ――ニューヨーク・ハーレムの公営団地とストリート文化』(大月書店、2010)である。


はじめてこの本を読んだとき、すでにその時点で絶版になっていたにもかかわらず、そのひらかれた文体や、記述のスタイル、若者たちの声に耳を傾けながら、彼らの生に関与する研究のあり方などに強い感銘をうけ、いつか日本に紹介したいと思った。なによりも、若者たちのなまなましい語りが、魅力的だった。
著者のひとりであるテリー・ウィリアムズに向けて送った、2003年1月29日付けの熱っぽいメールが記録に残っている。このメールのなかで、わざわざ本のなかから抜き書きした箇所を引用し、地域の若者たちに関与する彼の研究スタイルにいかに感銘をうけたか、それが日本の民俗学者・宮本常一のスタイルともいかに共通性があるか、などを熱っぽく書いた。
抜き出して送りつけた箇所は、たとえば以下のような記述だ。
若者たちがハーレムの外の環境へと足を踏み入れて行く際には、異なる社会的状況のなかでどのように立ち居振る舞うべきか経験を積んでいくことになる。その点でテリー・ウィリアムズは、彼が若者たちに紹介した大人たちとともに、重要なお手本となっている。彼は目立たない仕方で、間接的に、若者たちに影響を与えようと努めており、なにをすべきか、どのように振る舞うべきかを教示することはめったにない。そうする代わりに彼は、日常の些細なやり取りのなかで存在そのものによって、若者の習慣的な振る舞いに光を当て、時にそれと対立するような異なる態度のあり方を伝えるのである。たとえばテリーは、彼のしごとばがあったラッセル・セージ財団の建物に、デクスターやシーナ、マリサを連れて行ったことがある。デクスターは、洒落た革製の帽子を横に傾けてかぶっていた。ストリートや仲間たちの間では、帽子は特定の意味を持つ。だが、ラッセル・セージのような仕事のための環境では同じような意義は持たない。テリーは、彼にそっと注意を促し、帽子を脱ぐように言った。デクスターは、少し驚いた様子だったが、言われるとおりにした。その後、テリーの家で、デクスターは帽子を脱いだ方が良いのかと聞いてきた。テリーは彼に自分の好きなようにして良いと伝えた。テリーはデクスターに、彼が帽子を被ることは尊重されるべき文化的、私的な表現のひとつの形ではあるが、同時に彼は自ら慣れ親しんだ世界を超えたところにある環境や文化的コードに敏感になるべきだということを伝えようとしていた。デクスターたちは、自らのルーツを否定したり、異なる文化コードのみを全面的に受け入れたりするべきではない。だが、行動範囲を広げるために、異質なものに対する感受性を育んでいく必要があると伝えようとしたのだ。
テリーは、「適切な」行動を示すことで、また、若者たちが不慣れな世界について議論し手ほどきすることで、人生についての見方や理解が広がり豊かなものになればと願っている。そうすることで、彼らの可能性もまた広がり、彼らの批判的思考も深められていけばと。(pp.151-152)
このような引用を示したうえで、私はウィリアムズに宛てたメールのなかで、次のように書いた。
これ〔上に抜書きした箇所〕を読むと、あなたの研究が単にエスノグラフィを書くということだけに終始していないことがわかります。そうではなく、あなたは文字どおり、自分自身をこの研究プロジェクトに身を投げ出しているのです。若者たちと時間と空間を共有し、言葉を交わし、仕草や行動を見せることで、彼ら自身が将来(何年先であっても)省みることができるものを与えているのだと思いました。こうしたアプローチは私に、民俗学者・宮本常一のことを思い起こさせました。戦後、急速に有無を言わせず近代化する日本の地域をあるき、人びとの語りに耳を傾け、地方に根ざした自発的で持続的な発展のあり方を考えた人物です。(2003年1月29日付けのメールより)
宮本常一とテリー・ウィリアムズ、その意外な共通点
思い返すとこの頃は、エスノグラフィを書くということに関連して、強烈な罪悪感と違和感をもっていた。当然、エスノグラフィを書こうと思ってハーレムに自分からすすんで行き、そこに住んで研究しているわけだから、矛盾といえば矛盾である。しかし、研究して書くだけでよいのだろうか、という違和感があった。だから、書いて作品化するだけでなく、書くことを通じて、ある種の運動を展開し、問題にコミットしているウィリアムズの姿に、強い感銘を受けた。
宮本常一についても、おなじである。宮本が単にすぐれた民俗学者というだけだったら、ここまでのめり込んでいたかどうか、わからない。記述にみられるやさしいまなざしと同時に、離島振興法成立への尽力や農業指導など、知識と知恵と実践とを結びつけようとした姿に、惹かれていたように思う。
私のメールは、宮本作品の英語訳がでる以前の話なので、ウィリアムズとしても困っただろうと思う(現在は、『忘れられた日本人』英語版が、ジェフリー・アイリッシュ氏の翻訳によって読める。Tsuneichi Miyamoto, translated by Jeffrey Irish. The Forgotten Japanese: Encounters with Rural Life and Folklore. Stone Bridge Press, 2010.)。
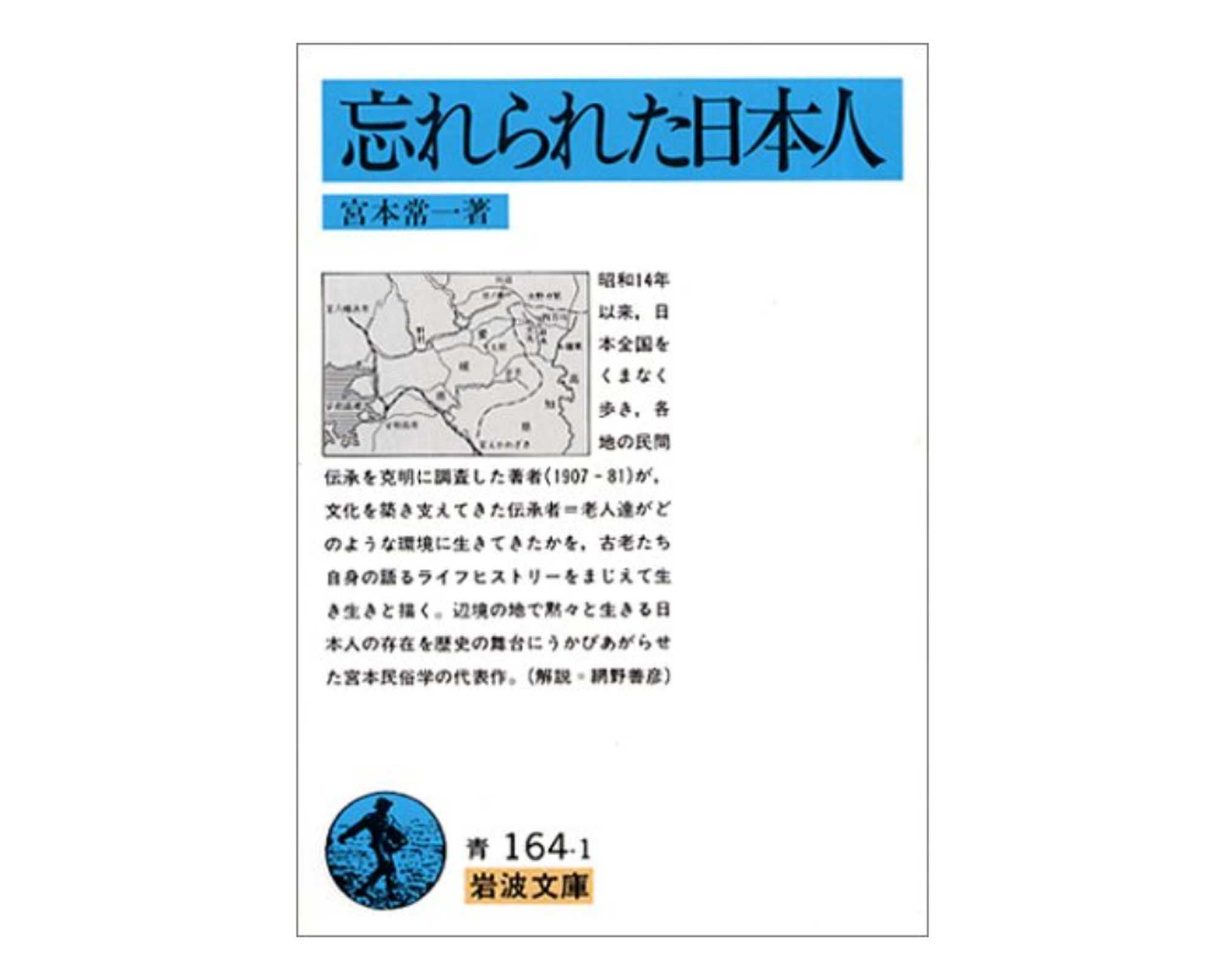
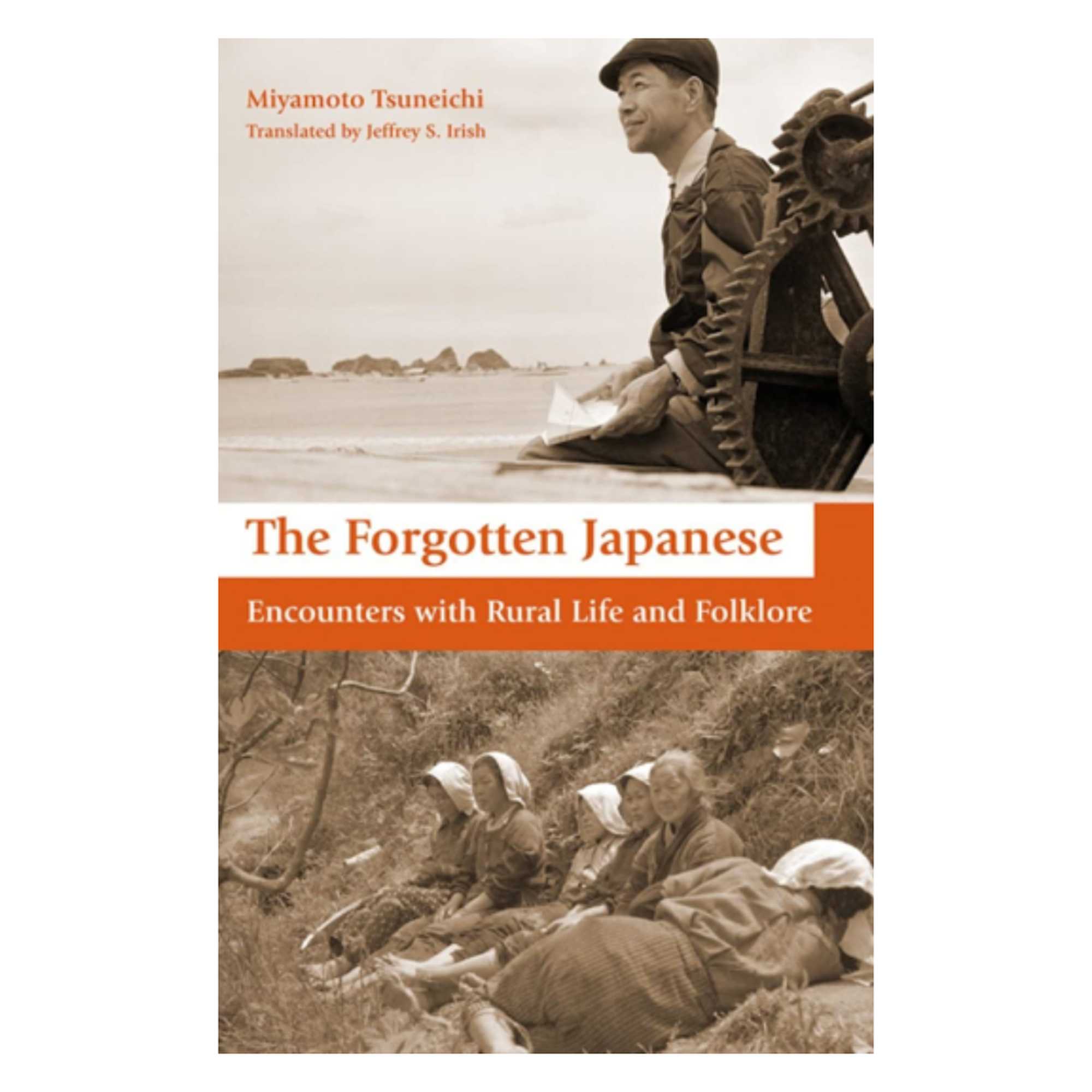
対象とした地域や時代において、宮本もウィリアムズも、まったく異なる。宮本は、戦前、戦中、戦後の日本を記述したし、ウィリアムズは、1980年代から現在にいたるまでのハーレムやニューヨークの他の地区を記述している。
しかし両者は、①記述・記録を残したという点、②地域の文脈と声を聞いたうえで必要な場所・箇所に「介入する」という方法をとった点、で共通する。いわば、聞き書きやエスノグラフィという学問的手法を用いて、社会・文化的介入をおこなっていたことになる。
テリー・ウィリアムズのストリートへの介入
ウィリアムズのとった具体的な介入の第一段階は、ストリート文化を生きる若者たちが語り合える場を設定することだった。ハーレムに隣接するワシントンハイツで、コカインの取り引きによって生計をたてる若者たちのフィールドワークをおこない、『コカイン・キッズ――麻薬ビジネスの青春』(小林礼子訳、平凡社、1991)を著したウィリアムズは、彼らの人生への介入の必要性を感じ、「プロジェクト」と呼ばれる公営住宅団地の若者たちを対象に、鉛筆とノートを配り、日誌を書いてきてもらう。そして、それを読み合う場をつくった。ウィリアムズらはその集まりに、《ハーレム・ライターズ・クルー》という名前をつけた。
はじめてウィリアムズの自宅に招待されたときのフィールドノートが残っている。以下、抜粋を記載するが、読みやすさとプライヴァシーを考慮して、若干の修正をほどこしてある。
2004年8月7日(土)
7:00頃家を出て、赤ワインを買ってから、テリー〔ウィリアムズのこと、以下同様〕の家に向かう。テリーの家は、◯◯丁目ストリートと◯◯ 番アヴェニューの角にある大きな建物の中だった。正面には警備員がいて、アパートメントの住所を告げると、中に入れてくれる。かなり立派なつくりの建物だった。奥に進むと中庭のようなものがあり、植物が飾られていて、いくつかのアパートメントの入り口が分かれている。
ブザーを押して、中に入れてもらい、部屋の扉を叩くと、テリーの息子らしき若い男性が、中に入れてくれる。部屋の中で、テリーの妻ミラナ(仮名)と、クリス(仮名)という若い男性に会う。ハキムも来る予定だったらしいが、何かあって、急遽これなくなったらしい。
スタンディング形式のパーティのようなものを想定していたのだが、少人数で座ってのディナーだった。やがてキッチンからテリーが気さくな様子であらわれ、料理中だけど挨拶だけといって、握手をしに来る。食事はテリーが作っている。ミラナに聞くと、テリーは毎日料理をするし、とても料理が上手なのだと言う。
部屋はとても広く、趣味の良い大きな絵が二枚かざってある。部屋の片隅には本(社会学・哲学を含め、あらゆるジャンルの本)がつまれており、中央には大きな6人がけのテーブルがある。また部屋の隅には、小さなソファがたくさん置かれている。この場所で、ハーレム・ライターズ・クルー(The Harlem Writers Crew)が集まり、それぞれが書いてきた日誌を読みあったのだ。テリーのホスピタリティ。テリーはこれだけの食事をつくりメニューまでつくって人をもてなしておきながら、まったく「もてなしを受けている」という感覚を人に抱かせない。恐ろしいほど、気さくに振る舞う。何よりも食事がおいしく、またテリーの話術も相当のものだった。授業でもそうだったが、テリーはストーリーを語るのがうまかった。人をひきつける話の仕方をした。このようなテリーの性向は、間違いなく多くのteenagerたちを魅了しただろう。
食事の前、ワシントンDCで十年ほど勤めて、ニューヨーク市に二年前に戻ってきて、現在ドロップイン・センター 〔ホームレスの人たちが眠るためだけに利用できる共用スペース〕で働いているクリスが、現在の彼のプロジェクトを話してくれる。ドロップイン・センターは、シェルターと違って、まったくの自由が与えられている。ベッドがないかわりに、椅子があり、誰でも入ってくることができる。シェルターのような厳しいチェックがない。椅子しかないのに、そこにやってきて寝ることを好む人たちがいる。仕事を得て、その場所を出ることができても、なお戻ってきて、そこで出会った人たちと頻繁に連絡を取る人たちがいる。これは一体なんなのかということ書きたいと思っている。今は、作品としてどうなるかはわからないが、ただ人の話しを聞いて、色々なデータを集めている。
クリスは、もう10年以上前に始まったハーレム・ライターズ・クルーを現在代表として引き継いでいるとのこと。食事をしながら、現在の日本の政治的状況についての話が一段落した後に、クリスがライターズ・クルーの困難を話す。ライターズ・クルーを卒業した人たちも、全然手伝ってくれないか、もしくはお金を要求してくると言う。新しいメンバーにとって、どのような試みができるのかがまだわからない。
テリーがそれを聞いていて反応する。「私が用いた方法は、二つのアプローチに基づいていた。ひとつは、科学的方法で、エスノグラフィ。もうひとつは、ソーシャル・キャピタル〔社会関係資本と訳されるコネクションやネットワーク〕に関わる問題で、これは『孤独なボウリング』〔ロバート・パットナムの著作〕から得たアイディアだ。こうした方法をつかえば、一個人として変化を起こせると思った。変化をうむために、たくさんの人や組織は必要ないと。書く、ということについていうと、通常は、私は君やここにくる人たちについて書くことができるけど、君らは私について書けないってされてる。でも、なぜだ? この書くことの権力を、ひっくりかえすことができるって考えたんだ。」
「最初に、若者たちを招いたとき、どうやったら彼らの注目を集めることができるかがとてもよくわかってた。一度ここに来れば、そのあとにも戻ってくるだろうってわかった。ある人にとっては、ここが人と出会う場所になった。他の人にとっては、なにかを学ぶ機会になった。きみ〔クリス〕にとっては、おカネだったね。きみはおカネを稼ぎたがってた。だから、1ページにつき、ほんのちょっとおカネを払った。そして、もちろん、きみは1ページをきちんと文字で埋めたりはしなかったね(笑)。こうやって、おっきな文字で、罫線を無視して、スペースを埋めるように書いてきて、『ほら、1ページ分書いたぞ』って言ってた〔みんな笑う〕。」
(後略、フィールドノーツより)
エスノグラフィと社会関係資本
このときにウィリアムズ宅で出会ったクリスが、じつは先述した『アップタウン・キッズ』に「デクスター」という仮名で登場する人物である(ちなみに余談だが、このとき来る予定で急遽来られなくなってしまったハキムは、ミチェル・ドゥニアのエスノグラフィ『Sidewalk』に登場する人物である。ハキムはこの当時、ニューヨーク・メトロポリタン大学の教員で、《アーバン・ダイアローグ》という、アメリカの都市社会に関連するさまざまなトピックをあつかうトークシリーズを運営していた)。
ウィリアムズはこのとき、《ハーレム・ライターズ・クルー》をはじめるにあたって、少なくともふたつのことを明確に意識していたと語っている。
ひとつは、エスノグラフィの活用。ウィリアムズと共著者のウィリアム・コーンブルム(コーンブルムも社会学者で、かつてのウィリアムズの先生で現在は同僚・共同研究者)は、エスノグラフィという人類学や社会学のうちに生成した知の様式を、ハーレムの若者たちのうちに開放している。若者たちに日誌を書いてきてもらうという仕掛けを用意することで、彼らは自分自身の経験を書くことになる。日誌はフィールドノーツに類似するもので、エスノグラフィの一歩手前の存在だ。そして、それを読み上げ、参加者からのコメントを受けたり、議論したりすることは、いわばエスノグラフィを練り上げていくときの営為に似ている。プロの書き手でも、コメントや査読などを通じて、文章は集合的に書かれていくということを知っている人は多いと思う。若者たちは、いわば、日誌を読み合うことで、集合的にエスノグラフィを書くのと類似する行為をおこなっていることになる。
そして、ウィリアムズやコーンブルムがその様子を観察し、それを今度は書いていく。そうすることで、集合的に書き、読み合い、話し合うという運動の記録が残る。その記録は、ハーレムの公営住宅団地に暮らす若者たちを、「黒人」「ラティーノ」「アフリカ系アメリカ人」「貧困層」「スラム生活者」などのカテゴリーとしてしか見ない人びと――そのなかには研究者やジャーナリストも含まれるし、映画やドキュメンタリーなどに表象された姿を消費する者たちが含まれる――に、なまなましく血の通った具体的な姿を見せる。また、その土地の者たちが、未来を考え、歴史を捉え直すときの資料になってくれる。さらに、類似する試みを、異なる場所や時代においてなそうとする者たちに、参照軸を提供する。
ふたつめは、ソーシャル・キャピタル。『アップタウン・キッズ』を読むと、ウィリアムズがことあるごとに若者たちを、彼らの日常的なネットワーク内にはいない大人たちに、つないでいるのがわかる。たとえば、仕事やインターンの機会がないハーレムの若者に仕事を紹介したり、トラブルに巻き込まれた者を養護するために判事に手紙を書いたり、将来の機会を拡張するために教え子である大学院生を紹介したりしている。
介入の暴力を縮減しながら関与/伴走/ケアする
ウィリアムズ宅にはじめて招かれたとき、私はアフリカ系アメリカ人ムスリムのコミュニティ内で、子どもたちを対象にした夏のプログラムを新しく考案しようとしていた。ウィリアムズたちの《ハーレム・ライターズ・クルー》が念頭にあった。その一年前、英語の読み書きに苦労するハーレムの子どもたちをみて、自分のたちの身近なことがらを言葉にすることからはじめて、英語の読み書きトレーニングを試みたらどうかと思い立ったのだ。興味のない古典からはじめるより、好きなヒップホップやファッション、生活上のさまざまな関心事であれば、言葉を学ぶきっかけになるかもしれない。そんなことを考えた。
ハーレムでの夏のプログラムは、いろいろな事情があって実現しなかった(詳しくは『残響のハーレム』参照)。けれど、文章を書いて、持ち寄り、読み合うというセッションをつくりたい、そうすることで化学反応のような変化が起こる場をつくりたいという気持ちはつづいた。日本に戻ってからも。
2008年、多摩美術大学に着任し、文化人類学の授業をもつようになった私は、自主ゼミを主催にするようになった。やがてそれは、《人間学工房》ゼミへと発展していった。そこで冊子『Lost and Foound』プロジェクトをはじめ、専攻の異なるつくり手たちが集まり、文章を書いて持ち寄り、読み合う場をもった。
ある部分において私より圧倒的にすぐれた能力をもつ美術大学の学生たちと言葉を交わすのは、刺激が大きかった。出会った美大生たちは、手をうごかして形にしながらものごとを考え、そうすることでなにごとかを打ち立てようとしていた。そして、彼らが日々おぼえる違和感のなかで、言葉を探し求めているようだった。互いに介入しつつ、介入され、一緒に考えていける余地がありそうだった。
その後、職業的なアーティストやデザイナーと言葉を交わす機会が増えていった。そして彼らを通じて、企業経営者や、民間企業・行政内で働く「つくり手/担い手/メディエーター」たちとも言葉を交わすようになった。彼らもまた、彼らのやり方で、「顧客」「ユーザー」「組織」という言葉を使いながら、いわゆる経営学や定量的データ解析からは抜け落ちるなにかに気づき、人間と社会のダイナミズムを捉えようとしている。人類学が介入し、一緒に分析・開発・制作・サーヴィス提供することで貢献できる部分が、かなりある。
なによりも、商品やサーヴィスが提供されてしまってからそれらに批判的検討を加えているのでは、手遅れになる問題が多い。学問は、批判的分析を得意とするし、それは意味のあることではある。だが、学問もまた、従来のように研究成果の最終プロダクトを書籍や論文といった文章作品にこだわるより、もっと柔軟にその実践を変化させてもいいはずだ。「社会実装」を担う人びとと一緒に、よりましな社会のグランドデザインをつくり、そのスケールを拡大させたり、逆に抑えたりすることに意味があるように思った。
ふたたび、眼の前にいる人たちとなにかをしようと試みはじめた。デザイナー、経営者、官民のつくり手・担い手・メディエーターたちと、である。とくにデザイナーたちとは、一緒にやれることが多いように思った。グッドデザイン賞に「外部クリティーク」という役割でかかわるようになり、デザインの幅がこの20年ほどで大きく変化し、地域や社会課題解決のための取り組みをも含むようになったことを知ったのも大きかった。なかには、人類学者や社会学者とおなじかそれ以上に、地域をあるいているデザイナーもいた。そして、彼らと話せば話すほど、デザイナーと一緒にできることがかなりある、という確信をもったのである。
*
ここまで読んでくださってありがとうございます。これからデザインを学んだり、デザインで仕事をはじめようとしている方は、ぜひ人類学の著作や論文に触れてみてほしいと思います。また、これから人類学、社会学、哲学、民俗学、歴史学、心理学などの分野で仕事をはじめようとしている方は、ぜひさまざまなデザイナーやデザイン思考者と協働の機会をつくってみてください。これからは、すべてのデザイナーや経営者の横に、人文・社会科学者が必要とされる時代だと思います。




