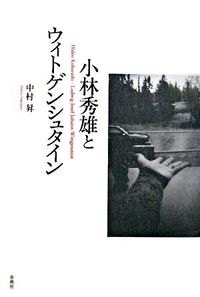――今日は、言葉とはどういうものかについてお聞きしていきたいと思います。言葉というと普通は、もともとあるモノにつける名前だったり、自分の中の考えや感情を入れて表現する「箱」みたいなイメージだと思うのですが。
普通はそう思いますよね。でもソシュールはそうじゃないと言いました。彼は言葉が先にあると。われわれが何かを考えて、その考えに言葉というレッテルを貼るのではなく、最初に言葉ができて、それに内容がくっついている。くっついているっていう言い方は変ですけど、言葉がまずあって、その言葉をやり取りすることで私たちは何かを考えるのであり、言葉に具体的なモノや思いのようなものが一対一で対応しているわけではないという考え方ですね。
――山というモノを見て「山」と名付けるのではなく、「山」という言葉を知ることで山というモノが見えてくると。そうすると、その言葉は最初どうやってできたのかっていう疑問が生まれると思うのですが。
非常に難しいですね。それについてソシュールがどう考えていたかはわかりませんが、やはり最初は何かを見て叫んだり、恐怖を感じておびえる声を出したりといった動物的な発声だったのではないでしょうか。そして、ある場面である発声が繰り返されるうちに、それぞれの発声が各場面に対応していく。
対応していくんだけど、一定程度そういう「言葉」が増えると今度はそれが自律する。最初は確かに現実の状況とくっついていたんだけど、語彙(い)がどんどん増えることによって、言葉だけの世界が出来上がったと考えるのが自然でしょうね。
――はじめは状況に応じて発していた叫び声や鳴き声のようなものが、徐々に現実から切り離されて、言葉だけの世界がつくられていった。
そう考えた方がいいと思いますね。ただ、不思議なのは、日本語でたとえば痛いときには「いてっ」て言うじゃないですか。でも英語圏の連中は反射的に、まったく考えずに言ってるのに「アウチ」って言いますよね。信じられないわけですよ、われわれには。
「いてっ」にしても「アウチ」にしても、それこそ動物の叫び声に近いようなものですけど、バックグラウンドに日本語や英語があるから出てくるわけです。同じ状況で発せられるのに、どうして「いてっ」と「アウチ」になったのかはわかりませんが、もしかしたら最初は人類共通の痛みの表現みたいなものがあったのかもしれない。
でも、ボキャブラリーが増えて日本語という体系ができてしまうと、日本語を話す人は「いてっ」としか言えなくなる。そもそも動物の叫び声が徐々に言葉になっていったというのも仮説に過ぎませんが、反射的な痛みの表現でさえも、バックグラウンドにある母語という体系によって異なるわけです。それがすごく不思議ですよね。
犬の鳴き声にしたって英語はバウワウなのに日本語はワンワン。バックグラウンドに日本語があるから
――そう聞こえる。
というふうに、言葉という体系が聴覚にも影響を与えているんだと思います。
――現実にはあり得ないですけど、どの言語圏にも属さない人が生まれて初めてタンスに足の小指をぶつけたときの発声、それが原初の言葉だと言えるかもしれない。
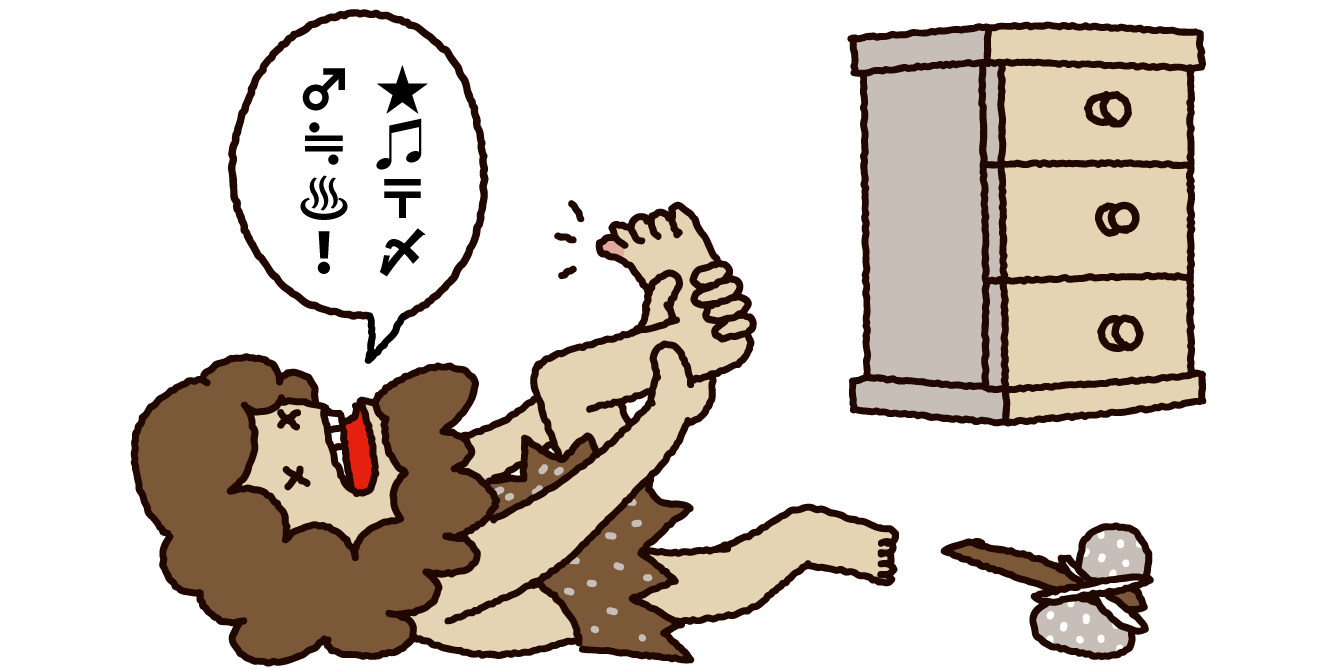
そのとおりだと思いますね。それが本当の痛みの表現だと言っていいかもしれません。でも、そういう人間が痛みの表現をするまでにどういう育ち方をするかですよね。たとえば、オオカミに育てられたらオオカミと同じような表現をするかもしれないし。実際にはやっぱり人間が育てるので、育てた人間の母語が影響することになるでしょう。
――私たちはまったく考えずに「いてっ」と言ってるけれど、そのときは母語がもはや血肉化してしまっているわけですね。
ということですね。「いてっ」て言いますもんね、痛いときには。
――今のお話でちょっと思ったんですけど。少しオフィシャルな場というか、たとえば今こうやって先生とお話しているときに私が何かに足をぶつけたとして、はたして「いてっ」と言うかなと。反射的ではあっても、ちょっと丁寧に「いたい」って言う気もします。
そうですね、それはコンテクストによって決まるわけです。
――置かれた状況や前後のつながりによって、言葉遣いも変化すると。
言語ゲーム
言葉の使い方はコンテクストによって変化するというのが、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」という考え方です。私はいまこういう話し方をしてますけど、自分の親と話すときは九州弁になりますし、学生と話すときはもっとざっくばらんです。もう本当に、コンテクストによって違うんですね。
大きくいえば日本語を使ってるわけだから日本語という体系の中にいるんですけど、個々の場面で異なる言葉の使い方をする。
――話す場所や相手、前後のつながりによって変わるわけですね。
ウィトゲンシュタインはもともと論理学者として出発しました。だから若い頃に書いた『論理哲学論考』という本の中では、世界のベースには普遍的で堅固な論理があり、それによって世の中は成り立っているし、われわれが日常使ってる言語も、同音異義とかいろんな混乱があるけど、それらを解消していけば最終的には非常にクリアで論理的な構造が現れてくると考えたんです。
ところが歳を取ると考えが変わってきて、最終的には、論理的でクリアなものではなく、話しているその場その場で流動的に変化していく、それこそが言語の本当の姿だ、という考えに行き着きました。われわれが日常的にいろんな所で使っている言語こそが本当で、それを仮に言語ゲームと呼ぼうと。
――なぜ「ゲーム」なんですか?
「言語」って呼んでしまうとただ一つの、イデア的なものを想像してしまう。すると、普遍的な論理につながるものがあることになってしまうけど、「言語ゲーム」という言い方ならいろいろなものがあるということになる。言語ゲームって原文では複数形なんです。さまざまな言語ゲーム。そのさまざまな言語ゲームの織りなす全体こそが言語で、しかもその全体も言語ゲームなんだ、というような言い方をしています。
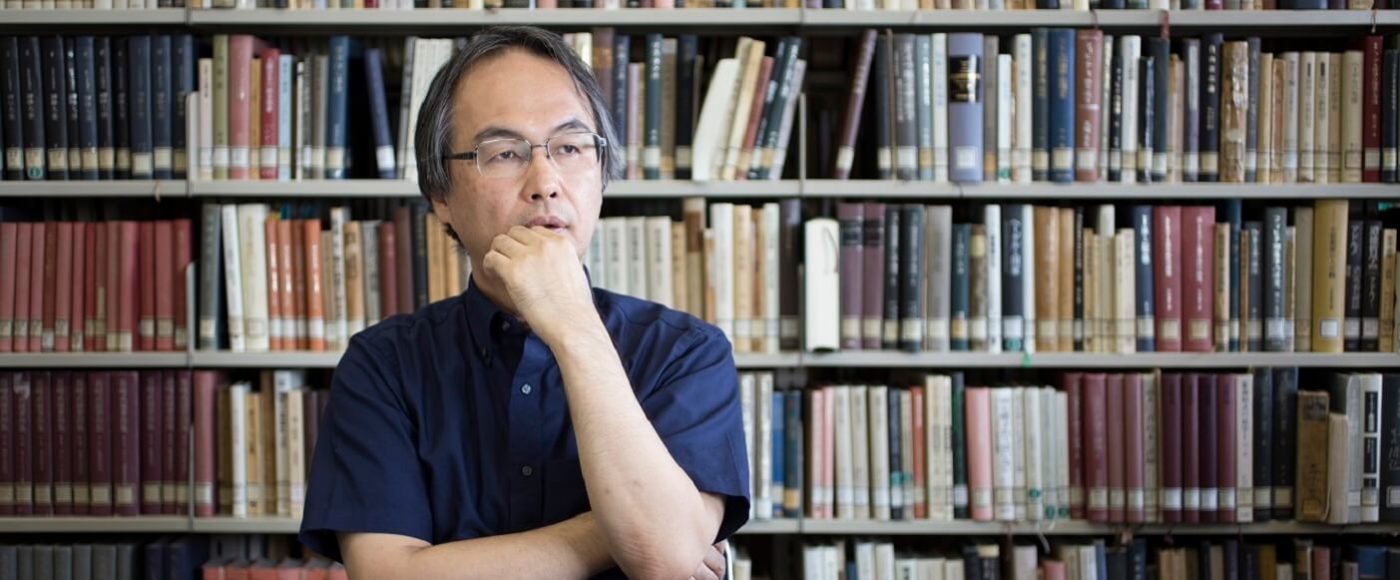
言葉とはひとつの論理ではなく、日常的にいろんな場面で交わされるもの。たとえば今のこの会話だって一つの言語ゲームなんです。世界中のあらゆる場所で、さまざまな言語ゲームが生成消滅している。その全体が言語なんだというわけです。そうすると言語に対する見方はガラッと変わりますよね。
――ゲームという言葉に込められているのは、ルールがあるということでしょうか。
ルールもありますね。もちろん各言語の文法的なルールもありますし、さっき言われたように、さすがに「いてっ」て言うのはちょっと気がひけるみたいな。それもルールなんですよ、この言語ゲームでは。このコンテクストでしか成り立たないような約束事というか、暗黙のうちに決まることってあるじゃないですか。そういうのもルールの一つです。
――なるほど。
言語ゲームはドイツ語でシュプラハシュピールというんですけど、シュピールがゲームですね。このシュピールという言葉にはもちろんゲームという意味もありますが、演劇とかそういう意味もあるんです。何かそこで演じている一場面みたいな。そういうちょっとふくらみのある概念ですね。日本語のゲームよりもっと広い、一つの行為とか、演技、演劇といった意味もあります。
――いまのこの会話も言語ゲームだし、友達とLINEするのも、会社で仕事の打ち合わせをするのも、ぜんぶが言語ゲーム。
言語ゲームですね。
――じゃあ一人で本を読んでいて、これどういう意味だろうとか、何が言いたいんだろうなって考えるのも。
そうです。その本との対話が成立している。
――ということは、言語が出てくる以上、言語ゲームじゃないものはないということでしょうか?
そうなりますね、言語が出てくる以上は。
――言語は常にその場その場の状況によって変化する。
コンテクストに依存して出てくる。
――絶対的なものではない。
そういうことです。