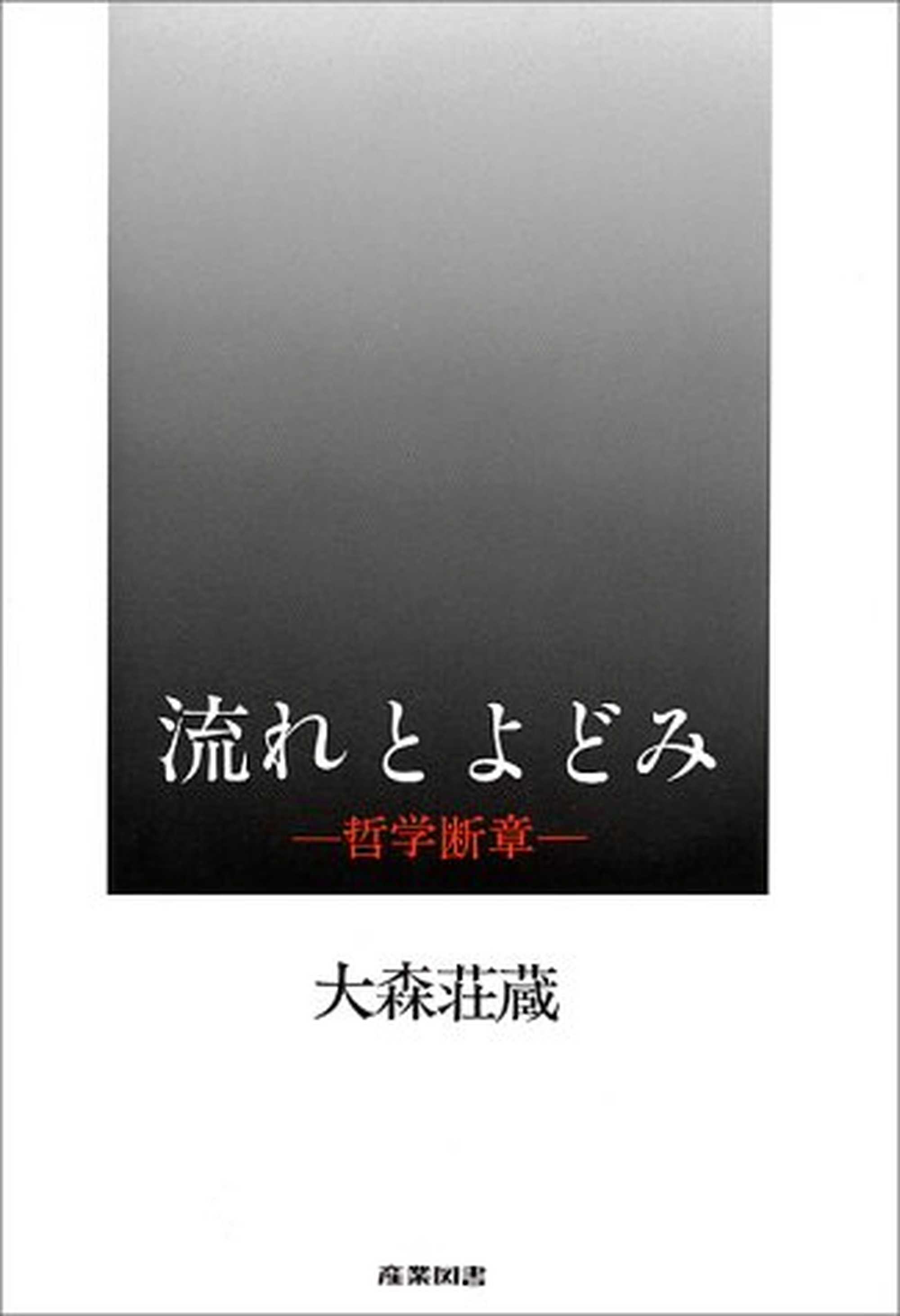この連載の一回目に、この連載で何を書くつもりかということを述べました。そのとき、「日本語で哲学する」試みについても書いていました(さっき確認しました)。ご存知のように(?)、この連載は、計画や予定というものとはまったく無縁ですので、この「日本語で哲学する」試みという伏線も回収されずに終わってしまう可能性もひじょうに高かったのですが、ハイデガーや西田について、いろいろな角度から書いているうちに、突然思いだしたというわけです。
何しろ、「日本語で哲学する」というのは、ずいぶん前から考えていたことなので、いくら私の連載が蛇行を続けていたとしても、いくら私が計画や予定を忌み嫌っていたとしても、ここに至って、私の「深い部分」(?)からの呼びかけがあったというわけです。
そこで、今回からは、「日本語で哲学する」というテーマをめぐって、いろいろ考えてみたいと思います。まずは、「日本語で哲学する」というのは、どういうことなのか、あるいは、「日本語で哲学する」ということをどういう風に私は考えているのか、といったところから始めたいと思います。
日本のとんでもない哲学者
この連載の最初の方に、ヨーロッパの言葉で哲学していくのは、とにかく大変だといった愚痴を書きました。西洋哲学では、「理性」だの「論理」だの、われわれが普段交わしている母語による会話では、絶対に使わない単語を使っているからです。でも、だからといって、日常の言葉だけで「哲学」できるのか、といったら、これもまた難しい。ずいぶん前に、私の「真の母語」である佐世保弁だけで哲学するブログを始めましたが、あっという間に挫折しました。
今回は、その難しさの理由がどこらへんにあるのか、そして、実際に「日本語で哲学」できるのかどうか、といったことを探ってみたいと思っています。
日本にも、とんでもない哲学者はいます。個人的な好みだけで言いますが、まず鎌倉期の道元。もし無人島に一冊だけ本をもっていっていいと言われたら、「一冊ではなく、四冊にしてくれ」とタフなネゴーシエイションをして、岩波文庫の『正法眼蔵』(編注:道元の主著)全四冊をもっていくと思います。
これは、以前どこかに書いたと思いますが、高校生の時、初めての読書会(日本史の先生と同級生と一緒にやりました)で読んだのは、道元の弟子・懐奘(えじょう)の『正法眼蔵隋聞記』でした。その頃から、無人島に行くとき、あるいは、晩年一人ぼっちになったら、道元本人の濃密な言語世界(『正法眼蔵』)に浸りたいと思っていたのです。
そして、江戸期の三浦梅園。江戸時代に、こんなとんでもない形而上学者がいて、しかも、九州の大分にずっと住んでいたというのを知ったときには、心底驚きました。この人の『玄語』とも、いずれじっくりつきあいたいと思っています。そのような至福の時間を、死ぬまでに、つくることができるでしょうか。
さらに最近で挙げれば、大森荘蔵先生の『流れとよどみ』。この本の深い哲学的思索と、このうえなく流麗な日本語は、私にとっては垂涎(すいぜん)の的です。『流れとよどみ』のような文章を書けたら、私の人生の目標の一つは達成されたと思いそうです。『正法眼蔵』や『玄語』とは、かなり異なる系統の本ですが、「日本語で哲学する」お手本といってもいいと思います。
対象と言語の関係
さて、「日本語で哲学する」ということを、はっきり意識したのは、和辻哲郎の「日本語と哲学の問題」(『続日本精神史研究』)を読んだときでした。今回は、新しいテーマに入るための瀬踏みのような回ですので、まずは、和辻のこの文章を少し見てみたいと思います。
この文章は、昭和四年(1929年)に書かれたものです。ドイツ留学から前年帰国したばかりですので、この文章には、ハイデガーの影が色濃く落ちています。Daseinやbesorgendといったドイツ語が、原語のまま書かれていますし、日本語についての細かい歴史的な考察も、ハイデガーのドイツ語やギリシア語の語源学的な説明の影響かも知れません。とにかく、ハイデガーの姿が、ここかしこに垣間見えるのです。
和辻は、まず、われわれが母語によって、ものを考えていることを指摘します。これは、ごく当たり前のことですが、われわれが文章を書くときや何かを話すときは、特定の共同体の特定の言語(多くの場合は母語)を使っています。どんなに普遍的で抽象的なことを話すときでも(たとえば、哲学)、それを表現するのは、限定された特殊な一言語(母語)なのです。これも、実はとても不思議なことです。
どれほど一般的なことであっても、全人類が共有している普遍言語で話したり書いたりすることは、できません。そんなものは、どこにもないからです。われわれが使っているのは、いつでも特定の限定された一言語なのです。
このように考えると、言葉にかんしては、私たちは、とても特殊な状況にいるといえるでしょう。普遍的な対象を表現しようにも、それに見合う言葉を、われわれは、そもそももっていないのです。
中華料理(普遍的なこと)を食べるのに、それぞれ和食用のお皿で食べたり、フレンチの味付けをしたり、フォークとナイフで食べているようなものです。それぞれの母語の都合で、人類に共通の事柄を料理してしまっているのです。美味しい(正確に理解している)はずがありません。母語独自の世界に変えられているからです。
和辻も、つぎのように言っています。
それぞれの特殊な言語を離れて一般的言語などというものがどこにも存しないことは、何人も認めざるを得ない明白な事実である。(『和辻哲郎全集 第四巻』岩波書店、1962年、509頁)
それぞれの多くの「母語」とは異なる「一般的言語」が存在し、全人類がその言語を使用するならば、その言葉を使うすべての人たちは、共通の認識ができ、どんなに異なる地域に住む人同士との間でも、ほぼ誤解のないコミュニケーションができるかもしれません。ただ、言語そのものがもつ現実との乖離という性質(嘘をつくことができる、言葉そのものが嘘(虚構)である)がありますので、それほど簡単ではないでしょう。言語化すると、そもそも基準となる共通の現実から離れてしまうからです。
ただ、数学や論理学のようなわれわれ人類が共有しているのと同じようなシステムに、言語がなれば(それこそ「一般的言語」かもしれません)、たしかにあまり誤解や問題は、起こらないかもしれません。
でも、そうはなっていない。私たちは、誰もがそれぞれの母語を使わざるを得ないのです。ところが、もちろん、この「母語」も、とても自分自身の言葉とは言えない。誰がつくったのかもわからない、生まれた共同体に最初から(すでにつねに)あったものなのです。「誰のものでもあり、誰のものでもない」ものなのです。「母語」のなかの「母」は、どこまでさかのぼっても、決して見つからない「母」なのです。はっきり言えば、この「母」は、共同体のすべての構成員にとって(そして歴史上の誰にとっても)「他者」なのです。
このように考えれば、最も身近な「母語」でさえも、つきつめれば自分自身の言葉ではなく、「他者」なのですから、母語ではない英語やドイツ語などを日本語に翻訳したものは、さらに遠い存在だということがわかるでしょう。「こころ」と日本語でいっても、本当のところは、何のことだかわからないのに、よその言葉を翻訳して「精神」や「理性」や「知性」と言われたら、もう皆目手がかりさえつかめないということになるでしょう。
そうはいっても、やはり、「他者」のなかでも、私にとっては最も身近な「他者」である日本語を、もう一度、哲学の言葉として見直してみようというのが、いまからやろうとしていることなのです。
日本語の特徴
和辻は、日本語の特徴をつぎのように説明します。
たとえば「もの」を言い現わす名詞は、そのものが単数であるか複数であるか、一定のものであるか不定のものであるか、一例としてであるか一般的にであるか、男性的女性的或は中性的のいずれであるか、というごときそのものの有り方の種々の様態については全然介意せず、ただ類型的にそのものを言い現わすことに満足する。だから複数形もなく性の別もなくまた冠詞も伴なわない。元来名詞は、客観的にあるもの自身を示すのではなく、精神がその生産によってそのものを把捉したところを、あるいは生のそれ自らの内におけるそのものとの交渉を、表現するのであるとすれば、右のごとき「もの」の見分け方ののんきさは、そこから悟性的認識の努力が強く発展し得ないような特殊な生の性格を示すと言えるであろう。(同書、512頁)
和辻は、日本語は「もの」を言い表す際に、そのあり方(単数か複数か、一定か不定か、一例か一般的か、男性的か女性的か等)には頓着せず、ただ「それが何であるか」を形式的に表現するだけであり、そしてそのことは誰がどのようにその「もの」を認識しているか(悟性的認識)を重視しないという日本語の性格を示している、というのです。
しかし、同時に日本語の長所もまた、つぎのように指摘します。
樹木は本来一本でもあれば多数でもある。そのいずれかに片付けてしまうのは樹木の本質に忠なるものではない。樹木が一本であるかあるいは多数であるかは樹木の数の問題として樹木に関して考えられることである。たから樹木そのものにおいては単数多数の別のない方が事態に忠実なのである。同様に性の別は、人間存在にあっては、不可的な限定によって初めて生ずるものではない。男女は根本的な区別である。従って男女、父母、夫婦、兄妹というごとき名詞自身が性の別を本質的に含意するのであって、ことさらに冠詞をもって示すを要しない。もし名詞自身がこの別を含意しないならば、冠詞によって男女の別を付加するということは無意義である。従って名詞が性の別を持たない方が事態に忠なのである。さらにまた動詞に、人称の別のないことは、人間の動作が個人的・社会的なものとして、いずれかの人の立場に固有するものでないことの了解を示すのである。我が見るのも汝が見るのも見る働きとして同一であるならば見るという動詞は形を変えるに及ばない。—なおその他の点についても同様のことが言えるであろう。しからば日本語の非分別性は、悟性による綿密な分別を加えなかったがゆえにかえって真実なる存在の了解を保存するものと言えるであろう。(同書、514頁)
このように和辻は、日本語の特質を、実に鮮やかに示しています。一見「悟性的認識における不熱心」(512頁)という特性を日本語の文法がもっているようだけれど、それは、他面「真実なる存在の了解を保存」しているというわけです。
こうして和辻は、さらに「の」や「に」といった助詞のもつ「余韻」の「交響」(516頁)の複雑さや、過去形を表す多数の助動詞の「濃淡差別」(517頁)など、日本語の文法構造の「異常」な「進歩」(518頁)にも言及していきます。
そして、つぎに「日本語と哲学の問題」という本丸に入っていくのです。
その話は、また次回に。